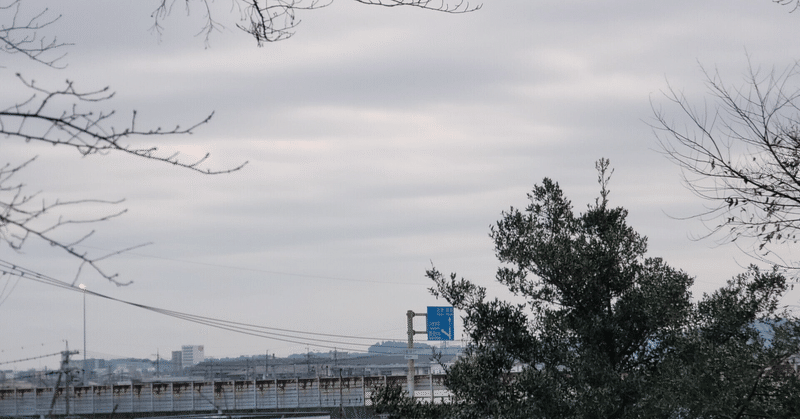
下手糞な文章についてクソ真面目に語ってみた。#1
下手糞な文章。そんな概念がこの世界には転がっている。だが、下手糞な文章について語られたクソ真面目な文章やコンテンツ、授業というものは全く持って存在しない。なぜだろう。下手糞な文章とはそもそもいかなる者であって、いかなるものでないのだろう。
「下手糞な文章」の定義を見つけるため、アマゾンの奥地へ乗り込むような野暮な真似をすることなく、ただ気ままにベラベラと、ジャズを流しながらウィスキーを飲み干して語るだけの記事である。どうか、僕と同じように時間を持て余したが、考えることは嫌いではないような人に読んでもらいたい。もしもあなたが自分の文章が下手糞な文章なのではないかという脅迫観念に取りつかれて、昼も夜も眠れぬ毎日を過ごしている文筆家なのであれば、この文章はおそらく世界一の駄文(無駄な文章、あるいは下手糞な文章の亜種)であるという前提に立って楽しんでもらいたい。
下手糞って何だ
考えてみると、「下手糞」という言葉は面白い。下手は上手の反対、しもて、うわてという読み方もあるが、それ以上に「よい」「わるい」という意味で使われていると推測できる。続いてそこに続く言葉は「糞」。KUSO。要は日本語で言う「うんこ」である。となると、下手糞という言葉は「わるいうんこ」ということになる。
下手糞な文章、という言葉の定義を、言葉通りに取るのであれば「わるいうんこの文章」になる。まったくもってお下品だ。上品の逆が下品である。品がない。つまり、下手糞な文章とは品がない文章のことだろう。
だが、こんな文字通りの定義に真っ向から反対する文章という物が世の中には少なからず存在する。村上龍の『限りなく透明に近いブルー』なんかは、文章の表現自体を切り取った時にはあまりに綺麗だが、その内容はお世辞にも上品とはいいがたい。ドラッグとセックスと暴力の描写(それからハエなど)が9割を占めるこの文章は、品がないといえばそれまでだ。
ところが、この作品は不思議なことに「芥川賞で一番売れた本」である。嘘だろとおもったそこの君。そうなのだ。そして実際のところ、この本の文章は下手糞な文章ではない。むしろ先ほども言った通り「綺麗な文章」である。このことから分かるのは、下手糞=下品というわけではない、という事実である。
さて、では、元の定義に戻って「わるいうんこ」の文章を考えてみよう。そもそもこのためには「わるいうんこ」と「いいうんこ」の定義を厳密に定めるところから始めなくてはならない。「わるいうんこ」と「いいうんこ」である。
本ブログの続きはまた次回に続く。連載頻度は未定である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
