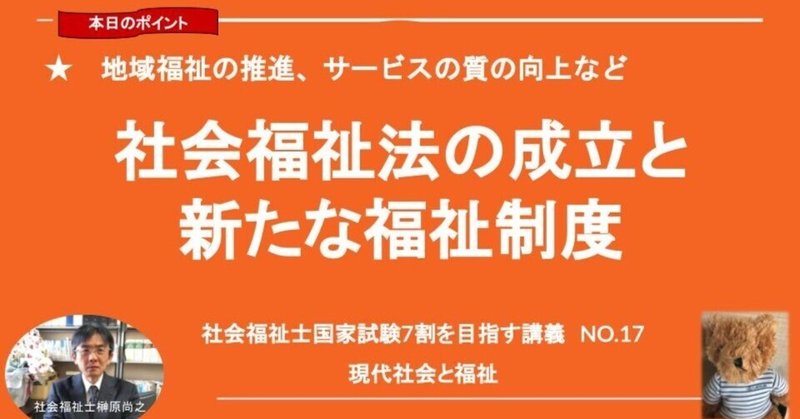
7割を目指す講義NO.17 社会福祉法の成立と新たな福祉制度
1.社会福祉法の成立と社会福祉基礎構造改革に伴う新たな福祉制度
1998年の中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会による「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」で示された「利用者主体」や「措置から契約へ」という方向性に基づいて、2000年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が制定されました。
この改正の対象になった法律は、社会福祉事業法をはじめとして、民生委員法等の8つの法律になります。
この時に、社会福祉事業法が、現在の社会福祉法に名称が変更されました。
社会福祉法が成立した際、4つの基本方針の下、新たな福祉制度を創設していきました。
①利用者の立場に立った社会福祉制度の創設
②地域福祉の推進
➡地域福祉計画を新たに規定、社会福祉協議会や共同募金等の活性化
③サービスの質の向上(事業運営の透明性の確保等)
④社会福祉事業の充実・活性化
➡特に相談支援事業を社会福祉事業としました。これは、利用者が自分でサービスを選択していく際に専門的なアドバイスが必要になってくるからです。
以上の4つの基本方針の下、新たな福祉制度を創設しました。
これは、考えてみたら当然のことです。
社会福祉の基礎構造を大きく改革しようとする場合、改革後に懸念される事項が出てきます。この懸念事項について前もって対策を立てて、福祉サービス利用者に不利益にならないようにしなければなりません。なので、新たな福祉制度を創設するわけです。
2.各論
では、今回は、
(1)利用者の立場に立った社会福祉制度の創設
(2)地域福祉の推進
(3)サービスの質の向上
を詳しく見ていきます。
(1)利用者の立場に立った社会福祉制度の創設
①措置から利用契約へ
福祉サービスの利用については、大別すると、措置方式と利用契約方式があります。
ここから先は
¥ 110
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
