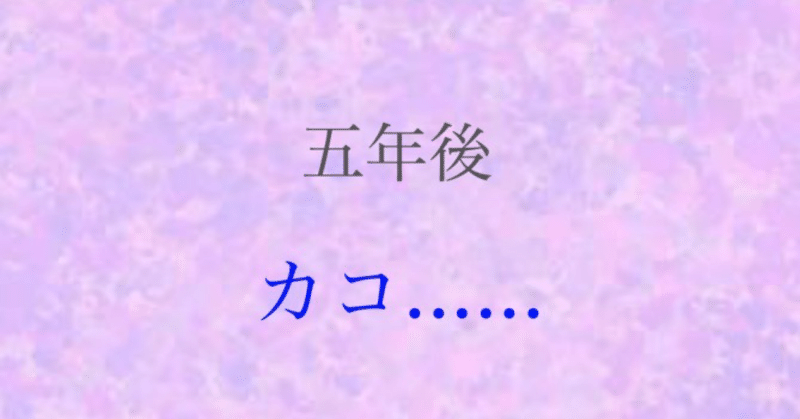
五年後、カコ......
山の中腹にある校舎、そこから森の小径を通った高台にその館はある。私立白樺女子学園の理事長・源財芳子の邸宅である。
絵里はその邸宅に向けて歩を進めた。訪ねるのは理事長ではなくその孫娘の華子。絵里とは学園在学中からの親友である。
二人とも演劇部に籍を置き、輝かしいとまでは言えないものの楽しくも有意義な日々を共に過ごした。ある一点を除いては。
「久しぶりね」
華子は以前と変わらない笑顔で絵里を部屋に招き入れた。
「どう? 学園の司書の仕事は、慣れた?」
「そうね、ようやく何とか、という感じ。それより理事長先生……、華子のお婆様には随分とお世話になったわ」
「絵里の実力よ。採用の選考に関して祖母は何も口出ししてないって言ってたわ」
「いえ、この就職難の時代に、本当に助かったの」
「教職の免許も持っているんでしょ」
「ええ、まあ国語科なら、出来ると思うわ」
「絵里なら大丈夫よ。しっかりしてるから」
「そんなことない。今でも丘先生なんて呼ばれると、背中がくすぐったくなるわ」
絵里はふふっと口元に笑みを湛え、部屋の内部を鑑賞した。
「ちっとも変わってないわね。この部屋」
「ほとんど留守にしてるから」
華子は現在、都内の大学院に通っている。今は夏休みで帰省中だ。
「いつまでこっちにいるの?」
「来週には戻るのよ」
「え、そんなに早く?」
「だってもう夏休みも終わりじゃない」
「そう言えばそうね。全く月日が流れるのは早いわ」
絵里は学園に在学していた頃、何度かこの邸宅を訪ねている。華子が演劇部の部長で絵里は記録係兼マネージャーみたいな立場だったから何かと打ち合わせと称して二人で話す機会があった。
「あのバルコニー……」
絵里は華子の部屋に隣接したバルコニーに視線を移した。
「うん? どうかして?」
「いえ、昔、よくあそこで森を眺めたよね。懐かしいわ」
「そうだったわね。ちょっと出てみる?」
今日は空も曇り空で夏の日差しは軽減されている。それにこの辺りは高原で夏でも涼しい風が吹く。
二人は揃ってバルコニーに出てみた。白い石垣で囲われたその場所は開放的で学園の裏側一体に広がる森を一望し、遠くの山の稜線が遥かに見渡せた。
絵里は久しぶりに眺めるその風景に目を細めてその空気に触れた。
「あ、あれ」
「なぁに?」
「あそこの木々の隙間から、駅のホームが見えるわ」
「そうね、端の方だけど」
あれは……、昔、あの忌まわしい……。
絵里がほんの少し回想に耽っていると、
「あら、あの子達、何をしてるのかしら?」と、華子が森の小径を指差した。
見ると学園の生徒が二人、体操服姿で小径をウロウロしている。
「ああ、あの子達、さっきここへ来る途中で会ったわ。部活動なんだって」
「え? あんな所で、何してるんだろ?」
「森の中は危険だから早く戻りなさいと言ったのに、まだあんな所にいたのね」
絵里はため息をついて腰に手を当てた。
「部活動て、何のクラブ?」
「えっと、確か、ミス研とか言ってた」
「何? ミス研て」
「多分、ミステリー研究部のことじゃないかな」
「え、そんなクラブ有ったっけ?」
「私達の在学中には無かったわよね」
絵里は、つい先程、その二人組と小径で出会った時のことを思い出す。
突然、林の中から出て来た二人組に絵里は大層驚いた。体操服姿で学園の生徒だと分かる。臙脂色だから三年生だ。
何してるの? 絵里の問い掛けに目の大きな利発そうな子が臆せずに応えた。部活動です、と。
首から大きなカメラをぶら下げている。もう一人の子は髪をツインテールにして眼鏡をかけて少し内気そうな素振りをしていた。こちらも双眼鏡を首からぶら下げ、手には何かメモするノートを握っている。
絵里が何と言おうか戸惑っていると、利発そうな方の子が、大丈夫です、もう戻りますから、と言って、じゃ、と去って行こうとする。
体操服の胸にはそれぞれの苗字が手書きされた布が貼り付けられている。チラッとそれを見ると『星井』という名が見て取れた。もう一人は、何だったかな、『早』という文字が見えた気がする。
去り際に、何のクラブ? という絵里の問い掛けに、星井という名の生徒が目を輝かせて答えた。「ミス研です」
ミスケン? その言葉が、ミス研、ミステリー研究部に落ち着くまで、絵里には数秒の時間を要した。
一体、ミス研が森の中で何を調べているのだろうか?
まさか! と絵里は一瞬、ある事柄に思い当たる。しかし、それこそ、まさかのまさかだ。長年絵里が不審に思っていること、それを誰が知るというのか……。
そろそろと西の空の方の雲が朱色に染まり始めた。徐々に森の色が深く濃くなる。
「ねえ、華子、実は以前から貴女に尋ねてみたいと思っていたことがあるの」
絵里の質問に華子はちょっと微笑んで小さく首を傾げた。
「何かしら?」
「わたし、実は、何度か見かけたの」
「見かけた? 何を?」
「このバルコニーで、貴女が大きな鳥を肩に乗せているところ」
「鳥?」
「ええ、多分、この森に住んでる野生の鳥だわ。種類までは分からないけど」
華子は暫く黙していたが、観念したようにやがて口を開いた。
「ラファエルというのよ」
「ラファエル?」
華子は少し微笑んで、「わたしが勝手に名付けてそう呼んでるだけ。小さい頃からのわたしの友達」
「友達?」
「ええ、時々このベランダに来ては、羽を休めていたの。丁度今あなたが立ってる石垣の上辺り」
えっ、絵里は驚いて後退りし石垣に目をやる。もちろん今はただの白い石があるだけだ。
「それを手懐けたの?」
「手懐けたは酷い言い方だわ。友達だって言ったでしょ」
「そう、それは今でも?」
「そうね、あなたが来る少し前にもそこに居たのよ」
絵里は再び驚いて石を見る。何の形跡も無い。
「あれは、もしかして、この森の主?」
「さあ、それはどうか分からないけど、もうかなりの老梟ね」
「梟だったの?」
「正確にはシマフクロウて言うらしいけど、そんなことなんだっていいわ。わたしにはラファエルで充分、それが聞きたかったこと?」
「いえ、実は、あの頃の、あなたと園子の間のことだけど……」
絵里は思い切って初めて正面からそう切り出した。それはこの学園に戻ってから日に日に思いが募っていたことだ。
「園子?」
華子は泰然としたまま、まるで初めて聞く名前のようにその名を口にした。
「表向きには、演劇部の部長と副部長という関係だし、実際に仲も良かったのだろうけど、何か、それだけでは無かったのじゃないかしら?」
「それだけでは無い? どういうこと?」
「う〜ん、上手く口では言い表せないけど、いつも主演は園子で、そしてそれは学園中の誰もがそう望んでいたし……」
「……だから?」
絵里は少し落ち着こうと深呼吸をした。
「この際だから、はっきり言うわ。貴女、園子に嫉妬していたのじゃない?」
「嫉妬? まさかそんな」
「知ってるわ。貴女がそんなこと、決して口に出さないことも、でも貴女はこの学園の理事長の孫だし、校長の娘。本来なら演劇の主役は貴女が務めるべきものよ」
「そんなことは関係ない」
「関係無くはない筈よ。演劇部の女子達はみんな貴女の味方だった。だからこそ、園子さえ居なければ、なんて口には出さないけど、みんな思ってた。実際、部内で園子が孤立してたこと、知ってたでしょ」
「それで園子が自殺したとでも言いたいの?」
「そうじゃないわ。あれは……」
「あれは、何?」
「……事故よ」
「事故? そうなのかな」
華子は黙ったまま遠く山の稜線に目を向けた。それはまるで五年前の過去を思い出して眺めている様にも見えた。
「ここから見える駅のホーム、あそこからあの日、園子は走って来る電車に飛び込んだのよね」
華子は何かしら悲しいものを見るみたいに厳しい眼差しでそちらを見詰めた。唇はギュッときつく結ばれている。
「ねえ、聞いて、わたしの勝手な憶測だけど」
華子は静かに絵里に視線を戻す。
「まさか、まさかだけど、華子、貴女、ここからラファエルに命じて……」
華子は若干、不意を突かれた様にたじろいだ素振りを見せたが、
「ラファエルに命じて、何をしたと言うの?」
「そ、園子の背中を……」
それ以上は言葉にならなかった。
少し涼しい風が強く吹いて来た。
「ああ、そろそろ暗くなる。わたし戻らなきゃいけない。今話したことは忘れて、全部わたしの勝手な妄想だから」
華子と絵里は黙ったまま、部屋を出て玄関へと続く階段を降りた。
「それじゃ、また、今度いつ会えるか分からないけど、元気でね」
絵里はそう言うのがやっとだった。
「もし……」華子が口を開いた。
絵里は黙って振り向いて華子を見た。底の知れない大きな瞳が絵里を捉えている。
「もし、ラファエルが園子を突き落としたとして、それがわたしの命じたことだったなんて、誰が証明出来る?」
ひっと喉の奥で何かが鳴るのを絵里は感じた。
夏の終わりを告げる冷たい風が吹いた気がした。
「冗談よ」華子は笑った。
「そんなこと、ある訳ないじゃない」
華子はそう言ったけれども、何だか気不味い妙な空白が生まれた。
「ひとつだけ聞かせて、あの日の夜、駅のホームに立っている園子を華子はバルコニーから見てたの?」
一瞬の間があった。しかし、素っ気ない風に華子は一言口にした。
「見てないわ」
二人は互いの瞳の奥を覗き合った。
「華子、これだけは信じて、わたし貴女を糾弾しようと思ってここへ来た訳じゃないのよ。ただ、ただ、あの日何があったのか、本当のことを知りたくて、それだけなの、でないとわたし、園子に申し訳なくて……」
暫く黙していた華子はきっと目元を強くして絵里を見た。
「分かってる。わたしだって園子のことを思うと、胸が苦しくなる。でも、あの頃のわたしはどうしようもなくて……、園子が、憎かった。それがまさか、あんなことになるなんて……」
華子はゆっくりと呟いて、初めて絵里の前で顔を歪めた。
絵里は俯いて顔を背けた華子の背中に手を置いた。
思ったより華奢な肩先に震えを感じて絵里はハッとした。
結局、互いにそれ以上の言葉を発することが出来ないまま、小さく手を降って、二人は別れた。
邸宅を出て暗くなりつつある鬱蒼とした森を見上げた。
全ては謎のままだ。
しかし、これ以上、何を訊けばいいのか?
絵里は再び、あの忌まわしき過去の出来事を、胸の奥深くに封印することを選んだ。
けれど、園子の美しく、それでいてどこか淋しげな横顔を思い出すたび、心のどこかが痛くなる。多分、これからもずっと……。
けれど今更、何を思ってもどうしようもないことだと諦めて、ふとため息を漏らした。もう園子は戻らない。
その時、傍でガサガサと音がして走り去る足音を聞いた。
林の影にチラッと臙脂色の体操服の背中が見えた気がした。
まさか、ミステリー研究部のあの子達、まだ近くにいたのだろうか?
もしや先程の華子との会話をどこかで聞かれていたのかしら。
妙な胸騒ぎがした。
あの子達、三年生の星井さんともう一人、早、早、そうだ思い出した。早戸さん。
要注意な二人だわ、と絵里は思った。
でも、二人とも感じの良い生徒だった。ミステリー研究部だなんて、一体誰が顧問をしてるのだろう。
今度誰かにそっと尋ねてみようかな。
小径を歩きながら絵里はそんなことをふと考えていた。
終
この物語はフィクションです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
