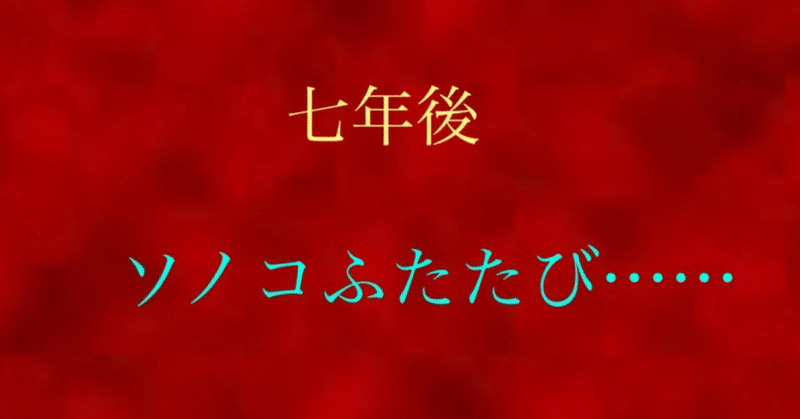
七年後、ソノコふたたび…… 後編
理事長室を出た絵里が、廊下の角でぶつかった相手は、園子にそっくりな少女、鈴木沙耶香だった。
「すみません。あっ」謝った沙耶香は右肩を押さえて顔を顰めた。
「肩を打ったのね、何を急いでいたの?」
「いえ、部活の練習に行こうとしてて……」
「そう、とりあえず、一緒に保健室に行って診てもらいましょう。部活の方は後でわたしからちゃんと説明するわ。これでも演劇部のOBなのよ」
沙耶香は頷いて立ち上がった。背の高さも園子くらいだ。
保健室で診て貰ったところ、単なる打撲らしい。骨折などしていなくて安心した。
「でも今日は静かにして落ち着いたら帰った方がいいわ」
「はい、ご迷惑かけてすみません」
「もう謝らなくていいから」絵里はすっかりしょげている沙耶香の手の甲の上に自分の手のひらを重ねた。
絵里の方も壁に背中をぶつけたので一応診て貰ったが、こちらは何ともなかった。丈夫に出来てるのねと笑った。
鈴木沙耶香は二つある簡易ベッドの壁際の方に横たわった。絵里は向かいのベッドに腰掛けた。
「ねえ、鈴木さん、いい機会だから、ちょっとお話ししたいのだけど、いい?」
「あ、はい、もちろんです」
「あ、その前にわたし、誰だか分かる?」
「お、丘先生ですよね」
「そうよ、知っててくれたんだ。良かった。それでね、突然変なこと訊くようだけど、鈴木園子という名前に心当たりない?」
「え? いえ、ありません」
沙耶香は唐突な質問に目を丸くして返答した。
「そう、私と同級生だったのだけど、親戚とかそんなんじゃないわよね」
「ええ、違います」
「そう、実は七年前、ここの学園に在籍中だった時、亡くなったのよ。あなたと同じ演劇部でね」
びっくりした様子。
「どうして、亡くなったのですか?」
「ちょっと、事故があってね」
「そうですか……」
「で、なんでこんな話をしてるかって言うと、あなたがよく似てるのよ。園子に」
「えっ? 私が?」
「似ているなんてものじゃなくて、そっくり生き写しみたいで、わたし初めてあなたを見かけた時、園子がいるんじゃないかとびっくりしてしまったのよ」
「え、そんな……」
「ああごめんね、いきなり変な話しちゃって、でも園子はあなたと同じでちょっと人目を引く程の美少女だったの」
「いえ、わたしはそんな美少女だなんて……、あ、でもそれでなのかな?」
「なあに、何か思い当たることでも?」
「いえ、そうじゃないのですけど、実はミステリー研究会の方がわたしに何か取材させて欲しいって、今度の日曜に家に来てくださる予定になっているんです」
「えっ、ミステリー研究会? 星井さん達ね」
「そうです。三年の星井さんともう一人メガネの……」
あの二人か、もう何か嗅ぎつけたのね、やっぱり油断ならない生徒達だわ。
「彼女たち、その取材の件、何か言ってた?」
「いえ、ただ、学校ではなくてお家に伺いたいって言うものですから」
「お家の方へね」つまり、身元調査かな?
「はい」
「そう、分かったわ。ありがと。じゃ、今わたしが話したことは気にしないでね。もうとっくの昔の話だから。さ、そろそろ私は行くから、今日は安静にして早い内に帰った方がいいわよ」
そう言って絵里は立ち上がった。
「いろいろすみませんでした。ありがとうございました」
沙耶香はベッドの上で上半身を起こして頭を下げた。
「いいから、いいから、じゃ、またね」
絵里は保健室を後にした。
それから一週間ほど後のこと、絵里は用あって体育館に出向いたついでに、裏の小径に出てみた。
ほんとだ、こんなところに小径があるなんて知らなかった。この辺りはほとんど人も通らない。ひっそりとした場所だ。小径はなだらかな坂になっており、そのまま森の奥まで続いて行くように思えた。
少し先まで歩いて見ると木々の隙間から空が見えた。そして、源財家の館がかすかに臨く、華子の部屋にあるバルコニーの辺り。
そうか、ミス研のメガネのツインテールの女の子、名前は何と言ったっけ、去年の秋、ここから森に飛んで行く大鳥(たぶんラファエル)と華子の姿を目撃したという。それはこの場所からだったのに違いない。もうこの先は大きな樹木に囲まれていて、そのまま森の奥へと入ってしまう。
しかし、華子はもう一年以上もラファエルの姿を見ていないと言った。あれはラファエルではない別の鳥だったということもある。でもそうじゃないとすると、隠しているのか、もしくは記憶違いなのか、定かではない。
そんなことに考えを巡らしていると、そのバルコニーにほんの一瞬、人影が見えて、すぐ消えた。
あれ? 華子だったのかな? 確認出来なかった。今は昼休み、華子の場合は常に理事長室に詰めている訳ではないから、自宅に戻っていたとしても、何ら不思議ではない。
反射的にあたりの空を見回してみたが、シマフクロウらしき大鳥の姿はどこにも見えなかった。
小首を傾げながら体育館の方へと戻る。大きな鉄製のドアを開けようとしたら、向こう側から外に出ようとした生徒と鉢合わせした。
「あら、あなた達」
「あ、丘先生、こんにちは」
ミス研の星井真実とツインテールメガネ、名前は……、そうだ、伊達マキ!
「何してるの? また調べもの?」
「いえ、そうじゃないんです。こうやって学園内のあちこちを回って歩くのが、私たち部活の一環で……」
「そうなの、ご苦労様ね。あ、ところで、あなた達、一年生の鈴木沙耶香さん、知ってるわね?」
「え、ええ、まあ……」
二人は急にもじもじし出す。
「鈴木さんから聞いたんだけど、何か取材に行ったとか」
「あ、はあ、はあ、そうでした。お聞きになりましたのですね。はい、行きました」星井が答える。
「それは、何故?」
「は? 何故と言いますと?」
「どうして鈴木さんを選んで取材に行ったの?」
あきらかに星井はドギマギし出した。マキは下を向いてる。
「いや、特に意味はなく、って言うか、あの子凄い美少女で、演劇部員で、なんか凄く才能あるって聞いてて、それで、ちょっと話を聞いてみたいな、ていう、それだけなんです」
「そう、ほんとにそれだけ?」
「え、そ、そうです」
絵里はふ〜んと呟きながら二人の周りをジロジロと見て回った。そこで質問を変えてみた。
「ねえ、星井さん、あなたの書いた論文、『春光』に掲載することに決定したわ」
「は、そうなんですか。ありがとうございます」
二人揃って深々とお辞儀をする。
なんだか、アーティスティックスイミングの選手みたいだ。微笑みたくなる。
「それでね、ひとつ訊いてみたいのだけれど、論文の中に七年前に事故死した生徒Sさんてあるでしょ」
「……はい」
「星井さん、あなた、Sさんを知ってるの?」
二人は明らかに不意を突かれてその場に硬直したように見えた。引きつった顔の表情も見事にシンクロしている。
この後、絵里の尋問により、星井真実の話したことの要点を絞ると、Sさんつまり園子の写真を姉の翔子が持っていて、それを見たという。当時園子が三年の時、星井翔子はまだ中等部だったのだが、園子は学園内では下級生達から憧れの的とも言われる程の有名人だったから、写真を持ってるくらいのことは充分に有り得る。そして、真実は当時の列車事故の件も姉から聞いたと言う。
鈴木沙耶香が園子に瓜二つであることは園子の写真を見れば一目瞭然だ。しかも同じ演劇部。そこに不思議な共通点を見出せる。ミステリー研究会が放っておくことはまずない。
絵里はミス研の二人が鈴木沙耶香と園子の間に何かしらの接点は無いものか、それを捜りに行ったと推測している。だから、その結果が知りたかった。
「それで、何か、分かったことは、あるの?」
絵里の問いに、二人は落胆の素ぶりを見せ、
「全く繋がりはありません。鈴木園子さんと鈴木沙耶香さんは他人の空似でした。演劇部に入ったのも単なる偶然のようです」と、やはり飼い主に叱られた仔犬のような顔をして答えた。
だからと言って、この子達が油断ならないことは絵里もだんだんと分かって来ている。何か隠し事をしていても不思議ではない。
けれど、ひと先ず今はこれくらいにしておいてやろう。そう思ってミス研の二人とはそこで別れた。
その日の放課後、絵里は三たび理事長室に出向いた。運良く華子は在室していた。
ほんの少し、世間話を交わした後、不意に絵里は本題を切り出した。
「ラファエルのことだけど、この前、私があなたに尋ねたこと覚えてる?」
華子はほんの少し思いを巡らすふりをして、
「最後に見たのはいつだったかって話?」
「そう、それ、華子は一年以上も見ていないと言ったけど、去年の秋頃に、見たのじゃない? もしかしたら、ラファエルじゃなくて、別の鳥だったかも知れないけど」
「去年の秋? どうして?」
「ミス研の子がね、体育館の裏の小径から見かけたらしいの、バルコニーに立つあなたと、飛んで行く大鳥を」
「体育館の裏の小径、そんなところから見えるの? 知らなかった」
「そう、それはわたしも今日の昼間、確認したわ。あなた、その時、自宅にいたのじゃない?、チラッと人影が見えたのよ」
華子は何か深く考え込むような姿勢でいた。その指先はほんの少し震えているようにも見えた。
「そうね、お昼休みは一度、自宅に戻ったから、あの時ね。それにミス研の子が見たというのが、去年の秋のことだというのね」
「ええ、そういうこと」
「じゃ、わたしの記憶違いだったわ、そうだったのかもしれない。でも、それが何か重要なことなの?」
「いいえ、そうじゃないの、最近、不思議なことが続いてたから、何か気になってて、あの一年の鈴木沙耶香って子があまりにも園子に似てたから」
「やっぱり絵里はまだ、ラファエルが園子の背中を押したと思ってるのね」
華子のド直球な指摘に、絵里は背中が冷やっとするのを隠せなかった。
「まさか! そんなこと、この前も言ったでしょ、そんなこと思ってないわ、思ってない、だけど……」
「だけど、何?」
「分からない」
そう何も分からない。分かったところで、それがどうなることでもない。けれど、気になってしまう。本当はどうだったのだろう。園子は自らの意思で自殺しようと列車に飛び込んだのか、あるいは何かに押されて……、あの星井真実が書いた『シマフクロウの生態について』という論文を読んでから、絵里の胸の中に一旦は深く鎮めたはずの疑問が、再び、沸々と湧き上がって来たのだ。
その時、理事長室のドアをコンコンとノックをして年配の男性がおずおずと入室して来た。学園の用務員をしている初老の男性職員で昔から絵里も華子とも顔馴染みだ。
「あ、お話中のところ、すみませんでした。理事長代理様宛に郵便物が届いておりましたので、お持ちしました」
「ああそう、ありがとう」
華子はそれを受け取ってチラッと表書を見てデスクの上に置いた。
用務員は、その場で一言二言、前理事長の様子を華子に伺って、その返事に安心したように部屋を出て行った。
一時は寝込んでいた華子の祖母も最近は室内や館の周りを散歩したり、体調は徐々に回復して来ているという。絵里もその話を聞いて良かったと心からそう思った。
さて、何の話をしてたんだっけ?
用務員さんのゆっくりで穏やかな物言いを聞いてたら、頭の中がポカンと真っ白になったみたいだ。
ふと、時計を見ると、もうこんな時間だ。
「ごめん、長居しちゃって、そろそろわたし行くわね。『春光』の編集がもう大詰めに近付いて来たから何かと文芸部も忙しいのよ」
「有能な部員さん達がいるじゃない」
「芥川さんと直木さんね。ほんとにあの子達には助かってる。だけど顧問として、ちゃんと傍にいて見守ってやらなけりゃね」
華子は嬉しそうに微笑んで見せた。
「エリは昔からそういったタイプだったわね。いつも傍にいて私を支えてくれてた」
「そんなこと」
「『春光』の発行、楽しみにしてるわ」
華子はそう言って絵里を送り出した。
絵里は理事長室から文芸部部室に続く長い廊下や階段、渡り廊下などを歩きながら、独り回想に耽った。
華子はわたしを信頼してくれている。わたしだって、華子を、でも、なんだか、今日の華子の様子はいつもとは少し違う感じがした。気のせいだろうか?
冷たく無機質に光る学園の長い廊下を歩きながら、絵里は何か小さな違和感のようなものを感じ始めた。
何だろう? いろいろなことが頭を駆け巡る。最近絵里の周りで起こった様々なこと、耳にした言葉の数々、深く考え込むような姿勢でいた華子の姿。震える指先、用務員さんの言葉、ミス研伊達マキが証言した去年の秋に見かけた理事長先生らしき姿という言葉。
何だろう? 何かが引っかかる。何か、わたし、とんでもない大きな間違いをしていたのではないだろうか?
用務員さんの言葉、そうだ、確か郵便物を持って来て……、理事長代理様宛……、そう言った。
華子が理事長代理になったのは二年前、だから今の一年生や二年生にとっては華子が理事長先生だ。
でも三年生はどうだろう。そもそも理事長が生徒の前に出て話をするのは入学式と卒業式の二回だけ。
すると三年生にとっては理事長先生というのは自宅療養している華子の祖母、源財芳子のことだったとしたら……。
ミステリー研究会三年生の部員・伊達マキにとっての理事長先生とは?
去年の秋、バルコニーに見た理事長先生と思われる人とは、もしかしたら……。
今日の昼間、体育館の裏の小径からチラリと見えたバルコニーの人影は、本当に華子だったのか?
そして、華子が子供の頃から親しくしているシマフクロウが同じように祖母である芳子にも懐いていたとしたら……。
シマフクロウは人を襲わない。けれど故意に人の手によって調教されていたとしたら……。ミス研星井の論文の言葉がよみがえる。
めまいがして頭がくらくらする。
学園の廊下や階段、教室、窓、天井などが渦となって迫って来る。そして、その中心から猛禽類の鋭い瞳が、今にも獲物を捉えようと……
絵里は声にならない悲鳴をあげてその場に蹲って両手で顔を押さえた。
ねえ、園子、教えて、あなたは何故、死んだの?
ああ、わたしにはわからない。
終わり
♡次回作予告
タイトル(仮)
『九年後、サヤカ……』
三年生になった鈴木沙耶香が高校生活最後の文化祭にて演劇部公演の主役として登場する。ところがその劇中に事件は起こる。
教師となって母校に戻って来た星井翔子と丘絵里はコンビを組んで事件解決に奔走する。
そして二人が見たものとは……⁉︎
発表時期未定 お楽しみに♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
