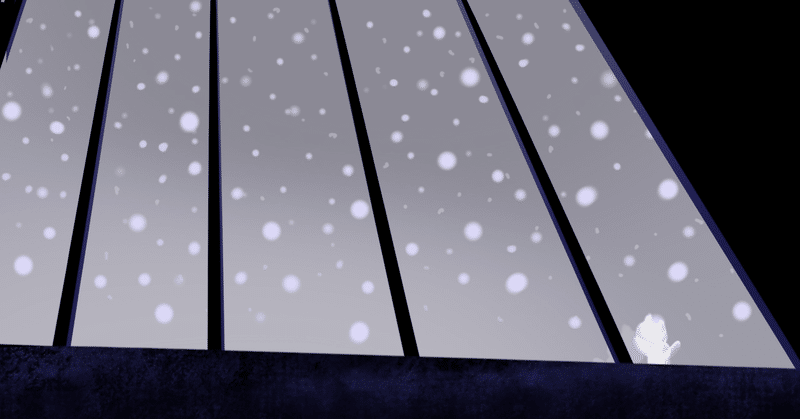
白銀の美しい世界と、雪をもとかす真心の交歓|柳家さん喬師匠「雪の瀬川」
柳家さん喬師匠の「雪の瀬川」を約三年ぶりに聴くことができました。
前回聴いたときにとても感動して、絶対にまた出会いたいと願っていた噺です。
記録を見ると、前回聞いたのは十月。
さん喬師匠の語る白銀の冷たい空気のなかに自らも身を置いていたような感覚があって、そんな早い時期に聴いていたんだなァと驚きました。
この噺は、年が明けて晴れの続く日和を過ぎ、ちょうど会のあった1月の24日前後のお話だったようで、今回良い時期に再会でき、とても嬉しかった……(旧暦だとずれてしまうかな)。
瀬川が吉原から脱け出し、忠蔵の家へと辿り着いた場面の描写が、息を呑むような美しい色彩の連続で。さん喬師匠ならではの風景描写の鮮やかさに、鳥肌が立つほどでした。
今回もその印象は変わらなかったのですが、噺の内容についても思うところがあったので、少し残しておきたいと思います(とはいえ長文芸人なので例のごとく長いです)。
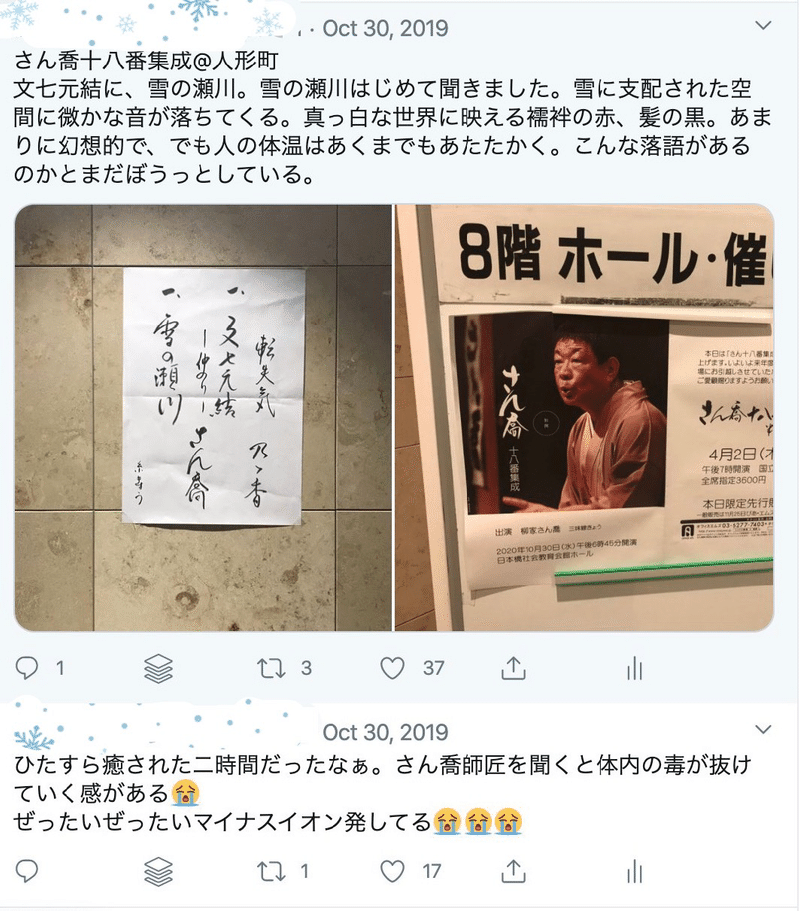
「雪の瀬川」あらすじ
このnoteの後半にも「松葉屋瀬川」のことを書いたけど、「雪の瀬川」はどうやら「松葉屋瀬川」の後半部分のみを抜き出したもののようで、さん喬師匠しか演じ手がいらっしゃらないそう。
さん喬師匠の美しい情景描写はここでは省きつつ、物語の筋書きのみ。
忠蔵と若旦那・鶴次郎の再会
古河の大店で奉公していた男・忠蔵(ちゅうぞう)。同じお店の女中であったお勝と恋に落ち、二人で駆け落ちして、現在は浅草界隈で屑屋を生業にしている。
ある日、忠蔵が永代橋に通りかかると、今にも身投げしようという若者が一人。声をかけてみれば、かつて奉公していたお店の若旦那・鶴次郎だった。
元々、実の両親が心配するほどの本の虫で、家に閉じこもっては本ばかり読んでいた若旦那。
親旦那の計らいで江戸へと出され、少しは遊びも覚えるようにと、番頭に色々と外へ連れ出されるようになった。そこで紹介された儒学者を名乗る崋山(かざん)──もとは生薬屋の若旦那で、放蕩の末に勘当され、今は太鼓持ち──の手引きで、吉原の花魁・瀬川に出会う。
すっかり瀬川に夢中になった若旦那は、半年のうちにあっという間に千両という大金を使い果たし、とうとう勘当になってしまった。
ただ瀬川に会いたくて会いたくて仕方がなくて、こんな思いをするくらいならもう死んでしまおうと思っていたと言う。
忠蔵は若旦那を長屋に連れて帰り、面倒を見ることにする。
忠蔵、吉原へ遣いに行く
若旦那が忠蔵の家に来てしばらく経った頃、金の工面のため瀬川に手紙を届けて欲しいと頼む若旦那。今や居候の身の若旦那を花魁が相手にするはずはないと忠蔵は戒めるが、若旦那は瀬川はそんな女ではないのだと語る。若旦那の言葉を信じた忠蔵は、吉原の太鼓持ち・宇治吾朝(ごちょう)の家を訪ねる。
若旦那が無事だと聞いて喜ぶ、吾朝とその妻。
聞けば、勘当になった若旦那の世話を引き受けたいのはやまやまだったが、太鼓持ちの家に身を寄せていたなどと知られてはかえって親旦那の不興を買うと遠慮し、仲間内で相談しているうちに、若旦那は行方知れずになってしまった。死んだのではないかという噂も流れ、瀬川花魁も吾朝宅でもすっかり気を落としていた。
若旦那からの手紙を受け取り、すぐに吾朝の家から吉兵衛という男が瀬川花魁の遣いに走り、花魁からの伝言を預かってくる。花魁の人となりは若旦那の語った通りで、若旦那の無事を知った瀬川花魁は涙を流して喜んだのだという。
雨の日の再会を約束する瀬川の手紙
後から届いた瀬川の手紙。一通は忠蔵の妻お勝へ礼を述べる手紙。もう一通はもちろん、若旦那宛。忠蔵の話も耳に入らず、夢中で手紙を読む若旦那。
「雨の日に瀬川がここに来るって」。──命がけの足抜きを仄めかした瀬川の手紙に、「瀬川が来ればそれでいい」と語る若旦那。二人は心中するつもりではないか? 忠蔵には嫌な予感が走る。そんな忠蔵の不安をよそに、ひたすら雨の日を心待ちにする若旦那。
大晦日も三が日もすぎ、晴れの日が続いて二十日ばかり経った頃、江戸の町に黒い雲が立ち込め、雪が降り始める。町を覆うように降り積もる雪を見た若旦那は、「瀬川、来るよね」とひたすら忠蔵の内職の邪魔ばかり。
夜も更け、町が眠りにつく頃。しんしんと雪が降り積もる中、サクッサクッと雪を踏み締める人の足音が聞こえ、忠蔵の家の戸が鳴る──。
偏見のない若旦那のまなざし
「雪の瀬川」に出てくる若旦那・鶴次郎は、落語でよく聞く勘当された若旦那像とは少し異なる。周辺の登場人物に身内はほとんど出てこないのだが、それでも驚くほど、出てくる人皆に深く愛されているのだ。
「本の虫」で、自らのことを「畳の上の水練」だったと語るほど、頭でっかちだった若旦那。
口ぶりだけは達者な人物が、出会う人皆からそうも愛されるものだろうか……となんとも不思議に感じたのだが、すべては噺のなかで語られていたように思う。
そのエピソードのひとつが、若旦那が忠蔵の家に居候し始めてからのこと。
居候の身にもなって、若旦那然とした態度が一向に抜けない。そんな自分を恥じて謝る若旦那に、忠蔵は、お店で奉公をしていた時分のことを話して聞かせる。
「若旦那、あなた、ご本家にいたとき、あっちのことをなんて呼んでいましたか。『忠兄ちゃん』『忠兄ちゃん』って呼んでくれたじゃあ、ありませんか。奉公人のあっちを『兄ちゃん』って言ってくださったじゃありませんか」
「ここは兄ちゃんの家ですよ。弟が兄貴に甘えるのは当たり前だ」
奉公人となれば、契約上、主人家とは当然主従の間柄である。ましてや封建制度下にあった江戸時代であれば、現代よりも身分に対する差別は厳しいはずだ。にもかかわらず、若旦那は一介の奉公人であった忠蔵のことを、身分で隔てることなく「兄ちゃん」と慕った。
店の跡取りだからといって、自らの身分にあぐらをかいて傲慢にふるまったり、身分や職業でその人の人となりを判断したりせず、ひとりの人間として人と向き合う、そういう気質が若旦那にはあったのだろう。
若旦那が瀬川花魁に手紙を届けてほしいと頼んだとき、忠蔵は最初、その言葉を真に受けなかった。商売で客を相手にしている花魁が、金のなくなった若旦那の力になるなどあり得ない。そう考えるのは、ごく当たり前のことである。
けれど、若旦那の重ねる「瀬川はそんな女じゃないんだ」という言葉で、忠蔵が若旦那の頼みを引き受ける気になったのは、彼の人が職業というラベルではなく、人そのものを見ていることを、忠蔵自身が誰より知っていたからだろう。
そして実際、宇治吾朝の家へと出向いて、忠蔵は若旦那の語ったことが確かだと知ることになる。
そればかりではない。宇治吾朝やその妻、遣いの吉兵衛までが心底若旦那の行く末を案じ、瀬川との恋路を応援していたのだ。
真心だけが交わされる世界
「雪の瀬川」に出てくる人物は、皆とても善い人だ。
若旦那の世話を引き受ける忠蔵やその妻のお勝はもちろんのこと、長屋の大家さん、瀬川花魁、太鼓持ちの宇治吾朝やその妻、遣いの吉兵衛さんにいたるまで、少しの打算もなく、誰かの力になりたいと奔走する。
登場人物がそれぞれに善良といってしまえばそれまでだが、物語の起点となる若旦那その人が、人のあるがままを受け容れることのできる人物だったから。だからこそ、真心が人から人へと連鎖していったように思えてならない。
若旦那と瀬川の恋も、そう。相手への要求や依存、打算もなく、ただ、互いに互いのことが好きという澄みきった想いだけが寄り添っているようだった。
なかでも印象に残っている台詞が、いよいよ勘当になったときに、瀬川が若旦那に言ったという言葉。
「私たちは好き同士なのだから、互いを好きという気持ちさえあれば、この先もどうにでもなります。だからどうかご両親を大事にしてあげて」
すでに記憶が曖昧になっているものの、たしかこの日は「私たちはいずれ夫婦になるのだから」ではなく、「好きという気持ちがあればどうにでもなる」という言い回しを遣われていたと思う。
酸いも甘いも噛み分けた花魁が言うからこそ、「好き」という想いの純粋さ、この想いを貫こうとする強さが伝わってくる。
そして、この想いは、ふたりを見守る忠蔵にも身に覚えがあったのではないか。
忠蔵にとって大旦那は、かつての自分の主人であるだけでなく、将来役に立つようにと字まで教えてくれた恩人だ。奉公人同士の恋愛が御法度だったために、忠蔵はその恩ある大旦那の顔に泥を引っ掛けるようにして、お勝と逃げて、一緒になった。
たとえ人の道から外れても、好きになってしまったらどうしようもないことを、この人も知っている。だから、若旦那の気持ちを否定することなく、力になってやる。雪の日の再会に「寒くないか」と抱き合う恋人たちを前に、何も言うことができない。
包みこむ雪のやさしさと、和解の雪溶け
冒頭にも書いたように「雪の瀬川」は雪の情景描写が主役と言ってもおかしくないほど、雪のモチーフに主眼が置かれているように思う。
雪は、遠くから見る分には白くて美しい。
翻って身近くなると、とても冷たく、生き物にとっては厳しい存在である。土足で踏めば、すぐに汚れてしまう、儚いものでもある。
けれど「雪の瀬川」で描かれる雪は、どこかやさしい。
雪ともなれば花魁の足抜きの道中は、より厳しいものになったはず。ところが、夜すがら降り続ける雪は、命をかけて鶴次郎のもとへと向かう瀬川を、再会した若き恋人たちを、追っ手から隠し、世間の疑いの眼や批判から守り、包み込んでいるようだった。
江戸の町を白く染めるように、しんしんと降りしきる雪が、鶴次郎と瀬川、ふたりの純愛をより穢れなきものへと昇華していた。
瀬川花魁が逃げてきたときの情景があまりに美しくて忘れられなかったのだけれど。雪がこんなにもやさしかったんだなぁと。二人を世界から隠すように、包み込んでいた。
— ゴリ李 (@akari_gorigori) January 24, 2023
身分違いの恋や、父子のわだかまり。人と人を隔てるものがとけていくことも含めての、雪の描写なのかと。素晴らしかった。
命がけの再会を果たし、土間に倒れ込むようにして互いのぬくもりを感じるふたり。この先のふたりの運命が気になるところだが、ここで一旦物語りは終わり。春になる頃には二人の関係が許され、晴れて夫婦になることを観客は聞かされる。
若旦那と、両親のわだかまり。
大店の若旦那と花魁の身分違いの恋。
ただ、互いに真心を持ち寄るだけではどうにもならない、人のあいだに立ちはだかる社会の規範や偏見。理想的なことを言えば、本来、人と人をつなぐのにそう重要ではないはずのものが、春になり、辺り一面を白く染め上げた雪が溶けていくのと同時に、消えてなくなる。ふたたび、心が通い合う。
この物語にとっての雪は、ふたりの穢れなき純愛と、そして融和のメタファーでもあったのではないかと、わたしは思う。
最後の一文までが、なんとも美しく、改めて聴いても見事な一席だった。
(おまけ)天どん師匠の「松葉屋瀬川」
ちょうどタイミングよく、天どん師匠が「松葉屋瀬川」をかけられている会があり、配信で拝聴しました。(※現在は配信終了)
この合わせ技により、瀬川の来る夜、忠蔵が家で内職をしているのは、紙屑屋は雨雪の日だと仕事にならないからだとか、その写本が『赤穂義士銘々伝』で、ここでも雪のモチーフが重なっているのだとか、「雪の瀬川」で(おそらく意図的に省略されて)捉えきれなかったディテールが埋められていきました。
なにより天どん師匠は、人情噺あるあるのご都合展開に、「都合よく」とか「なんだかな〜」とか、突っ込んでくださるのがいい。
若旦那が忠蔵に瀬川への遣いを頼むとき「普通だったらぶん殴ってる」と言ったり、太鼓持ちの吾朝の代わりに吉兵衛さんが使い走りに行ってくれるとなれば、「どんどん気のいい連中が出てくるのが、この噺の妙なとこ」と言ったり。
率直にご自身の感覚を投げてくれるところ、ある意味とても誠実だよなァって思いました。
いや逆だろという意見はさておき。
— ゴリ李 (@akari_gorigori) January 13, 2023
でもやっぱり、わたしの記憶操作という気もするので、これを機に色々な方の聞いてみたい。
個人的には、後半のトントン拍子っぷりにツッコミを入れてくれる天どん師匠のものが忘れられんw だ、だよねー!思ってたー!ってなったw
↑ 師匠の「文七元結」も、率直で、とても印象にのこっていた。
天どん師匠の新作聞いてみたいなと思ってるのだけど今回も古典。吾妻橋でのワチャワチャに、とにかく近江屋に帰って欲しがる長兵衛とマイペースな近江屋主人w 終演は21:15😂
— ゴリ李 (@akari_gorigori) November 13, 2020
結び、後に文七とお久が所帯を持って…の所で「よくわかんないんスけど」とぼやいたのには思わず「それな思ってた」と頷いた😂
私は文七が特別善人とも情の深い人間とも思っていなくて、娘のお久や佐野鎚の女将さんにそういう扱いを受けたから、だから吾妻橋でのあの振る舞いが引き出されたのだろうと思っているので、一貫して自分の言いたいことを主張してやりたいようにやる今日の長兵衛にはけっこう納得感があった🙃
— ゴリ李 (@akari_gorigori) November 13, 2020
(文七元結と聴いたときの感想。文七ではなく長兵衛と言いたかった…)
忠蔵の家に倒れ込むように、若い恋人たちが再会を喜ぶさん喬師匠の「雪の瀬川」。見守るのはただ忠蔵ひとりで、ふたりに掻巻をかけてやることもできずに立ち尽くしていました。
天どん師匠の「松葉屋瀬川」は、瀬川と若旦那が互いに雪のなか歩み寄って、抱き合うんですね。周りには、忠蔵のほかにも、太鼓持ちの崋山や吾朝、吉兵衛という影の立役者たちが見守っている。
前者はふたりの恋の切実さ、想いの深さを思わせるし、後者は、こうして周りの人たちが見守ってくれているならば、決して心中では終わらない、終わらせないという希望が見える。
いや〜。どちらもすてきでした。
* * *
今回改めて、自分が雪のモチーフにいかに心惹かれてしまうのかを実感しました。これは落語にかぎらず、昔からそう。
白銀に埋められた世界の美しさは、想像の上でさえ目を奪われる感覚があるし、雪の冷たさとの対比で、人間の吐く息や体温のあたたかさをより身近に感じることができる、その擬似的な身体感覚も好き。
そしてなにより、確かにそこにいたものを、まるで何もなかったかのように降り積もる雪が埋めていく──わたしにとっては、そんな無常観的カタルシスもあるような気もします。
雪の落語、もっと聴きたいな。そして、「雪の瀬川」どなたか引き継いでくださっている方はいらっしゃるのでしょうか。天どん師匠も、今はさん喬師匠しか他に演る方がいらっしゃらないと仰っていた。
若手の落語家さん、どなたかぜひ、この美しさを引き継いでくださらないものだろうか。噺が円熟するまでとても時間がかかろうとは思うけれど……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
