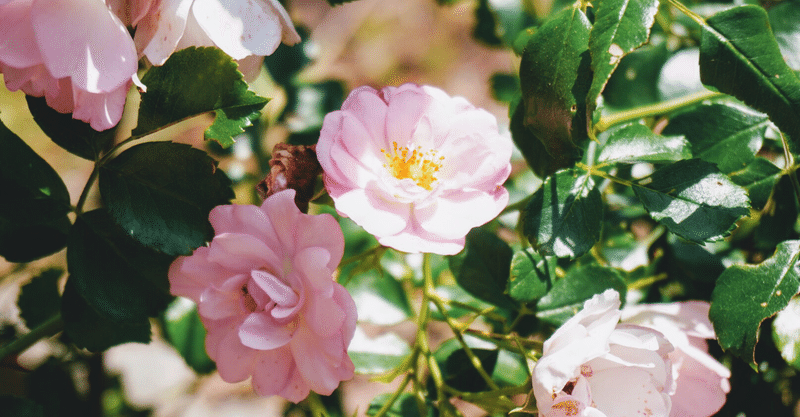
最初は童話からでした。
さて。
吉屋信子は少女小説! その後家庭小説! なんですが、実のところ最初に投稿で活字化されたのは童話でした。
そんでもって最初にまとまったのも童話です。
明治43年。まだ女学生の頃です。
で、当時の童話雑誌『良友』とか『幼年世界』に定期的に載る様になって。その辺りで浜田廣介から文章指導を受けたとか。
これがだいたい大正9年まで続くんですね。ちなみに「花物語」は大正7年から。平行してやっていた時期もあるってことです。
その辺りの研究は研究者の中では山田昭子氏がやっている…… くらい……ですな。この方の童話関係については、専修大学デボジトリにある学位論文にその辺りが詳しいんですよね。
ワタシは「通俗小説」中心で、こっちも少ないんですが、「童話」は更に少ない。つか単行本が確か4種類しか出ていません。初出探すのも大変な状態。つか吉屋作品ってのは大概そうなんだけど。
ワタシが入手して、現在は上記の氏の手元にあるのは二番目に出た作品集の『野薔薇の約束』と、戦後すぐの昭和20年12月発行の『てんとう姫の手柄』でした。あと『赤い夢』『黄金の貝』というのもあるようなんですが ……まあ手に入らないと思った方がいい。
『野薔薇の約束』(洛陽堂 大正9年3月1日発行)収録作品
1 野薔薇の約束
2 蒔いた鈴
3 茸の家
4 湖の蘆
5 赤い鳥
6 残された羊
7 光のお使
8 黄金の貝
9 魔法の花
10 湖の唄
11 鳩のお禮
12 鐘の音
個人的に思ったのは、冒険するのは女の子(「鐘の音」)やお后様(「黄金の貝」)で、少年が主人公の時には(「魔法の花」「湖の唄」)少女に助けられる、って展開だってことですね。
あとは基本的に擬人化された植物や動物。
『てんとう姫の手柄』(湘南書房 昭和20年12月20日発行)収録作品
・てんとう姫の手柄
・野薔薇の約束
・眼なし鳩
・光のお使
・姉妹と宝石
・あえ゛まりあ
・おばあさまの話
・小さい女王様
・三つの夢
・四つの木の葉
・紅雀の姉妹の話
・からたちの花
・おみかん
・大きい兄さん
で、こっちは初出が殆ど判らないんですが、最後の「大きい兄さん」に国民学校が出てくるところを見ると、吉屋の昭和戦前にあちこちで書いた話を時系列順にまとめたんじゃねえかな、って感じがする。最後がもう昭和16年より後ってことだし。
「おみかん」はみかんに対する「かわいいから丁寧にゆっくり食べる」的愛着とかの書かれた少女向けエッセイかな。「紅雀の姉妹の話」は姉は子供に好かれるのに妹は「男の子」に「空気銃で撃たれそうになった」という内容。「何でそんなことを」で終わっているけど。
「三つの夢」は「花物語」やその前段階の「七彩物語」に通じる登場する少女達が一人一人が語って行くという形のもの。「花物語」の「最初の七編」がオルコット(「若草物語」の作者)の「花物語」の「一人一人が自分の持っている話を語っていく」という形をなぞっている、そのやり方。
ちなみに吉屋は「リットルウィメン」という形で紹介したり映画の日本語版の監修もしていたな、確か。ともかく影響はある。
ところで「童話」と今ひとつ違うらしい少女が出てくる初期の短篇に「小さき者」というのがありまして。
これは吉屋が唯一『青鞜』に書いた話でして。……宮本百合子は「そんなものもあったわね」的な文章を書いておりましたが(青空文庫で発見したよ(笑))。
これがまあ、7つ程の尋常小学校一年生の女の子の話なんだけど、結構辛い。
どう辛いかというと、「空想好き」の女の子の悲劇なんですね。あらすじとか以下。
笹島ふさ子という子は小さい頃、事情があって里親に預けられた。戻ってきた時には母親にも、他の家族にも既に彼女に対する愛情も関心も無かった。
>寂しい痛ましい現実は、かくしてふさ子を苦しめ苛んだのでございます。その結果は、いつとしはなく、ふさ子は沈鬱ないぢけた子となつてしまひました。
で、小学校に入ったふさ子だけど、行儀はいいけど、先生に呼ばれてもどぎまぎして答えられない、という状態。そして空想に耽るようになったと。
>先生が教壇で熱心に教場内の小さひ生徒の焦点となつて黒板の前でお話をしてゐる時小さき異端のふさ子は、ただひとり空想の境地に身も心も委ねてゐるのでございました。
二宮金次郎の話の最中、彼女の目の前に浮かぶのは野原。その幻に没頭している時に、隣の教室からのオルガンの音が聞こえてくると。そのオルガンの音が彼女の耳には牧場の牛の鳴き声に聞こえて、思わず歌い出したと。
だけど先生に怒鳴られてはっとしてみると、彼女は実は「机の前に腰かけて、唄ひだし」ていた訳と。先生は「恐ろしい顔で睨めつけ」、周囲はくすくす笑い、ふさ子はただもう縮こまるだけ。先生は「立て」というけど立てない。竹の鞭で脅すけど机にかじりつくのみ。そして何度も竹の鞭で背中を打つと。で、立たせておくんだけど、この時の台詞がまあ当時というか吉屋というか。
>「ほんとうに、私んとこの笹島つて子の低能児には困り切つちまふの。あれほど、出来得るかぎりの力をそそいで補導しても仕方がないんですもの、ほんとに悲観しつちまふんですよ」
で、「うす寒い日」で「今にも雪がふりさう」なのにすっかりふさ子を立たせていたことを忘れて火鉢に当たっていたと。彼女を気遣ってくれたのは小使いの爺さんだけだった訳で。
で、彼女はふらふらと歩き出して、稲荷社の前で「可愛想な虐げられた自分自身の姿を、朧げながら、意識して、お稲荷様に切なる救ひを求め」る。
それから吊り橋を渡って以降とするんだけど、その河の音に誘われて、また「甘く香ぐはしい夢幻の中にいつしか吸ひ入れられて」行く。授業中の時の歌が口をつく。
>歌ひゆくにつれて、ふさ子の胸は楽しさに潤ふてゆきました。寂しく痛ましく暗い現実に小さい身を虐げられた幼い女の兒は、果なき人類の性の野に立ち微妙なる愛欲の階調を魂に芽生えさせて、自分の為に与へらるべき(愛)を求め探せども、そは空しき願ひに化してしまつたのでございます。そして、いぢらしい泪と悲しみとを小さい彼女は、いつぱい受けねばなりませんでした。愛を求める魂の何処にも持つて行き様のない、ふさ子は幻の世界に愛のいのちを自ら築きあげました。
で、最後の一行がこうなる。
>――ふさ子は、流るる水底に、美くしい愛に輝く俤をみとめました。幻から幻へ。
童話っーにはちと悲惨過ぎる最後ですな。いや、童話って当時の小川未明も浜田広介も結構悲惨か。
つかワタシこれを最初に読んだ時、「ハイジ」の「フランクフルト編」を思い出したんですよね。あれだ。ハイジがクララと一緒に勉強している間、アルムの山の幻を見て、知らず机の上に乗って手を振っている、っての。
ハイジはホームシックでそうなったけど、こっちの場合は何つかもっと切実というか、妙な実感がこもっているというか。
吉屋の初期は大抵救いの無いものを美文で綺麗にまとめて、そこに少女の哀愁だのが語られる訳だけど、まーこれはそれどこじゃねえ。空想好きのコミュ障の末路、って感じで本当に救いが無い。
だけど宮本百合子からしたら、
>伊藤野枝が引きついで満一年後の大正五年の新年、『青鞜』はその経営の困難をまざまざと語って表紙には何の絵もなく発刊された。寄稿の中に吉屋信子の稚拙な詩があるのも面白く、
(「婦人と文学」http://www.su-ki-da.com/aozora/search?query=cache%3Awww.aozora.gr.jp%2Fcards%2F000311%2Ffiles%2F2927_9212.html+%B5%C8%B2%B0%BF%AE%BB%D2)
と書いたりしているところを見ると、さほど彼女の中に印象が残らなかったらしい。
一方で吉屋自身は『自伝的女流文壇史』の中で「白いおでこの印象」という宮本百合子に関する文章を書いてるけど、吉屋は宮本を怖がっていたふしがある。つーかまあ、当然だと思う。
まあ吉屋がコミュ障とまでは言わないが、空想好きだったのは確かで、(まあだからこそあれだけのフィクションが書けたんだが)四谷の教会に通っていた時の証言の中にも
>後年、当時の吉屋信子について、ライダーに次いで寮監となった諫山イネは「あの方はとてもいい話をお書きになりましたが、生活や言語までが皆小説化されて人とかけ離れたやうな風でしたので、よく人に誤解されるやうなことがありました」と述べている。
古谷圭一『近代日本の戦争と教会 日本基督教団四谷教会史』さんこう社 2011.9 p102
というものがあったりするところから、例えばオタクが「普通に振る舞う」時に起きる微妙な一般人との差、「あ、これは同類だ」と判る時のシグナルが出ていたんじゃねえかと思ったりもしますわ。オタクとして!
というか、「小さな者」のエピはどうも妙なリアリティがあるんだよな。吉屋の文章の中では珍しいくらいに。
コミュ障っぷりは「屋根裏の二処女」の章子もそうなんだけど、あれは一応「そんな上手い話があるかい」と思いつつも救いがある。なのだがこっちは小さくてなおかつ救いが無い。
でももしこれを彼女にとっての「自然主義」として書いたものとして、それで『青鞜』の人々には認められなかったというなら、まあそういう時代だったというか、彼女にとっては不幸な時代だったというか。
それとも単にコミュ障「どころではない」時代だったというべきか?
その辺りは判らないんですがね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
