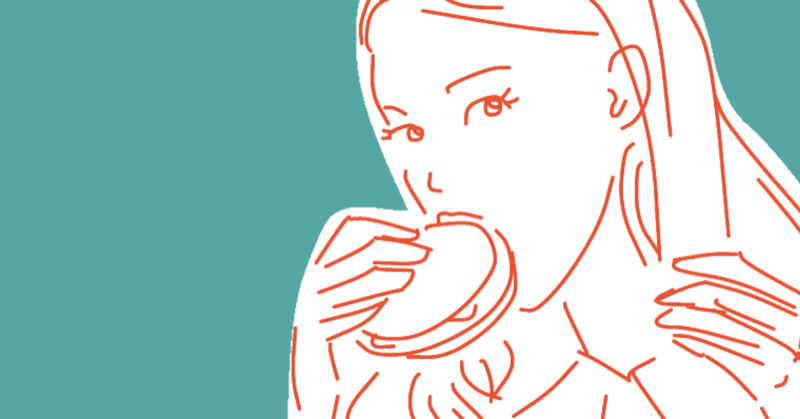
げてものはマンネリを救う?
今年の夏の初めのこと、
実家のある福島へ帰ったついでに、栃木の道の駅で、「いちごのカレー」なるものを見つけたので、自分用のお土産に買ってみた。

夫は怪訝な顔で「俺は絶対食わないぞ」と言っていたけど、そもそもあげるつもりはない。
私は、子どもの頃から、変わった食べ物やちょっとしたゲテモノが好きだったのです。
東北の田舎育ちなので、子どもの頃からイナゴとか蜂の子を食べていたからかもしれない。
台湾に行った時は、屋台で一人、豚の脳のスープを飲んだ。屋台の衛生面もさることながら、我ながらよくそのメニューを選んだと思う。(美味しかったし、腹もこわさなかった)
話は変わって、こないだ行きつけの美容師さんと、タコを最初に食べようと思った人は偉い、という話で盛り上がった(どんな話題や)
私は、その話をしながら、道端に生えているよく見かける草がニラに似てることを思い出し、あれって、もしかして食べれたりして、、という妄想を繰り広げていた。笑
現代なら、色々調べる方法もあるだろうが、昔は食べれるものと食べられないものを見分けるには実際口に入れるしかなかった。
だから、どんな食べ物も、最初に食べようとした人は偉大だ。死ぬかもしれないし、本当に毒にあたって死んでる人もいるだろう。
恐れより、好奇心や食欲が勝つ、そういう人がいつの時代にもいたということだ。
もし、私が大昔に生まれてたら、そうやって怪しいものを試し食いする職業(そんなのあるのか)になってたかもしれない。
煮たり、焼いたりして、どうやって食べれるのか、研究したりして。なかなか楽しそうである。死と隣り合わせということを除けば。。
そもそも、変わったものを食べたいという欲求は、一つの人間の心理という説もある。
近年、心理学・行動科学の分野で、ある仮説が提唱されました。「人は単純な食事には"飽き"を感じ、料理により変わったものであったり、“微妙なずれ“を求める」というものです。つまり、普段とは違う食事を食べることによって、いつもの食事では感じないちょっと変わったワクワクやドキドキを感じたいという欲求が、人の心理、すなわち人の脳に生まれながらに備わっているのではないかという説です』(「料理と科学のおいしい出会い」石川伸一著/化学同人)
残念ながら、この説は立証には至ってないようだが、私はまさに、食べたことのないものを食べる時、恐れよりも「どんな味なんだろう!」というワクワクが勝っているので、とても理解できる
。
もし、マンネリ化した日々に刺激が欲しいなら、あっと驚くような組み合わせで料理を作るといいかもしれない。
ワクワクドキドキが簡単に味わえるし、美味しくできたら、それこそ料理史に残るレシピになるかもしれない!
(どんなものができても、自分で責任を持って食べましょう)
ちなみにいちごカレーは、普通に美味しかったです。ほのかに感じるいちごの酸味がたまりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
