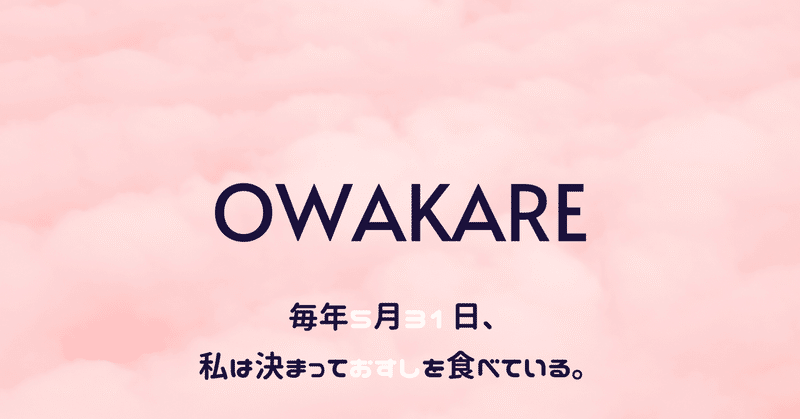
Vol.13 お別れ【毎年5月31日、私は決まっておすしを食べている。】
20歳まで生きれないと言われた兄にまつわる数々のストーリ。幼少期から順に連載しています。毎週土曜日更新中。
お別れに向けて
父と母がリビングでお通夜やお葬式について話している間、わたしは兄の頭を撫でたり、顔を摩ったりしていた。けれど、やっぱり彼はずっと穏やかに眠ったままだった。
少し経ってから彼氏やサークルの親友が様子を見に家まで来てくれた。その時は悲しくて泣くというより、心の中が空っぽになってしまった様で、むしろ何の感情もなく笑顔が作れた。
どこからともなく葬儀屋も現れ、「早速ですが...」とお通夜やお葬式のプランを広げていた。棺桶は、お花は、と決めることが多すぎて、家族が哀しみに浸る余裕さえ与えてくれなかった。「今はそっとしておいてください。10日後にまた来てください。」 できるものならそう言いたかった。けれど言われるがままに準備は進み、居間には着々とお通夜の用意が運ばれた。
続いて町内会の会長さんが近所の人達を引き連れてやってきた。石塚では、お葬式を町内会で仕切るのが古くからの慣しだった。決めることだけ決めたら、家族は無闇に手を出してはいけない。朝早くから夜まで色んな人が代わる代わる家に上がり込み、お茶出しやら会場設営やらを手伝ってくれる。
石塚の町内会はだいぶ高齢化していて、引越してきたわたし達が一番若い家族だった。近所の人達が、毎日手持ち無沙汰な様子で家に居るのは、正直心地良いものではかった。家主は「湯呑みはどこですか?」「お茶菓子ありますか?」と聞かれることに指示だけ出す。有難い一方、お年寄り達にやってもらうのも気が引ける。そして、手伝ってもらう人達に毎食お礼の仕出しを用意するのにむしろ手がかかる。伝統、風習とは概してそういうものだ。
お葬式の準備を進めていくと、父がはじめに「家族葬が良い」といった気持ちも少し理解できた。けれど、やっぱり兄は多くの人に見送られた方が喜ぶに違いない。
遺影には、同級生だった寿司屋の息子とツーショットで撮影した時の写真が使われた。寿司屋の息子は名前も同じく"まー君"で、幼稚園の頃から事あるごとに兄に会いに来てくれた。常に一緒にいる訳でもない付かず離れずの男の友情は傍から見ると不思議なもので、学校を卒業した後もずっと続いていた。写真の中の兄は自然体そのままの笑顔を見せ、男同士で少しだけ格好つけた凛々しさも漂う素敵な写真だった。
お別れ
お葬式当日。お経をあげてくれたお坊さんは父の同級生だった。親戚、第二第三の母達、兄の友人達、初恋のしのぶちゃん、園長先生、学校の先生達、寿司屋の一家、兄の折り紙ファン、引越し前に住んでいた近所のおばさまグループなど多くの人たちが、兄の旅立ちに集まってくれた。
園長先生は、会うなり涙を堪えきれず母と抱き合った。
「ちょうど久しぶりに、家に飾っているマー君のおりがみ作品を何気なく眺めていたところだったの。そしたら訃報が届いて...。マー君が知らせてくれたみたいだったわ。」
一階は居間もダイニングも親戚や町内の人たちに占拠され、二階の姉の部屋が家族の休憩所となった。父は合間を縫って時々タバコを吸いにやって来た。
「お父さん、大丈夫?お水飲んで少し休んだら?」
「あぁ、大丈夫。」
「喪主の挨拶も大丈夫?」
「あー、そうだな。少し考えておいた方がいいな。」
タバコをボールペンに持ち替えて言葉を並べようとした時、一階から誰かが父を呼んだ。その後も何度か二階にあがって来ては父が呼び出され、挨拶文は一向に完成しなかった。
「お父さん、挨拶は私が書いてあげるよ。」見かねた姉が買って出た。
「そうか。そうしてもらえると安心だ。」
いつも宴会隊長の父は、人前で話すことは得意だったけれど、今回ばかりは心の整理が必要のようだった。
「本日は、雅之の為にお集まり頂き誠にありがとうございました。故人も皆様に見送られ、喜んでいることと思います。生前お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。
3歳で原因不明の病に冒され...20歳まで生きられないと言われましたがっ、彼は......
彼は...24年の人生を、精一杯...、精一杯生き抜きました!
どうか、雅之がこの世で生きたことを忘れないでやってください。」
父は皺苦茶の泣き面で深々と頭を下げた。俳優顔負けのスピーチに多くの参列者が目頭を抑えていた。父が久しぶりに格好良く見えた。
*
お葬式がひと段落し、埋め尽くされていた居間にぽつりぽつりとスペースが空き始めた。最後まで残っていたのは、母を囲んでいた第二第三の母達だった。
玄関で見送るわたしにみんな口々に「お母さんのことよろしくね。」と託して帰っていった。
「うん。わかってる。」
“わたしも辛い” とは言えなかった。支えになってくれる彼氏や友人達にさえ、話を聞いてもらうより、ただただ独りで泣きたかった。
読んで頂いて、よろしければあなたが感じたこの小説の価値をお伝え頂けると嬉しいです。頂いたサポートは今後の出版&映画化活動に大切に使わせて頂きます。よろしくお願いいたします。
