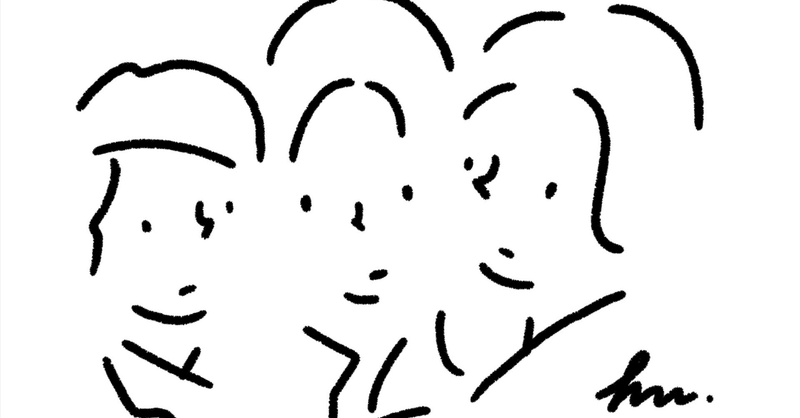
『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』 ちぐはぐなのは私か他者か
奇妙なちぐはぐさというか、違和感がずっと追いかけてくる本だった。
書いてあること全てが、限りなく正しくて説得的なのに、本質的なところを避けてぐるぐるしている。恐らく中心に、「直視できない認められない何か」がある。
我ながら失礼極まりないとしか言いようがないのだが、そういう感想を持ってしまう本だった。
『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』,ブレイディみかこ著,文藝春秋社,2021年
ひとつには、この本の前提となる「自分」「他人」というものが、あまりにも明瞭にくっきりと分離されていることに、違和感を覚えているのだと思う。
自分を大切にし自分を保ちつつ、なおかつ他人の立場を理解しその視点でものを考えてみる能力を常に磨き続けること。他人に同一化したり憑依したり否定したりするのではなく、「靴を履く」ということを繰り返すこと。それこそが良い社会を作っていくために不可欠である――というのが、この本がずっと叫び続けることで、逆に言うとそれしか言っていない本でもある。
その主張自体は極めてまっとうかつ、「分断の時代」にまさしく必要な指摘であろう……と思いつつ、しかし疑問から離脱することができない。
自分と他人て、そんな明瞭に、「靴を着脱する」主体として分かたれているものなんですかね?
私にとって、自己と他者は、もともとそこまで明瞭に区分できるものではない。
「自分」というものを掘り下げていくと、その一番奥の奥に最後に立ち現れてくるのが「他者」であるし、また逆に「他者」を追いかけて追いかけて最後に出会うものが「自己」である――というのが私の人生だった気がする。
そういう人間からすると、自己と他者を峻厳に分離してその上で「自らの靴を自由に着脱して他者の靴を履いてみよう」という主張は、言葉の上では限りなく正しくまっとうであると同時に、「絶対に嘘をつかないで生きていきましょう」並に実行不可能な、思考実験に感じられる。
★★★
本を読んでいて、もしかしたら、ブレイディみかこさんという方は、本当はものすごく「エンパシー」が苦手な人なのではないか、という失礼かつ勝手な想像が浮かんでいた。
多くの文献や思想家の論を縦横無尽に引き、エンパシーという概念を分析し危険性を解毒し必要性を明文化しようとする、この本の試みは……文章自体はこんなにも流暢で読みやすくて淀みがないのに、どこか学位論文を取ろうとプレゼンしている大学生みたいなぎこちなさを帯びている。
比べるのはおかしいのかも知れないが、たとえば上野千鶴子さんや北村紗衣さんがフェミニズムを語る時の、言わんとすること全てを自家篭中のものとしている感覚がない。指導教授の厳しい視線をにらみ返しつつ、論点をひとつひとつ指さし確認しているかのようだ。
ところが、「頑張って論文を通そうとする大学生」じみたところが全くなく、自由にのびのびとした印象を与える部分が、一章だけある。マーガレット・サッチャーの批判に費やした第4章だ。ここだけが、他の部分に比べるとめっぽう面白い文章になっていて、「魂がこもった人間の姿が描かれた」という感じさえするのだ。
この章のサッチャーは、残酷無比な「あってはならないもの」として描き出されているのに、強烈な生命力があって、アメコミの魅力的なヴィランのように躍動している。
対照的なのが、同じく「あってはならない政治家」として再三言及されるドナルド・トランプである。ドナルド・トランプは、エンパシーを利用することに長けたエンパシー搾取者だが、この本に描かれる彼の姿は、その恐ろしさに比して、生きている人間としての生気が全くない。悪霊か、単なる概念のようである。サッチャーの躍動感とは対照的だ。
もちろん、イギリスに住むブレイディさんにとってサッチャーは「わがごと」であるのに対し、トランプは所詮、「よその国のはなし」でしかない。どんなに欧米の距離が近く分かちがたいとしても、だ。
だから、単にそういう熱意の差に過ぎないのではという解釈が妥当だろうと思うのだけれど、しかし私はふと、とても失礼かつ勝手な想像をしてしまった。
ブレイディさんはサッチャーの姿に、強過ぎる自己を他者に力強く押し広げていく「リアルな人間」の姿――もしかしたら自分の弱点を、無意識に見ているのではないだろうか。
この章だけは、借り物の意見ではなくて「自分のことを書いた」のではないだろうか。
ブレイディさんはエンパシーが欠如したサッチャーは、自分の実感を持って「人間として」非難することができる。だが一方で、自他という区分にひそむ曖昧さの中を自然に無意識にただようことができる、「自己認識のバグを突くクラッキング能力の具現者」トランプは、ブレイディさんにとってあまりにもかけ離れた存在すぎて、人間として認識することすらできないかのようだ。
そういうクラッカーへの対処において、「自己をしっかりと確立して、そのうえで他者を理解しましょう」というド正面から対抗するやり方が、果たしてうまくいくのだろうか。
いやそれ以外まっとうな方法はないだろうという善良なる天使の声を聞きながら、その裏で悪魔が「闇に光を当てれば当てるほど、もっと闇がその暗さを増すだけなのさ」と嘯く声を、私のような歪んだ人間は勝手に聞いてしまうのである。
★★★
たぶん、ブレイディみかこさんにとっては、「アナーキー」という概念の方がずっとずっと自分のもので、大切な感覚なのだろう。
「女たちのテロル」から続く、金子文子への傾倒(というよりほとんど信仰)はこの本にも強く現れているが、ブレイディさんと金子文子は、強烈なまでの「自己」を自認していて、その自認が自明過ぎて、他者や他者の総体である社会との折り合いに、潔癖なまでのナイーヴさで臨んでしまう傾向が共通している。
ブレイディさんにとって「エンパシー」は、アナーキーという概念をうまく社会の中に着地させ自分が世を渡っていくための武器であり、本質ではないという気がする。
私の誤読だと非難されるだろうし、自分でもこの読み方が真実だとは思いたくないのだが、ブレイディさんは、自身とエンパシーという概念の間に溝があることを理解していないか、あるいは理解はしているのだが公に認めることができない、という状態なのではないか。
本当は「自分の中から出ているもの」ではないのだが、しかし役回りとして、私はどこまでもエンパシー概念の伝道者として振る舞わなければならない――という光景を想像してしまって、どうにも不自然さから逃れることができない。
唐突に金子文子という自分の信仰対象を持ち出してエンパシー概念を説明するくらいなら、もっと素直に、「エンパシーという概念は、外からやってきた概念なので、まず自分の信仰対象にひきつけて理解を試みてみます」と言ってもよかったのではないか。
個人的には、客観性を手放し、わからない中を手探りで進んでいき、最後にそれが完成形かどうかはわからないけれど自分の中で得た、「私が理解した、私なりのエンパシー概念」を明らかにする――という正直なスタンスで書かれたものを読みたかった。その個人的な営みの向こうにこそ、むしろ普遍性と客観性が開かれたのではないだろうか。
けれどブレイディさんの強くて明る過ぎる自己認識は、そういう自己韜晦の揺らいだ影などかき消してしまうものなのだろう。彼女にとって、アナーキック・エンパシーは「マイエンパシー概念」ではなく、あくまでも客観性を担保された、人類の問題を解決し得る大文字の概念でなければならなかったのだ。
そう求めること自体にある種の偏向があるのだ、という考える私の方が、たぶん歪んでいるのだろう。けれど、金子文子の持ち出し方があまりにも唐突なのに、その唐突さに対して全然疑問を感じていない書き振りからは、自分が履いている靴についてはスルーしてしまう何かを感じてしまう。
…と、長々と書いているこれは、読んでいる私個人が持っている葛藤を、本に投影しただけではないのか?という疑問は当然あってしかるべきだ。というか、自分でもそう思う部分がある。
私にとって自己と他者は、そんなに綺麗に分離できるものではないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
