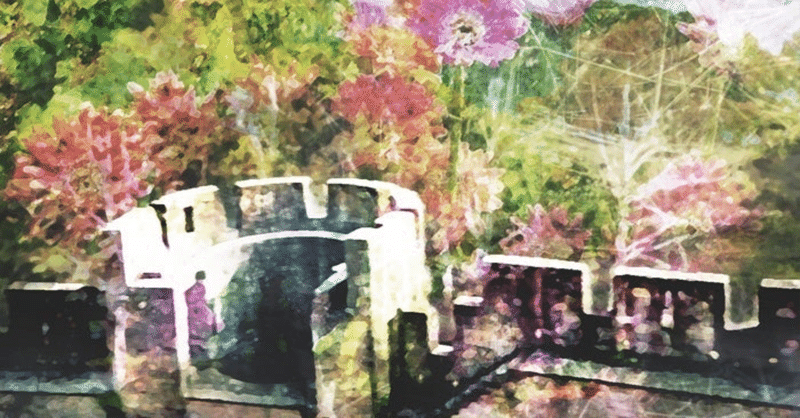
『ずっとお城で暮らしてる』
『ずっとお城で暮らしてる』,シャーリイ・ジャクスン著,市田泉訳,東京創元社発行,2007年刊行
皆の読後の感想が非常に似通うように見えて、それぞれ異なるものになる作品だろうと思う。
実際、色々な人のレビューを読むと途中までは似たような感想がつづられ、ある地点から不意に、少しずつ違うものを見出し始めるのが見える。人間の顔のように、同じなのに全部違う、そんな感想。
閉鎖的な村と、かつて砒素で家族が皆毒殺された、村外れの名家の生き残りの姉妹と老人。姉妹と老人の持つ狂気。そして彼らに恐ろしいまでの憎しみと嫌悪と嘲笑を見せる、村人たち。語り手たる姉妹のうちの妹メリキャットが、典型的な「信頼できない語り手」であるために、どこからどこまでが実際に存在した悪意と犯罪だったのかはわからず、全ては誤解と被害妄想だったという極北も含めて、様々な解釈の幅がありうる物語だ。
「ふつうの人間」「善良な人間」の抱く邪悪と狂気。それらを描いた、心理的な恐怖小説。というのが、一番正統的な感想で、それはたぶん正しい。
けれど私には、この物語は恐怖の物語ではなかった。狂気はどうかと問われれば、それは立ち位置次第という気がする。
私が恐怖を全く感じなかった理由は簡単で、この物語の中に、理解不能な部分がなかったからである。むしろ、わかりやすい物語、という気がした。様々な人間の性質が、全て悪い方へ噛み合わさっていってしまって、引き返せない状態にすでになっており、こうなるしかないだろうという結末に流れ込んでいくという感じだった。
そういう意味では、この作者の人間に対する理解と、私のそれが、たまたま似ていたのかも知れない。
私の受け取った物語を蛇足を承知で説明すれば、この物語はメリキャットの心象風景を描いているという意味で完全に事実に正確ではないけれど、信頼できない妄想というほどあやふやでもない。
というより、そもそも妄想とは、土台のないところに楼閣を出現させるような曲芸ではなく、ある勘所をつかめばむしろ解釈するのは容易い(解釈することが状況を好転させるかどうかは別として)ことさえあるものだ。
メリキャットが家族を毒殺した理由は、サマー・ハウスでの「家族の声に耳を傾ける」場面で明確に語られていると思う。家族たちが「最愛の娘」とメリキャットを讃え、お仕置きなどしないとうやうやしく語る光景は、現実に彼女が夕飯抜きのお仕置きをされている以上、わかりやすい陰画として見るほかなく、かつて彼女が家族の中で爪弾き者であり、虐待かどうかは微妙としても、少なくとも愛情を向けられなかったことをストレートに伝えてくるのだ。
そしてかなり解釈というよりも想像の領域の話だが、その愛情の欠落(あるいは虐待)の中心にいたのは、実はメリキャットが誰よりも憧憬するコンスタンスではないかと思う。悪意というよりも、コンスタンスは、良妻賢母かも知れないが根本的に他人を理解するとか思いやるような感受性が、あまりなかったのではないだろうか。
だがメリキャットにとって、コンスタンスは憎むことが決してできない世界の中心で、それがゆえに彼女に向けられてしかるべき敵意は他の家族全般に拡散され、「姉さん以外は皆殺し」という行為に至ったのではないか。そしてコンスタンスが、「私が全て悪い」と言い、メリキャットの犯行を隠蔽してしまったのは、それを薄々わかっていたからではないのか。
そう私が想像するのは、こういった家族の感情のもつれは、意外と外から見て原因らしい人が原因ではないパターンがあり、「最も犯人らしくない人が犯人」だったりするからだが、これについてはさすがに、私の勝手な想像である。普通に考えれば、コンスタンスだけがメリキャットにある程度の愛情を向けてくれたから、メリキャットが殺さなかったというのが「一番ありうる状況」だろうとは思う。
ともあれ、メリキャットの言動は、あるポイントから見るととてもわかりやすくて、不条理なところが全くない。それゆえに、恐怖は覚えない。狂気というのすら、微妙に違うように感じられる。最終的には彼女と暮らすことを選ぶ、コンスタンスの心もまた。
★★★
不条理なところがないというのは、ある意味では、不条理すぎるように見える他の登場人物たちにも言える。底流の法則さえ見えれば、とてもわかりやすくてアルゴリズム通りに見える人びと。
自らが殺されかけた一日にしがみつくことで生きる意味を見出そうとするジュリアン叔父。
いじめが高じて火事をきっかけに狂躁状態になり、燃え上がる屋敷を強姦のように蹂躙してから、後に「我に返って」それを詫びに来る村人たち。
完全に善意だが、善意というものが相手に受け取られるまでに時間がかかることを認識しておらず、忍耐がないために迷惑な隣人になる、ヘレンやレヴィ医師。
金目当てにコンスタンスに近づき、そのくせ彼女を助けられなかったことを悔やむ片鱗を見せる、典型的俗人のチャールズ。
メリキャットという人物に、こういう人びとがこのタイミングでこのように交錯してしまったら、こういう破綻を迎えるしかないだろうと思う。誰かが特別に悪いとか、特別に間違っているというのでもない。この物語の結末は、予想通りというのとも少し違うけれど、こうなるしかない印象を与える。
常識的には幸福とは言いがたい結末を、しかし不幸とも呼べず、さりとて祝福するのもはばかられるのは、この帰結が「こうならざるをえない」安定性を持っていて、それでいて本当は何も解決できていない(何が「解決」なのかはまた難しい話だけれど)からなのだろう。
長々書いてしまったけれど、この物語は、不条理な恐怖小説とは私には思えない。わかりやすい、不可解なところが何もない、心象風景をつづった物語だと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

