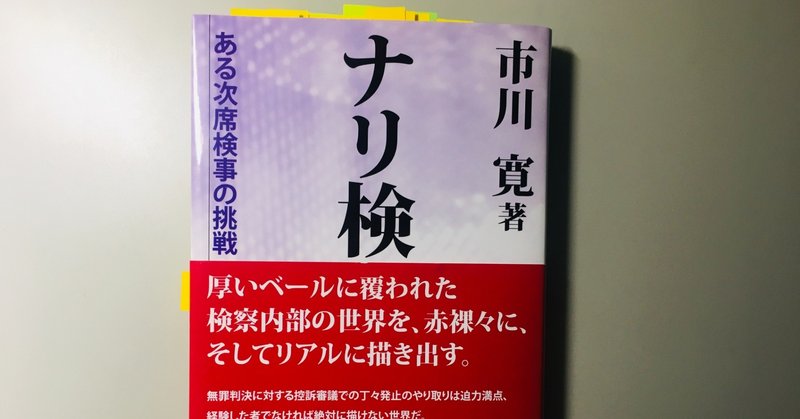
『ナリ検』市川寛(日本評論社)感想
市川寛先生の小説デビュー作『ナリ検』読了。耳慣れない言葉だ。ある登場人物いわく、
「検事を辞めて弁護士になる『ヤメ検』はいくらでもいるが、君のように弁護士から検事に転じた人は、まず聞いたことがない。いわば弁護士から検事になった『ナリ検』だな」
主人公は、”事実上の凍結状態”にある、弁護士が検事に任官する制度(と、とある裏技)を使ったナリ検の中年男性。
ある理念を抱いて検察に飛び込んだ彼が、次席検事として着任したばかりのS地検で、部下である三席検事が担当した公判で無罪判決が出る。あくまで被告人を犯人と信じる三席は控訴を望み、控訴審議でも上司など周囲がみな控訴を支持するなか、被告人を無罪と考える主人公は、無実の人を冤罪から救うべく、孤立無援の闘いを始めるが――というお話。
とにかく検事にまつわる「リアリティ」が圧倒的だ。
控訴審議の場で、証拠開示を巡って、三席は主人公に畳みかける――
「こちらがどんなに公平公正な視点で調書を巻いても、反対尋問でその調書の信用性を落とそうと粗探しするしか能がない。それが弁護活動の実態です。(中略)検事はしっかり捜査して、ある証拠が有罪認定にマイナス一の価値しかないと正しく評価しているのに、それをあわよくばマイナス二や三、いいえ、マイナス九や十に仕立て上げようとする。挙げ句の果てには被害者を吊し上げることも厭わない。弁護人はそうやって証拠を破壊しているではありませんか(後略)」
ご存知の方はご存知のように、作者である市川先生はご自身が検事経験のある弁護士さんだから当然、なのかもしれないが、本作は「検察のリアル」を描いただけの小説ではない。
作者はナリ検の主人公にもこんな風に反撃させる――
「刑事訴訟法一九六条が弁護人に『捜査の妨げにならないように注意』しろと命じているのはなぜだと思う? 捜査の結果得られた証拠は弁護人も使うことになるから、証拠を破壊するような捜査妨害はするなと戒めているんだ。証拠は我々法律家の共有財産なんだよ。なのに証拠を独り占めして、それにアクセスできない弁護人をせせら笑う。そんなアンフェアな仕打ちをしておいて、法律家として恥ずかしくないのか。検事なんて、ハンディキャップをもらっておきながら、それに気づかず『勝った、勝った』と喜んでいるだけの子供じゃないか。検事こそが有罪方向の証拠だけを出して、裁判所をたぶらかしているじゃないか」
笑ってしまうほど辛辣な検察批判。
市川先生の前著『検事失格』(新潮文庫)を読んでいれば、作者がなぜこのような主人公を設定したのか、想像できる。『検事失格』は、現在は弁護士(主人公とは逆のヤメ検)である市川先生が、ご自身の検事時代の体験を綴ったノンフィクションだ。あまりにも赤裸々に「検察のリアル」が描かれ、ここまでぶちまけてしまって大丈夫なのか、と一読者として心配になったほどだ。
だが、検察のあり方に関して疑問を投げかけるこの本も、組織を告発する内容には終わっていない。『検事失格』という衝撃的なタイトルは、検事として自らの理想をまっとうできなかったご自身の悔恨を込めたものなのだ。
『ナリ検』の主人公は、「あるべき検察」へと組織を内部から変えるという理想を抱いて弁護士から検事になった。市川先生ご自身の理想を持つ、いわば分身のような存在なのではないか。前著で描かれた痛恨が、今回、理想へ向かって進む主人公の原動力となっているのは間違いないだろう。書き手が本当に書きたいことを書いているという熱気のようなものが、本作の小説としての疾走感につながっていると感じた。
同時に、理想を実現するための主人公の闘いが本作のメインプロットでありつつ、「検察=悪」という単純な勧善懲悪にしていないところも本作の魅力だ。
主人公は猪突猛進に突き進むのではなく、何度も自らの正しさを疑い、迷いながら一歩ずつ歩んでいく。周囲のすべてに対して、感じすぎるくらいに感じてしまう繊細な人物であり、父親との確執に悩む弱さや、ピート・タウンゼントを愛するギタリストで(学生時代、バンドで学際に出た際、ウインドミル奏法で右手がブリッジに激突して、派手に出血しながら演奏したといいうエピソードはやけにリアルだ)、トミー(!)という愛猫を飼う人間臭さもある。
不思議なことに、中年男が主人公なのに、どこか青春小説を思わせる爽やかさが全編に漂っている。物語は、この主人公ならではの結末を迎えるが、それがどんなものかはぜひ本を手に取ってご自身で確かめていただきたい。
最後に、ここまで一切触れていなかったが、本作には印象深いヒロインも登場する。主人公と対立する三席検事・平戸薫だ。めちゃめちゃ優秀で、主人公が舌を巻くほどの切れ者。デレのないツン。彼女が非常に魅力的で、実写化するなら誰かなー、なんて考えてしまいました。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
