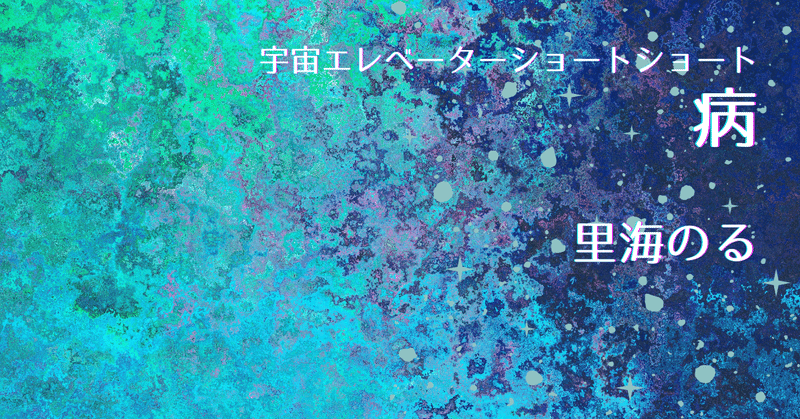
【3分ショートショート】病
「あれに息子が、乗ってるんです」
展望窓の外を見つめたまま、その老女は目を細めた。
地球に向かって伸びるケーブル上で、太陽光がキラリと反射する。遠くてはっきりしないが、編成の長いクライマーのようだ。
「貨物便、でしょうか。息子さん、クライマー乗務員なんですね」
「ええ」老女はかすれ声で答えた。「初仕事、なんですよ」
もしかすると、見た目の印象ほどには老齢ではないのかもしれない、と介護士は思った。痩せた全身を包む外骨格スーツと骨張った口元を覆う酸素マスクからそう思いこんでしまったが、わずかに露出している肌には張りが感じられるし、血色がよくないように見えるのは青い地球光を浴びているせいだろう。
「展望室には、あまりいらっしゃらないのですか」
まだこの介護療養施設に配属されたばかりで、入所者の顔も名前も覚えきれてはいない。この女性もはじめて見る顔だった。
女性は視線を外に向けたまま、ええ、と答えた。
「できるだけ、目に入らないようにしていたから」アシストモーターの軽やかな作動音とともに窓に手を伸ばす。「でも、懐かしい」
静止軌道ステーションは無重力なので、ここには重力から逃れなければならない人たちが入所していた。地球からは重度の心臓病や過度の肥満のためにQOLが著しく低下した人が来ていたし、宇宙からは長期におよぶ無重力の影響で地球や月に降りることができなくなった人が来ていた。だがこの女性は、どちらの典型とも違って見える。地球からの人が外骨格スーツを使うことは希だし、宇宙からの人はたいてい太っている。痩せているということはおそらくあの病気だろうが、なぜこの施設に入所しているのだろう。
「地球にいらしたことが、あるのですか」
女性はしばしの沈黙ののち、ぽつりぽつりと語りはじめた。
――出身は地球。若い頃は宇宙エレベーターの海上ターミナルで洋上勤務をしていて、そこでのちに夫となるクライマー乗りと出会った。夫と結婚し、息子が産まれてからは、家族三人で宇宙船暮らし。それも地球近傍ではなく、木星のトロヤ群小惑星のような深宇宙を回り、地球に戻ることは一度もなかった。生活は苦しかったが、家族で力を合わせ、なんとか暮らしを立てていた。夫は懸命に働いたし、家事もこなしてくれた。とくに息子の教育には熱心で、その甲斐あってか宇宙船育ちの息子は、一度も対面の学校に通ったことがないにもかかわらず、静止軌道ステーションの大学に合格することができた。
「いい旦那さんだったんですね」
女性は微笑んだ。「そう見える、でしょうね」
――息子が寮に入り、夫婦二人での宇宙船暮らしが始まってすぐに、夫は体調を崩した。船内の限られた医療設備ではどうにもならず、静止軌道ステーションの病院で診てもらおうと説得したが、頑なに地球圏を避け、そのまま帰らぬ人となった。気にかけていた息子とも、会えず仕舞いだった。
「……そうだったのですね。お悔やみを申しあげます」
「ありがとう」と短く礼を言い、女性はつづけた。
――夫の死後もしばらくは、ひとりで宇宙船を飛ばしていた。ひとりは寂しかったが他にできる仕事もなかったし、夫との思い出が染みついた宇宙船から離れるのは忍びなかった。しかし気がつくと、自分も病気になっていた。病院で診てもらうと、ステージ4の癌が見つかった。
「手の施しようがない、と告げられたわ」
「それは……なんといったらいいか」
女性は目を伏せた。「よくあることよ」
――できることは緩和ケアだけなので入院するまでもないのだが、息子が心配して、この施設を手配してくれた。そして、費用は自分が持つと言って聞かない。
「父親譲りなのか、頑固なの」
「いい息子さんですね」
「ええ」女性は目を細めた。
――地球を捨てるように出ていったのに、戻ってみるとやはり心が惹かれてしまう。両親はすでに亡くなったが、親戚や古い友人は地球にいる。宇宙船暮らしと違って、ここではほぼ遅延なしにお喋りもできる。もはや地表に降りたつことはかなわないが……。
女性は視線を窓に向けた。
「でも、地球を目にしてしまうと、もう一度あの潮風に吹かれたい、と思ってしまうの」
眼下の青い海に雲が白い渦を巻いている。
「この歳でホームシックだなんて、可笑しいわね」
そう笑う瞳が、涙で潤んでいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
