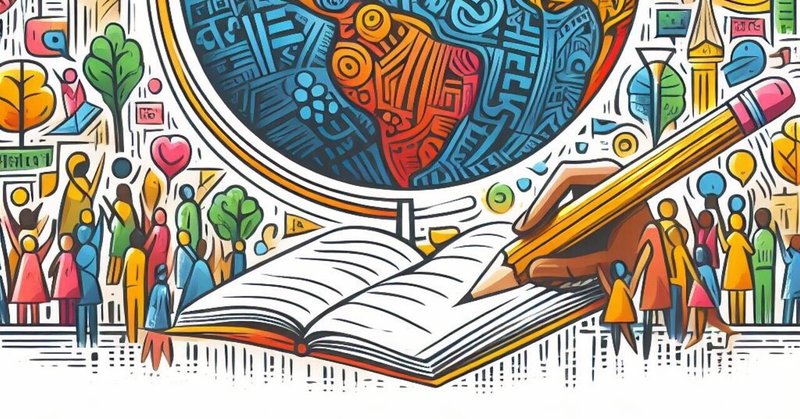
ナラティブとクリティシズム(2)(2023)
3 物語の氾濫
身分や階級が国民へと集約されたように、近代では散文ジャンルが小説に標準化される。近代小説はその意味において体系の文学と呼べる。それ以前に存在していなかったにもかかわらず、小説は文学の主権が自分たちにあると主張する。とは言うものの、小説は自ら根拠付けなければならず、批評はその代理人として社会に訴えなければならなくなる。
等身大の人物が文学の主人公たり得るのはその内面性にある。さもない人物であっても、内面にはドラマがある。近代は公私の区別が原則とされている。私の領域である内面は自分だけのものであり、公が干渉することは許されない。近代小説はこの公私の区別に則っている。それは、取り扱い方こそ客観的=写実主義であるが、内面に関しては主観的=心理主義である。公の部分は客観的、私の部分は主観的に描かれる。登場人物は読者と同じ普通の人間である。心理描写を通じて読者は自分のことが描かれているようだと彼らに共感する。
こうした主観性指向の近代文学を評価する批評としてエッセイが求められる。それは主観性に基づく形式である。作品は作者の自己表現であるから、内面を明らかにすることが重要である。作者の意図に焦点を合わせ、それをもたらした伝記的事実を立証する。作家はある時代の社会を生きている。作品にもそれが反映する。作者の内面は主観的、伝記的事実は客観的で、その相互性が作品である。批評はそこから子の文学活動の社会的意義を論じる。
しかし、モダニズム文学の登場は創作を自己の表現から表現自体へと関心を移動させる。それに伴い、作者の願望を反映しやすいロマンスが現代小説として復権する。ただ、先祖返りしたわけではなく、ジャンルの多様化をもたらす。近代小説の経験を踏まえて、SFやミステリー、アドベンチャー、ファンタジー、ホラー、サスペンス、ヒストリー、ピカレスクなど新たなジャンルが誕生したり、古いものが復活したり、融合したりする。実際の価値観の多様性や権利としての物語は現代小説の出現以降に顕著になっている。
現代文学の登場人物や語りは抽象的・一般的な近代人ではない。それは具体的・個別的な現代人である。彼らは多種多様な歴史的・社会的背景や個人的事情・特性を持っている。主観性指向の近代文学と違い、複雑化・専門化・細分化した思想状況も反映して現代文学に標準的なモデルを見出すことは困難である。
現代は近代の批判的発展だ。方法の文学であるモダニズム文学は近代文学の急進的あるいは批判的な前衛主義である。近代文学の理念を過激に推し進めようとしたり、それが抑圧・隠蔽してきた世界を露わにしたり、前提にしてきた社会が変動し現実にそぐわないと異議申し立てたりする。しかし、しばしば写実主義や自然主義と比べて、ヴァージニア・ウルフやジェイムズ・ジョイス、シュルレアリズムが端的に示しているように、難解である。そのため、それが現代社会においていかなる意味を持つのかを解説する批評が必須だ。現代の文学理論の走りとも言うべきロシア・フォルマリズムが言語学の影響を受け、モダニズムの1910年代に登場したことは決して偶然ではない。のみならず、作家は精神分析や存在論を始めとする批評の提案に基づく実験的な作品も創作していく。現代文学は創作と鑑賞において批評が共通基盤を提供する。批評も作者の意図に焦点を当てる必要がない。「作者の死」を宣言し、表現自体を論じるようになる。その際の論拠はすでに広く認められている諸理論である。記号言語学の他、マルクス主義や精神分析、フェミニズム、ポスト植民地主義、脱構築などアカデミズムで共有されている理論がその批評の主張の妥当性を保障する。
すでに述べた通り、リオタールはポストモダンの特徴の一つとして「大きな物語」の終焉を唱えている。それはマルクス主義を含む近代思想の信頼性の失墜である。しかし、近代思想は体系づけられ、社会を理論的に基礎づけている。近代社会は、前近代と違い、人為的である。近代思想の不信や無視はその根拠を危うくする。噴出した「小さな物語」は概して恣意的で、グロテスクでさえある。この氾濫の中、批評への関心が弱まる。恣意的な物語の正当化に検証可能な理論など必要ない。しかし、批評による相対化を失った物語は自己絶対化に陥る。
こうした時代の下、批評においてジャーナリスティックな姿勢が後退し、アカデミックさが前面に出て来る。それは批評と言うより、研究である。 批評も近代を基礎づける理論体系に基づいていなければならない。作家は同時代的社会を生きているので、その作品がそれを表象すると自明視する。しかし、近代は「社会の中の文学」の時代である。文芸批評はアカデミックな方法論を利用してテキストを論じるだけでは不十分である。そこに、「今なぜこの作品なのか」や「なぜ今この作家なのか」、「今なぜこのトピックなのか」というジャーナリスティックな問題設定が不可欠である。過去の作品や作家を扱う場合も同様である。批評はそういった暗黙知を明示化するメタ認知を提示する。
批評の衰退と物語の氾濫が90年代以降の状況である。2000年に映画監督の小栗康平は、『映画を見る眼』において、現代日本社会には物語が氾濫していると次のように指摘している。
前の章で、「埋もれ木」は二つの物語がパラレルに進んで行くと書きましたが、映画の中で女子高生たちが作る架空の物語は、劇中劇に近いものです。映画という劇の全体を括るだけの、単純で強い物語は「埋もれ木」にはありません。あるのは映画の登場人物がつくるゲームとしての物語、これはいわば言葉遊びといってもいいものですから、人物そのものを語る物語にはなりません。過去にどんなことがあり、それが今、このことにこうつながっているという因果関係、起承転結をもたないのです。
劇中で、「物語は乗りもの。私たちはそれに乗って、ただ生きているだけ」「でも、選べるのかなあ、その乗りものって」「だって、物語は、ことば、だから」といった会話がやりとりされます。もちろん私たちは、言葉だからといって自由に、自分の物語をじっさいの人生の中で生きられるわけではありません。女子高校生のそれはロール・プレー イング・ゲームと同じことです。
しかしこのゲームは、ゲーム・マスターがいて、ある約束事のもとにという限定があるにしても、物語の展開はプレーヤーのそれぞれにまかされています。映画のシナリオはストーリー・テラーとダイヤローグ・ライターが別な人でも問題ないのに、小説では地の文と会話とを別な人が書くことはない、そういいましたが、このゲームは映画的な物語のつくりに似ている、そういえるかもしれません。ゲームや漫画から小説、映画が作られたりしていることを考えると、こうした手法がさまざまな物語づくりにまで持ち込まれるようになった、そうもいえるでしょうか。
ここには二つの問題があるように思います。一つは、世の中のいたるところで物語が過剰にあふれていることと関係する事柄です。しばらく前から大ヒットしたパチンコの機種名は「海物語」です。もちろん、パチンコ屋さんでドラマを追うはずもなく、ただCGでつくられた色とりどりの魚が動いているだけのものですが、物語というネーミングになにやらロマンを感じたことも、この機種をヒットさせた原因の一つではあったように思います。
世の中が物語を欲しがっている、ということなのでしょうか。結婚式の披露宴で流される新郎、新婦のなれそめをつづる映像。ナレーションで語られるのは赤い糸で結ぼれていた運命の山会いです。余興といえばそれまでですが、私などはとうもつき合いきれません。物語化できるほどの起伏のある毎日を生きていない、その裏返しとしての物語。使い古された陳腐な物語はテレビにもあふれ、テレビのコマーシャルの中ででも「物語」が語られています。物語は詰るというカタストロフィーを与えてくれますから、ぼんやりした人生だってそれなりの居場所を見いだすことができるということでしょうか。物語は今日、いたるところで消費されています。
もう一つの問題として、「私」というものが不確かになり、とらえにくくなった、そういう事情もあるのかもしれません。歴史的な現実、社会的な現実といったものに対応するかたちで、私たちは自我のありよう、私のありようをつかみにくくなっています。若い人たちに対して批判的にいわれる社会性、歴史性の欠如といったことも問題でしょうが、私たち自身の中にも、なにに向かって私とはと問いかけてきたのか、その設問のあり方が揺らいでいる、そういう実感があるのではないでしょうか。こうありたい、こうあるべきだという考え方が、もしかしたら数ある問いの一つでしかなかったのではないか、そんな反省です。
近代において国家は社会の要請に基づいて設立される。個人は社会に属しているので、本来、そのアイデンティティは国家に直結しない。その空間である社会の中で複合的に形成される。個人の「居場所」もそこに見出される。だから、社会の不安定化は少なからずの個人にアイデンティティの探求を誘う。物語は登場人物としてそこに居場所があることを語る人に意識させる。それは、認識の中でもう一つの世界を構築し、その登場人物としてアイデンティティを確保させる。物語が精神的危機の際に、自己治癒として効果があるのはそうした理由による。
寺山修司は、戦後初の長期不況期である70年代、お決まりの物語で生きることを批判する。その上で、新たな居場所を探すための「家出」や自分だけの物語を表現することを勧めている。しかし、世の中には「傷ついた果実たち」も生きている。傷ついた心の自己治癒として自分お物語を紡ぐことを寺山修司は提唱している。彼は、エーリッヒ・ケストナーにならって、『人生処方詩集』を「人生の傷口の治療に役立てたい」から書いたと記している。抒情詩は「薬にたよらずに、詩によって心の病気を治療する」ための「心の病のための処方箋」である。自己治癒力としての詩だ。
90年代以降は70年代以上に混迷の時代である。流動性が高いために、「自我のありよう、私のありようをつかみにくくなって」、物語の登場人物としての自分自身を認識することで「私」を感じられる。確かに、「居場所」は見つかるものの、その物語はあくまで「ロール・プレー イング・ゲーム」でしかない。「ゲーム・マスターがいて、ある約束事のもとにという限定があるにしても、物語の展開はプレーヤーのそれぞれにまかされています」。その上で、ただ「物語は語るというカタストロフィー」を味わっている。「陳腐な物語」は人並みの物語とも言える。それを達成してこそ、自分独自の物語も語り得る。社会の流動化に伴い、人並みの物語さえ感じられなくなっているから、「陳腐な物語」の「ロール・プレー イング・ゲーム」を求める。
それは義務としての物語の復活でもある。語るべき物語が類型化され、その追及によって逆に精神的に疲弊してしまう。SNSに投稿されるセレブのきらびやかな姿に自分を見失って模倣する。資本主義は欲望を刺激するので、依存症を生み出しやすい。物語の氾濫はナラティブへの依存も用意する。また、慣れと飽きを打破して話題になるために、より奇抜で過激な物語を顕示しようとする。物語の氾濫は極端と陳腐の二極化を生じさせる。埋没を避けるために、より奇妙な物語を提示、急進的な価値観による常識への異議申し立てを試みる。ただ、それは刺激のインフレを招き、センセーショナリズムの自己目的化に堕する。また、陳腐な物語は同時代から見て保守的な価値観を帯びている。それは克服されるべき通俗道徳や時代離れした信念、現代的諸課題への忌避を温存させる。物語は価値観をはらむために、行動を促すだけでなく、それを倫理的に正当化する。陳腐な物語の氾濫は独善的な行動を蔓延させやすい。
The narrative constructs the identity of the character, what can be called his or her narrative identity, in constructing that of the story told. It is the identity of the story that makes the identity of the character.
(Paul Ricoeur)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
