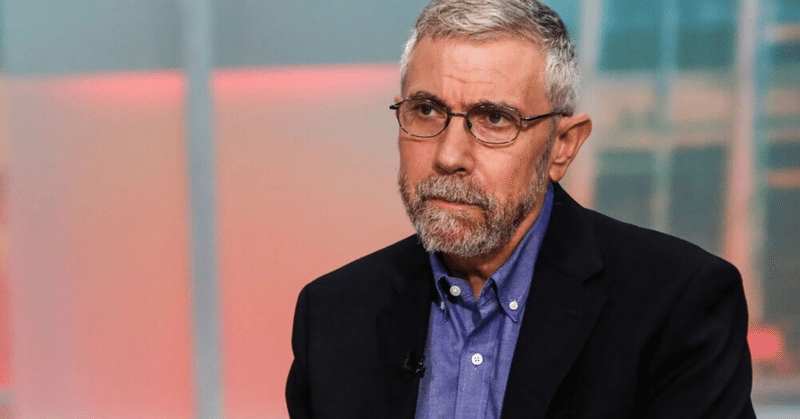
インフレ・ターゲットと経済学史(2012)
インフレ・ターゲットと経済学史
Saven Satow
Feb. 04, 2012
「インフレーションは、特に投資家階級にとって不公平であるので、貯蓄にとって好ましからざる影響をもつ。物価下落の原因となるデフレーションは、損失回復のため企業者の生産制限を導き、労働と企業にとって貧困化を意味する」。
ジョン・メイナード・ケインズ「貨幣改革論』
米連邦準備制度理事会は、2012年1月25日、長期的なインフレ率を「年2%をゴールにする」と発表している。インフレ目標を初めて設定し、それを目安に金融政策をする方針である。08年12月に始まった実質ゼロ金利を従来より11年以上延ばし、14年後半まで続けることも表明している。
現在のアメリカの最優先の国内課題は失業率の改善である。FRBのインフレ・ターゲット政策もその対策である。失業率が高止まりしたままでは、バラク・オバマ大統領が再選しても、共和党の候補者にノックアウトではなく、判定勝ちしただけと有権者は見なすことだろう。
資金不足が不況の原因であれば、量的緩和によって雇用創出も可能である。しかし、貨幣の供給量が増えても、需要がなければ、有効に生かされない。アメリカに有効需要の減少があるなら、投資家は国内より国外に目を向ける。いくら緩和を続けても、新興国の方が高い利益率を予想できれば、彼らは国内に投資しようとしないだろう。政府と違い、彼らの目的には国民の生活水準の向上といった抽象性はない。その場合、雇用創出には産業の空洞化への対策が必要となる。
金融政策の諸外国への影響も見過ごせない。FRBの動向を受けて、今後、日本でもインフレ・ターゲット論議が再燃するかもしれない。インフレ・ターゲットをすでに実施している国は少なくない。しかし、日銀は、一貫として、慎重な姿勢をとっている。1月31日に日銀が公表した01年の議事録によると、当時の竹中平蔵経済財政相が強く政策実施を迫ったのに対し、速水優総裁を始めとして委員はおおむね否定的な態度を示している。
日本経済は、1990年代後半、デフレに突入し、日銀は99年2月にゼロ金利政策を導入する。00年8月に解除したものの、01年3月に再開し、銀行に大量に資金を投入する量的緩和政策も併用している。それでもデフレが継続したため、政府や与党は日銀にインフレ・ターゲットに基づくさらなる金融緩和を求めている。
インフレ・ターゲット提案の代表格はポール・クルーグマンである。残念ながら、一般の市民を対象にしたマスメディアでその解説とお目にかかることはあまりない。中央銀行は短期金利をコントロールしている。不況期には、金利を引き下げ、企業や家計が借金しやすくして、景気浮揚を図る。長期停滞が進行すると、中央銀行は金利をゼロへと近づけていく。この新たな新古典派総合は、中央銀行がインフレ目標を設定することで、人々が予想する将来の物価上昇率を高める政策を提案する。いずれインフレによって物価が高くなるのなら、消費行動が前倒しされるだろう。将来のインフレが現在の消費を刺激し、財・サービスの需要を増す。
クルーグマンは金融緩和をするだけで景気回復ができるとは考えていない。中央銀行によるインフレ目標というアナウンスメントが必須である。金融緩和政策は物価を上昇させることが経験上わかっている。多くの経済主体は、インフレの上昇期間中、事態を予期しながらも、直面する現実とのギャップに失望する。すべてを知り得ることはできない。彼らは、たんに現状に適応するだけでなく、政策決定者の情報のうち、利用可能なものに基づいて期待を形成する。政策決定者と情報を共有すれば、経済主体は合理的に期待を形成できるので、インフレ目標が有効だとクルーグマンは考える。
クルーグマンのインフレ・ターゲットの前提となるのが合理的期待形成仮説であるが、これは経済学者が数学を用いる際に時間性を見落とす、もしくはごまかす典型例の一つである。
1961年、ジョン・F・ムース(John F. Muth)が『エコノメトリカ(Econometrica)』7月号に、証券・商品市場に関する考察「合理的期待と価格変動理論(Rational Expectations and the Theory of Price Movements)」を発表する。これまでいかなるルールやモデルも投機市場の価格予想を成功しなかったが、それは経験してきた利用可能な情報が合理的な期待を行う投機家によって現行の決定に織り込み済みだったからだ。当時はさして注目されたわけではなかったが、約10年後に急に脚光を浴びる。1970年代前半、スタグフレーションがケインズ主義によって解決困難であることが顕在化すると、ロバート・E・ルーカスとトーマス・J・サージェントがこの見解を数学を使って経済学上の仮説に仕上げる。
合理的期待形成仮説は、その後、多くの経済学者の手によって精緻化する。ところが、彼らは期待の直接的な測定をしていない。すでに認められた計量経済学のモデルを技術的に導入しただけである。例えば、期待を表わす変数が観測可能なタイムラグのある値に置換されている。この操作によって市場では清算が瞬時に達成されることになるが、それはあまりに非現実的である。合理的期待形成仮説は計量経済学の成果に依存し、必ずしも直接的には実証できない。経済学は、数学と違い、純粋に演繹的世界ではない。
事象の発生の確率的期待値を予想するので、攪乱的事態が起きない限り、それは平均的に正しい。率直に言って、この合理的期待形成仮説はジュグラーの波のような景気循環現象の説明に適しているのであって、禁欲的に使うべきである。なお、景気循環を初めて言及した経済学者はクレマン・ジュグラーではない。ジョン・スチュアート・ミルが『経済学原理』の中で「商業における周期的な急変」を考察したのが始まりである。
今日「ケインズ主義」と呼ばれる政策はその20世紀最大の経済学者に由来していない。失業問題対策としての公共事業や貨幣供給量拡大、赤字予算などは彼以前の主流派も唱えている。1893年に始まる不況の際、アメリカでは5人に1人が失業したと伝えられている。全米各地で民衆デモが地方政府を突き上げ、道路工事による雇用創出を勝ちとっている。
ジョン・メイナード・ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』は政策提言の書ではない。経済の働きに関する従来の理論への批判が大部分を占めている。思考法の観点から経済学者を分類すると、アダム・スミス型=詳細化型とデイヴィッド・リカード型=抽象化型に二分できる。ケインズは明らかに後者に属する。まず、論路展開に必要なわずかな変数を用意し、基本的な操作を設定する。それを現実的な結論を導き出せる単純な分析モデルへと抽象化する。これにより、広範囲に亘るさまざまな経済的問題の把握が可能になる。ごたごたとした記述に満ち溢れ、複雑なメッセージを秘めたカール・マルクスの『資本論』とは好対照である。ケインズの名声はこの大胆不敵な抽象化によってもたらされている。
ケインズは、先行者が中長期に熱心だったのに対し、短期分析に絞っている。短期はイノベーションの効果も無視できるし、景気循環もさほど考慮しなくてよい。アルフレッド・マーシャルは『経済学原理』の中で分析の対象期間が短期であれば、需要側、長期になると、供給側からの考察が有効だと主張している。確かに、ケインズは期待や予想を重視している。けれども、その関心は短期に集中している。新古典派であるルーカスは、分析焦点を中長期に伸ばして、ケインズ主義の手法を拡張しようとする。だが、そうなると、ケインズが斥けたセーの法則に近づいてしまう。
クルーグマンは「市場支持のケインズ主義者」を自称している。しかし、彼のインフレ・ターゲット論にもルーカス同様のセーの法則への回帰が見られる。森嶋通夫が強く主張するように、ケインズの最大の功績の一つはセーの市場の法則、すなわち「供給は自らの需要を創造する」への完膚なきまでの批判であって、それを軽視して「ケインズ主義」もない。
金融政策による対処が限界である場合、景気循環と見なせない攪乱状況である場合、有効需要の創出のために、財政出動が必要となる。しかし、連邦政府の財政は苦しい。インフレ・ターゲットの採用は現在が10年周期程度の景気循環の途上であると信じたい米金融当局の願望の現われのように思える。インフレ・ターゲットは、本来、景気循環対策である。もっとも、金融緩和のみならず、クルーグマン当人はオバマ政権の財政拡張政策も支持している。今の不況をたんなる景気循環とは見ていない。そうなると、インフレ・ターゲットとの整合性がない。
需要が先か供給が先かが重要なのではなく、その相互作用が経済活動である。それが滞るとき、社会は不況を迎える。
2012年2月3日、ニューヨーク株式市場は、1月の米雇用統計の改善を受けて、大きく値を上げる。ダウ工業株の終値は1万2862ドル23セントで、これは3年9カ月ぶり、すなわちリーマン・ショックの2008年5月19日以来の高値である。雇用統計が市場の予想を上回り、米景気が回復しつつあると投資家が判断したと見られる。
注目すべきはナスダックの動向である。総合指数は前日よりも45.98ポイント(1.61%)高い2905.66ポイントへと上昇している。実に、11年2カ月ぶりの水準である。この原動力はフェイスブックの上場申請だろう。時価総額1.000億ドルと推定されている。フェイスブックがアンカー効果となりIT株の幅広い買いを後押ししている。
新産業の活発化は投資家に投資意欲をかき立てる。彼らは、その時、楽観的になる。しかも、金融政策は諸外国へ影響が及ぶため、自国の都合を優先させ続けるのも好ましくない。インフレ・ターゲットよりも新たな産業勃興のための取引費用軽減など制度設計の方が効果的である。需要と供給は相互作用が経済を活性化する。その回復には制度の用意が不可欠だ。
〈了〉
参照文献
根井雅弘、『現代の経済学』、講談社学術文庫、1994年
根井雅弘編、『現代経済思想』、ミネルヴァ書房、2011年
野村達朗、『フロンティアと摩天楼』、講談社現代新書、1989年
ジョン・メイナード・ケインズ、『貨幣改革論』、中内恒夫訳、東洋経済新報社、1978年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
