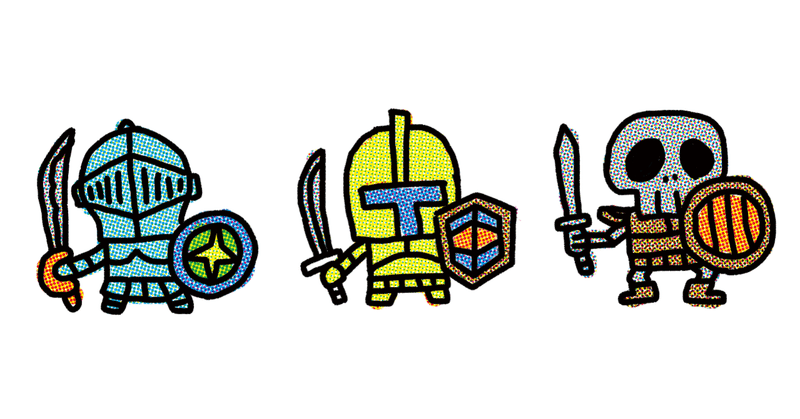
小学2年の時、怖いおばあさん先生がパンをくれた思い出。
小学2年生の時は、家ではやんちゃと言われていたが、学校では、人見知りをする、まだ、白いキャンバスのような感じの子で、学ぶ準備も、心構えも不十分なまま、人の言うことに従う、すなおな子供だったように思う。
それで、クラスで隣に座った、悪ガキ1号のいうことにもすなおに従った。
ある午前、先生が留守をして、自習時間となったとき、その悪ガキ1号から、「外に出てキャッチボールをしよう」と誘われた。
ちょっとは、「大丈夫かなぁ」と思ったものの、すなおについていき、悪ガキ1号と、悪ガキ2号は、しばらくキャッチボールをしていた。
そこへ、担任のおばあさん先生がやってきた。
50代で、明治末期か、大正の初期に生まれた、しつけの厳しそうな、ほとんど笑わない人だった。
その先生に、ちょっと叱られ、クラスに連れ戻された。そのあとは、普通のように授業が行われた。
午前中の授業が終わり、給食が始まる前、先生が、悪ガキ2人の所にやってきて、
「2人に、パンをあげましょう。ついてきなさい」といわれた。
「パンをくれる」という言葉と、先生の無表情な感じに、違和感を感じながらも、白いキャンバスは、素直に付いていった。
先生は、教室の前方にある自分の机の所まで行って、私たちの方に向きを変え、「さあ、パンをあげましょう」というやいなや、思いも寄らぬ早業で、二人に「パン、パン」と左右の頬に1つずつ、パンをくれた。
何が起こったのかわからなかった。
突然のことに、びっくりして、茫然自失の状態になったのだと思う。
あっけにとられた。
これがパンか?
こんなパンもあったのか!! 知らなかったあ。
先生は、そのときパンを2つずつくれただけで、うるさく叱られた記憶は無い。
てっきり、給食のコッペパンをくれるのかと想像していた。
でも、先生がくれなくても、給食ではパンが出る。
いったい、どんなパンをくれるのかな? と思っていたところへ、
まさかの、電光石火のほっぺパン。
痛かったという記憶はあまりない。手加減してくれたのかもしれない。
それにしても、このおばあさんが、この早業。プロの手並みだ。
あまり、笑わない、子供が好きそうでない、おばあさん先生だった。
そのときに、自分の白いキャンバスには、気をつけて、慎重に絵を描いたほうがいい、というような刷り込みができたかもしれない。
今から思えば、それは、良かったとも思えるし、最初はもっと自由に描ける絵心がほしかったとも思う。
しかし、このほっぺパンをもらっていなかったら、以前のまま、ずっとのんびりと、白いキャンバスに何も描かないで過ごしていたかもしれない。
それを思うと、世の中に向かって、自分のキャンバスに、自分で絵を描き始める「目覚めの2発」のようなものだったのかもしれない。
小学時代は、ずっと女の先生だった。
おばあさんが、この人を含めて2人。 そのあと、おかあさんが3人。
だんだんとやさしい先生にあたり、自分と合う先生にあたるようになっていった。
もし、小学時代で、出会った先生や、その順番が、違っていたとしたら、自分の生き方の「核」も、違っていたかもしれない。
今から思えば、勉強がどうのこうのと言うより、小学校の先生と、友達からは、子供ながらも、「人への信頼」と「生き方の核」をつくってもらったような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
