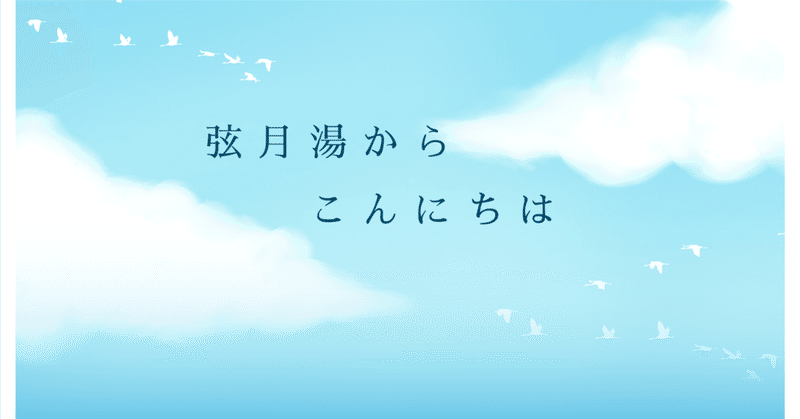
小説「弦月湯からこんにちは」第4話(全15話)
これまでのお話
・第1話はこちら
・第2話はこちら
・第3話はこちら
*
第4話
*
弦月湯から帰ってきて、私はのろのろと片付けを始めた。とは言え、数年前にこんまりさんの本を読んで以来、ミニマリストに憧れるようになったので、もともと物は少ない。紺のパンツスーツが1着。季節を問わずに着られる白いシャツが5枚、カーディガンが2枚、ジーンズを含めたズボンが3本。スカートは昔から苦手で、持っていない。職場では制服があったので、必要最低限、行き帰りだけの洋服が必要だった。冬物のコートが1枚、靴は黒のフラットシューズと白のリーボックの2足。それに下着や靴下など。くるくるとまとめ、細かい物は風呂敷に包み、キャリーバッグに入れていく。
入社以来、大事に保存し続けて来た紙資料は、シュレッダーにかける。もう二度と、使うことも、読むこともない資料の数々。保存しておきたかったのは、私のエゴだったのかもしれない。こんなことを成し遂げた、こんなことで認められた、こんなことで人の上に立つことが出来た……そんな薄汚い、どろどろとした承認欲求の現れ。書類の文字にはひとつひとつ、過去の思惑がべったりとこびりついて、腐臭を放っていた。書類の群れをシュレッダーにかけていくと、過去の自分を縛り付けていた鎖から解き放たれていけるような気がした。
6年半住んだ社員寮の部屋には、暦くんからもらったマグカップと小皿、スプーンとフォークくらいしか食器はない。全エネルギーをあの店に傾けていたから、食事もいつも、うちの店で済ませていた。人気が落ちて来たメニューがあるとそれを食べて、改善点を考えていったのも懐かしい。全部を仕事に預けていたから、休日もこの部屋で食事を作ることはしないと決めていた。だから、この部屋には炊飯器も、鍋も、フライパンもない。テレビもない。あるのは、備え付けだった折りたたみのテーブルと、布団と、洗濯機ぐらい。自分で買ったものといえば、CDラジカセくらいだ。学生時代から大好きなノラ・ジョーンズのCDを聴くためだけに、購入した。置いていこうかどうしようか少し悩んだが、手に持って運ぼうと決めた。
と、敷きっぱなしの布団が目に入った。万年床ってこういうことなのね……と変な感心をする。この二週間かけて、部屋のインテリアのようにしっくりと馴染んでしまった布団を、床からめりめりと引き剥がす。せめて最後に、この布団を干しておこう。私は、窓を開けて、ベランダの手すりに布団をかけた。むわっと、生暖かい空気が立ちのぼる。2週間、いやそれより前からずっと干していなかった、寝汗の沁み込んだ布団。せめてもの罪滅ぼしに、私は除菌タイプのファブリーズを布団にスプレーした。
本も、新聞も特にない、がらんとした部屋。新聞は電子版で読んでいたし、気になったビジネス本もKindleで購入していた。出来るだけ、この部屋に物を増やしたくなかった。ここは社員寮で仮の住まいなのだから……という気持ちが強かったので、自分の気配を充満させたくなかった。
普通に賃貸マンションを借りるという選択肢がなかったわけではない。けれど、社員寮の方が福利厚生もしっかりしていたし、気楽だった。おまけに入居している社員は少なかったから、余計に気が楽だった。互いに干渉することもなく、気を使い合わなくても済む、とても気楽な関係。すれ違った時に、ぺこりと会釈をする位の、限りなく空気に近い距離感。一日中、店のざわざわした空気にいることが多い私にとっては、思考のクールダウンのためにも必要な距離感だった。
そうだ、引っ越すことを管理人さんに伝えなくては……と思い至り、私はエレベーターで1階に向かった。新聞を読んでいる管理人さんを確認して、ガラス窓をこんこんと叩く。管理人さんは私を確認すると、慌ててマスクをつけて、ガラス窓を開いた。
「山口さん、どうも」
「こんにちは。すみません……急なのですが、明日引っ越すことが決まりました」
「そりゃあまた、急ですね」
「実は、ついさっき、決まったのですが」
へええ、と管理人さんは眼鏡をずり上げる。
「ご縁があって、よかったですねえ」
「本当に」
「いや、このところ山口さん見かけなかったし、ここに残っているのも山口さん含めてあと2人になったので、心配してたんですよ」
「ご心配をおかけしました」
私はお辞儀をする。
「いやいや、本当によかったです」
「入居の時に備え付けだった、テーブルと洗濯機と布団は、そのまま置いておけばいいですか」
「大丈夫ですよ、みんなこちらで片付けてるんで。他では、本棚や、本を置いていく人もいましたね」
「へえ」
「こんな状況で大変ですけど、生きてたら、時が巡って、またいいこともありますよ」
「……ありがとうございます」
私はぺこりと頭を下げる。管理人さんも頭を下げて、また新聞に目を落とす。
「じゃ、また明日」
「はい、また明日」
エレベーターで上りながら、さっきの管理人さんの言葉を思い返す。生きてたら、時が巡って、またいいこともある……か。そうかもしれない。今の私には、時が巡ることも、いずれいいことが訪れるかもしれないことも、何もかも信じられないけれど。それでも、時は誰にでも平等に巡っていく。私は目を瞑った。くう、と腹が鳴る。そういえば、お腹が空いた。考えてみたら、朝の豆乳コーヒーしか飲んでいないのだった。
私は電気ポットでお湯を沸かした。カップ麺も残り少なくなった。私はピリ辛のわかめラーメンを手に取り、ぺりぺりと蓋を開ける。粉末スープと、くちゃくちゃに乾いたわかめの入った小袋を開けて、お湯を注ぐ。タイマーをかけて、窓を開ける。風が舞い込んでくる。この部屋に風を通したのも、2週間ぶりだ。
「このままじゃ、わたし、干涸びちゃう」
思考がそのまま、口から漏れた。さっきのわかめラーメンの、小袋に入っていた乾燥わかめみたいに、わたし、いまくちゃくちゃに乾いている。わかめは、お湯をかけて3分待てば元に戻るけど、私は戻れるのだろうか。そもそも、私にとってのお湯って、何だろう。
右目から、つうっと涙がこぼれた。泣くつもりなんて、全然ないのに。それでも、涙はこんこんと溢れてくる。鼻水も出てくる。いったんこうなってしまうと、止まらない。私はティッシュの箱をたぐり寄せた。鼻を勢いよくかんで、ティッシュを両目に当てる。それでも、止まる気配はない。私は、しゃくりあげて、嗚咽しながら、ティッシュの箱を抱きかかえた。
タイマーが鳴った。涙ににじむ目で、スマホの液晶画面をタップする。とにかく、今は、食べなくちゃ。私は蓋を剥がして、割り箸を割って、手を合わせる。「いただきます」と呟いて、麺を啜る。柔らかいようでも硬いようでもあるインスタントの麺を啜る。今日はやけにしょっぱい。なんの塩味なのかよくわからないままに、私はただ麺を啜り続けた。
(つづく)
*
つづきのお話
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話はこちら
・第12話はこちら
※第13話は、5/29(水)公開です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

