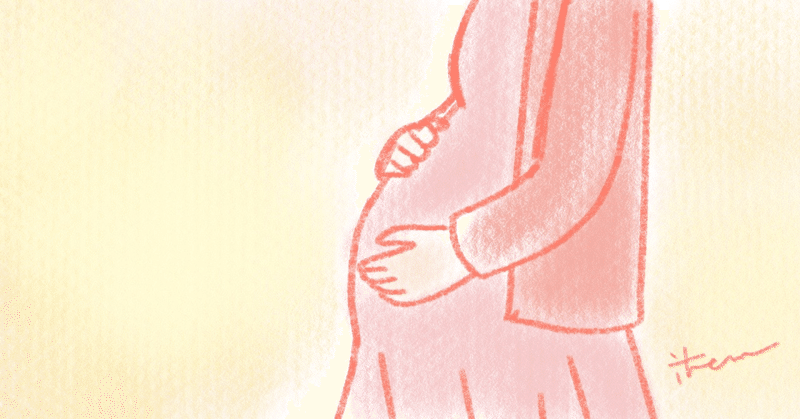
【炎の刻印】第23~24話(完)
ⅩⅩⅢ「月食―DOOM―」
「願えば必ず応えてくださる。まさに私にとっての神だ」
かつて、オクタビアはメンドーサにそっと触れようとし、拒まれたことがあった。彼はオクタビア自身を嫌っていたわけではなく、おそらく人間との触れ合い自体を拒絶していただけなのだが、そのことはオクタビアの心にはしこりになって残っていたのだろう。いま、ヘルマンが残していったメンドーサの片腕を、オクタビアはなんとも愛おしげに拾い上げ、頬ずりし、口づけし、しまいには自らの肉体へ取り込んでしまう。ずっとずっと触れたかった、その手、その身体……。オクタビアの「願い」に、メンドーサはまたも(間接的な形ではあるが)「応えて」くれた。
さらにメンドーサは、魔戒騎士と戦うための力をもオクタビアに与えてくれた。魔獣装甲と呼ばれるそれは、人間の憎悪を餌にして成長し、纏った者の心と体を食いつくす生き物だ。目には目を、鎧には鎧を。装甲の常人離れした力のおかげで、オクタビアはアルフォンソ・エマの二人と同等以上に渡り合うことが出来る。メンドーサの結界空間での戦いでは、エマの連続ターザンキックや、ソウルメタルの重さを利用して墜落させるアルフォンソの頭脳プレイなど見ごたえ抜群であった。結界を破って城下町に戻ってきてからも、落下する一本の材木の両端でシーソーのようにバランスを取りながらの立ち回り、角材の断面が楕円にたわむほどの力がこもったガイアの蹴り飛ばしには目を見張らされる。すかさず何本もの鉄骨をぶち込んだエマのアシストによりやっと倒せたかと思いきや、片腕を失った姿でゆらりと復活。メンドーサ様とおそろいですね、なんて言っている場合ではない。
アルフォンソを送り出してエマは再びオクタビアに向かい合う。義足から繰り出された凶悪な銃口に絶体絶命のピンチを迎えるが、オクタビアの肉体ももう限界であった。エマの前で彼女の鎧と身体はぼろぼろに崩れていく。
メンドーサに道具として使われようとも、自らの行く末が決して報われなくても、オクタビアの信仰は揺るがない。世界へのあくなき呪詛がその礎だ。最後まで「守りし者」を呪いながら、彼女は絶命する。「目的のために人間もろとも街を滅ぼそうとしている」というご尤もな指摘は本当ならば番犬所や元老院に向けられるのが筋であるが、オクタビアにとってはレオンもアルフォンソもエマも、そんな御大層な大義名分を掲げる傲慢な強者のひとりにすぎないのだ。
エマとともにオクタビアと戦っていたアルフォンソだが、戦闘が一区切りついたところで、彼にしかできない、彼自身の戦いへと赴くことになる。エマに頼んでその身を飛ばしてもらったのは、空から優雅に降ってくる番犬所の真下だ。これ番犬所だったのか!
魔戒騎士とは「守りし者」である。生粋の魔戒騎士であるヘルマンとレオンは、人間同士の諍いには首を突っ込まない。魔戒騎士が剣を向けるのはホラーのみであるべきだからだ。
だが、アルフォンソは迫りくる番犬所の先端部に、自らの切っ先を躊躇なく構える。それが出来るのは、彼が騎士である前に王子であるからだ。かつてアルフォンソは、自らの国民をなんとしても守ると誓った。彼の民の脅威になるのであれば、ホラーだろうが番犬所だろうが、アルフォンソにとっては等しく倒すべき存在なのである。堅陣騎士ガイアの鎧は、まさにすべての災厄から国を守らんとするアルフォンソにこそふさわしい。
頭部を覆う金属は砕けて顔が半分露出している。全身の鎧にも幾つもの亀裂が入り、いつばらばらに千切れてしまってもおかしくないような状況だ。だが、アルフォンソは決して引かずに剣を向け続ける。たかが騎士一人、剣一本で、あの莫大な質量にどうやって打ち勝てるというのだ。並の神経なら早々に諦めてしまうところであるが、アルフォンソはどこまでも大まじめだ。そして、その一途な思いは報われる。
剣の切っ先と塔の先端が触れた瞬間、ガルムらの企みは失敗に終わる。ちゃんと自分たちで後始末をしろ、なんて無気力に告げながら、番犬所は解けるようにその姿を消す。城下町の危機はひとまず去ったのだ。
そんなぎりぎりの攻防が行われているとはつゆ知らず、街の人々は月食に怯えている。ヘルマンを心配するあまり家を飛び出したヒメナは、途中で住民を避難させているガロロボたち一行に出くわし、請われるままに誘導の手伝いへ走って行く。不安に駆られてやみくもに走り回るよりも、今確実にできることを選択したという感じだ。
ヒメナはヘルマンを心配しているが、オクタビアはメンドーサのことをこれっぽっちも心配していない。それが、愛情と崇拝の違いなのかもしれない。ヒメナの中には、再びヘルマンに逢いたい、無事な姿を見たい、という未来への希望がある。だが、オクタビアはメンドーサの勝利を確信しているし、そのためなら自分など今ここで死んでしまっても構わないと思っている。「メンドーサの作る世界をこの目で見たい」とは言うものの、それがために自分一人生き残りたいとはこれっぽっちも感じない。自分自身の心配すら、オクタビアはしていないのだ。
愛情が生の交歓であるのならば、すでに死んだようなものであるオクタビアとメンドーサの間にそれは芽生えようもないのかもしれぬ。少なくとも、子孫を残せぬわが身を呪うあまり、子孫繁栄を貴ぶ魔戒騎士に唾を吐くようなメンドーサにとっては。オクタビアの側はもしかすると、メンドーサのことを食べちゃいたいほど大好きだったのかもしれないが(実際片腕は吸収したわけだし)、彼女は彼女で勝手にメンドーサに神性を見出していただけなのだし、それを愛情と呼ぶのはちょっと違和感がある。
別れの接吻とともにエマに送り出され、レオンはひとり遺跡の最奥部へと向かう。父が待っているはずのそこには、しかしメンドーサが一人で立っている。
前回から組み立てていた巨大なパズルを、メンドーサはようやく完成させようとしている。真っ赤に輝くそれは、宙に浮かぶ十字架だ。レオンの目の前で、その最後の1ピースが組み込まれていく。魔戒騎士や魔戒法師たちから作られた、輝く結晶。飛び出した柄のデザインに、レオンは見覚えがあった。幼いころから、嫌と言うほど見てきた剣だ。ここで待っているはずだった、自分が助け出すはずだった人の愛剣だ。
煽るようなメンドーサの言葉に、レオンはもう心を乱されない。一見、怒りが一周回って逆に冷静になってしまっているようにも見えるのだが、それでは感情に飲まれて我を忘れた前回と同じことだ。雌伏の期間を経て、レオンは「守りし者」としての自覚と覚悟をすでに手に入れている。彼のやるべきことはただ一つ――メンドーサを斃し、街への被害を食い止めることだ。
恐ろしい数の素体ホラーを瞬く間に切り捨て、レオンは寸分のいとまもなくメンドーサに肉薄する。そして、躊躇なくその身体を貫く。良い覚悟だ。ホラーに与しているとはいえ、仮にも人間であるメンドーサを、容赦もせずに殺すことが出来るのだから。
だが、腹の刺し傷は致命傷には至らない。メンドーサとレオン、二人の目の前で、魔戒へと通じるゲートが開く。こぼれるように溢れだす無数のホラーを両掌の風穴から吸い込むように食い、アニマはとうとう復活の時を迎える。
胎児のように丸めていた体を起こし、アニマは城の外へ姿を見せる。首から上のない真っ青な身体は女性的な特徴を有しており、その胸にはメンドーサが作り上げた輝く赤い十字架が斜めに貫通している。ただの短剣に戻ったヘルマンの魔戒剣も、その身体には刺さったままである。運よく短剣を掴んだレオンだが、アニマの恐るべき剛腕により手近な建物に叩きつけられてしまう。
アニマが女性型だったのには少し驚いたが、よく考えればかつてのラスボス・メシアも巨大な女性の姿をしていた。これはもう、シリーズのお約束なのだと理解する。命を育むどころか、幾千のホラーを朝食代わりにぺろりとたいらげ、メインディッシュとばかりに街と国とを蹂躙しようとしているアニマ。アルフォンソもエマも各々の戦いを果たし、倒れ込んだままだ。この状況を打開するため、残された戦力はもはやレオンだけである。勝ち目あるのか?
ⅩⅩⅣ「光芒 ーCHIASTOLITEー」
メンドーサをめぐる物語、最終回である。TVアニメ「GARO 炎の刻印」の主人公はレオンであろうが、この2クール流れ続けた時間の主人公は、もしかするとメンドーサであったのかもしれない。というのも、ヘルマンより受け継いだレオンの物語はエマやアルフォンソ、ヒメナやまだ見ぬ弟妹(弟妹!)へ引き継がれ、これからもずっと続いていくからだ。アニマを吸収して「永遠」を手に入れたメンドーサは、魔界の底で絶えることの無い業火に包まれ、永遠に終わり続けるほかない。
蘇ったアニマは結界を張り、その中で人々を赤いキューブ状に分解しては次々吸い込んでいく。バックパックのように貫通している赤い十字架は、いわばアニマを起動させるための外部バッテリーか。レオンを払いのけた時の緩慢な動きといい、アニマは基本的には巨体ゆえの剛力と不死身の生命力を持つだけで、主な性能は分解と吸収がメインなのであろう。
その分解・吸収能力こそ、メンドーサが目を付けたポイントでもある。レオンがつけた傷から自らの臓物を引きずり出すメンドーサ。小柄な矮躯に詰まっていたとは思えないほどに展開される、白い骨のような結晶。すると、アニマの胸に刻まれたタトゥーのような紋章が輝き、それに呼応する。メンドーサはアニマの力を使い、逆にアニマを吸収・融合しようとしているのだ。
メンドーサの肉体は瞬く間に細かく分解され、リングのような円を形作る。それはらせんに姿を変え、頭でっかちの胎児の形となり、ついには成人の大きさに成長する。脱力したようにのけぞって腕を垂らしたシルエットは、腰から下にスカートのように布を巻き付け、まるで女性のようにも見える。だが、一面を塗りつぶすような光がやむと、そこに立っているのは若々しい顔をしたメンドーサその人である。彫刻のような白磁の肌には太いラインが模様のように走り、切れ長の瞳をあたかもエジプトの壁画がごとく神々しく縁取っている。いつも被っていた大きな帽子は完全に後頭部と一体化している。剥き出しの上半身に乳房は無い。女性体を持つアニマを超越することにより自分の男性としての肉体を作り直したか、もしくは人間をやめることで両性を併せ持つ存在となったか。「子をなすことが永遠? たわ言だ」「この不滅の身体こそが永遠だ」とレオンを憐れむ様子を見るに、もはやメンドーサにとって性別などどうでもよいカテゴリー分けにすぎないのかもしれない。
しっかし、この期に及んで「子をなすこと」に言及するとは。メンドーサときたら、元老院から受けた子孫をなせないという仕打ちについて、結局一番根に持っているのではないか。壮大な台詞をいくらほざいても、彼自身連綿と続く魔戒騎士・魔戒法師の血のつながりや価値観からは逃れられずにいるのだ。
レオンもまた、その血のつながりの中に自らを置いている。だが、彼の鎧と思いは血のみによって受け継がれるものにあらず。ヘルマンからは戦う力を、母アンナからは炎の守りを与えられ、ララからは守りし者としての決意を、エマからは自分も血をつなげていくのだという覚悟を教わった(相変わらず彼氏面していて微笑ましい)。アルフォンソには一時、自らの鎧を奪われもした。が、誰かを守りたいという強い願いとともにレオンの生きる力はよみがえり、再び黄金の鎧は彼のもとへ戻った。
アルフォンソもまた、血によらぬつながりで堅陣騎士ガイアの鎧を受け継いだ。固い決意とたゆまぬ修練は、師弟の間に切れぬ絆を生み出したのだ。倒れ伏したアルフォンソは朦朧とする意識の中、師匠の幻を見る。立ち上がれと叱咤するその言葉が、アルフォンソの四肢に再び力を与える。
ヘルマンの双剣のうち、一振りはアニマを経由してレオンの手に。そしてもう一振りは遺跡の中に放置されていたが、アニマ噴出のタイミングで一緒に地上へと放り出されている。目ざとくそれを見つけたエマは、自らの糸で剣を手繰り寄せ、アルフォンソへパス。アルフォンソはゲートへと落下していくレオンへそれを投擲する。三人分の思いが乗ったそのきらめきを、レオンは自分の持つ双剣で受ける。柄同士が接合し、双剣は上下に刃を持つ一振りの大剣となる。
片手に自分の剣、もう片手には父の剣。それぞれの切っ先で空中に円を描くと、光の輪がレオンを包み込むようにいくつも出現し、輝く球体を形作る。現れるのは黄金と銀色を併せ持つひとりの騎士の姿だ。ヘルマンとレオンの思いが一つになった、奇跡みたいな鎧を身にまとい、レオンはメンドーサごと閉じかかったゲートに突っ込む。無限の回復力を持つメンドーサを今自分一人で倒しきることはできない。だが、取り急ぎ魔界に閉じ込めることはできる。「人の因業がゲートを開く限り何度でも舞い戻ってやる」と哄笑するメンドーサに、レオンは力強く言い放つ。自分一人がお前を斃せなくても、自分の血や思いを受け継ぐ者たちが、いつの日かお前を斃すだろうと。自分が大きなつながり、魔界騎士の歴史の中に身を置く者であると、レオンは心の底から確信している。
メンドーサと心中するつもりのレオンだが、皆はそれを望んでいない。
エマは必死にゲートの入り口を縫い留め、アルフォンソとふたりでその穴を保持しようとする。レオンが無事に帰ってくるという希望を、二人はまだ捨ててはいない。
魔界側でも、レオンの帰還を促す者がいる。消えることの無い炎とともに現れるのは、レオンの母・アンナである。
「メンドーサは私が炎で包み続けましょう。朽ちることの無い身体を、永遠に……」
アニマは今まで魔女狩りで犠牲になった魔戒騎士・魔戒法師の魂を糧として復活した。ならば、同じく魔女狩りで命を落としたアンナの魂がそこに含まれているのも道理である。アニマを取り込んだメンドーサから、いま再び分かれ出でたのか。レオンに宿された炎の守りが、強いきっかけとなってアンナの姿を蘇らせたのかもしれない。
アンナにそっと背を押され、レオンは魔導馬の背にまたがってゲートを目指す。そこに轡を並べるのは父ヘルマンだ。レオンが間に合わなかったことをヘルマンは責めない。この期に及んで、そんな言葉は必要ない。アンナから隠れるようにこっそりヒメナのことを頼んで、ヘルマンはレオンを送り出す。……それを言いたいがためにわざわざ出口近くまでついてきたわけではなかろうな?
とにもかくにも、レオンはゲートを飛び出し、人間の世界へ帰還する。待ち構えていたエマとアルフォンソを見つけた彼の顔には、どこかさわやかな笑顔が浮かんでいる。仇敵と別れ、父母と言葉を交わし、レオンが最後に勝ち取ったのは離別の涙ではなく、清々しい達成感であった。
自らに与えられた「炎の刻印」が、復讐の炎なんかではなく、彼を守る母の強い思いであったことをレオンは知った。それがレオンに自らを肯定させる最後のひとパーツとなった。ララたちとの暮らしにより随分自尊心と自信を取り戻していたレオンだが、今この瞬間、彼はようやく自分自身の運命を完全に受け入れることが出来たのだろう。
そして、世界は日常へ回帰していく。
アルフォンソは泥にまみれながら、現場で復興の陣頭指揮を執る。ガロロボも健在だ。かつてアルフォンソは自分の見える範囲ばかりを気にして、城下の貧民街のことなどは何も知らない、世間知らずの王子さまであった。だがこうやって現場に赴き、民と混じって汗を流していれば、きっともっといろんな角度から自分の国を眺めることが出来るはずだ。
王子御自らが町場でご活躍と聞けば、取り巻く貴族たちの意識も少しずつ変わり始める。手伝いをしている貴族の娘たちを見て、アルフォンソは顔を赤らめる。騎士である前に王族である彼は、より確実に血のつながりを紡いでいかねばならない立場なのである。
エマは元居た町へ帰るという。騎士たちにはいいようにこき使われ、夫はホラーとなり果てた、あまりいい記憶はなさそうな土地である。それでも、彼女が新しい人生の再スタートを切るには、やはり始まりの地へ戻ることが必要なのだろう。自分はついていけない、と口ごもるレオンだが、そもそもエマはレオンについてきてもらう気などさらさらない。「いい男になりなさい」と言い置いて、彼女は颯爽と去っていく。エマは魔戒騎士ではなくあくまでも魔戒法師だが、それでも守られるよりは守る者でいたいのかもしれない。
レオンはララの墓標に参り、エマに別れを告げて街へ戻る。彼が今寝起きしているのはヒメナの宿だ。亡き父の形見であるジルバはいま、ヒメナの胸元に揺れている。これから生まれてくる、ヘルマンの血を引く赤ん坊を見守るためだ。レオンにとってはだいぶ年の離れたきょうだいにあたる。戦いで失われたものは多かったが、新たに生まれるものもある……なんて、陳腐でありきたりだが力強い事実を以て、物語はその幕を下ろす。アンナがレオンに刻んだ炎の刻印、一般的には愛と呼ばれるその感情は、えてして陳腐でありきたりな、目には見えないけれどどこにでも存在するものなのだ。
というわけで、『GARO 炎の刻印』完走。久々にじっくりアニメに向き合えて楽しかったです。実写を意識した迫力あるアクションシーン、大変良い物でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
