
檀信徒カルテの実践エピソード~葬儀編~
寺檀関係と葬儀
亡くなった時に咄嗟に思い出してもらえない。
檀家寺であっても抱える課題の1つではないでしょうか。
檀家・信徒が「いよいよ・・・」という状況ではなく、故人になられて葬儀社も式場も決めて、日時の相談がある。
つまり「今亡くなりました・・・」ではなく、「昨夜亡くなって葬儀社は●●で式場は・・・」と連絡があるようなケースが珍しくありません。
檀家・信徒からの葬儀依頼がどのくらいの確率で葬儀社よりも先に寺院に電話があるか、把握しているお寺は実際のところ少ないのではないでしょうか。
ただなんとなく「そういうものだろう」と受け入れている僧侶と「先にお寺に連絡がないなんて・・・」と眉をひそめるのみで、正しくこの課題と向き合っているお寺がどのくらいいらっしゃるでしょうか。
また、葬儀の依頼が少なく、紹介会社やインターネットの会社経由で葬儀を受託した葬儀社からの依頼で導師を行い、関係性が0の方の供養をどのようにしていけばいいのか。戒名はどのような想いで授ければ良いのか、そんな風に思い悩む僧侶の方も増えています。
檀信徒カルテを実践しているお寺では、檀信徒の交流を深め、寺檀関係を深いものにすることで年あたりの葬儀件数が増えているケース出てきました。
どのように、実践しているのか?
今回は実践寺院のエピソードをご紹介します
※エピソードは檀信徒カルテ研究所のメルマガ【第3号】檀信徒カルテ便り2021年7月7日分から転載・編集したものです。
「葬儀の事前相談記録」
<檀信徒カルテ実践者>
50代 東京都 檀家数300程度 納骨堂 寺務台帳利用
<檀信徒カルテ実践者の声>
寺院葬を自坊で行えることをきちんと檀信徒に伝えることがなかなかできておらず、一念発起して「寺院葬儀」のパンフレットを作成。
寺院で葬儀ができる内容:価格の平均目安と項目、担当葬儀社、お布施についてなどを記載。
パンフレットを受け取った檀信徒から「実は父の容態が・・・」などご相談を受けることも増えて手応えを感じていました。
ところが、ある日「今、父が亡くなって・・・」とお電話が。頼っていただけたことに安心したのも束の間。
「それで前にお話していた感じで父の葬儀をお願いしたいんです」と言われてヒヤリ。
「一体、どんな希望だっただろうか?」と内心冷や汗をかきながらなんとか受け答えをして葬儀社に連絡をして、担当者から喪主に電話してもらうことに。
思い返してみると
・人数は親族ばかりで15名程度
・お父様は山が好きだったので祭壇は緑調がいい
・料理はきちんとしたものを出したい
・遠くから親戚が来るので寺院で泊まれるなら宿泊したい
など細々としたところを聞いていたのにそのメモを相談を受けた2年前の手帳に大事にしまいこんでとっさのことで出てきませんでした。
これではいけない。
と考えを改めて、それ以降、葬儀相談があれば檀信徒カルテが搭載されている「寺務台帳」にメモを写真で撮ってあげて、履歴にも葬儀の依頼があったら「写真の要望を葬儀社に伝えてあげること」と記録しました。
葬儀社を紹介して事前見積もりが出た場合も同様に、事前見積もりのコピーを「寺務台帳」に保管しました。
亡くなってすぐは喪主も手元に見積書があるとは限らず、気が動転していることもあるので「あの時の葬儀社さんに見積書通りおねがいしたい」と言われれば寺院から葬儀社に見積書を添えて依頼しました。
こうすることで見積書を作成した担当者が不在の場合でも滞りなく喪主と葬儀社の話が進むこともありました。
檀信徒の葬儀についても記録しておくことで一番喪主が大変なときに寺院に電話を1本入れるだけでスムーズに進み、安心していただけます。
小さなことですが、こういった手間ひまが「寺院葬にしてよかった」と言っていただけることに繋がると実感しています。
<具体的に檀信徒カルテに記録したこと>
基本情報:お名前、連絡先、家族構成
相談者の特徴:代々の檀家、お父様の容態が悪く次世代の息子
話した内容:葬儀に希望すること(人数、祭壇、料理、親族対応)、葬儀社に紹介したかの有無、見積書あるなし など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
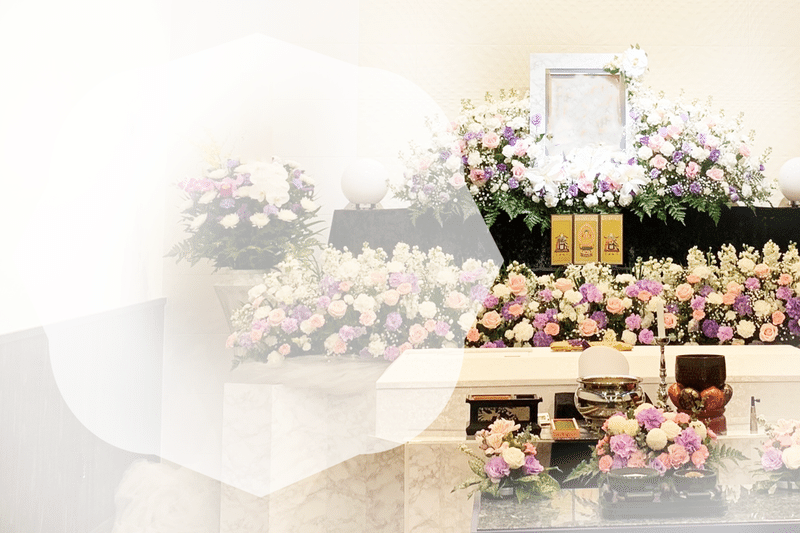
結び
筆者は相談員として葬儀相談を10年以上受けていますが、「葬儀はもうほんと小さく」「少人数で質素でいい」「お布施が高いな・・・。もっと安いお布施にならないかな?。そもそもお寺って呼ばなきゃいけないのかな?」。
など、本当にお金がない方は除いて、供養はしたくないわけではないが、儀式に価値を感じられないから安くしたい、または供養体験がないので価値がわからないから消極的になる方が珍しくありません。
それでもなんとか、仏式の葬儀を行ったのに、価値を感じられず「高かったな・・・」「金額のわりにいまいちな葬儀だったな・・・」と「供養してよかった」という実感がない体験をしてしまうと、次の法要などの供養に繋がりにくい傾向にあります。
これは、供養業界内で何重にも紹介料が重なってしまったがために喪家からの支払額には相当しない、質の低い供養体験の台頭も影響していますが、供養の主軸を担っている僧侶との関係性の希薄さや供養体験の少なさ(法要や人の葬儀に参列したことがないなど)も大きな要因だと感じています。
無神論者や無宗教者は難しいかもしれませんが、せめてお寺とすでにつながっている檀信徒や会員の方には、お寺を頼ったお葬儀がいかにゆったりとした時間が過ごせ、費用も結果的に安くなり、安心して悲しむことができる。そんな体験をしていただきたい。
と思っています。
ですから、
・お寺で葬儀相談ができる体制を設けること
・寺院葬ができるなら寺院葬について告知すること
・事前相談があればしっかり記録して万が一にしっかり支援すること
ができるお寺が増えれば
「少人数でもしっかり葬儀ができた」
「お金をかけなくてもちゃんと供養ができた」
という体験をするご家族が増え、仏さまと故人さまに手を合わせる文化も続いていくと信じています。
※お布施が正しくお布施として満額が仏さまに捧げられるという点も重要だと思っています。
私達も青山霊廟にて、地道に10年間、葬儀相談の告知と相談業務を行い、檀信徒カルテに記録することで、おかげさまでじわじわとお寺に直接の葬儀依頼が増えてきました。
すこしづつ、寺院から檀信徒へ歩み寄り、檀信徒が困ったことがあれば頼れる寺院になっていく。
そんな風景が増えていくことを願って、お知り合いの僧侶にこうしたお話をすると、「自坊でも取り入れたい」という相談をいただくこともあり、パンフレットの作成や告知方法など共に考え、配布物を作成させていただき、準備と実践の支援も行ってきました。
私たちが直接支援できないお寺であっても、檀信徒カルテを用意し、葬儀相談の記録を残していただくことで寺檀関係を深めていくことをおすすめしていきたいと思います。
池邊
上記のような情報を発信している檀信徒カルテ研究所のメルマガ登録は以下より。※寺院の方のみの登録とさせていただいております。
また、檀信徒カルテの葬儀に関する講座も開催します。
「必要とされるお寺」が取り組む檀信徒カルテ実践講座~葬儀編~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
