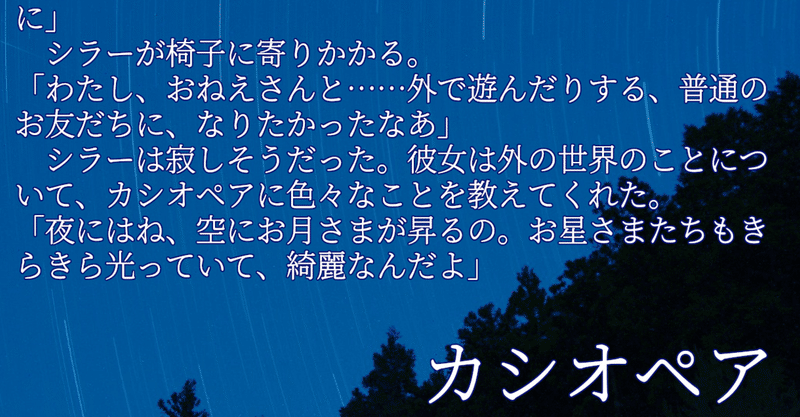
カシオペア
※前書き※
この小説は、コラボ企画展 HAKOLIEN文×画「椅子のある部屋」(箱の中のユーフォリア様主催) に千梨が参加し、展示された作品の再掲載です。
コラボイラストは、坂本みちよ様に描いていただきました。ありがとうございました。
ファンタジー、シリアス、ほのぼのなイメージで描きました。5000字作品です。
加筆版を収録したコピー本が存在しています。
※前書きおわり※
○本編○
カシオペアと呼ばれた少女は、自分が座っている椅子を愛しむようになでた。この椅子は、彼女の肉体の一部と言っていいほどに、カシオペアの人生を共にしてきた相棒のようだった。カシオペアが持つ記憶には、いつもこの椅子の、滑らかな石造りの感触が染みついている。椅子は彼女のことなら何でも知っていた。
物心ついた時から、カシオペアはこの椅子に座っていた。周りは暗闇ばかり。手探りで分かるのはこの椅子があることだけだった。なぜなら、身体は縄で縛られ、カシオペアはここから一歩も動くことができなかったから。彼女は自分がどこで生まれて、どんな家族がいたのかさえ知らなかった。
窓のない部屋。他人との会話もなく、ただ黙々と一日が過ぎていく。そのなかでカシオペアは自分がすべきことを教えられた。
それは、神のために身を尽くすこと。彼女は神に祈り続けなければならない宿命を背負っていた。ずっとそんな風に過ごしてきたので、カシオペアはそれをちっとも変だとは思わなかった。
その日やってきた食事係が、いつもとは違う人物であることに、カシオペアはすぐに気がついた。足音の軽さから、その人物がまだ子どもであるということも。
その少女はシラーと名乗った。
シラーは他の世話係と比べると変わっていた。他の世話係はカシオペアが声をかけても、少しも反応しようとしなかったのに、彼女は自らカシオペアに話しかけてくるのだ。シラーはよくしゃべり、よく笑った。今まであまり人と話すことのなかったカシオペアは、そんな彼女に戸惑うばかりだった。
「おねえさんは、いつもここで何をしているの?」
「……神さまに奉仕をしているの」
「『ほうし』って?」
「祈りをささげるのよ」
「一日中ずっと? そんなことばっかりして飽きないの?」
「飽きたりなんてしないわよ?」
シラーは納得できない様子だった。
「ふーん。外にはもっと楽しいことがいっぱいあるのに」
シラーが椅子に寄りかかる。
「わたし、おねえさんと……外で遊んだりする、普通のお友だちに、なりたかったなあ」
シラーは寂しそうだった。彼女は外の世界のことについて、カシオペアに色々なことを教えてくれた。
「夜にはね、空にお月さまが昇るの。お星さまたちもきらきら光っていて、綺麗なんだよ」
彼女が楽しそうに話していても、カシオペアは何も答えられずに、相槌を打つばかり。
――私はこの部屋以外、何も知らない。……私がはっきり分かるのは暗闇と、座っているこの椅子と、神さまのことだけ。
シラーが生き生きと話すのを見て、カシオペアは少し羨ましかった。
随分前から誰も見かけない。カシオペアは、自分が、もうとっくに誰からも忘れられてしまったのだと思った。
座っている椅子だけが、ずっと彼女の人生に寄り添っている。シラーとの思い出は、自分が勝手に想像して作り出したものではないだろうか。カシオペアにはそう思えた。
忘れられようと、今日もカシオペアは天に祈り続ける。それが彼女の生きる理由だから。
「おねえさん!」
その時、久しぶりに懐かしい声が聞こえた気がした。頭で考えるよりも先にカシオペアの唇が動く。
「シラー?」
「……? 違うよ。わたしの名前はルシア」
シラーと同じくらいの年頃で、口調も似ている。しかしその子が自分が思い描いていた子ではないことは、姿は見えずとも、声を聞いてすぐに分かった。
カシオペアはがっかりした。しかしルシアという少女は反対に、カシオペアのことが気になるようだった。
「あなた、お名前は?」
「……カシオペアよ」
「カシオペア?」
ルシアは驚くように声を上げた。
「あなた、お星さまと同じ名前なんだね」
「え?」
「星座のこと! ……ここで何をしているの?」
暗闇のなかで言葉だけが響いてくる。
「……待っているのだと思う」
「誰を? さっきのシラーって子?」
「そうね。……多分」
ルシアは不思議そうに見て、話を促す。
「いつから待ってるの?」
「ずっとよ、ずっと……。時間なんて分からないわ」
「そうなの?」
「だってそうでしょう? この部屋は石の壁に囲われていて何も見えない。だから、いつからなんて、私分からないわ」
「……そっか」
それを聞いたルシアは優しく答えた。彼女の話し方はなんとなくシラーに似ているような気がして、カシオペアは少し嬉しかった。
ルシアは元気よく言う。
「とにかく、カシオペアはシラーって子に会いたいんだね。じゃあ捜しに行こうよ! わたしも手伝うよ?」
「……無理よ」ルシアの提案を、カシオペアは悲しそうに拒絶した。
「私、ここにいなければならないの。みんなの為にも、ここでずっと祈り続けていなければならないわ」
ルシアは何も言わなかった。沈黙が流れる。
彼女に嫌われてしまったかもしれない。カシオペアはそう思った。
その時、ふと頬に何かが優しく触れた。目を上げると、そこには不思議な虹色の玉が沢山、ゆらゆらと漂っていた。
「これは……?」
「シャボン玉。綺麗でしょ?」
シャボン玉は彼女の身体をすり抜ける。
――どうして?
わけが分からないでいる内に、シャボン玉たちは部屋の上の方へと迷うことなくまっすぐ昇っていった。
――そこから外へは出られないのよ……。
カシオペアはそう思って天井の方を仰ぎ見た。けれどもそれは間違いだった。
確かに天井は存在した。しかしその石造りの壁は明らかに年月によって古びてしまっていて、穴がぽっかり空いてしまっている。その隙間からシャボン玉は広い空へと、ふわりと緩い曲線を描きながら飛び立っていった。
空には丸い月が一際明るく輝いている。
――さっきまであんなに暗かったのに、急に色んなものがとても良く見えるようになったわ。……それにしても、この部屋はどうしてこんなに急にぼろぼろになってしまったの?
カシオペアはやっとルシアの顔を見ることができた。カシオペアが自分を見ていることに気がつくと、ルシアは嬉しそうに笑った。
「やっとこっち向いてくれた」
パチンとカシオペアの中で何か弾けるような音が聞こえた気がした。
「あ……」
まるで魔法が解けたかのように、カシオペアは理解した。自分の街が滅んでしまっていて、自分自身も、もうとっくに死んでいたのだということを。だから誰も、ここへ来なくなってしまった。
「気づいたみたいだね。 ……一緒に外に出よう? 星を見に行こうよ」
促されて、カシオペアは恐る恐る椅子から立ち上がった。身体を縛っていた縄は役割を終えて、静かに朽ち果てた。
二人は部屋を出て外に出た。周りにはススキがどこまでも続き、建物にさえぎられなくなった紺色の空には、点々とした光がどこまでも広がっている。
「これが、星……?」
「そうだよ! それに、こっちがお月さま」
ルシアが満月を指差す。
「わたし、星のお話を知ってるんだ。あなたに教えてあげるね。今は秋だから……お姫さまが勇者さまに助けて貰って、幸せになる話ね。あれがお姫様のアンドロメダ、そしてこっちがペルセウス……お姫様を助けてくれるの」
聞いている内にカシオペアは、星たちがまるで命を持ったように動き始めて、物語を語り始めているような気がしてきた。
「それであそこにある星をつなげると、カシオペア! あなたと同じ名前なんだよ。昔神さまに怒られて、椅子に座ったまま空を回り続けなきゃいけなくなってしまったんだって」
カシオペア。自分と同じ名前を持つ星の形を、彼女は食い入るように見つめた。
「おねえさん」
もう一度懐かしい声が聞こえて、カシオペアはひどく驚いた。
声のした方を向くと、半透明の身体をした女の子がこっちを見ていた。姿は知らなかったが、声は間違いなく知っている。
「シラー……」
シラーははにかむ様に笑った。彼女の身体の向こう側には、ススキが揺れている。
「おねえさん、ずっと気づかないんだもの。わたしはいつもお姉さんに話しかけてたのに」
「そうだったの……ごめんなさい」
自分の殻に閉じこもっていた彼女には、シラーの声など届かなかった。死んでしまってから、カシオペアは世界に閉じ込められていたのではなく、自ら世界を拒絶し、閉じこもっていたのだった。カシオペアはそのことを自覚して、シラーに語りかけた。
「私は多分、あなたの話を聞いてから、外の世界のことをもっと知りたくなってしまったのね。もっと知りたかったのに、外の世界を何も感じることができずに、自分が死んでしまったのが嫌だったんだと思う。だから、身体を失ったまま独りでずっと、ここに居た」そう言ってから、少し眉をひそめて、「……自分のことなのに、気持ちがはっきり分からないなんて、なんだかおかしいわね」と、恥ずかしそうに笑った。そんなことないよ、とシラーも笑う。
「……実はね、わたし、もっと早く、おねえさんに言いたいことがあったの」
シラーは少しためらいがちに言葉を紡ぐ。
「わたし、おねえさんと普通のお友だちになりたかったって、言ったじゃない?」
「ええ」
「本当はね……わたし、おねえさんとお友だちになりたかったんじゃないの。……お友だちじゃなくって、家族になりたかったの」
「えっ……?」
あまりにも予想外な発言に、カシオペアはびっくりした。
「お父さんとお母さんから、わたしに血のつながったお姉ちゃんがいるって聞いたの。……でもお姉ちゃんは、みんなのために、わたしたちと離れて暮らさなきゃいけないんだっていうことも聞かされてた。それでもわたし、お姉ちゃんに会いたくて……おしゃべりしてみたかった。その人に、お姉ちゃんって言いたかった。……そのお姉ちゃんが、おねえさんのことなんだ」
カシオペアは突然の告白に、頭の整理が追いつかなかった。
「そうなの? 私があなたの、お姉さん?」
シラーはこっくり頷いた。
戸惑っている所にルシアが声をかける。
「その子、捜してた子だよね? 会えて良かったね!」
ルシアは自分のことのように喜んだ。
「ふたりは姉妹なんだね」
「そうみたい。……でも、突然すぎて、実感が湧かなくて。だって、私とシラーって、全然違う気がするもの」
その言葉にシラーも頷く。
「わたしも、おねえさんとわたしって全然似てないなって思う。わたし、おねえさんみたいに落ち着いてなくて、子どもっぽいし……」
「私は、シラーみたいに自分が感じていることを上手く伝えられない。この子みたいに明るく振舞えなくて、それが羨ましかったわ」
ふたりの話を聞きながら、ルシアは少し笑う。
「そっか。でもね……わたしはあなたたちが姉妹っていうの、なんか分かる気がするよ?」
カシオペアとシラーは不思議な様子でルシアの方を見る。
「わたしには、おじさんがいてね……お父さんと兄弟の。ふたりとも全然性格が違くて、いつも喧嘩ばっかりしてるんだ。でもね、本当は仲が良いんだよ。カシオペアとシラーも、仲良しなんでしょ? なら別に、性格が似てなくても、それが姉妹じゃないなんて理由にならないんじゃない? ……それに」
「それに?」
ふたりが同時に尋ねるのを聞いて、ルシアはやっぱり笑った。
「……ほら、今の、そういう所。やっぱり姉妹なんだなって思うよ。息ぴったり」
カシオペアとシラーは驚くように顔を見合わせて、照れるようにふたりとも笑った。その時のふたりの顔はお互い、相手にそっくりだった。三人はひとしきり笑いあう。優しい風が吹いていた。
「お姉ちゃん」
「なに?」
「お姉ちゃんは、みんなからカシオペアって呼ばれてたけど、それはお母さんがつけた名前じゃないの。……わたし、知ってるんだ。お姉ちゃんの、本当の名前。……シェダルっていうんだよ」
「シェダル……」
シェダル。カシオペアは繰り返し呟く。カシオペアは自分自身が身も心も軽くなったのを感じた。自分に自分だけの名前が与えられることによって、「カシオペア」という、役に縛られた者ではなく、普通の人間の「シェダル」として居ていいのだということを、少し実感できたような気がした。
「シェダルお姉ちゃん、いこう。お父さんもお母さんも、お姉ちゃんが来るのを待ってるよ」
シラーが差し出す手を、シェダルは強く握る。彼女はルシアの方を見て微笑んだ。
「ありがとうルシア。……さよなら」
「バイバイ、シェダル」
ルシアが手を振ると、穏やかな風がふたりを乗せて舞い上がる。
ふたりの魂は、遠い星空の向こう側へと、旅立っていった。
主を見守る役割を終えた椅子は、月光に照らされて、静かに自分が滅びる時を、待ち続けている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
