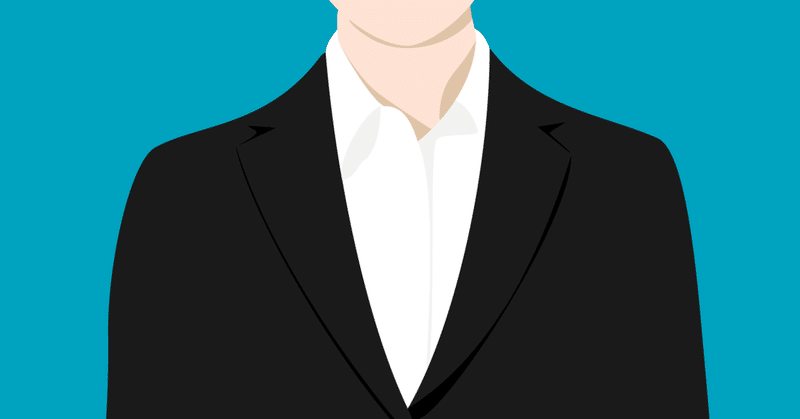
何者でも共感できる小説【『何者』を読んで】
はじめに
朝井リョウ氏の小説『何者』(新潮文庫、2015年)の感想を述べる。著者は本書(厳密には私が手に取ったのは文庫版であるが)で第148回直木賞(2012年下半期)を受賞した。
本作は映画化され、2016年に公開された。私は当時その映画を観たが、映画の内容が、特にラストの「どんでん返し」が強く印象に残っていた。大学生になった現在、再び映画を観てみようと思い観たら、さらに引き込まれ、原作を読んでみることにした。私は、普段小説はほとんど読まず、ブログに読書感想文を書くとしても論説文がほとんどであるが、せっかく読んだので感想を文字にしておこうと思った。
本書のあらすじは以下の通りである。
就職活動を目前に控えた拓人は、同居人・光太郎の引退ライブに足を運んだ。光太郎と別れた瑞月も来ると知っていたから――。瑞月の留学仲間・理香が拓人たちと同じアパートに住んでいるとわかり、理香と同棲中の隆良を交えた5人は就活対策として集まるようになる。だが、SNSや面接で発する言葉の奥に見え隠れする、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えて……。(裏表紙より)
引くほどリアル
本書の内容は、現実の世界を鏡のごとく映しているようである。それは、本書に散りばめられた、日常の普段は言語化されないような些細な状況が、登場人物の心情と重ねられるように描かれる情景描写にまずいえる。直接話法が地の文にそのまま出てくることも多かったが、それもセリフと言うよりかは音声として描かれている感じを醸し出している。文を読みながら、具体的な状況を思い浮かべやすいという意味で「リアル」であった。
しかし本書で最も注目されるべき「リアル」は、登場人物の個性である。主人公の拓人は、人間を観察し、まるで演劇のプロデューサーのように分析を行う、落ち着いた感じの男性である。一方で、光太郎は、明朗快活で、ノリで生きているような振る舞いを見せつつも、実は合理的な一面も垣間見える(ちなみに留年している)。理香や隆良は(両者のベクトルは違えど)いわゆる「意識高い系」で、私のようなひねくれた人間や拓人がどうしても心のどこかで嘲笑してしまうような人種である。舞台である御山大学は、おそらく中堅から少し入学が難関なくらいであると思われるが、そこに所属する彼らは「大学生の縮図」かのようである。このように本書は、登場する人物の人となりが、いかにも「あ~いるなぁ~こういう人」と共感できるようにありふれていて、それが詳しく描写されるところが特徴といえよう。
加えて、SNSと就活という題材がいかにも現代的である。本文中に、幾度となく彼らのツイートが登場するが、そのツイートは彼らの特徴をうまく表しているうえ、やはりどこかで見たことがある感じがする(ステレオタイプ的で一周回って見ない気もするが)。ツイートという私たちの日常にあるものがそのまま出てくるので、作中の世界観に親近感が湧き、自らもその世界の一員かのように没入する感覚さえ抱く。一方で就活に関する描写もかなり現実での実態を捉えているようである(これはなんとなく思っただけで、私は本格的な就職活動はまだしていない)。「リクルートスーツ」「インターン」「ES」「キャリアセンター」「模擬面接」「OB訪問」「webテスト」「グルディス」「内定」。数々の就活用語が頻繁に、普通に文章内に登場し、臨場感のある就活模様が描かれる。現代的な題材でいかにも「リアル」な印象を読者に抱かせ、引き込んでいく。
就職活動に関連して、本書の言葉で非常に共感したものがある。光太郎の就活についての持論である。
「俺って、ただ就活が得意なだけだったんだって」
「足が速いとかサッカーがうまいとか、料理ができるとか字がうまいとかそういうのと同じレベルで、就活が得意なだけだったんだよ」
「なのに、就活がうまくいくと、まるでその人間まるごと超すげえみたいに言われる。就活以外のことだって何でもこなせる、みたいにさ。あれ、なんなんだろうな」
「それと同じでさ、ピーマンが食べられないように、逆上がりができないように、ただ就活が苦手な人だっているわけじゃん。それなのに、就活がうまくいかないだけで、その人が丸ごとダメみたいになる」(p.291)
本書を読み進めていき、就活に関するリアルな状況をみていくにつれて、就活が一種の競技、スポーツのように感じてくる。特殊な訓練と試験を伴う就職活動は、人間性そのものが評価されているようで、実は一定のルール上での競争に適応できるかが問われているかのようである。
このように、本書は描写がリアルなだけでなく、人間の様子や就活のなんともいえない雰囲気をリアルに感じとらせる。
[以下、ネタバレ注意]
ラストに読み手が指される仕組み
人物の分析が好きな主人公の拓人は、実はTwitterの裏垢で、光太郎や理香、隆良などを冷笑するようなツイートをしていた。それが物語終盤、理香にバレていたことが発覚する。理香は拓人に以下のように詰め寄る(これは、本当のタイトル回収の場面でもある)。
「距離をとって観察していないと、頭がおかしくなっちゃいそうになるんだもんね。でもね、そんな遠く離れた場所にひとりでいたって、何も変わらないよ。」(p.316)
「思ったことを残したいなら、ノートにでも書けばいいのに、それじゃ足りないんだよね。自分の名前じゃ、自分の文字じゃ、ダメなんだよね。自分じゃない誰かになれる場所がないと、もうどこにも立っていられないんだよ」
「心の中で思ってることって、知らず知らずのうちに、相手に伝わっているもんだよ。どれだけちゃんとスーツ着てても、どれだけもうひとつのアカウントを隠しても、あんたの心の内側は、相手に覗かれてる」
「カッコ悪い姿のままあがくことができないあんたの本当の姿は、誰にだって伝わってるよ。そんな人、どこの会社だって欲しいと思うわけないじゃん」
「そうやってずっと逃げてれば? カッコ悪い自分と距離を置いた場所で、いつまでも観察者でいれば? いつまでもその痛々しいアカウント名通り【何者】かになった振りでもして、誰かのことを笑ってなよ。就活三年目、四年目になっても、ずっと」(p.317-318)
これはなかなか突き刺さるセリフである(特に映画ではホラーであった)。観察者として分析し、自分は周りの人間よりも高次の世界にいると思っていた(思い込むようにしていた)拓人にとっては、耳が痛い。
このシーンでさらに面白いのが、この小説を読む読者も、拓人のようにダメージを負うという点である。おそらく読者は、本書の前述したようなリアルな描写によって作中の世界に没頭していく一方、「光太郎ってこういう奴だよな」「理香は○○な感じだよね」というように、人物を批評するなど、様々に「観察」と「分析」を行ってしまう。私たちは、本書の人物について考えてしまったうえで、終盤のシーンを読むことで、大げさに言えば小説の登場人物と読者というメタ的な関係を崩されてしまうような感覚に襲われる。読みながら神の視点から登場人物を捉え、「何者」かになったつもりで批評し、人に話したりそれこそブログなんかに記したりしていると、本を持ちながら震えることとなってしまう。
ちなみに、拓人に関する描写は小説と映画では少し異なる。映画では「心の声」のようなものはあまりないため、最後に「こいつこんなことしてたのか!」となるのに対し、小説でははじめから拓人の本音が、心理の記述によってそこそこ明らかになる。いくらか拓人が考えていたことがわかっていたからか、小説を読みながら「拓人イタいなぁ…」と思う部分もあったが、そこで(私が先に映画を観ていたこともあるかもしれないが)、理香さんの言葉でカウンターを食らってしまう。
「下手くそでも向かえ遠く向こうへ」
私がこの物語から強く感じ取ったことは、「ポジティヴな面もネガティヴな面もありながら、それを受け入れてなんとかもがいて生きていく人間」である。
拓人が指摘するように、光太郎や理香、隆良にはマイナスと捉えられる一面がある。光太郎は内輪のノリでバカ騒ぎするお調子者である。理香は肩書をひどく意識し、自己顕示欲とプライドが高い。隆良は自分が特別で、周りよりも感性が鋭いと思い込んでいる節がある。
一方で、これらの登場人物は完全に嫌な奴じゃないということもわかる。光太郎はとてもやさしく、正直である。理香は泥沼かと思いきや、拓人に「ダサくても続けるしかない」と説きながら、自分の弱さにも気づこうとしていた。映画オリジナルの演出ではあるが隆良も、拓人に「教えてくれよ」と下手に出るなど、終わりには人間的な成長を見せた。拓人本人ですら、最後の面接のシーンでは前とは違う感じがした。
このようなことを考えて小説を読み終えたところ、少し関連した内容が、三浦大輔氏の解説にもあった。
朝井さんの作品は、社会に警鐘を鳴らすような、強い問題意識を提示するような、いわゆる説教じみたものであるはずがない。ただ、そこにいる人間をありのままに描き、その愚かさをも含めて、全てを受け入れる。高尚なテーマを掲げたがる、頭でっかちな作家たちが目もくれない「俗」を見つめ続け、そこに無防備に石ころのように転がっている「本質」を逃がさず拾い集める。(p.345)
これらの人間の二面性、あるいは多面性とその矮小化は、光太郎の「『就活』が得意だっただけ」という主旨の発言と平行する。様々な能力が存在する中での1つの物差しにすぎない「就活」が、それ自体が人間の価値を決めてしまっているということが、人間を一面だけ見てTwitterで冷笑する態度にどこか重なってみえる。「採用」か「不採用」で二元的に人間を評価されてしまう(評価されざるをえない)就職活動と、実はTwitterなどでは分析できない人間の多面性というコントラストが興味深い。
以上のように本作では、「カッコ悪い」「イタい」「ダサい」「黒い」といった一面がありながら、なんとかもがいていく中で、完璧でも極悪ない「何者」かになろうとする人々が描かれる。そこに私は、「ポジティヴな面もネガティヴな面もありながら、それを受け入れてなんとかもがいて生きていく人間」の影をみた。
瑞月さんの黒い面も見たかった
ただし、瑞月に関しては「負の面」が感じ取れなかった。瑞月は、素直に他人の良さを認められて、健気で、家庭環境が荒れても力強く生きていこうとする、「悲劇のヒロイン」のような印象がある。そして、拓人や理香たちを受け入れようとする寛容さや、価値観が違う隆良に考えを伝えようとする気概もある。それに対し、黒い部分やダサい部分は挙げようとしても思いつかない。「好きフィルター」かもしれないが、拓人のアカウント【何者】でも叩かれていない。
私ははじめ、瑞月さんは拓人の憧れということもあって、理想的な人間像として存在しているのかもしれないと思った。人間の正と負の二面性を自覚し、受け入れ乗り越えた人間である。しかし、二面性に気づけたからといって、負の面がなくなるわけではない。もし「誰々より○○の方が進んでいる」みたいな線形的なモデルや、「これが正解」みたいな理想像があったら、それは多面的な人間が力を振り絞って生きていく様子とミスマッチである。
「負の面も見たい」という感想はサワ先輩にも抱いた。瑞月さんもサワ先輩も、自らの正負両面と向き合いながら懸命に生きているはずではないであろうか。その様子も描かれると、より本書全体から上記のような人間像を感じ取れる。もっとも、紙幅の都合上描き切れなかったのかもしれないが。
おわりに
本作は、現代の就活する大学生、というように若者の限られた特殊な状況を描いているようで、実は人間の普遍的な本質を題材としている、非常に長い射程をもった作品である。であるから、多くの人に楽しまれる(楽しまれている)のであろう。
映画と小説の片方だけでもみてみてほしいが、どちらもみるつもりなら、私は映画から見ることをおすすめする。ラストシーンは拓人が学生時代に力を入れた(ている?)演劇が効果的に演出として用いられ、衝撃展開がより映えるからである(ここまで読んでくださった方は真ん中のネタバレ部分も読んでしまったであろうか)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
