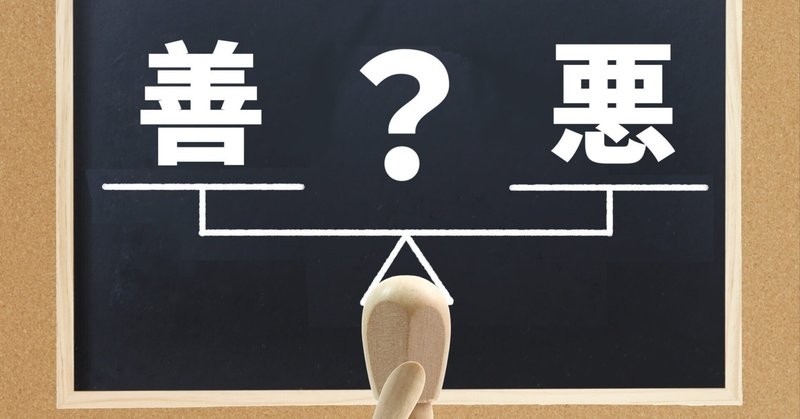
教育の中で最も重要なのは「徳育」?「徳育」の効果とは
国の教育目標の4つの「育」である「知育」「食育」「体育」「徳育」。この中で、徳育は忘れがちですが、人生の中ではとても重要なものです。子どもの教育に、もっと「徳育」を取り入れていけるよう、今回は「徳育」の重要性についてお伝えします。
●国の教育目標達成のためには「徳育」を!
みなさんは国の教育目標をご存知ですか?国は教育の目標を「知・徳・体の調和のとれた発達を基本に、自主自律の精神や、自他の敬愛と協力を重んずる態度、自然や環境を大切にする態度、日本の伝統・文化を尊重し、国際社会に生きる日本人としての態度の養成」と定めています。
少し堅苦しい言いまわしですが、現在の教育でこの目標は達成できているのでしょうか?昔と比較すると、教育も受け身の授業から、自分で学び、考え、生きる力を育てようとするものに大きく変化してきました。しかしながら、目標が達成していると断言するのは難しいかと思います。
それは、教育目標の後半にある「徳育」がまだ足りないからではないでしょうか?「徳育」は子どもの夢や志をどのように育て、大人になってからどう社会と接し、貢献していくかを教えていくものです。学校の道徳の授業では、社会一般のルールを学びますが、個人の夢や志を具体的にどう育てていくのか、というのは親の仕事になります。親もこの機会に、徳育について学んでみてはいかがでしょうか。

●「徳育」はあらゆる教育の礎
七田式創始者である七田眞氏は、「徳育」を江戸時代の思想家、中江藤樹の本で学びました。中江藤樹の本には、「子育てで大切なのは、人間として生きる道を教えることだ。いくら才芸に優れていても孝徳がない人は一時的な栄華を手に入れても、子孫は栄えない」という内容があり、この考えに触れ、徳育の重要性に気づいたそうです。
徳育を通じて身に付けられる資質、能力としては、「自己の生き方を探求する力の育成」「人間関係能力」「社会の一員としての責任感の育成」などが上げられます。どれも、大人になってから非常に重要なものですよね。
また、徳育は食育、知育、体育とも重なる部分が存在します。例えばスポーツを通してルールやチームワークを学ぶことは、徳育と体育が重なり合う部分になります。食育、知育、体育を取り入れている家庭も多いと思いますが、ぜひ一緒に徳育も子どもの教育にもっと取り入れてみてください。
人生において、全ての物事が論理的、合理的に進むわけではありません。人には感情があるので、頭で理解していても実際は違う選択をすることは多々あります。その感情で選択してしまう時、判断基準となるのがその人の「徳」です。子どもが大人になり、自分で選択しながら生きていくなかで、周りの人や自分のことを大切に考えられる選択をすることができるよう「徳育」をしていきましょう。
