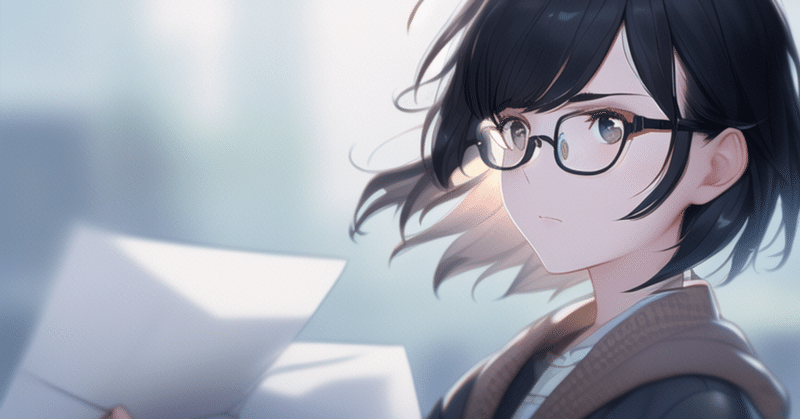
大学入学共通テスト「生物基礎」を解いてみよう——教科書をちゃんと読もうねという話
週末は大学入学共通テストが開催されました。生物系のサイエンスライターだし、せっかくなので生物科目の問題を解いてみることにしました。果たしてサイエンスライターと名乗るにふさわしい点数を獲得することができるのか!?(センター試験時代から12年連続使っている文章のコピペ)
文系志望が解く生物基礎
この記事では、まず「生物基礎」にチャレンジします。この科目を選択するのは、文系学部志望の受験生です。
生物基礎という科目は、文系のほとんどが解く問題であり、もちろん理系選択者は学習の範囲内です。つまり、今の高校卒業生は全員授業でやっていることとと考えてください。問題と解答はいろんな予備校のウェブサイトにあります。
さて、僕の結果は……

50点中50点の満点!生涯現役!!
教科書をしっかり読んで基礎固めをしよう
2年前の新傾向になってから長文読解や初見のグラフなど、「基礎知識があることを前提にその場で思考力を問う」というものは変わらずですが、今年は少し弱まったかな、という印象です。むしろ、「教科書に書いてあることをどこまで習得しているか」にやや重きを置いたかな、という感じ。
たとえばこの問題。

「ふむふむ、1つの場所で10万塩基対複製できるとすると、精子には30億塩基対あるから割り算で3000だ!」で考えるとトラップにハマります。
というのも、精子と卵子は減数分裂によってできるので、問題になっている体細胞の半分しかDNAをもっていません。なので、体細胞には60億塩基対あることになり、この数字を10万で割って6000が答えとなります。
減数分裂は、手元の教科書を見ると「発展」枠なので、こうしたところも含めて隅々まで教科書を読み込んでいないと苦戦しそうです。
そうそう、こういう問題もあります。


免疫のしくみをしっかり知っておきましょう、という運営からのメッセージを強く感じます。予防接種は前からずっと教科書には書いてあるんだけど、少し複雑化して広義の予防接種を問題にしているということは、まあそういうことなんでしょうね。
オトナのみなさんもぜひ考えてみてください。
おすすめ図書
↑生物基礎を受けるならこれを読んでおけば間違いなし。僕が現役のときからいまだに第一線で活躍している先生。
↑僕が編集協力した本。生物は暗記科目ではないですよ、体の中で起きていることを流れで理解すればいいですよ、という内容。今回の共通テストの考えにかなり近いです。
↑血液や免疫が苦手な人はこちらで勉強するのもおすすめ。
今週読んだ本(今年から始まる新コーナー)
* * *
noteユーザーでなくてもハートマーク(スキ)を押すことができます。応援よろしくお願いいたします。
(サムネイル画像はNovelAI作成)
ここまで読んでいただきありがとうございました。サイエンスの話題をこれからも提供していきます。いただいたサポートは、よりよい記事を書くために欠かせないオヤツに使わせていただきます🍰
