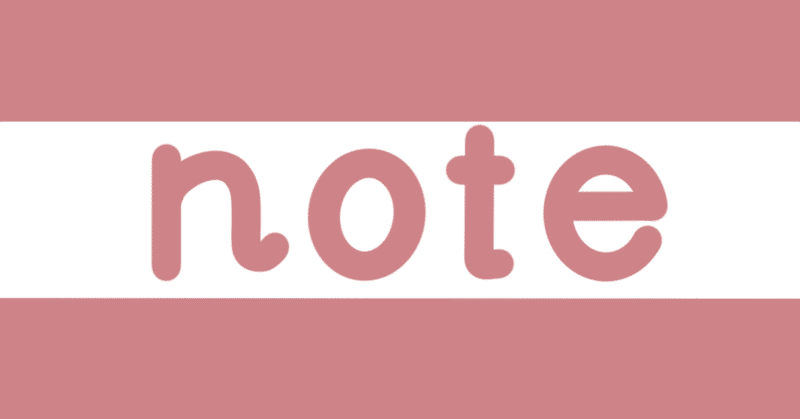
#2 多忙と文章制作
お久しぶりです。
Tomoyaです。
投稿間隔が開いてしまいました。
昨年末から今日まで、多忙な日々を送っています。
詳細は割愛しますが、日々、文章を書くことに追われ、精神的にも消耗する日々を送っています。
先日、1つの節目を迎え、次の節目に向けて、再始動するところです。
次の節目が過ぎると、もう少し余裕ができるので、そこまでは気を切らさない様に注意したいと思います。
さて、今回は、文章に向き合うことに費やしたここ数ヶ月に感じたこと及び考えたことについて書いていきたいと思います。
「文章制作って、考えることが多い。」
これが私が最近感じたことです。
好きな様に書けないのは分かっていたけど、予想以上の修正が毎回あります。文章構成のミス、内容の変更、全体のスタイルから細かい表記の指示まで色々なことが間髪入れずに舞い込んできます。勿論、自身の間違いも多々あるのですが、中には読んでもらう相手が持っている、文章に対する感覚の様なものなど、客観的に正誤の判定ができないものまでやってきます。正誤判定ができるのであれば、まだ楽ですが、個人の感覚にまで注意すると、考えることは倍増です。
どこまでいけば、完成なのか。どこまで書けば、気が休まるのか。
毎日考えては、精神を擦り減らし、擦り減らしては、疲れる。
文章制作に関わることは大変なことだと感じます。
以上の様に、頭がやや混乱気味ですが、冷静に考えたことを1つだけ書いておこうと思います。
それは、「文章制作は読者ありき。」
ここで大事なのは、「読者」の定義です。
読者って、誰を指すのでしょう。
よくある回答は、「この文章を読んでくれる人」というものです。
この回答、実は、答えになっていないと、私は思います。
具体的に誰なのかを指定しないと読者の定義はできていません。
例えば、小説家なら、「本を買ってくれる一般の人」または「自分のファン」だと考える人は多いのではないでしょうか。
私の考えは、違います。
小説家にとって「読者」とは、文章を添削する「編集者」だと思います。
本が書籍化するためには、編集者の承認が必要です。
編集者を納得させることができなければ、本は出版できません。
この様に、自分の文章の読者とは、「自分の文章を最初に提出する人」だと私は思います。
他の例を考えてみます。
論文を書く研究者の「読者」は、「学会誌の編集者」です。論文を学会誌に送ると校正や質問が返ってくるそうです。そして書き直し、認められて初めて公開されます。論文の読者は「他の研究者」だと思ったら何度も訂正を食らうでしょう。それでは苦労が増すだけです。
大学生であれば「レポートを見る教授」、受験生であれば「採点者及び作問者」、NOTEの様なWeb記事やSNSだと「アクセスしてくれる人及びNOTEの運営チーム」だと思います。例え感動的な記事を書いても、運営上良くない文章はおそらく削除されます。
この様に、自分の「読者」は誰か、ということを意識することで、少し楽に文章制作ができるかもしれません。「読者」の定義は大事です。
以上が私がここ数ヶ月で考えたことになります。
今回は、時間の都合上、文章をよく見直すことができていませんので、間違い等はご容赦ください。また、個人の一意見ですので、考えが違った時はスルーしていただけると幸いです。
これから間隔が開くかもしれませんが、また時間のある時に投稿したいと思います。
皆さんの参考にはならないと思いますが、読んでいただけると嬉しいです。
Tomoya
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
