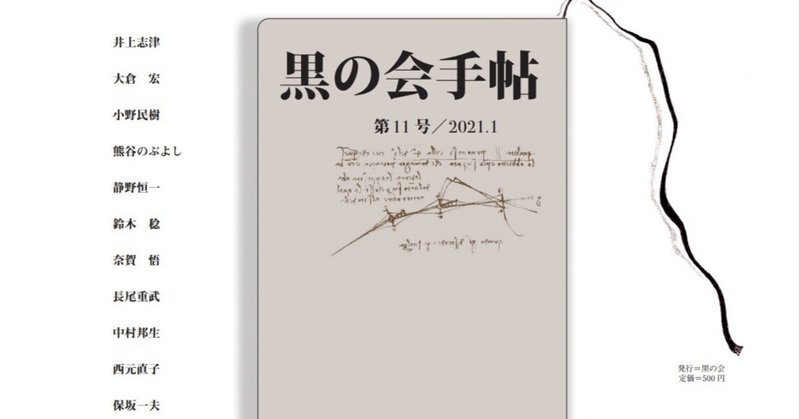
母の総括 その三 竜国館の謎
母が昨年六月、七十九歳で亡くなった。
母はがんが再発し、大学病院での約一年に及ぶ抗がん剤治療を経て、緩和ケア病棟のある病院に転院した。主治医から「これ以上の抗がん剤治療は逆に命を縮めることになるので、できません」と言われたためだった。どんなに無理と言われても抗がん剤を投与し続けて、治りたかった母は落胆し、渋々転院したので、亡くなるまでの七週間、緩和ケア病棟の病室は険悪なムードに包まれた。死にたくないのに緩和ケア病棟に入れられたと、一人娘の私を最後まで恨んでいた。
緩和ケア病棟の看護師は大学病院よりも患者と向き合う時間が多く取れるので、私はいいと思ったが、そのことに対しても怒っていた。
「トイレに行くと、いちいちついてきてうるさい」
「夜中、そっとカーテンを開けてこっちを見ているからいやだ……」
「看護師さんはママのことを心配してくれているんだよ」と言っても、決して納得しなかった。
痛みを取るため、モルヒネを投与されることにも不満を持っていた。母は三度目の再発で腸閉塞になり、大学病院に緊急入院して、そのまま抗がん剤治療に入ったが、そのときから実はモルヒネとは違う名前の医療用麻薬を投与されていた。でも、治療に意欲を燃やしている最中だったし、痛みはうまくコントロールされていたからか、その薬が何か、母はあまり気に留めていなかったようだ。けれど、緩和ケア病棟では抗がん剤治療をしないのにモルヒネを投与されるので、不信感を抱いたらしかった。
母は私に「モルヒネを打たれていると、竜国館のおばあさんみたいに頭がおかしくなってしまう」と訴えた。「リュウコクカンって?」と聞くと、「あんたには分からない」と冷たい目をして横を向いた。「旅館? お化け屋敷?」としつこく聞いた結果、「八幡の竜国館のおばあさんが昔、モルヒネ中毒になって気が狂って怖かった」ということだけ教えてくれた。しかし、私はそれを聞いても医師にモルヒネの投与をやめてくださいと言いに行く気にはならず、「それって戦後のヒロポン中毒とかと一緒でしょう。今のモルヒネは医療用だから昔とは違うんだよ」と返したので、母は「志津はどうせママの味方ではないからね」と言って口をつぐんだ。
転院から二週間くらい経ったころ、看護師から「だんだん眠っている時間が多くなると思いますので、意識がはっきりしている間に会いたい人に来てもらってください」と言われた。大学病院にいたとき、主治医から「残された時間を会いたい人と会うとか、言いたいことをしっかり伝えるなどして過ごされたほうがいいのではないでしょうか」と言われた母は、「会いたい人は別にいません」と答えて主治医を絶句させたものだが、この看護師の言葉を告げると「ユウコちゃんに来てもらって」と言った。「竜国館の話をしないといけないから」
母は四人きょうだいの末っ子で、七つ上の姉「ユウコちゃん」だけが存命していた。新型コロナウイルスの感染防止のため、普段の面会は私と高校生の娘の二人だけに限られていたが、ユウコおばちゃんと従兄がその日は特別に面会できることになった。面会の翌日、私は母に「どうだった?」と聞いた。母は「ユウコちゃんは耳が悪いから話がちんぷんかんぷんだった」と言うだけだった。
それから四週間後、母は息を引き取った。緩和ケア病棟では、母はたいてい怖い顔で「志津は病院にだまされている」とか「治療をしないこの病院に来たのが間違いだった」と私を責めたので、私は面会時間が十五分と決められているのをいいことに、毎日、逃げるように帰っていた。だから、自分が死んだら誰と誰に連絡をしてほしいとか、葬式はこんなふうにしてほしいとか、そうした事柄は一切聞いていなかった。そもそもそんな会話をこれまでにしたためしがなかった。父が二年前に亡くなってから、母のマンションのリビングには父の遺骨が置かれていたが、それをどうするつもりだったのか、父方の墓は福岡にあったが、母はその墓に入りたくないと言っていたので、それならどうしてもらいたかったのか、聞かない私も悪いし、そうした話は本来、もっと元気なころにするべきだったのだろうが、母と私はそんなことができる良好な関係になかった。
私は母が愛用していた赤い手帳を開いた。
母は父が晩年、パーキンソン病と認知症で寝たきりになったとき、胃ろうから気管切開、心臓マッサージ、人工呼吸器、昇圧剤までありとあらゆる方策を取るよう病院に要請したので、父は晩年の数年を、私から見ると「生きる屍」の状態で過ごした。私は「これ以上延命するのは見ていられない。本人の身になって」と抗議し、対立したが、母は自分が最後の入院で人工栄養法の措置が取られると、死が少し身近になったのか、「パパの死に方があれで良かったのか、まだ総括ができていない」とつぶやいたことがあった。母も母なりに悩んでいたのかと、少しかわいそうになったことを覚えている。
そのときから一年が経っていたので、父に対する思いや自分の死に方や、死を受容する苦しみなどについて、手帳に記されているかもしれないと私は思った。死後に私が困らないための連絡事項、もしかしたら、私への感謝のメッセージなども……。
しかし、手帳には何も書かれていなかった。母は何十年も前から毎年、赤い手帳を買い求め、日記代わりに使っていた。二〇二〇年の手帳は体がきつかったのか、ほとんど白紙だったが、二〇一九年の手帳は私の悪口ばかり書かれていた。その年の二月、私と娘は最後の旅行になると思い、母と三人で沖縄旅行に行ったが、母が思い描くような贅沢な旅行ではなかったからか、体がしんどかったからか、母はあまり笑顔を見せなかった。手帳には「もう志津たちとは旅行したくない」と書いてあった。
ただ、二〇一九年の手帳にはコピーが一枚挟まれていた。葬式でよく読まれる「白骨の章」である。
「おほよそはかなきものは、この世の始中終まぼろしのごとくなる一期なり。……朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり。……さてしもあるべきことならねばとて、野外におくりて夜半のけむりとなしはてぬれば、ただ白骨のみぞのこれり、あわれというも中々おろかなり。……あなかしこ、あなかしこ」
母はクリスチャンの友人が差し入れた「心をいやす五十五のメッセージ」という本を「枕元にこれを置いていたら、私が心をいやしたいと思っていると看護師に思われるからいやだ」と言って私に持ち帰らせたし、同じく差し入れられた聖書も結局開かなかった。でも、少なくとも母なりにいろいろと考えている途中だったことは分かった。
葬式についての希望は何も書かれていなかったので、私は家族葬を行った。父の葬儀のときは、お金は出さないのにケチは付ける母のせいでストレスがたまったが、母の葬儀では文句を言う人がいないので、なんて気が楽なんだろうと思った。
葬式のあと、私は伯母に「おばちゃんが面会に来てくれたとき、竜国館の話はしたの?」と尋ねた。
「そんな話は全然出なかったよ」
伯母は答えた。
母は伯母に「もう一度元気になって、外にお茶を飲みに行きたい」と「駄々をこねだした」という。それで伯母はこう諭したという。
「誰でもみんな、いつかは死ぬんだから、怖いことはないよ。私なんて不精者で、この世が面倒くさいから、苦痛さえなければいつ死んでもいいと思っているんだよ。あんたがぐずぐずしている間に、渡っている長い橋をすぐ追いついて、一緒に渡ってあげるから怖くないよ」
母はウン、ウンとうなずき、伯母の手を握って泣いたという。
「あの気の強い子が私の前で泣くなんて初めてだったから、ビックリしたけど、とても可愛らしかったよ」
私は伯母に竜国館のことも尋ねた。
竜国館は母が子どものころに住んでいた福岡県八幡市(現北九州市)の家の隣にあった映画館だったという。映画だけでなく、地方回りの歌舞伎や新劇、レビューなど何でも上演する芝居小屋だったそうだ。母たちはその後、空襲を逃れて大分に疎開したため、ほんのいっときの思い出しかなかったようだ。
「竜国館のおばあさんはね、四国の担ぎ売りから九州に流れてきて侠客と出会ってさ、興行界に幅をきかすまでになったんだよ。竜国館の建物は隠れ家みたいな、暗い秘密基地みたいな感じだったよ。私は小学四年生だったけど、マコ(母のこと)はそのころはまだ三歳だったから、竜国館のことなんて、ほとんど記憶にないはずだけどねえ。なんで覚えていたんだろうね。おばあさんがモルヒネ中毒で気が狂ったなんて。そんな記憶がなんであったんだろうねえ」
私は母から竜国館の話を聞きたくなった。
もしかしたら、私がもっと母に優しくしていれば、母は竜国館のことはもちろん、いろんなことを話してくれたかもしれない。もしかしたら、本当はもっと話したかったかもしれない。そう思う一方で、でも、やっぱり無理だったかもしれないとも思った。手帳にも「人に弱みを見せないこと」と書いてあった。その「人」の中には私も入っていたのだろう。
葬儀も終え、母のマンションを片づけていると、数十冊に及ぶ赤い手帳が見つかった。自宅に持ち帰り、開くと、そこかしこに私の悪口が書いてある。そのたびに落ち込んでいるので、娘は私に「もう手帳は捨てて、見ないようにしたほうがいい」と言う。
「ママのこれからの人生がダメになってしまうと思うよ」
でも、まるで中毒になったように、私は赤い手帳を見るのをやめられないでいる。
(黒の会手帖第11号 2021・1)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
