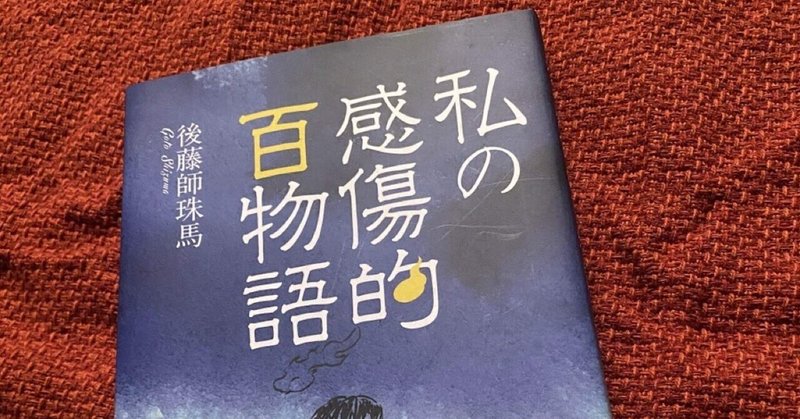
【私の感傷的百物語】第二十三話 豚の胎児を埋めに行く
高校時代、自然科学部に所属していた僕は、一応の「部室」である生物準備室に入り浸っていました。この部屋には、大量の実験機材と一緒に巨大な冷凍庫が置いてあって、いつもヴーンという低い唸り声を室内に響かせていました。冷凍庫の一番底には、解剖実験で使われた豚の内臓や胎児が入っており、初めて見た時には衝撃的でした。
その当時読んだ開高健の食べ物に関するエッセイに、朝鮮料理の「セキフェ」というのが載っていました。「赤ん坊の刺身」という意味だといいます。その作り方は、豚の胎児を羊水ごと抜き取り、包丁で細切れにするというもので、朝鮮ではご馳走とされていると書かれていました。これを読んで以来、時たま度胸試しに冷凍庫から豚の胎児を取り出す機会があると、セキフェのことが思い出され、どんな味がするのだろうと興味が湧きましたが、さすがに実際に調理する気持ちにはなれませんでした。
そんなある時、授業の準備などでたびたび生物準備室を利用していた、Yという生物の先生から、
「冷凍庫のスペースがなくなってきたから、豚の胎児や内臓を校内の松林に埋めてしまいましょう」
と指示を受けました。僕はなんだかもったいない気がしましたが、Y先生には日頃から授業の質問等でお世話になっていたので、率先して準備にとりかかりました。ビニール袋に入った肉塊を担いで、先生、そして同じ部員たち二、三人と連れ立って、僕は校門のそばにある松林へと向かいました。先生が、豚の胎児を眺めながら
「カワイイねえ、ふふふ」
と笑っていたのが、妙に印象的でした。
夕闇迫る松林の中へ入ると、ランニングしている運動部員にみられないように気をつけながら、スコップで地面を掘ります。松の落ち葉が積もった地面は思ったより固く、内臓や胎児を埋められるくらいにまで穴を広げるには、ずいぶんと骨が折れました。Y先生曰く、あまり浅いと、タヌキなどの野生動物が堀かえすおそれがあるので、なるべく深い穴のほうが良いのだそうです。数分ほど作業を行い、穴が完成すると、そこへ内臓、胎児を入れて、土を被せていきました。穴へ投じる直前に、あらためて見た胎児はカチカチに凍っていて、陶器の置物のようだったと記憶しています。穴を埋め終わり、動物にイタズラされないようスコップでしっかりと上から土を叩いていると、これまでの一連の行為が、まるで罪人が自らの犯罪の証拠を隠蔽しているかのように思えてきました。僕は周囲を神経質に確認する犯罪者になったつもりで、誰に見せるとでもなく、ニヤリと笑いました。
今でも、あの松林の下には我々が埋めた豚の胎児が眠っているのかと思うと、自分が血生臭い事件に関わったのを隠し、何くわぬ顔をして市井の住人へと戻った、そんな想像が沸いてきて、快感と恐ろしさが入り混じった、妙な気持ちになります。
豚の胎児の冥福を祈ります。
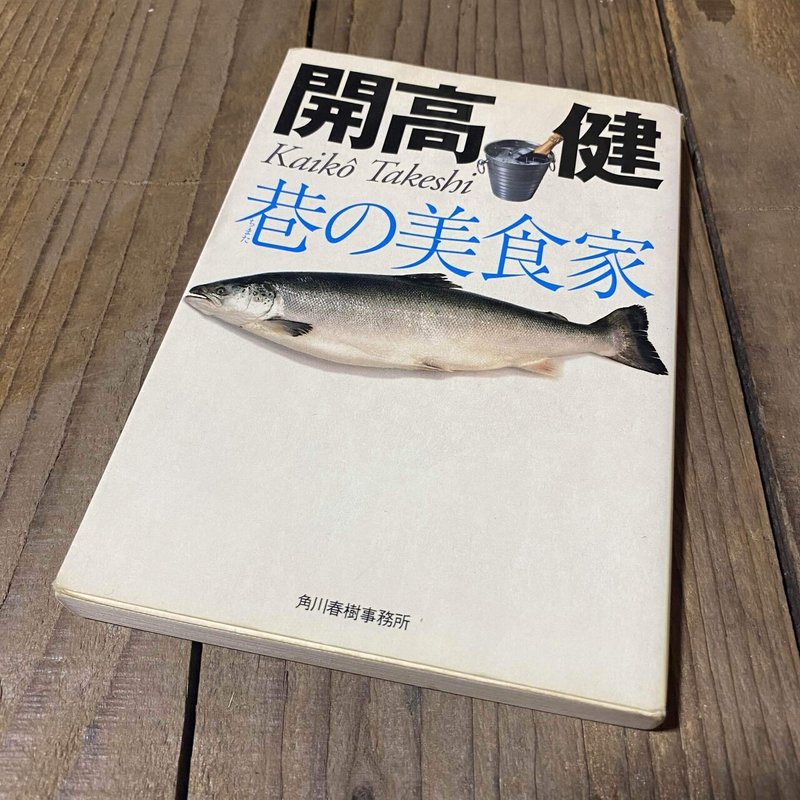
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
