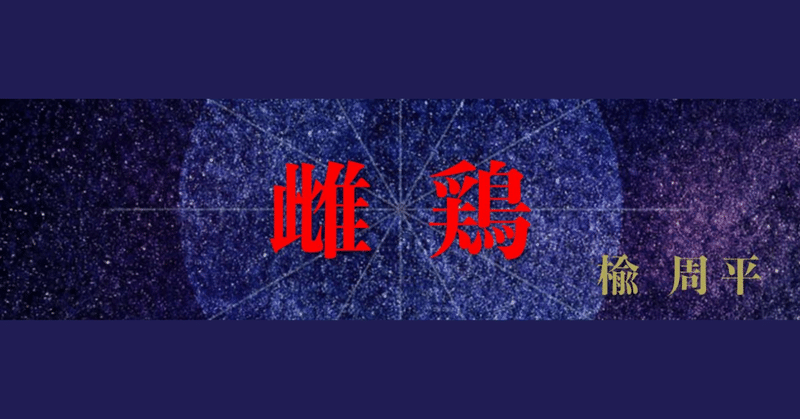
雌鶏 第六章/楡 周平
1
「ところで先生、ついでと言ってはなんですが、プライベートなことで一つご相談したいことがございまして……」
世間話に終始していた小早川(こばやかわ)が、改まった口調で切り出してきたのは、昭和五十年夏の夕刻のことだった。
初の来訪から四年。この間何度か卦(け)を立ててもらいにきたとはいえ、鴨上(かもうえ)を通さなければならないのは相変わらずだ。
突然現れた小早川は、「京都に用事がありまして、近くまで参りましたので、ご挨拶にあがりました」と、ふいに思いついて立ち寄ったかのように言う。しかし、東京の一流ホテルの洋菓子を持参し、一日の仕事が午後四時には終わるのを見計らったかのようなタイミングである。目的があってのことに違いないと踏んでいたのだが案の定だ。
「プライベートなこと?」
問い返した貴美子(きみこ)に、
「いや、掟(おきて)破りなのは重々承知しておりますが、たとえ鴨上先生であろうとも、他人には知られたくない悩みがございまして……」
小早川は神妙な顔つきで言う。
政治家は金のあるところに群がる。数は力となり、それすなわち権力となる。要は資金力に優(まさ)る者が権力を握るのが政界の力学なのだが、実際ヨドという資金基盤を確保して以来、小早川の台頭ぶりは、目を見張るものがあった。
選対委員に任命された菱倉(ひしくら)グループを突如離脱。主宰していた勉強会のメンバー十五名を引き連れて興梠(こうろぎ)グループに乗り換えた際には、長老議員の間から轟々(ごうごう)たる非難の声が沸き起こったものの、機を見るに敏でなければ政界では生き残れない。小早川の謀反がきっかけとなって、他グループの若手、中堅議員の興梠グループへの鞍替(くらが)えが相次ぐ事態となったのだった。
かくして大河(おおかわ)派を禅譲された興梠は、与党内最大派閥の長としての地位を確立。一連の動きのきっかけを作った小早川を興梠が高く評価したのは言うまでもない。
大河に代わって総理総裁となった興梠は、組閣と同時に小早川を大蔵政務次官に任命。小早川は中堅議員でありながらも、与党内で一目置かれる存在になったのである、
傍目(はため)には順風満帆、前途洋々そのもの。しかし、悩みなき人間はこの世に存在しないのは事実というものだ。
「悩みって、どんなことかしら?」
そこで、貴美子が訊(たず)ねると、
「ヨドから借り入れた資金の返済のことです……」
小早川は重い声でこたえる。
「返済? ヨドから返済を迫られているのですか?」
「いえ、そうではないのです……」
返済を迫られていないと言うなら、小早川が何を恐れているのか察しがつく。
借金が膨らみ続けていること以外に考えられない。
「資金を提供するのも、見返りを期待してのことですからね。とはいえ、先生は当選同期の中ではトップで、それも大蔵政務次官という重職にお就きになったのよ、大臣就任もそう遠くないでしょうから、ヨドだって先行投資と考えているんじゃありません?」
「だから怖いんですよ」
小早川の表情が、声が硬くなる。「実は、金を用立ててもらうに当たっては、ヨドが所有している手形に裏書きをするのが条件でして……」
「それって、どういう意味なのかしら?」
「裏書きをした会社なり個人が支払い義務を負うことになるのです。最初のうちは手形決済の期限内に返済いたしておりましたし、政務次官就任以降はパーティー収入、献金共に増えてもおります。ですが私が率いるグループが大きくなるに連れ、出ていく金も増えまして、正直なところ返済が追いつかなくなっておりまして……」
「なのにヨドは何も言ってこないわけね」
「最初に森沢(もりさわ)社長が『ある時払いの催促なしとはいきませんよ』と念を押されたにもかかわらずです……」
「興梠派が与党内最大派閥を確立するに当たっては、先生は大変な貢献をなさったわけじゃないですか。興梠先生だって、その点を評価して先生を大蔵政務次官に任命なさったんでしょうから、資金だって応分の援助があるのでは?」
「最大派閥の長にして、総理総裁ですからね。興梠先生に入ってくる金は桁違いですが、その分、面倒を見なければならない議員も多くいるわけです。正直言って興梠先生からの資金援助は、ないよりマシと言った程度でして……」
なるほど、小早川の言う通りかもしれない。
大蔵政務次官に就任して以来、小早川が率いるグループに合流する議員が相次ぎ、今では若手、中堅の一大勢力となりつつある。とはいえ、派閥全体を率いる興梠が必要とする資金は小早川の比ではない。結果、各グループへの支援額は十分とは言えず、不足分を調達するのはグループを率いる者の役目となる。
「今現在、ヨドから借りている金額はどれくらいになるの?」
貴美子が訊ねると、
「今現在、一億八千万円ほどです」
小早川は即座に返してきた。
「そんなに? それでもヨドは、返済を心配する素振りも見せないの?」
「ええ……。返済が遅れがちになっているにもかかわらず、手形に裏書きすれば、額面通りの金を用立ててくれますね」
「じゃあ、手形は誰が落としているの?」
「さあ……」
小早川は首を捻(ひね)る。
「さあって、気にならないの?」
能天気に過ぎるような気がして、思わず問い返した貴美子に、
「怖くて訊(き)けないんですよ」
小早川は真顔でこたえる。「おそらくヨドが立て替えているのでしょうが、訊けばどんな話が飛び出すか分かったものではありませんからね。サラ金と言えば聞こえはいいですが、とどのつまりは街金に毛が生えた程度のものですので……」
言わんとしていることは理解できなくもないが、「それにしても」と貴美子はため息を吐(つ)きたくなった。
資金源を確保するために鴨上にすがり、紹介されたのがヨドである。ヨドがサラ金業なのは承知の上で、資金援助を仰いだのに、今度は「街金に毛が生えた程度のもの」ときた。
まさに「喉元過ぎれば」というやつ以外の何物でもないのだが、一億八千万円は紛れもない大金である。サラ金ともあろうものが、返済が遅れても督促するどころか請われるままに金を貸すというのだから、小早川が不気味に思うのも無理はない。
「返済を迫らないのは、それだけ先生の将来を買っているからじゃありません? それに、サラ金は大蔵省の管轄ですからね。先生と深い関係を結んでおけば、ヨドも何かと心強いでしょうし、さっきも言ったように先行投資とも考えているんじゃないかしら」
「先生……私は政務次官ですよ。この先、大臣に就任するかもしれませんが、どの省を任されるかは時の総理が決めること。大蔵大臣になるとは限らないのです。それに実のところ、私は長く国会議員を務めるつもりはないのです。しかるべきタイミングで、息子に禅譲したいと考えておりまして」
「禅譲? ご子息に?」
もちろん、その件については鴨上から聞かされていたが、貴美子は素知らぬふりを装って驚いて見せた。
「鴨上先生には、最初にお会いした時にお話し申し上げたのですが――」
小早川は、それから暫(しばら)くの時間をかけて自分の狙いを説明する。
「なるほどねえ。ご子息にご自分の夢を託すとおっしゃるわけですか」
「親が言うのも何ですが、息子はなかなか出来が良くて、東大法学部を出ていましてね。官僚を志していたのですが、アメリカの大学院で政治学を学ぶと言い出しまして、今はニューヨークのコロンビア大学の国際公共政策大学院に留学中で、帰国後は私の秘書になることが決まっているんです」
「なるほど、申し分ないというか、華麗な経歴ですわね」
「息子を総理総裁にするのが私の悲願でしてね。そのためにはまず地ならし。党内基盤、資金源を確たるものにした上で、後を継がせたいと思いまして、それで鴨上先生にご相談申し上げたのです」
そう聞けば、小早川の悩みが明確になる。
巷間(こうかん)、議員になるための必須の条件に「地盤、看板、カバン」の三つがある。
地盤についての説明は要らぬが、看板とは肩書きや地位のことで、カバンはずばり金である。二世、三世議員はもれなくこの条件を満たしているのだが、東大法学部から米国の超一流大学院卒という経歴は、看板という点では群を抜いていると言えるだろう。
しかし、党内基盤を確たるものにするためには、まずは資金源の確保だ。かといって、借金は代替わりすれば消えるものではない。つまり、党内基盤を維持し、さらに盤石なものとすべくヨドに借金を重ねれば、返済義務を負うのは息子となる。小早川は、それを懸念しているのだ。
「だったら、ご子息にパトロンをおつけになればいいじゃありませんか」
貴美子は言った。「それほどご立派な経歴をお持ちなんですもの、是非娘を嫁にと申し出てくださるお金持ちはたくさんいると思いますけど?」
「それは、そうなのですが……」
ところが意外にも、小早川は冴(さ)えない表情になって口籠る。
「先生にお心当たりがないのでしたら、鴨上先生にご相談なさればすぐに見つけてくださるんじゃありません?」
言葉に弾みをつけた貴美子だったが、小早川は眉間に皺(しわ)を刻み、困惑するかのように押し黙る。
わけありなのは明白だ。
そこで貴美子は問うた。
「何か?」
再度の問いかけに、小早川は重い口を開く。
「先生がおっしゃるように鴨上先生のことです。条件を満たす嫁は、すぐに見つけてくださるでしょう。ただ、先生にご相談申し上げると、推挙された時点で縁談が成立してしまうことになるわけで……」
いったい、それの何が悪いというのだろう。
小早川が望んでいるのは、ヨドに代わる盤石な財政基盤。それも、借金ではなく、必要とあればいくらでも金を出せる裕福な家と縁続きになれば、懸念は一切払拭されるはずである。早い話が政略結婚ということになるのだが、政財界では当たり前だし、むしろそうではない縁組のほうが稀(まれ)なのだ。
小早川だって、その点は百も承知のはずなのに、この反応からすると何か躊躇(ちゅうちょ)するだけの理由があるらしい。
「先生……」
小早川は、覚悟の籠った声で言う。「資金源の確保の相談に上がった私に、ヨドを紹介してくださったのは鴨上先生です。そのことについては、先生に感謝申し上げてはいるのですが、借金が膨らむ一方なのに返済を迫るでもない、唯々諾々と資金を提供してくれる森沢社長の狙いは何なのかを考えますと――」
「不気味でしょうがないと、さっきおっしゃいましたよね、ですから、借金を綺麗さっぱり返済できるお金をお持ちの家と縁を結べば――」
話の途中で遮った、貴美子の言葉が終わらぬうちに、
「森沢社長には、一人娘がいるのです」
今度は小早川が言う。
「それが何か?」
「その一人娘というのは、息子よりも年下なのですが、夫婦になるにはちょうどいい年齢なのです。もしも……もしもですよ。鴨上先生から森沢社長の娘を嫁に推挙されたら……」
なるほど、そういう理由か……。
小早川が何を懸念しているのか、はっきりと見えた。
「金を有り余るほど持っているとはいえ、森沢社長はサラ金会社の経営者。総理総裁を目指そうというご子息の嫁の出自がそれでは、政治家としてのイメージが悪くなるとご心配されているわけですね」
小早川は頷(うなず)くと、
「森沢社長のお世話になって、もう四年。お互いの家庭のこと、家族構成もそれなりに分かってくるわけです。森沢社長が借金の返済を迫る気配を一切見せないでいるのは、ひょっとしてそこに狙いがあるのではないかと思えて……」
呻(うめ)くように言い、視線を落とす。
あり得る話だと思った。
財を成せば、次に欲しくなるのが地位や名声、そして権力である。
森沢は稼業からして地位や名声を手にすることは端(はな)から諦めているだろうが権力は別だ。娘が小早川の息子と結婚すれば、義理の息子が手にする力は、それすなわち森沢のものとなる。しかも、財源を握っているのは森沢だ。小早川の息子が政治家として生きていく限り、生殺与奪の権を持つ森沢の意向に逆らうことはできない。
となると小早川に残された手段は一つしかない。
「だったら先手を打って、縁談が持ち上がる前にご自分で相手を見つけ、ご子息を婚約させてしまえばいいじゃありませんか。ご子息だって、政治家になるつもりなんだし、色恋沙汰の果ての結婚なんか望んではいないでしょう。釣書を見れば相手の良し悪しなんて判断つくでしょうに」
貴美子にとっては当然の結論だったが、意外にも小早川は口をもごりと動かして、またしても沈黙する。
まだ何かあるのか……。
内心に覚えた疑念が顔に現れたのか、小早川は短いため息を漏らすと、
「それもまた、なかなか難しくて……」
語尾を濁して視線を落とす。
「難しい……とおっしゃいますと?」
訊ねた貴美子に小早川は視線を上げると、
「いや……。やはり、その手しかありませんよね……。早々に息子の結婚相手を探してみることにいたします」
慌てた口調で言い、続けて腕時計に目をやった。
その仕草がまたわざとらしい。
やはり他に理由があるのだ。
確信した貴美子だったが、今日のところは敢(あ)えてこれ以上、訊かないことにした。
占いの結果として、貴美子が菱倉グループから興梠グループへの鞍替えを奨(すす)めたのは、そう告げるよう鴨上から指示があったからだ。その結果、興梠グループは与党内最大派閥を形成することになったのだ。かくして現政権に及ぼす鴨上の影響力は以前にも増して絶大なものとなったのだが、小早川にヨドを紹介したのにも狙いがあるに違いない。
鴨上の目論見が分からぬうちに、小早川の相談に深入りすることはできない。
この様子からして、小早川は再びここにやってくる。それまでに、小早川が抱えている悩みを鴨上に報告し、指示を仰ぐべきだと貴美子は考えたのだ。
「今日は夜に東京で会合がありまして、そろそろ戻りませんと、間に合わなくなってしまいます。この件につきましては、後日改めてご相談させていただきたく存じます……」
小早川は鞄(かばん)を手にすると一礼し、足早に部屋の出口へと向かった。
2
「ほう、小早川がそんな相談を持ちかけてきたのか……」
受話器を通して、鴨上が苦笑を浮かべている様子が伝わってくる。
「まさに、喉元過ぎればなんとやら。資金源の確保に目処(めど)がついたら、今度は見返りに何を要求されるか怖くなったのですね」
「利息で食うのが金貸しだ。それが利息どころか元本も据え置き。事実上、ある時払いの催促なしじゃあ、そりゃあ小早川でなくとも怖くもなるよな」
「二人の子供が夫婦になれば、小早川の息子は森沢の義理の息子になるんです。森沢だってこれまでの借金はチャラにするでしょうし、可愛い一人娘の婿のためですもの、いくらでもお金を出してくれるでしょうに、『サラ金の娘は』って難色を示すんですからね。虫がいいにも程がありますわ」
「こと経歴に関しては、誰が見たって小早川の息子はピカピカのエリートだからな。その点森沢は、金はあり余るほど持ってはいても、とどのつまりは金貸しだ。息子を将来、総理総裁にと夢見ている小早川からすりゃあ、森沢と縁を結んでも、金以外にプラスになることは何一つとしてない。むしろ、マイナスになると考えたんだろうな」
「となると、見合いしかないのですが、小早川は、なぜか困惑した様子で口を噤(つぐ)むの」
そこで貴美子は直截(ちょくさい)に切り出した。「森沢の娘は困る。見合いも駄目だって、どういうことなんでしょう。小早川が息子の結婚相手に何を望んでいるのか、私には皆目見当がつかなくて……」
鴨上はすぐにこたえを返さなかった。
そして短い沈黙の後、
「資金源の相談にやってきた小早川に、森沢を紹介したのにはもちろん理由があってな」
鴨上はそう前置きすると、話を続ける。
「権力を手にするためには金が必要だ。あればあるほど権力者の座が近くなるのは事実さ。だがね、それはあくまでも必要条件の一つであって、十分条件にはならんのだよ」
「と、おっしゃいますと?」
「先見の明、大局を見る能力を持たずして、権力者の座を手にすることはできんのだ。たとえ、手にできたとしても、長くは続かんのだよ」
鴨上の言わんとすることが俄(にわか)には理解できない。
黙った貴美子に、鴨上は言う。
「小早川は、策士策に溺れるの典型でね。確かに大河の引退は、小早川が党内でのし上がる千載一遇のチャンスではあったさ。その点では、機を見るに敏ではあるし、賭けに出る度胸もあると言えるだろう。だがね、この機を逃してはならじと、とにかく今必要なのは金だと、森沢に縋(すが)ったところで彼の器が見えたのさ」
「政治家がサラ金と切っても切れない関係ができ上がってしまえば、後々厄介なことになると思いが及ぶはず。勝負どころを間違えたというわけですね」
「そうだ」
鴨上は断言する。「豊富な資金力を持つ政治家の下に、人が集まってくるのは間違いないが、主流には程遠いとはいえ、グループを率いるようになれば恒常的に一定の資金需要が生ずる。資金に不足なしと見れば人が集まり、グループは大きくなっていく。かくして資金需要は増すばかりとなるに決まっているからね」
「小早川は、他の資金源を探さなかったのでしょうか?」
「探しただろうね」
鴨上はあっさりと言う。「もっとも、資金源を他に求めれば、それだけ借りができる先が増えると、最初に私が釘を刺したからね。小早川が積極的に動いたかどうかは分からんが、彼だってそこまで馬鹿じゃないだろうさ。実際、森沢一人に頼れば、厄介なことになると気づいたんだからね」
「では、見つからなかったと?」
「唯一の資金源がサラ金。しかも大金を用立ててもらっている議員を支援しようという大口支援者がいると思うかね?」
「でも、興梠政権発足と同時に政務次官。それも大蔵政務次官という要職にお就きになったじゃありませんか」
「私が、そう仕向けたんだから当たり前さ」
鴨上は至極当然のように言う。「大河の後継を巡って、一族は揉(も)めに揉めたからね。無事に息子を議員にすることはできたものの、一族の結束には修復不能な罅(ひび)が入った。資金力が格段に落ちた大河派の再興はまず不可能。今後暫くは興梠に対抗する勢力は出てこなくなったんだからね」
「では、小早川の謀反は、興梠先生の意を汲(く)んで、先生が筋書きをお立てになったと?」
「血気盛んな年代が、高齢の既得権益者に反発を抱くのは、今に始まったことじゃない。決起する人間が出てくれば、後に続く者が少なからず出てくるものだ。小早川の場合、資金源に目処をつけてやりさえすれば間違いなく立つ。彼に合流する者も出てくるだろうし、興梠の下に馳(は)せ参じる者も続出するに違いないと踏んでいたのさ」
かくして、己の野心の成就と引き換えに鴨上に大きな借りを作った興梠は、これまでにも増して彼の意向を無視できなくなったというわけだ。
「小早川は、興梠グループを与党内最大派閥に仕立て上げ、長期政権を可能にするための鉄砲玉だったというわけですか」
こたえは分かりきっていたが、貴美子が敢えて訊ねると、
「まあ、そんなところだな」
果たして鴨上はあっさりと言う。
「では、小早川を今後――」
どうするつもりなのかと続けようとしたのを遮って、鴨上は平然と言う。
「鉄砲玉は発射したら終わりだ。最初は勢いがあっても、やがて力を失って落ちてしまう。ただ、それだけのことだ」
「つまり、使い捨ての駒に過ぎない。どうなろうと知ったことではないとおっしゃるのですね」
「ヨドは謂(い)わば毒饅頭(まんじゅう)だが飛び切り美味(うま)いときているから始末に悪い。実際、小早川はこの四年、毒だと知りながら喰(く)らい続けたんだからね。もはや体は毒まみれ。断ち切れば、禁断症状に見舞われて死んじまうかもしれんのだ。となれば、生き残る手段はただ一つ。毒を喰らわば皿までだ」
ついに鴨上は、愉快そうに笑い声を上げる。
「見合いに難色を示したのも、そこに理由があるのでしょうか」
貴美子が訊ねると、
「多分そうだろうな」
鴨上はすかさずこたえる。「返済を迫らず、言われるがまま金を用立てているところを見ると、間違いなく森沢は小早川の息子と自分の娘を結婚させることを目論んでいるね。どう足掻(あが)いたところで、一億八千万もの大金を肩代わりした上で、継続的に金を出してくれる支援者が現れるはずがないからね。小早川だって、その点は百も承知だ。見合いを躊躇するのも、借金の額もさることながら、借りている相手の素性を知られた途端、破談になると分かっているからさ」
「つまり、森沢に縁談を持ち出されれば、小早川は断ることができないとおっしゃるわけですね」
「小早川はとっくに俎板(まないた)の上の鯉(こい)なんだよ」
鴨上が鼻を鳴らさんばかりに言う。「もっとも、金は力だ。表に出れば世間の耳目を惹(ひ)いてしまうから、政界で今以上の要職に就くのは望めんが、裏で力を発揮することはできるだろう。本人が満足するかどうかは別として、それはそれで悪い話ではないと、私は思うがね」
要は、息子を総理総裁にするという野望を捨てさえすれば、小早川がロビースト、ひいてはフィクサーになるという願いは叶(かな)わないでもないと鴨上は言いたいらしい。
「では、私は当面どのように……」
別れ際の様子からして、小早川は再び相談に訪れるに違いない。
貴美子が指示を仰ぐと、
「何もせんでいい。黙っていても、小早川は再度君を訪ねてくるはずだ」
鴨上はこたえ、話を続ける。
「その時は卦を立てた上で、こう言ってやれ。『二兎(にと)を追うものは一兎をも得ず』。政界で力を奮いたいのなら、森沢の娘を嫁に迎えるべし。その力は、息子にも引き継がれることになるとね」
3
秘めていた思いを一旦口にしてしまうと、先々が気になって仕方がなくなるのは人の常である。
ふた月も経(た)たぬうちに、小早川は再び貴美子の元を訪ねてきた。
「先生、先にお訪ねした際にご相談申し上げた件なのですが……」
正面の席に座った小早川は、挨拶もそこそこに早々に切り出してきた。
「先にとおっしゃいますと、ご子息の件ですか?」
「ええ……」
思い詰めた様子が窺(うかが)えるのは気のせいではあるまい。
鴨上に指示されたままを告げてやればいいだけなのだが、いきなり筮竹(ぜいちく)を手にするのも芸がない。それに、占い師の前では誰もが正直になる。改めて小早川の心の内を聞いておいて損はない。
「あれから、森沢社長との間に何かあったのですか?」
そこで貴美子が訊ねると、
「いえ……特には……」
歯切れ悪くこたえた小早川は、そのままの口調で話を続ける。
「一週間ほど前にヨドを訪ねたのですが、その時お互いの子供の話になりまして……」
「そこで、どんな話が出たのです? まさか、縁談でも?」
「そうではないのです。ただ、来年の六月に、息子がアメリカの大学院を終えて、帰国すると言った時に、社長の表情に変化が現れたような気がしまして……」
「ご子息は、おいくつでいらっしゃるんですか?」
「二十六歳。帰国する頃には、二十七歳になっています」
「あちらのお嬢様は?」
「まだ大学生と聞いております」
「学校はどちら?」
小早川は、都内にある良家の子女が学ぶことで有名な女子大学の名前を口にする。
「お金もあって、一流大学で学んでいらっしゃるのなら、申し分ないじゃありませんの」
微笑んでみせた貴美子だったが、「でも、先生はお嬢様以前に、森沢社長の稼業を気になさっておられるのでしたね」
すぐに真顔になって、小早川の反応を窺った。
小早川は、真剣な眼差(まなざ)しを向けながら小さく頷く。
「あの様子からして、そう遠からずして社長は縁談を切り出してくると思うのです」
「ですから、先生やご子息が欲するがまま、黙ってお金を出してくださる良家のご令嬢を、お探しになるしかないと前に言ったではないですか。なぜ、先生はそうなさらないのですか?」
「そ、それは……」
小早川は、またしても言葉を濁し、俯(うつむ)いてしまう。
「先生……」
貴美子は小早川の頭上から、押し殺した声で呼びかけた。「選択肢は二つしかないのに、両方とも駄目だとおっしゃる。だったら、何のために私に会いにくるのですか? 相談に乗って欲しいのなら、なぜ見合いに難色を示すのか。その理由を聞かせていただかないことには、私だってこたえようがないじゃありませんか」
「確かに、おっしゃる通りなのですが……」
他人には知られたくはない、深い理由があるのだろうが、打ち明けるつもりがあるから、来ているのだ。
思った通り、やがて小早川が覚悟を決めたとばかりに、顔を上げると、
「息子は、私の実子ではないのです……」
呻くように漏らした。
想像だにしなかった言葉を聞いて、
「実の子ではないって……」
貴美子は絶句してしまった。
「夫婦共に健康状態は良好なのに、子供を授かる気配がなくて、医師の診断を仰いでみたのです。そうしたら、私のほうに問題があることが分かりまして……」
衝撃的な告白に、どう返したものか言葉が見つからない。沈黙してしまった貴美子に小早川は続ける。
「私は、小早川家の三男坊なのですが、海軍兵学校に進んだ長兄は戦死、次兄は幼い頃から体が弱く、結核を病んだこともあって、私が家督と議員職を継ぐことになったのです」
「そんな経緯がおありでしたの……」
そうとしか言いようがないし、言葉に同情が籠もるのも当然のことである。
小早川は訥々(とつとつ)とした口調で言う。
「このままでは、本家の跡取りが絶えてしまうと、父は大変な危機感を覚えましてね。かといって私に原因がある以上、離婚して新たに妻を娶(めと)ったところで問題は解決しません。それで止(や)むなく養子を迎えることになったのです」
「今アメリカに留学中のご子息のことですね」
「そうです」
小早川は、こくりと頷く。
「でも、小早川家の家督と議員職を継ぐことを前提に養子を迎えるとなると、誰でもいいというわけにはいきませんよね。養子はどうやって見つけられたのですか」
貴美子は訊ねた。
「本家を継ぐことが前提になるのですから、本来ならば分家、あるいは親戚に養子を求めるところなのですが、いずれも残っているのは長男のみ。分家とはいえ、やはり家督を継ぐのは長男です。東京にも親戚はいたのですが、空襲でやられてしまいまして……」
「真っ先に召集がかかったのは、長男以外の男子でしたものね……」
当時の状況は説明を受けるまでもない。
家督は長男が継ぐのが不文律であった時代である。大戦下にあっても、戦況がいよいよ逼迫(ひっぱく)するまでは、家が絶えてしまわぬようにと長男の召集は免除されたのだ。
「そんな事情もありまして、止むに止まれず外から養子を迎えることにしたのですが、縁は意外なところからもたらされましてね」
「意外なところ?」
「教会です」
確かに教会とは意外である。
「教会?」
思わず貴美子が問い返すと、
「母は敬虔(けいけん)なキリスト教徒でしてね。それに父が外務大臣を務めていたこともあって、毎週日曜日にはGHQの奥方も通う教会で、礼拝するのが習慣だったのです」
心臓が一つ、強い拍動を刻むのを貴美子は覚えた。
かつて鴨上から聞かされた、勝彦(かつひこ)を手放した後の状況に、酷似しているように思えたからだ。
そんな貴美子の内心の動揺を知るよしもない小早川は、淡々とした口調で言う。
「その教会で、戦災孤児の面倒を見ているご婦人と親しくなりましてね。かつて父親が駐アメリカ公使を務めた外交官で、その方がGHQに働きかけて施設を開設、運営なさっていたのです。私の父も外務大臣を務めたこともありましたので、話も合ったのでしょう」
「じゃあ、養子はそこからお迎えになったの?」
「ええ……」
「お子さんは、戦災孤児?」
「戦災孤児の面倒を見る施設にいたんですから、そういう扱いだったんじゃないですか」
「そういう扱いって、素性を調べもせずに養子に迎えたわけ? 外務大臣を輩出なさった家柄の跡取りになるのに?」
経緯を聞く限り、勝彦がもらわれていった状況とぴたりと一致する。
突然詰問調になってしまった貴美子に驚いたらしく、
「先生……。生まれて間もない子供ですよ。誰の子供かなんて、分かるはずがないじゃありませんか」
「戦災孤児なわけがないでしょう!」
貴美子は声を荒らげた。「ご子息は今、二十六歳。ってことは昭和二十四年生まれよね。終戦から四年も経って生まれた子供が、どうして戦災孤児扱いなの?」
「その点は、先生のおっしゃる通りなのですが、まだまだ戦後の混乱が続いている時代のことです。食糧事情も治安も劣悪で、貧困のあまり泣く泣く子供を捨てる親も少なくありませんでしたから――」
「じゃあその施設には、他に捨て子はいたの?」
話を遮る貴美子の見幕に、小早川は困惑した様子で顔を曇らせる。
「そんなことは分かりませんよ」
「おかしいじゃない。だって戦災孤児の面倒を見るのが目的で設立された施設なんでしょう? 他に捨て子がいないとしたら、なぜその子だけが施設に入れたのかしら」
話を聞くにつれ、内心に芽生えた疑念は深まるばかりだ。
尋常ならざる反応ぶりに、小早川も不思議に思えてならなくなったのだろう。
「先生、どうかなさったんですか?」
小早川は、小首を傾(かし)げながら問うてきた。
「どうかって、何が?」
「いや、孤児であろうと捨て子であろうと、実の子供ではないことに変わりはないのに、そこに酷(ひど)くこだわっておられるように思えまして……」
しかし、確証が得られないうちに自分の過去を話すわけにはいかない。
小早川が語るように、戦災孤児がたくさんいた時代である。捨て子も同じであったろう。状況は酷似しているとはいえ、以前鴨上から聞かされた話からすると、勝彦は養子としてアメリカに渡った可能性が高いのだ。今のところは、小早川の子供が勝彦かもしれないというう疑念が生じただけに過ぎない。
一瞬、貴美子は言葉に詰まったのだったが、
「その子を養子に迎えようと言い出したのはどなたなの?」
小早川の質問にはこたえずに、話題を変えにかかった。
「母です」
「お母様は、なぜその子を?」
貴美子は矢継ぎ早に質問を重ねた。
「それがですね……」
小早川は、返す言葉を思案するかのように口を濁すと、「勘……と言いますか、何か感ずるものがあったらしいのです」
困ったように頭に手をやった。
「か・ん?」
またしても意表をつくこたえが返ってきて、貴美子は思わず声を吊(つ)り上げた。「大臣職をお務めになった小早川家の跡取りを、勘で選んだと言うの? そんな馬鹿な!」
「先生が、そうおっしゃるのはもっともだと思います。実際、父だって、私共夫婦だって、氏素性も分からない捨て子を、養子にするなんてあり得ないと反対しましたからね」
「じゃあ、なぜ?」
「頑として、母が譲らなかったからです」
小早川は言う。「最初にあの子を見た瞬間、感ずるものがあったと言いましてね。私の目に狂いはない。あの子は間違いなく、小早川家の跡取りに相応しい、私たちの期待に応えてくれる人間に成長すると断言したのです」
小早川の言う通り、まさに『勘』以外の何物でもない。
もちろん、世間から名家と目される家に生まれても、『ドラ息子』、『放蕩(ほうとう)息子』、古くは『バカ殿』と称されるように、親や一族の期待に背く人物に成長してしまう例は枚挙にいとまがない。しかし、勘で跡取りを選んだなんて話は初めて聞いた。
「それに、母はこうも言いました」
唖然(あぜん)として言葉を失った貴美子に、小早川は続ける。
「身元は確か。家柄も申し分ない。閨閥(けいばつ)作りの役にも立つと見込んで迎えた養子が、期待外れであったならどうするのだ。頭を下げて迎えたからには、どうなろうと返すことはできないのだぞと」
その点、捨て子ならば縁を切るのも簡単だと言っているようにも聞こえるが、もしそうならば、慈愛に満ちた女性だと思いきや、やはり名家、有力政治家の妻はしたたかだ。
しかし、聞く限りにおいて、期待に背かぬ若者に成長しているようだ。
「結果的に、お母様の勘は的中したわけね」
「ええ……」
小早川は頷く。「うちには、物心がつかないうちにやってきましたのでね。私たち夫婦が実の親だと疑いませんでしたし、言葉や字を覚えるのも早く、小学校に入学すると同時に優れた頭脳を持っているのが分かりました。こうなると、養子も我が子と思えるようになるんですよねえ」
当時の記憶が脳裏に浮かんだのか、小早川は目を細め話を続ける。
「与えれば、与えただけの価値がある成果を挙げましたのでね。息子には、最高の教育環境を整えてやりました。番町(ばんちょう)小学校から、麹町(こうじまち)中学。日比谷高校から東大法学部。そして、コロンビア大学の大学院とことごとく期待に応えてきたのです」
「先生もまた、政界での地位を確たるものにしつつある。ただし、それも森沢社長の支援あってのこととなると、確かに思いは複雑でしょうね。ご子息のこれからを考えると、サラ金会社の令嬢を嫁にもらうのは得策とは言えませんもの」
「見合いもまた同じでしてね」
小早川の顔から笑みが消え、口調が重くなる。「息子の釣書を見れば、是非ウチの娘をと良縁が舞い込んでくるのは間違いないでしょう。ただ、そこで問題になるのが出自です」
「戸籍を見れば、分かってしまいますものね。もちろん、ご子息だって、自分が養子だと知っているのでしょう?」
「いや、息子は知りません」
「知らない? 二十六歳になるまで、戸籍謄本を見たことがないのですか?」
戸籍謄本を見る機会はそうあるものではないが、年齢からすればパスポートを申請するにあたっては、自分で手続きを行っただろう。その際、戸籍謄本は必須の書類だし、他にも見る機会は何度かあったはずである。
「実は、謄本上は実子ということになっておりまして……」
「そんなことができるの? 戸籍謄本の改竄(かいざん)なんて――」
「日本がGHQの支配下にあった時代ですからね」
貴美子の言葉半ばで、小早川が遮った。「さっき言ったように、孤児院はGHQの支援を受けて設立されたものです。詳しい経緯は分かりませんが、父もGHQと密な関係にありましたから、どうにでもなったんでしょうね」
終戦から四年を経ても、GHQが絶大な力を振るっていたのは紛れもない事実である。
貴美子にしても、二人の米兵を刺殺したにもかかわらず、量刑は懲役五年という異例の軽さだった。かつて鴨上は、あの判決にはGHQの意向が強く働いたと語ったが、判決は判例に沿って下されるものである。それを捻(ね)じ曲げることができるのだから、捨て子を実子として籍に入れることなど容易いことだったのかもしれない。
となると、新たな疑問が生じてくる。
「戸籍上は実子になっているのなら、ご子息が養子だなんて、誰にも分からないじゃないですか。出自なんか気にしなくても――」
貴美子はそこで言葉を呑(の)んだ。
小早川の顔に、今までにも増して困惑する様子が見てとれたからだ。
「それがですね……」
鴨上は呻くように言い、眉間に深い皺を刻む。
「それがどうしたの?」
しかし、小早川は沈黙する。
大腿に置いた両の手を握り締める気配がある。
「息子の出自を知っている人がいるのです……」
やがて小早川は口を開くと、低く重い声で漏らす。
秘密は必ず漏れるものだが、小早川の表情が困惑と言うより、苦悩の域に達しているところから絶対に知られてはならない人物に、息子の出自の秘密を握られてしまったに違いない。
「それは誰? 政界のどなたか?」
小早川は、すぐにこたえを返さなかった。
しかし、短い沈黙の後、意を決したように顔を上げると、全く想像だにしなかった人物の名前を告げてきた。
「か……鴨上先生です……」
驚天動地とはまさにこのことだ。
「鴨上先生が?」
驚愕(きょうがく)の余り頭の中が真っ白になって、それ以上言葉が続かない。
貴美子は、小早川の顔を凝視しながら椅子の上で固まった。
(次回に続く)
プロフィール
楡 周平(にれ・しゅうへい)
1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
