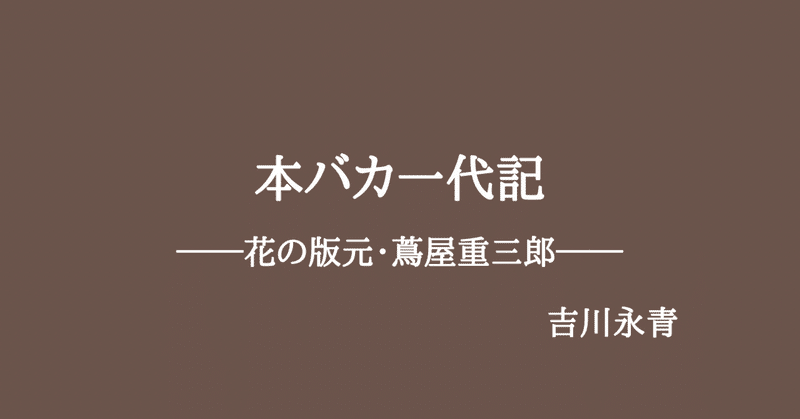
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第七話(上)
年が明けて松も取れ、天明四年(一七八四)一月も終わろうとしている。その日の朝一番、耕書堂の前に大八車が止まった。
「毎度どうも。刷り増しの二千、お届けです」
荷運びの男が暖簾をくぐり、威勢の良い声を寄越す。帳場にいた重三郎は「お」と笑みを浮かべた。
「ずいぶん早いね。注文して十日も経っちゃいないのに」
荷運びは「そりゃあね」と軽く笑った。
「遅くなっちゃあ職人の名折れだって、皆しゃかりきになってんでさあ。何しろ旦那んとこの刷り増しは後がつかえてんだから」
浅間山の噴火で萎えた人々の心を励ますべく、今年も多くの黄表紙を売り出した。中でも朋誠堂喜三二や恋川春町、四方山人――大田南畝の別名義である――の作は良く売れている。
が、今日届いた刷り増しはそれらの本ではない。
「それじゃあ運びますぜ」
荷運びが外に出て、紙に包まれた本の束を次々に持ち込む。帳場に積まれた包みは小僧たちの手で見世の奥、裏庭の蔵へと運ばれた。
「ほい、これでお終いだ。そいじゃ、また」
活きの良い挨拶を残して荷運びが帰って行く。帳場に残った最後のひと束は、見世先に積むためにすぐ荷を解かねばならない。そこから一冊を手に取り、重三郎は笑みを浮かべた。
「ここまで売れるとは思ってもみなかった」
狂歌本『老莱子』であった。昨天明三年、大田南畝の母の還暦祝いに狂歌会が催されたが、その席で詠まれた歌をまとめ、五冊ひと組に仕上げた一作である。
町衆の心は娯楽を求めるくらいに回復したが、著名人のお遊びである狂歌を受け容れられるか否かは定かでなかった。それを測ろうとして、他の本に紛れさせて売り出した。するとたちまち人気を得て、早くも版を重ねている。
「これなら」
小さく、しかし力強く頷いて立ち上がり、見世の奥に下がった。
廊下を進めば、裏庭の蔵を前に三畳間が三つ並んでいる。才を見込んだ絵師や戯作者に使わせる部屋だが、今は喜多川歌麿が左端の一室を使っているのみであった。
「歌麿さん、いいかい」
声をかけると、すぐに「はいよ」と返ってきた。障子を開けると、歌麿は少しばかり得意げな顔であった。
「ちょうど一枚、描いたとこさ。見てくれよ」
手渡された美人画に「どれ」と目を落とす。
「お。また少し良くなったね」
「だろ? けど、まだこの女の良さを十分に出せてねえ」
筆使いは十分に巧くなっていると思う。しかし当人が目指すものには届いていないということか。重三郎は「なるほど」と頷き、歌麿の前に腰を下ろした。
「そのための場数、どうやら踏めそうだよ」
「お。じゃ、やるのかい。狂歌の絵双紙」
「今月の『老莱子』が上々だからね。いけると思う」
狂歌に詠まれた面白さを挿絵で伝え、本当の流行りを作り出したい。その絵は歌麿の目指すもの――個々に違う女の美しさを伝えることに通じるだろうと、かねて思い描いていたのが狂歌絵双紙である。
沸き立つ思いを抑えきれず、重三郎の言葉はひとりでに熱を帯びた。
「今年の七月から毎回出してくよ。あ、黄表紙の挿絵も引き続き頼むからね。どんどん腕を磨いてくださいな」
「任せといてくんな。描いて描いて描きまくるからよ」
歌麿からも瑞々しい覇気が溢れ出している。重三郎は満足して立ち去った。
そして半年ほどが過ぎ、七月を迎えた。
この月の新刊で、耕書堂は四作の狂歌絵双紙を売り出した。歌麿が絵を入れたのは、そのうち一作のみである。付き合いの都合上、他の絵師にも注文しなければならないからだ。また、歌麿には黄表紙の挿絵も幾つか描かせていて、全てを任せては手に余ると判じたためでもあった。
これらが売り出されて一ヵ月、八月の声を聞いた頃――。
「こんちは! 刷り増し、お届けですよ」
いつもの荷運びがやって来て、狂歌絵双紙の山を運び入れに掛かった。前編『大木の生限』と後編『太の根』に分かれた一作で、前編は三冊ひと組、後編は二冊ひと組である。
それらの包みを帳場に下ろしながら、荷運びは珍しそうに問うてきた。
「ねえ旦那。これ、後編の方が注文の数が多いんだけどさ。間違いじゃないですよね?」
重三郎は「大丈夫」と笑みを返した。
「それだけ後編の売れ行きがいいんですよ」
前後編に分かれた本は、普通は前編の方が多く売れる。後編に手を出すのは、前編を見て「これはいい」と思った客に限られるからだ。
ところが、この狂歌絵双紙は話が別であった。何しろ一首、一首を楽しめれば、それで娯楽として成り立つのである。後編の売れ行きが良いのは、載せられた歌の力に加え、歌麿の絵が歌の面白いところを良く伝えている証と言えた。
*
ひと口に版元と言っても全てが同じではない。扱う本の違いで二つの種類があった。
西村屋に鶴屋、重三郎の耕書堂などは娯楽本を扱う地本問屋である。それらとは別に、学問や教養の本を扱う版元は書物問屋と呼ばれた。
和歌は教養に含まれるため、それらの歌集は一般に書物問屋から売り出される。上方が発祥の狂歌も、向こうではそちらの領分であった。が、狂歌が流行り始めて日の浅い江戸に於いては、その慣習は成り立っていない。書物問屋は、狂歌が面白おかしく詠まれた歌であることを以て「地本問屋の扱いではないか」と考え、地本問屋は地本問屋で「いやいや書物問屋だろう」と、互いに手を出さずにいた。
重三郎はその間隙を衝いた。しかも挿絵を入れた絵双紙として、紛うかたなき娯楽本に仕立ててある。江戸に於いて、狂歌本は地本問屋の扱うものとなった。
そして、天明四年の九月も終わろうかという日のこと。
「あいすみません、お求めの『太の根』は品切れでして」
「ええ? 流行ってるって聞いて、わざわざ買いに来たってのに」
重三郎が見世先に顔を出すと、ちょうど小僧の弥吉が客の男に詫びているところであった。歌麿が挿絵を入れた『太の根』は、ことほど左様に良く売れている。
もっとも、話は「品切れです」で終わりはしなかった。
「あと四日で刷り上がって来ますんで、少しお待ちくだされば」
「お、そうかい。なら取り置きで頼まあ」
客は、かえって「四日先の楽しみができた」という顔である。
顛末を見た重三郎は、深い笑みで頷いた。
江戸狂歌に於いて、耕書堂は間違いなく一番の版元になった。この先も大田南畝たち山手連の狂歌会に顔を出し、歌を拾って来れば本の種にはこと欠くまい。挿絵を入れる歌麿も、さらに腕を磨いてゆくだろう。上々の運びである。
「久兵衛長屋、印判彫りの新八だ。四日先の今頃に来るからよ。よろしくな」
「はい、確かに」
取り置きの客が出て行くと、重三郎は見世先の弥吉に声をかけた。
「弥吉さん。すまないが、ちょいと出て来ます。日暮れまでには戻るから」
「あ、はい。皆さんに伝えときます」
「よろしくね。見世番、しっかり頼むよ」
そして外に出る。このところ連日、こうして見世を空けていた。
とは言え、訪ねるのは狂歌師たちの許ではない。狂歌については今の流れを手放さなければ良いのだ。むしろそれ以上に考えるべき話、有り体に言えば憂うべきことがあり、これにどう対処するか見定めるために外へ出ている。昨日までの数日は懇意の版元を回って、その上で今日は昵懇の彫り方・藤田金六を訪ねるつもりであった。
「彫り金さん、こんちは」
「こりゃ蔦重の旦那。いらっしゃいまし」
藤田は昨年末に催した河豚汁の宴に招いた中のひとりで、気の置けない間柄である。そうした仲ゆえ挨拶は軽い。しかし、その先の話は重いものであった。
「ねえ金六さん。あっちこっちの版元さんに聞いたんだけど、あんたんとこ、仕事が減ってるそうじゃないか」
その話になると、藤田は深い溜息であった。
「いやあ……実はそうなんだよ。まあ、見えてた話ではあったんだけどな」
もっとも、仕事が減っているのは藤田に限った話ではない。全ての彫り方が同じであった。
「小せえ版元は仕方ねえとしても、西村屋だの鶴屋だの、でけえ版元まで一月のを減らすって言いやがるからな。参っちまうぜ」
その言葉どおり、多くの版元が来年一月の新刊を大きく絞り込もうとしていた。昨年の、浅間山の噴火が大本の原因である。
あの折の噴火は凄まじいものだった。浅間山から流れ出した溶岩は周囲の村々を焼き払い、今では一帯が岩に覆われて「鬼押し出し」と呼ばれているのだとか。加えてこの噴火では関東一円に灰が降り、田畑の土を傷ませている。
「お陰で上州も武州も不作、不作だ。その上、本まで出し渋られちゃ堪んねえよ」
「仕方ないさ。飢饉になるんじゃないかって、皆びくびくしてんだよ」
藤田も重三郎も、次第に面持ちを曇らせていった。
昨年の関東は不作で、米や青物が軒並み値上がりしていた。では今年はどうかと言えば、やはり諸々の値は高止まりのままである。灰で傷んだ土は、数年の間は旧に復さないからだ。
「飢饉か。嫌な言葉だぜ」
藤田が頭をがりがり搔きながら吐き捨てた。関東が不作なら西国や陸奥から米を回せば良いというような、単純な話ではない。西国は二、三年前から天候が悪く不作続き、陸奥も今年は不作なのだ。ない袖は振れないのである。
食うものが儘ならない中では、人は諸々を切り詰める。酒や菓子、遊びなど、生きる上で余剰と見做されるものには金を使わない。多くの版元は、それゆえに来年の一月刊を減らすのだ。
そんな話をするうちに、重三郎に向く藤田の目が諦めの色を濃く映し出した。
「……さてと。つまりは、旦那んとこも減らすって言いに来たんだな」
しかし、重三郎の考えは違った。
「馬鹿言っちゃいけない。他が減らすんなら、うちは増やすって言いに来たんだ」
「は?」
「他が減らすって話になって、あんた手が空いてんだろ? なら、うちの仕事を余計に頼むよ」
「いや。旦那……正気かい?」
もちろんだ、と胸を張った。
「浅間の一件で江戸中が悄気返ってた時だって、二ヵ月もしたら皆が元どおりに暮らすようになったじゃないか。大丈夫だよ」
「とは言っても今度は飢饉だぜ。ただ山が火ぃ噴いたのとは訳が違うだろうよ」
重三郎は「はは」と軽く笑った。
「じゃあ聞くけどさ。金六さん、飢饉が終わるまであの時みたいな気持ちで暮らしたい?」
「冗談じゃねえ。くさくさしたまんまじゃ気持ちが腐る」
「そういうもんだよ。あんたに限らず、誰もね」
通油町へ見世を移したばかりの頃、人々の気持ちを明るくしたいと願い、十日だけ大安売りをした。人々は本を読んで楽しみ、やがて少しずつ心を上向かせていったのだ。
あの時のことを以て、人は如何なる時でも心に潤いを求めるものだと確信できた。なるほど飢饉の最中には本も売れにくいだろうけれど、それでも――。
「版元ってのは、世の中に楽しい気持ちを振り撒く仕事さ。そういう奴らが、揃いも揃って湿気た面ぁ見せてちゃいけない。あたしはそう思う」
藤田は「む」と唸った。
「さすがの心意気……と言いてえとこだが、分の悪い勝負だと思うぜ」
「初めのうちは、そうだろうね。でも勝てる勝負だよ」
どのくらい経てば人々の心が上向くのかと言えば、噴火の直後のようにはいかないだろう。しかし、人々はいずれ必ず娯楽を求めるはずなのだ。
「少しばっかり楽しい思いをしたいって思った時、町の皆が買う本って何だい? 他はろくすっぽ刷らないで、うちだけ新しいのをバンバン出してんだよ」
「そうか……目に入るのは旦那んとこの本ばっかり、てえことに」
藤田の目が、じわりと見開かれる。我が意を得たりと、重三郎は頷いた。
「だから数を増やすんだ。でも、それだけじゃ足りない。目玉になる本が要る」
「そいつは?」
問われて「ふふ」と含み笑いを返した。藤田が彫り方である以上、いずれ知ることになる。まずは見ていてくれ、と。
〈次回に続く〉
【第一話】 【第二話】 【第三話】 【第四話】 【第五話】
【第六話】
【プロフィール】
吉川 永青(よしかわ・ながはる)
1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
