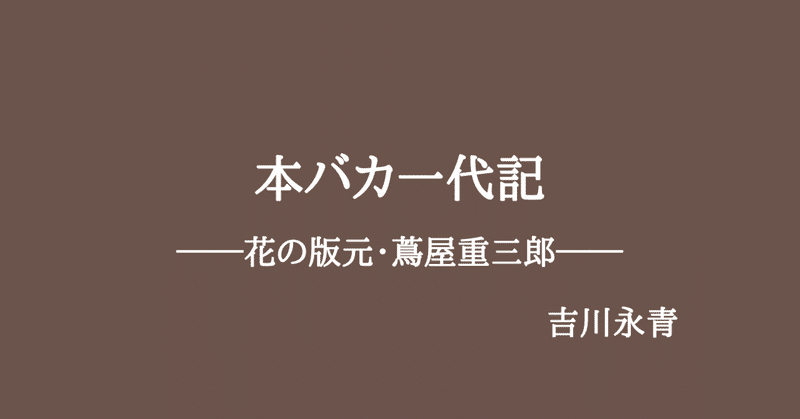
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第七話(下)
*
天明七年(一七八七)の五月二十日、重三郎は吉原五十間道の見世にあった。次の細見の版下が仕上がったと報せを受け、不備がないかどうか目を通すためである。
それを終えた夕刻、通油町へ戻るに当たって、お甲が見世先まで見送りに出た。
「おまえさん、またね。七月に新しいのを売り出す時ゃ、様子を見に来るんだろ?」
「来るよ。でも、こっちの見世はねえ」
飢饉になってからというもの、吉原からはすっかり客足が遠退いている。通油町で二十文かそこらの本を買う客はいても、遊里に来て散財する者はそうそういない。五十間道の見世は細見の売れ行きも悪く、本に至っては一冊も売れない日ばかりなのだ。
お甲は神妙な顔であった。
「ねえ。こっちの見世……そろそろ畳んでもいいんじゃない?」
「ああ。考えてはいるよ」
貸本については、今でも吉原の見世から日本橋界隈まで回らせている。その逆に、通油町から吉原に来させても良いのだ。細見についても、貸本の傍らで売り歩けば済む。
「でも、あと少し様子を見たい。飢饉が終わってくれりゃあ元どおりに商売できるんだから」
「そう。分かった、気を付けて帰んなよ」
お甲に「おう」と笑みを向けて五十間道を進んだ。
日本堤に至れば、昨今では珍しく、遊里の客を乗せて来た駕籠屋がある。駕籠舁きは若い男と五十過ぎの二人で、これを捉まえて帰路の足を頼み、代金を支払って乗り込んだ。
「日本橋、通油町ね。それじゃあ行きますぜ」
五十過ぎの声で駕籠が進み始めた。えっほ、えっほ、と前後から声が渡る。
それを、どれくらい聞いた頃だろうか。遠く向こうに、耳慣れぬ騒々しさが重なるようになった。
「何だい、こりゃ」
駕籠の中にあって、重三郎は眉を寄せた。
遠い喧騒に耳を欹てれば、太鼓や拍子木の音が聞こえる。だが、お囃子ではない。もっと荒々しく、目茶苦茶に叩いているようだ。そうかと思えば、今度は半鐘の音がカンカンと届く。
半鐘で思い出すのは、若い日の火事――吉原の全てが焼けた晩である。重三郎の背に、ぞわ、と粟が立った。
「ちょっと駕籠屋さん。これ、火事じゃないのかい?」
慌てて声を上げると、駕籠舁きたちは動きを止めた。少しの後に、前にいる五十男が覚束ない返答を寄越す。
「いやあ……違うと思いますぜ。どこにも煙が見えませんからね」
「じゃあ、あの音は何――」
問い返す言葉が終わらぬうちに、遠くから別の喧騒が伝わった。わぁん、わああん、と蠅の羽音が束になったような音である。人の声、それも相当に大人数の騒ぎ声だ。
「いけねえや。旦那、こりゃ何か騒動が起きてますよ」
「何だって?」
若い方の声に驚愕して、重三郎は駕籠を降りた。夕暮れの向こう、道の南側から届く喧騒が次第に大きくなってくる。
駕籠舁きの二人が、さっと青ざめた。
「父っつぁん、これ。まさか……打ち毀しか?」
「かも知れねえ」
打ち毀し――その言葉に重三郎は身震いした。あり得ぬ話ではない。
昨今、米の値上がりは酷いものだった。二年ほど前なら、百文あれば一升の米を贖えたのだ。それが飢饉になってからは百文当たり七合に、さらにこの五月には百文で三合になって、実に三倍以上の高値を付けている。
幕府も無策だった訳ではない。今年一月には米穀売買勝手令を発布し、江戸に持ち込まれた米は米問屋を通さず売買できるようにした。以後も同じ法度を繰り返して発し、今月、五月九日には三度目が発布されている。問屋より安く売る者を増やし、値を落ち着けようとしたのだ。
しかし、失敗に終わった。自由に売買できるようになったせいで、さらなる値上がりを見込んで米を買い込む者が出てきたからだ。これが品薄を助長し、今の高値に繋がっている。
「ここんとこ、川に身投げする人らも増えてたしな。なのに、お上は『何とか食い繋げ』って言うばっかりでよう」
若い方の駕籠舁きが声を震わせる。次いで、五十男が重三郎に声を向けた。
「ねえ旦那。通油町って言ってましたけど、この騒ぎ……きっと日本橋ですぜ」
日本橋には魚河岸や米河岸が集まっている。そして打ち毀しと言えば、狙われるのは決まって米問屋なのだ。
騒動が起きている辺りに行くのは避けたいと、駕籠舁きの目が語っている。重三郎は「仕方ない」と奥歯を嚙んだ。
「あんたたちは近寄んない方がいい」
「え? 旦那、まさか行くんですかい?」
若い方が目を丸くしている。危ない、よした方が良いという顔だ。しかし。
「行くんですかも何も。日本橋にゃあ、うちの見世があるんだ」
叫ぶように応じ、重三郎は駆け出した。
通油町と米河岸は少しばかり離れているが、それとて四半里(一里は約四キロメートル)かそこらである。騒ぎに巻き込まれないとも限らない。頼む、無事であってくれ。巻き込まれないでいてくれと願いながら、懸命に走った。
米河岸の近くに至れば、ざわざわと人垣ができていた。皆が呆然と慄きながら、打ち毀しの様子を見守っている。
「ごめんよ。ちょいと通してくださいな」
人を掻き分け、掻き分け、重三郎は前に出た。そして。
凄惨な光景を目の当たりにして、わなわなと身を震わせた。
「何だい、こりゃあ……」
米河岸の狭い道が、人でひしめき合っている。鍬や鋤、鳶口や棒を持ち、それを振るう一群が米問屋に押し寄せていた。
「これじゃあ埒が明かねえや。車だ、車!」
打ち毀しの誰かが叫び、別の誰かが「おうよ」と返す。何人かの男が乗った大八車が曳かれて行き、その車が激しく見世の間口にぶつかって押し破った。
「次だ! 斧持って来い」
応じて二人、三人が屋根に登り、目茶苦茶に斧を振り下ろして瓦と棟木を叩き割っている。それらの者は、また、遠巻きに見ている者たちに怒鳴り声で呼びかけた。
「おめえら何見てやがる! こいつらのせいで、俺たちゃ殺されかけてんだぞ」
「何でも構わねえ、道具持って手伝いやがれ!」
重三郎の周囲、人垣を作る面々が息を呑む。
少しの後――どよめきが起き、辺りがざわついた。
「え? いや……」
確かに感じた。先ほどまで呆然としていた面々の中に、心を裏返らせた者がいる。
しかも二人や三人ではない。それらは血走った目を爛々と光らせながら、ゆっくりと前に進んで行った。
「いや、だめだ! だめですよ、皆さん」
必死に叫びながら、重三郎は手近にいる男の右腕を摑んだ。すると。
「うるせえ、腰抜けは引っ込んでろい!」
狂乱の一喝と共に突き飛ばされた。火事場の馬鹿力とでも言うものか、驚くべき勢いである。抗いようもなく道端に転げ、強く尻餅を搗いた。
「あ痛たた……」
顔を歪める向こうで、人垣の中から十人、二十人と打ち毀しに加わってゆく。何の道具も持っていない面々は、壊された見世の材木や障子の桟を拾い、これを振り回して暴れ始めた。
「何だよ、これ。何だってんだよ」
重三郎は呟いた。はっきりと、恐怖していた。
他人の見世を襲い、壊す。やってはいけないことだと、誰もが分かっているはずなのだ。しかし今は、皆がやっているのだから許されると思っている。自分たちは正しいと勘違いしている。
そうなった人間の群れは歯止めが利かない。本の力、娯楽で世の中を動かすのとは訳が違う。昔日の火事の時とも、明らかに違う。自分ひとりで食い止めることなど、できようものか。
「……とにかく」
重三郎は痛む尻を擦りながら立ち上がり、震える足を励まして自らの見世を目指した。
打ち毀しのすぐ傍を、息をひそめながら通り抜ける。
見物の人垣を縫って裏路地に逃れる。
そうやって、どれほど経った頃か。向かう先に「蔦屋耕書堂」の看板を見ると、額からどっと汗が溢れ出した。
幸いにして、耕書堂と近辺の版元は襲われていなかった。だが、辺りの道はどこも米河岸を指して進む人で溢れ返っている。それらの面々が騒動に加わろうとしているのか、或いはただの見物人なのかは分からない。ただ、如何にしても町は騒然としていた。
「皆、無事かい」
やっとの思いで見世に戻り、開口一番で呼び掛ける。皆が「旦那様」と声を上げ、安堵の息を漏らした。
「旦那様も良くぞご無事で。おい、もういいよ。見世、閉めとくれ」
番頭の声に、小僧たちが見世の間口を閉めに掛かった。夕刻には戻ると言って吉原の見世に向かったからか、わざわざ帰りを待って、開けていてくれたらしい。
外は夕暮れが夕闇に変わろうとしている。閉め切って真っ暗な帳場に、行燈の暗い明かりが運ばれた。人心地がついたか、皆が「ふう」と息をついた。
米河岸の喧騒は、夜遅くまで続いた。
明くる日の朝、重三郎は番頭と手代二人を連れて、米河岸の様子を確かめに向かう。思ったとおり、目も当てられぬ有様だった。
米問屋の見世は無残に壊され、四隅の通し柱さえ傾いている。畳や箪笥、長持などの家財は言うに及ばず、米を搗くための臼や杵、桶や帳面などの商売道具が目の前の川に捨てられ、ぷかぷかと所在なげに漂っていた。道端には米や麦、味噌などがぶち撒けられている。
「……参った。こんなんじゃあ」
呟いて、重三郎は強く眉を寄せた。
正直なところ途方に暮れている。先が読めない。こんな世相で、どう商売をしていけば良いのだろう――。
〈第八話に続く〉
【第一話】 【第二話】 【第三話】 【第四話】 【第五話】
【第六話】
【プロフィール】
吉川 永青(よしかわ・ながはる)
1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
