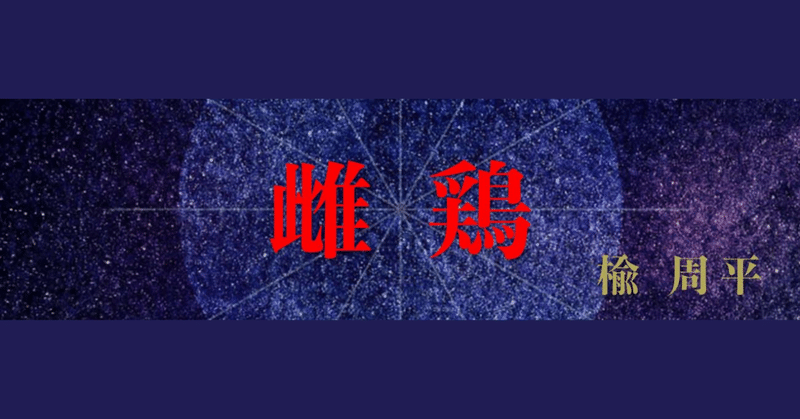
雌鶏 第六章 2/楡 周平
4
小早川(こばやかわ)の告白を聞いて、貴美子(きみこ)は動揺した。
誕生の時期といい、手放してから養子にもらわれていくまでの経緯といい、鴨上(かもうえ)から聞かされていた話と酷似している。
だが、もしその子供が勝彦(かつひこ)であったなら……。
止(や)むに止まれぬ状況下にあったとはいえ、我が子を手放さざるを得なかった母親の心情は鴨上にも理解できるはずだ。鴨上にしても、空襲で亡くなった妻子のことを語ったのは一度きり。その後一切触れずにきたのも、今に至るまで後妻を娶(めと)ることなく独り身を通してきたのも、二人に対する思いの深さゆえのことだと貴美子は推察していた。
だから、もし小早川の息子が勝彦ならば確証がなくとも、あの時点で貴美子に匂わせるぐらいのことはしたはずなのだ。
そう思う一方で、ならば知ったら知ったで自分はどんな行動に出ただろう……。
実母の顔も判別できぬうちに、手元を離れてしまった勝彦は、小早川夫妻を実の両親と認識し、大事な跡取りとして育てられてきたのだ。それに戸籍を改竄(かいざん)したほどである。小早川家にしても、いまさら私が実の母親だと名乗り出たところで認めるはずがない。
しかも捨て子なら簡単に縁が切れると言わんばかりの言い草は、おそらく小早川家の本音であったろう。だとすれば、当の本人も小早川家の期待に応え、幼い頃から相当に優秀であったはずである。
実際、番町小学校、麹町中学、日比谷高校から東京大学法学部という学歴はエリートコースの王道だし、今やアメリカ有数の名門、コロンビア大学の大学院で政治学を学ぶ身である。
もし、小早川の息子が勝彦であったなら、果たして自分はこれほどまでに、恵まれた環境を整えてやれただろうか……。
考えるまでもなく、こたえは否だ。
ある日突然、「私が実母だ」と名乗り出て、小早川夫妻が認めたとしても、勝彦は戸惑うばかりだろうし、それ以前に自分には殺人の前科がある。いかに鬼頭(きとう)、鴨上の庇護の下、政財界に隠然とした影響力を発揮する占い師になったとはいえ、その過去を消すことはできない。いや、実母が殺人の前科を持つと分かった時点で、小早川家は勝彦を放逐し、彼の前途を断つに違いない。
そこに思いが至ると、ここまで立派に育ててくれた小早川夫妻には感謝の念すら覚えるのだが、それでもやはり実の子への思慕の念は捨て切ることはできない。
ここはまず、小早川の息子が勝彦なのかどうか確かめるべきだ。
鴨上が小早川に見切りをつけるのは構わないが、もし彼の息子が勝彦で、森沢(もりさわ)の娘を妻にしてしまえば、政治家としての将来を閉ざしてしまうことになりかねない。
ならばどうする……。
まずは、小早川家が養子を迎えるまでの経緯を詳細に調べることだ。
小早川は、養子を迎えることに積極的だったのは母親だったと言った。
以前、鴨上から聞かされた話には、いくつかのキーワードがあった。
一つは、勝彦が入所したのは駐アメリカ公使の娘がGHQの協力で設立した戦災孤児院であったこと。もう一つは、GHQの家族も日曜礼拝に通う教会のシスターが、縁を取り持ったことの二つだ。
小早川から息子の出自を聞かされた時には、驚きのあまり思考が停止してしまったこともあって、訊(き)きそびれてしまったのだったが、まずはそこからだ。
貴美子は受話器を手にすると、衆議院議員会館にある小早川の事務所に電話をかけた。
昼を過ぎたばかりとあって、あいにく小早川は昼食を摂りに外に出ていると言うので、「大事な話があるので、折り返し電話を頂戴したいとお伝えください」と伝言を残し、受話器を置いた。
小早川から電話が入ったのは、午後二時を回った頃のことだった。
一度目のベルが鳴り止まぬうちに、受話器を取り上げたのは、僅か二時間にも満たない待ち時間が、異常に長く感じられたからである。
「もしもし……」
貴美子がこたえるや、
「あっ、先生。小早川でございます。お電話を頂戴したそうですが、大切な話とは何でしょう」
小早川が、改まった口調で問うてきた。
用件は縁談だと察しはついているだろうが、息子が養子であることは秘書も知らぬはずである。
「先生、今どちらにいらっしゃいます?」
「議員会館の執務室ですが?」
「ということは、周りに人はいないのですね」
「ええ……。秘書たちは隣の部屋におりますから大丈夫です……」
小早川の声も自然とトーンが低くなる。
他人に知られてはならぬ話だと悟ったのだ。
「実は、先日の件。ご子息の縁談についてなのですが、二、三お訊(たず)ねしたいことがありましてね。ご子息の将来を左右する重大事ですし、先生も森沢家と縁を結ぶことを望まれてはいないとはいえ一旦鴨上先生を介して、森沢が縁談を持ちかけてきたら、お断りすることはできません。ですからそうならぬよう、事前に策を講じておくべきだと思いまして……」
「実は、それができるのは先生だけだと思いまして、ご相談に上がったのです」
小早川は、百万の援軍を得たかのように声を弾ませる。「縁談話が出れば、次に鴨上先生は京都に行って先生に卦(け)を立ててもらえとおっしゃるだろうと思いましてね。その際、先生から否定的なお言葉を頂戴できればと――」
貴美子の見立ては、全て鴨上に指示されたままを伝えているだけに過ぎないのだが、そのことを知る者は、二人以外に誰一人としていない。
小早川がこんな言葉を口にするのも、貴美子の占いを通じて政財界を支配するという鬼頭、ひいては鴨上の目論みが機能している証左である。
しかし、鴨上に京都へ行けと言われたら、その時点でゲームセットだ。貴美子にしても鴨上の指示に逆らうことはできない。
だから、貴美子は小早川の言葉を途中で遮り、ピシャリと言った。
「森沢社長から仲介の労を頼まれでもしない限り、鴨上先生は京都へ行けとはおっしゃらないと思いますよ」
「なぜ、そう思われるのですか?」
「だって、先生は借金の返済を一向に迫る気配のない森沢社長の真意を図りかねて、鴨上先生のところへ相談に上がったのでしょう?」
「ええ……その通りですが……」
「だから、ご子息と森沢社長のお嬢様を結婚させれば借金はチャラになると鴨上先生はおっしゃったんですよ。当たり前じゃないですか。お二人が結婚すれば、ご子息は森沢社長の義理の息子になるんですもの。支援することはあっても、大事な娘婿に金を返せなんて言う親がいるわけないじゃありませんか」
痛いところを突かれたとばかりに沈黙する小早川に貴美子は続けた。
「でも、先生は森沢家と縁を結ぶのは嫌だとおっしゃる。ならば、借金を全額返済するしかないのですが、そんなことできますの? できないからお悩みになっているのでしょう?」
「おっしゃる通りです……」
「それに、グループを率いていく限り、資金の需要は尽きることがない。借金は今後も増え続けることになるのですよね」
「はい……」
苦しげな声から、受話器の向こうで、屈辱に耐える小早川の表情が浮かんでくるようだった。
「それは、ご子息にも言えることじゃありませんの?」
貴美子は言った。「ご子息は先生のグループを率いることになるのでしょう? もちろん、いきなりリーダーになることはないにせよ、早いにこした事はない。そう考えておられるのでしょう?」
「ええ……」
「つまり、代替わりしても、資金が必要であるのに変わりはない。先生がお作りになった借金も、代替わりしたからといってチャラにはならない。今度は、ご子息が引き継ぐことになるんじゃありませんの?」
小早川はぐうの音も出ない。
受話器を通して、小早川の息遣いが聞こえてくるだけとなった。
「先生……」
貴美子は呼びかけた。
「はい……」
「先生が森沢家との縁談に乗り気ではないのは、私も理解できます。優秀なご子息の前途を、親がこしらえた借金で閉ざすようなことはあってはならないことですからね」
「全く、面目次第もございません……。先生のおっしゃる通りです……」
「ならば断る……いや、先方に縁談を断念させるような状況を作るのが最もいいのですが、正直言って、今のところこれと言った妙案は私にはありません」
「そうでしょうね……。借金を綺麗さっぱり返済すれば縁を切ることができるでしょうが、金額が金額ですので……」
「実は、それでお電話申し上げたのです」
貴美子は、いよいよ本題を切り出すことにした。「森沢社長がどうお考えか分かりませんけど、ヨドを業界一の会社に育て上げた方ですが、所詮はサラ金業者ですからね。由緒ある家柄の人たちからすれば、成り上がり者以外の何者でもありません。いくら莫大(ばくだい)な財産を築いたとしても、決して仲間には入れてもらえないのです」
「おっしゃる意味が、今ひとつ理解しかねるのですが?」
「この手の人たちは、得てして次に欲しくなるのは、社会的地位、名家の仲間入りをすることなんですよ」
貴美子はこたえた。「実際、戦後の混乱に乗じて、一代で莫大な財産を築き上げた人がたくさんいますが、お金の力で落ちぶれた華族のご令嬢を娶って、上流階級の仲間入りを果たした例は少なからずありますからね」
「確かに、思い当たる方は何人かいますね……」
小早川は、納得した様子で相槌(あいづち)を打つ。
「落ちぶれても華族は華族。既に廃止されたとはいえ、名家の証(あかし)には違いないんです。現に今でも華族の会が存在していて、折に触れて集まっては旧交を温めていますからね」
「旧華族の会? そんなものが存在するのですか?」
「人間、一旦手にした称号は、そう簡単には捨てられないものなんですよ」
貴美子は冷笑を浮かべた。
「しかし、うちは華族ではありませんが?」
「存じております。でも、大臣を輩出した家ではありませんか。爵位を持っていなくとも、立派な名家じゃございませんの」
肯定すれば傲慢に過ぎるとでも思ったのか、
「それは、まあ……」
小早川は、言葉を濁す。
「もし、森沢社長の狙いがそこにあるのだとすればですよ、ご子息の出自を明かせば――」
「息子の出自と言いますと、養子だということですか?」
言葉半ばで遮ったところからも、小早川が提案を否定するのは明らかだ。
果たして小早川は言う。
「そりゃあ縁談は断念するでしょうが、息子の出生の秘密を社長に知られるのはまずいですよ。それに借金はまるまる残るんですから、それは駄目ですよ」
「分かっています」
貴美子は断言すると、「ただ、打開策を考えるにしても今までお聞きした範囲では、なかなか妙案が浮かばないのです。特に、ご子息を養子に迎え入れるまでの経緯には、釈然としないところがありましてね。その辺りをもう少し詳しくお聞かせいただけますか?」
親身なふりを装って水を向けた。
「なんなりと……」
「確かご子息は、GHQの支援で設立された戦災孤児院におられて、養子話のきっかけとなったのは、GHQの家族も礼拝に通う教会でしたね」
「そうなんです」
果たして小早川は言う。「空襲が始まってすぐ、父の指示で母親と私は軽井沢の別荘に疎開することになったのです。その間に麻布にあった自宅は空襲で焼失しましてね。戦後すぐに同じ場所に家を建ててからは、両親は近くの教会の日曜礼拝に欠かさず出席するようになったのです」
「先生もご一緒したのですか?」
「ごく、たまに……」
小早川が苦笑する気配が伝わってくる。「両親は熱心な信者ですけど、私は連日仕事に追われていましたのでね。休日の半分を祈りに捧げるなんて気にはなかなかなれなくて……」
「それで、お母さまに養子の話が持ちかけられたのですね」
「間を取り持って下さった教会のシスターと母は旧知の間柄でしたし、母は英語が達者でしたのでね。戦後三十年経った今でも、英語が通じる日本人って滅多にいないじゃないですか。まして戦中、英語は敵性語で学ぶことを禁じられましたからね。英語が通じる日本人は珍しかったこともあってGHQ、特に奥様方と親交を結ぶようになったんです」
「ご子息を養子にと持ちかけてきたのは、シスターなんですか? それともGHQのどなたかなんですか? 戦災孤児院は、GHQの支援で設立されたのでしたよね」
「そこはよく分からないのですが、両方かもしれませんね」
「両方?」
「そのシスターには、母が絶大な信頼を置いていましてね。ご存じかとは思いますが、教会には懺悔室があって、抱えている悩みや過ちなどを神父に告白する場所があるんですけど、同性ということもあったんでしょうね。プライベートなことも含め、そのシスターには胸の内を洗いざらい打ち明けていたようなんです」
「先生ご夫妻に、お子様がなかなかできないことをお話しになったと?」
「多分そうだと思います。しかも、原因は私、つまり息子にあると分かったんですからね。私は小早川家に残る唯一の跡取り。このままでは、家系が絶えてしまうことに危機感を抱いたんでしょうね。母にしてみれば悩みは深刻ですもの……」
小早川は声のトーンを落とし、短い間を置くと話を続ける。
「そうこうしているうちに、そのシスターを介してGHQの高官夫人の一人と知り合ったんですが、馬が合ったんでしょうね。住まいも近かったこともありましたし、頻繁に行き来するようになったんです」
「じゃあ、お母様はその方にも?」
「ええ、話したんです。そうしたら、ならば養子を迎えればいいではないかと勧められたそうでして」
やはり……。
何もかもが、鴨上から聞かされた勝彦が養子に行った経緯と一致する。
息が止まる、心臓の鼓動が速くなる。
対面であったなら、間違いなく貴美子の表情の変化から、ただならぬ気配を察しただろうが、電話での会話が幸いした。
小早川は、淡々とした口調で続ける。
「養子については我々も考えたのですが、先にお話しした事情から、身内から迎えるのは難しい。半ば諦めかけていたのですが、だったら外から迎えればいいじゃないかと、そのアメリカ人の夫人から言われたんです。いかにもアメリカ人らしいですよね。外から養子、それも跡取りを迎えるなんて発想は、我々にはありませんでしたので……」
「それで、戦災孤児院に行かれたと?」
「いろいろ話し合ったのですが、結局はそうなりました。ただ、先のことを考えると問題はいくつもあるわけです。特に戸籍はどうにもなりませんのでね。後に養子と分かった時に本人がどう思うか。本人が気にしなくとも、私の跡を継いで政治家になるのですからね。支援者が後継者と認めるかどうかということも懸念されまして……」
「そこのところは、そのGHQ高官夫人が解決してくださったのですね」
「ええ、そうなんです」
「戸籍を改竄するだけの力があるなら、高官と言っても、かなりの地位がある方なんでしょうね」
「本国の国防総省から転勤してきた将官。確か少将だったと思います。ちょうど朝鮮戦争が勃発した頃に赴任してきた方で――」
間違いない。勝彦だ!
もはや、小早川の話など耳に入らない。
アメリカに渡ったとばかり思っていたが、勝彦は日本にいたのだ。
しかし、貴美子の胸中を満たしていたのは、我が子に対する思慕の念ではなかった。会いたいという気持ちすら覚えなかった。
もし、勝彦が不遇な道を歩んできたのなら手を差し伸べる気にもなっただろうが、当時は殺人犯として獄に繋がれた身であったのだ。十分な教育を受けさせることもできなかったはずだし、まして政治家の道を志すことなど夢のまた夢どころか、絶対に不可能だったに違いないのだ。
ここまで順調に歩んできた道を閉ざすことなどできるものではないし、名乗っただけでも勝彦の将来に影を落とすことになる。
思いがそこに至った瞬間、今の自分がなすべきことは一つしかなかった。
それは、勝彦に政治家としての王道を歩ませること。障壁となりそうなものは、ことごとく潰すことだ。
占い師を続けてきた中で築きあげた政財界の人脈。そして影響力を駆使すれば、何ら難しい話ではないし、勝彦に天下を取らせることも夢ではない。
そのためには、まずもっかのところ小早川が抱えている最大の難題である、借金と縁談を解決しなければならない。
「先生……」
小早川の話が一区切りしたところで、貴美子は呼びかけた。
「はい……」
「どうでしょう。一度、森沢社長と一緒に、京都に来ていただけませんか? うまくいけば、借金と縁談、二つの問題を円満に解決して差し上げられるかもしれません」
「えっ? 本当ですか?」
「ただ、来られる前に、一つだけやっていただきたいことがあります」
「それは何でしょう?」
「大蔵政務次官ならば、簡単にできることですわ」
貴美子はそう前置きすると、思い浮かんだ策を話し始めた。
5
新宿にあるヨドの本社から赤坂までは僅かな距離だ。
時刻は午後七時ちょうど。
高い黒板塀に囲まれた料亭の前に停まった車の後部ドアを、法被を着た下足番が引き開けた。
路上に降り立った繁雄(しげお)は、迎えに出た女将(おかみ)に軽く手を挙げてこたえると、そのまま玄関に向かって歩き始めた。
「先生は先ほどお着きになっておられます。お支度はいつもの通りでよろしゅうございますね……」
少し遅れて後に続く女将が、背後から訊ねてくる。
「ああ、それでいいよ」
森沢は鷹揚(おうよう)にこたえた。
小早川と会うのは三ヶ月ぶりになる。
連絡をしてくるのは小早川からと決まっていて、用件はただ一つ。金の融通である。
その際、提示された金額分に相当する手形に裏書きをさせ、現金を手渡すのだが、違法行為には当たらないものの、やはり他人に見られるのはまずい。僅かな時間だが、人払いをするのが常である。
靴を脱ぎ、玄関に上がったところで、繁雄は背後にいた秘書に向かって手を差し出した。
「今日は、ここまででいい。話が長くなるだろうから、君は先に帰っていいよ」
「はっ……」
頭を下げた秘書が、手にしていた鞄を差し出してくる。
それを受け取った繁雄は、女将の先導で廊下を歩き、一番奥の部屋へと向かった。
「森沢社長がお見えになりました」
廊下に立膝をついた女将が部屋に向かって声をかけ、障子を引き開ける。
座布団から身をずらした小早川が、そのまま畳に両手をつき、
「ご無沙汰致しております。今回もまた、無理なお願いにもかかわらず、ご快諾いただきまして恐縮に存じます」
深々と頭を下げる。
毎回毎回、代わり映えのしない言葉を……。
丁重ではあるが、上辺を繕っているだけのように感ずるのは気のせいではあるまい。
そんな内心を微塵(みじん)も見せず、
「いや、先生。頭を下げるなんてやめてください。大蔵政務次官ともあろうお方に、そんなことをされると、身の置き所に困ってしまいます。ささ、席にお戻りください」
繁雄は小早川を促し、正面の席に腰を下ろした。
「今回は、三千万円でしたね」
改めて金額を確認した繁雄に、
「興梠(こうろぎ)先生の政権基盤は盤石で、党内に対抗できる勢力はありません。興梠先生の資金基盤も豊かになるばかりです。もちろん、私もその恩恵に与(あずか)っている一人ではあるのですが、自分のグループを率いる身です。それに、息子も来年の春には学位を取得して帰国する予定で、なるべく早いうちに後を継がせようと考えておりまして……」
「ほう、ご子息は、いよいよ帰国なさるのですか」
もちろん、小早川にアメリカに留学中の息子がいることは承知しているが、これまで自ら息子のことを話題にしたことがなかっただけに、繁雄には意外に思えた。
「ご存じでしたか?」
意外そうに言う小早川に、
「そりゃあ、優秀だともっぱらの評判ですからね。悪い噂はあっという間に広がるものですが、いい噂はなかなか広まらないものです。なのに私のようなものの耳に入るぐらいですから、周囲も一目置かざるをえないほど優秀なんでしょうなあ」
繁雄は思い切り持ち上げてみせた。
「まだ海のものとも、山のものとも分かりませんがね。それに政治の世界は、優秀な人間が上に立つとは限りませんので……」
「確か、東大法学部を出られて、ニューヨークのコロンビア大学の大学院で学ばれておられるとか?」
「ええ……」
「東大もさることながら、コロンビア大学はアメリカでもトップレベルですからね。アメリカ歴代の政権で重職に就いた教授も数多くいますし、数多(あまた)の同窓生がアメリカの政財界で活躍しているんですから、先生の後を継がれたら、対米外交の要として異例の若さで要職に就くこともあり得るでしょうなあ」
小早川が自ら息子を話題にしたのをこれ幸いとばかりに、森沢はさらに持ち上げた。
「ただ一つ、気になるのは息子が、私のグループを率いるようになるまで、かなり時間がかかるという点です」
「と言いますと?」
「日本はまだまだ年功序列。経験値が評価される社会です。それは政治の世界も同じでしてね、それなりの当選回数を経ないと要職には就けません。グループを率いるのにも、同じことが言えるわけでして……」
「なるほど。つまりご子息が先生のグループを率いるようになるまで、先生の影響力をいかにして維持するかが、ご子息の将来を大きく左右するわけですね……」
「もちろん、代替わりした後も、息子の後ろ盾として影響力を行使するつもりではおります。ただ、ご承知のように政界での影響力は、とどのつまり金。興梠先生のように、絶対的な政権基盤をものにできれば、黙っていても金は集まってきますが、そうなるまでにはやはり――」
「時間がかかる。その間、どうやって凌(しの)ぐか。豊富かつ、安定的な資金源を確保できるか否かにかかってくるというわけですね」
その資金源をどこに求めるかとなれば、答えは明らかだ。
なのに頼み込むでもなし、相談を持ちかけるような言い回しをするのは、こちらから資金の提供を持ちかけさせるのが狙いだろう。
同じ借金にしても、「出して欲しい」と頼むのと、「私が出す」と言わせるのとでは、どちらが優位に立つかは明らかだからだ。
なるほど、そうきたか……。
いずれタイミングを見計らって、縁談を持ちかけるつもりではいたが、図らずもその時が来たようだ。
内心でほくそ笑みながら、繁雄は無表情を装い、
「もちろん、これまで先生をご支援してきたのですから、出せとおっしゃるのなら、出して差し上げてもいいですよ。でもね先生、今日三千万用立てれば、これまでお貸しした金額と合わせて二億一千万。今後も資金の需要は尽きないでしょうから、幾らになるか分かったものではありません。まして、ご子息がグループを率いるようになって、政界で影響力を発揮できるようになるまでに、どれほど時間がかかるかを考えると、十億、いやその倍、三倍はかかるかもしれませんが、返済はどうなさるおつもりです?」
サングラスの下から、小早川を睨(にら)みつけた。
ところが小早川は怯(ひる)む様子も見せず、不敵な笑みをさえ浮かべる。
「息子の将来に賭けて欲しいといったら、虫が良すぎますか?」
その反応ぶりから、彼が何を目論んでいるか察しがついたような気がした。
借金をチャラにするための方法は一つしかない。
息子と櫻子(さくらこ)を結婚させることを目論んでいるとしか考えられない。
望むところだ、と思いながらも、
「将来に賭ける?」
繁雄は片眉を吊り上げた。「確かに、ご子息は飛び切り優秀でいらっしゃるようだ。ですがね、政界は権力欲に取り憑かれた魑魅魍魎(ちみもうりょう)が蠢く場ですよ。それこそ一寸先は闇。何が引き金になって、失脚するか分かったものじゃありません。この際、はっきり申し上げておきますが、これまで一切借金の返済を迫らなかったのは、それこそ先生の将来に賭けたからなんです。そう遠くないうちに代替わりするお考えを聞かされたからには、これ以上金をお貸しすることはできませんね」
こんな返事は、想定していなかったのだろう。
「ちょ、ちょっと待ってください」
小早川は身を乗り出し、慌てた口調で言う。「新人議員には違いなくとも世襲の、それも四代目からのスタートとなるんですよ。これまで私が築き上げてきたグループも、いずれ引き継ぐことに――」
「世襲議員なんてわんさかいるじゃありませんか」
繁雄は小早川の反論をピシャリと遮った。「その中で総理総裁に上り詰めた人間が何人います? そりゃあ、初代に比べれば出世する確率は高いと言えるでしょうが、ご子息の場合は、華麗な経歴が仇になるかもしれませんしねえ」
「と言いますと?」
小早川は理解できない様子で、眉を顰(ひそ)める。
「ご子息は、既に勲章、それも望んでもなかなか手にできない勲章を胸にぶら下げているからですよ」
小早川は、まだ先があるのだろうとばかりに、繁雄の言葉を待っているようだ。
繁雄は続けた。
「小、中、高、そして大学は日本の最高峰。文字通りのエリートコースの王道を歩んで来られた。しかもいずれも国公立。つまり、実力で最難関を突破したんです。なるほど二代目、三代目議員の中にも同等の学歴を持つ者がいないではありませんが、欲しても手にできないものを持つ人間。しかも、それがライバルともなると――」
「妬み、嫉(そね)みの感情が先に立つ……とおっしゃりたいわけですね」
今度は小早川が、繁雄の言葉を遮った。
「それに日本人は、異物を排除しようとするきらいがあるように思うんです」
「異物?」
「この国では以心伝心、阿吽(あうん)の呼吸なんて言葉があるように、同類でつるんだ方が何かとやりやすいんですよ。そんな中に、アメリカで政治学の学位を修めたご子息が入ってきたら、異物と見做(みな)されることになるんじゃありませんか?」
「ならば、現幹事長はどうなんです?」
小早川は、納得がいかないとばかりに反論に出る。「彼は中卒、しかも世襲議員でもなく、与党の幹事長の座を手にしたんですよ。しかもまだ五十八歳。庶民の人気も抜群で、今太閤とさえ呼ばれてもいるじゃありませんか」
「あの人は例外中の例外ですよ」
繁雄は苦笑を浮かべた。「戦中戦後は、学力優秀でも進学を断念せざるを得なかった少年少女がごまんといましたからね。それに、日本人は立身出世のストーリーが大好きですし、なんといっても、ご自分で立ち上げた事業で成功し、確たる財政基盤を自ら築き上げられた。そんな真似を三世、四世議員ができると思いますか? 度胸も根性も、野心の強さ大きさも、サラブレッドの比ではないんです。数多の修羅場を潜り抜けて、今日の地位を手にしたんです」
反論などできるものではない。
果たして小早川はぐうの音も出ないとばかりに、険しい顔をして押し黙る。
「先生……」
繁雄は小早川に向かって呼びかけた。「私は金貸しです。そして貸した金に金利を乗せた金額を回収できて初めて成り立つ仕事を生業(なりわい)としてるんです。消費者金融は信用貸しですが、手形金融は金額が大きい分だけ、リスクが伴います。ですから貸付金相当分の手形をもう一枚、担保としてお預かりしているのです」
繁雄が行っている手形金融の仕組みを小早川が理解しているかどうかは関係ない。『担保』という言葉を印象づけるために言ったのだ。
「これまで先生には、金利をつけず、催促もせずで金を貸してきました」
繁雄は続けた。「こんなこと、金貸し稼業を始めてから、一度としてなかったことなんです」
「その点は、重々承知しております……。甘えてばかりで申し訳ないとは常々思っていたのですが、社長の好意にすっかり甘える形になってしまって……」
心底恐縮した体で、小早川は肩を落とし、項垂(うなだ)れてしまう。
「私が勝手にやったことですから、それはいいのですが、なぜこれまで乞われるまま、黙って金を出してきたのか、分かりますか?」
さあ、そろそろ落としにかかるか……。
繁雄は、内心で舌舐(したな)めずりをしながら話を続けた。
「それはね、先生が在任中に、貸した金に見合う何らかのメリットを私、あるいはヨドにもたらしてくれるか、それなりの地位に就き、貸した金を耳を揃(そろ)えて返してくれることを期待していたからなんです」
「そこのところも十分に理解しております……」
小早川は呻(うめ)くように言う。
「でしたら、貸した金に見合った働きもしていないのに、議員職は息子に譲るから、引き続き支援をしてくれとは、あまりにも虫が良すぎませんか? 代替わりとはいえ、政界では一年生議員からのスタートなんですよ? それなりの地位、力を保つまでにいったいどれだけの時間がかかり、金が必要になるんですかね」
「何もかも社長のおっしゃる通りではあるのですが、議席を譲った後もグループに所属する議員への私の影響力が衰えるとは考えておりません。息子の背後には常に私がいる。つまり、息子を通して――」
「どうやって?」
繁雄は小早川の言葉が終わらぬうちに訊ねた。「先生が影響力を発揮できるのも、確たる財政基盤があればこそ。私の支援が得られればこそではありませんか。私が、手を引いたらどうするのです?」
「そ……それは……」
返答に窮して、小早川はそれ以上言葉が続かない。
「となると、方法は二つしかありませんね」
仕留めた。もう逃げられない。
確信した繁雄は、冷徹な口調で告げた。
「一つは、現時点でお貸ししている残額一億八千万を耳を揃えて返していただくか――」
「できません! 今日だって三千万を用立ててもらうつもりできたのです。全額返済など、とても無理です」
顔面を蒼白にした小早川は、必死の形相で訴える。
それを無視して、繁雄は次の提案に入った。
「二つ目は、担保を入れていただく」
「担保?」
小早川は小さく呟き、眉を顰める。「今までお借りした分の返済すら追いつかないのに、担保に見合う財産など私にはありませんが?」
「担保はね、換金性があるものだけとは限りません。人だって立派な担保になるんですよ」
「人と言いますと?」
「ご子息ですよ」
繁雄があっさりこたえると、
「息子? なんで息子が担保になるんですか?」
小早川は、驚愕(きょうがく)のあまり声を張り上げる。
「先生、おっしゃったじゃないですか。息子の将来に賭けて欲しいと……」
「確かに言いましたけど――」
「最近でこそ聞かなくなりましたけど、借金の形(かた)に身を差し出した時代があったんですよ」
繁雄は小早川を遮り、明確に告げた。「要は縁を結ぶ、ご子息が私の身内になればいいんですよ」
「息子と社長のお嬢さんを結婚させろと?」
「二人が結婚すれば、先生のご子息は、私の義理の息子になるんです。息子に借金の返済を迫る親がどこにいますか。いないでしょう?」
「それはそうですが、しかし――」
「娘の幸せを願わぬ親はいませんからね」
繁雄は勢いのまま畳み掛けた。「義理の息子のため、それすなわち娘のためとなれば、私だって出し惜しみはしませんよ。先生の願い、ご子息の願いを叶(かな)えるべく、全力でお支えしますが?」
*
やはりそうきたか……。
驚き、戸惑う素振りを見せたのは、もちろん演技である。
何もかもが想定通りの展開になったことに、小早川は胸中でほくそ笑んだ。
そんな内心を噯(おくび)にも出さず、
「おっしゃることは分からないではありませんが、それじゃまるで身売りじゃないですか……」
小早川は、か細い声で抵抗感を示してみせた。
「政治家や良家の結婚なんてそんなもんでしょう」
繁雄は平然と言う。「息子、娘の結婚が、両家にどんなメリットがあるのか。親も当事者もそれを吟味した上で縁続きになるのを良しとするんじゃないですか。閨閥(けいばつ)なんてものは、そうやって出来上がるものでしょう」
時代と共に変化しているとはいえ、未(いま)だ家同士の打算によって成立する結婚があるのは否定できない。
「戦国時代の大名は、もれなく側室を設けていましたよね」
繁雄は続ける。
「あれはね、幼くして亡くなる子供が多くて、跡取りを確保する目的もあったでしょうが、側室の子だって殿様の実子には違いありませんからね。娘を他の有力大名の元に嫁がせれば縁続き。男子なら人質に差し出せる。子供は戦(いくさ)を抑止する道具となり得たからだと私は考えていましてね。とうの昔に戦の心配は無くなりましたが、その分だけ一旦縁を結べば家同士の絆(きずな)はより強固になるんですよ」
「結婚にそうした一面があるのは否定しませんが、社長からの借金は、息子が与り知らぬところで私がこしらえたものです。その形に息子を差し出すのは、親としてはさすがに……」
「まだ事の深刻さが分かっていないようですね」
繁雄の口調が明らかに変わった。
穏やかではあるものの、声の質感が重く冷たくなる。
そう、いよいよ金貸しの本性を現したのだ。
果たして繁雄は言う。
「先生が裏書きなさった手形が不渡りになっていないのはね、私が肩代わりして落として差し上げたからですよ。手形は全部コピーして私の手元にある。私が一括返済を迫ったら、先生どうなさいます? サラ金から、こんな方法で政治資金を用立ててもらったことが、明るみに出たら先生どころか、ご子息の将来だって危うくなるんじゃありませんか?」
繁雄はケロイド状になった火傷の跡が残る顔を歪(ゆが)ませ、薄い唇の間から歯を覗かせる。
「いや、それは……」
「私を紹介した鴨上先生になんとかならないかと、ご相談に上がるとでも? それもいいかもしれませんが、果たして鴨上先生は助けてくださいますかね?」
話しぶりからして、鴨上に助けを乞えば、どんな言葉が返ってくるか。繁雄は間違いなく知っている。
やはり、最初から筋書きはできていたのだ。
改めて確信しながら小早川は、
「いや、これ以上鴨上先生のお手を煩わせるのはちょっと……」
悄然(しょうぜん)と肩を落とし、俯(うつむ)いてみせた。
「だったら、どうなさるのです? 私の提案を呑(の)んで資金提供を受け続けるか、全額耳を揃えて清算なさるかのいずれかしか選択肢はないじゃありませんか」
逃げ場を失った獲物を屠(ほふ)るかのような冷酷な声が頭上から聞こえた。
「分かりました……」
短い沈黙の後、小早川は決然として顔を上げた。
してやったりとばかりに、繁雄の頬が緩んでいるように見えるのは気のせいではない。
まだ、勝負はついちゃいないぜ……。
小早川は内心で毒づきながら、繁雄に言った。
「縁談の件、前向きに検討させていただきます。ただし、それに当たっては一つ、条件があります」
「条件?」
「私と一緒に京都に行って欲しいのです」
「京都に? なんでまた」
問い返してきた繁雄に向かって、小早川はその理由を話し始めた。
(次回に続く)
プロフィール
楡 周平(にれ・しゅうへい)
1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
