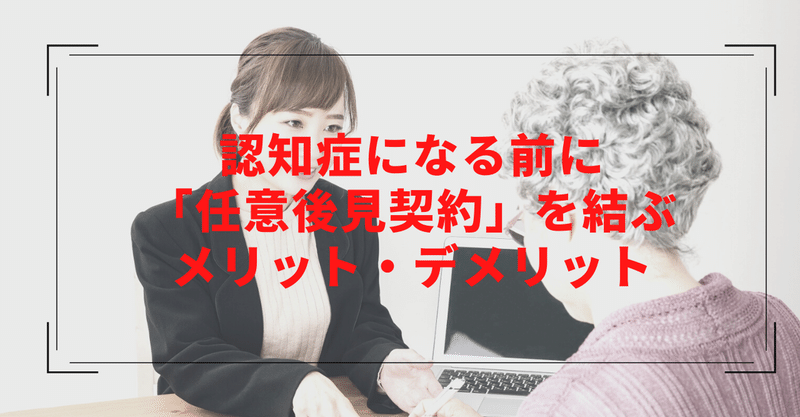
認知症になる前に「任意後見契約」を結ぶメリット・デメリット
皆さん、こんばんは!
親が認知症になってしまって施設に入る事になり、
急にお金が必要になってしまっても
息子が親の家を売却することは出来ないってご存じでしたか?
今日はそんな事が起こる前に知っておくべき
「任意後見契約」について、
2~3分で読める程度に書いていきます。
1.成年後見制度とは
まずは、「成年後見制度」とは何かという説明からしていきます。
「成年後見制度」とは、将来自分の判断能力が失われた場合、
財産の管理や看護・介護サービスの契約などを成年後見人が
本人に代わって行う事が出来る制度のことです。
成年後見人制度には2通りのパターンがあります。
①法定後見制度
本人の判断能力が欠如・又は不十分になってしまった場合に、
家族が家庭裁判所に申立てをして
家庭裁判所が「法定後見人」を選ぶ制度のことです。
家族内に法廷後見人にふさわしい人がいたとしても、
家庭裁判所がその人を選ばず弁護士を選任するという事
もあります。
本人の状態によって、
「後見」「保佐」「補助」の3類型から選ばれます。
②任意後見制度
まだ本人の判断能力があるうちに、本人の希望する人を
「任意後見人」にする事が出来ます。
任意後見契約書は公正証書にて契約を締結します。
また、「こういう介護施設に入りたい」
「家を売却する時の条件」など、
本人が希望する内容を契約書に盛り込む事が出来ます。
2.任意後見契約で出来ること
選ばれた後見人は、「財産管理」と「身上監護」を
行う事が出来ます。
ただし、実際の家事や買い物、介護などの事実行為は
含まれません。
以下に、任意後見人が出来ることを挙げてみます。
【財産管理】
・銀行の預貯金や現金の入出金管理
・不動産の管理・保存・処分
・税金の申告・納税
・年金の申請・受取
【身上監護】
・病院・施設での手続きや支払い
・医療・福祉サービスに関しての手続き
・ガス代・電気代などの支払い
・住居の手続きや契約・支払い
・要介護認定の申請
3.任意後見契約のメリット・デメリット
任意後見契約のメリット・デメリットには
どの様なことがあるのでしょうか?
【メリット】
・本人の意思で任意後見人を選ぶ事が出来る
・任意後見契約の内容は本人の希望で具体的に指定する事が出来る
・任意後見人の地位が公的に証明される
【デメリット】
・本人の判断能力が低下した状態だと契約が出来ない
・本人が死亡した時点で契約終了となる為、
死後の手続きや事務処理などは委任出来ない
・任意後見人には同意権・取消権がない
4.任意後見契約の流れ
ここでは、任意後見契約の流れを見ていきます。
①まだ判断能力があるうちに
本人と任意後見人が「任意後見契約」を締結する
②本人の判断能力が低下してくる
③任意後見人が家庭裁判所に
「任意後見監督人選任の申立て」をする
④家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
⑤任意後見監督人が任意後見人を監督する
⑥任意後見契約による支援開始
5.任意後見契約の注意点
便利に感じる任意後見契約ですが、注意点やポイント
を挙げておきます。
①任意後見人(特に弁護士や司法書士など)や
任意後見監督人にはそれぞれ内容に応じて月額報酬
を支払う必要があります。
②「おひとりさま」は同時に
「見守り契約」
「死後事務委任契約」
「任意代理契約」
など、他の契約も締結しておくと安心です。
②たとえ息子が成年後見人であっても、
ただ「空き家にしておきたくない」
と言う理由だけで親の家を売却するには
家庭裁判所の許可ハードルはかなり高い様です。
まとめ
・成年後見制度とは
・任意後見契約でやれること
・任意後見契約のメリット・デメリット
・任意後見契約の流れ
・任意後見契約の注意点
今日は、「任意後見契約」について
書いてきました。
認知症が進んでしまうと、多くの法律行為が
出来なくなってしまいます。
認知症になる前に、本人の希望も考慮できる
「任意後見契約」を締結しておくべきですね。
また、親が施設に入る為の資金にしたいなど、
家を早く売却したい場合は、まだ本人の判断能力が
しっかりしているうちに
親と一緒に売却などの行動に移した方が良いと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
