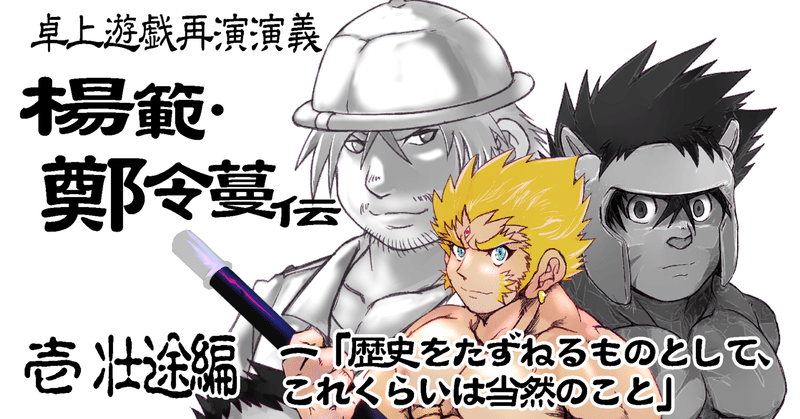
楊範・鄭令蔓伝 壮途編 一「歴史をたずねるものとして、これくらいは当然のこと」
第1章 会稽山
一 「歴史をたずねるものとして、これくらいは当然のこと」
会稽の関氏というのは、随分立派な豪族らしい。少なくともテレマコスの目にはそうはっきりと感じられた。なにせ邸宅が大きいししっかりしている。そう、成金者によくある金ぴかの、どこかいやらしい趣味の邸宅とは違って、地味だが重厚なつくりなのである。古い貴族の家なのだろうか、壁もしっかりしているし塀などは小さな要塞のように頑丈だった。
いや、考えてみれば豪族の私邸というものはもともと要塞なのである。豪族同士のトラブルとか勢力争いとかで私兵同士が戦闘するとかいう話はあたりまえなのだから、家が要塞になるのもあたりまえのことだった。だから歴史のある貴族の家はそれだけ堅固なのである。
テレマコスがそんなことを考えていると、門のところから門番がひょいと首を出した。さっき取り次ぎを頼んだ初老の男である。番人はにこりと微笑むとテレマコスに声をかけた。
「どうぞ、当主様がお会いになります。」
「おお、わざわざ主様が?」
「ははは、我が主人は客を愛するお方ですよ。あなたも良くこの家に目をつけられた。」
会稽の関氏が「客を愛する任侠の人」ということはどうも噂以上らしい。なにせ外国人であるテレマコス達を快く迎えいれるというのだからたいしたものである。テレマコスは傍らにいる小柄な青年にうなずき、番人に導かれるまま邸宅の門をくぐることにした。
* * *
屋敷はいくつもの建物が渡り廊下でむすばれた広いものだった。廊下から見える庭はきちんと手入れされており、柳や桃の木が形良く植えられている。一番大きな庭には舟遊びができそうなほどの広い池があり、真っ赤に塗られた太鼓橋まである。
その大きな庭に面した部屋で主人は待っていた。会稽郡の関氏当主、関子邑である。身の丈はテレマコスとほとんど変わらない。サクロニアの人間の中ではテレマコスは決して大柄なほうではないのだから、関子邑も長身というわけではないのだろう。ただどこか鋭さのある目と、しかし穏やかな顔つきという複雑なとりあわせはこの子邑という人物が見かけどおりの人物ではないことを示している。
(貴族というより、どこかのやくざの親玉みたいではないか…)
そうテレマコスが感じるくらいにこの子邑という人物は独特の雰囲気をもっていた。まあもっともテレマコスほど(年齢に比べて)老練な魔道士でなければそういう風には感じないかもしれない。
子邑はテレマコスを立って出迎えた。
「良くぞ我が関家の門を叩いてくださった。一門の名誉となるでしょう。」
「御好意いたみいります。鄭令蔓です。それからあそこで控えているのは私が面倒を見ているリンクス。身の周りの世話をしてもらっています。関家の皆様に栄えがありますように。」
「鄭令蔓…鄭子とお呼びいたしましょう。お連れの若い方も頼もしそうですな。」
サクロニアから来た人間らしくテレマコスは西方風の挨拶をした。「鄭令蔓」というのはテレマコスの中原風名前である。名前に無理矢理当て字をしたのであるから、なんだか意味がおかしいかもしれないがこれはしかたがない。連れであるリンクス…さっきからほとんど何もしゃべらずにテレマコスの傍に控えていた小柄な、しかしたくましい青年は部屋の外で彼らを守るように立っている。
テレマコスは子邑に勧められるまま、西側の席に座った。子邑自身は南側の席である。なぜ机を挟んで正面に座らないのかというのは(これはテレマコスが後から知ったことだが)、座席にはそれぞれ意味があってうっかり間違えると「主従関係」かなにかのようになってしまうからだった。既に二人の目の前には熱いお茶と菓子がならべられている。机の上には丸い、ちょうど野球のボールくらいはある見事な水晶玉が置かれている。
最初に子邑はその水晶玉を手にとってしげしげと見つめた。普通の水晶とはちがって中にきらきらと金色の光のしずくがきらめいている。珍しい上にこれだけのサイズなのだからかなりの価値である。
「こんな素晴らしいものをいただいてもかまわないのだろうか?鄭子…」
「いえいえ、私の故郷の国では手に入らないものではないのですよ。無論ここまでもってくるのは大変なのですが…」
テレマコスは内心苦笑した。彼の故郷の国サクロニアでは、安いというわけではないがこういう水晶玉は手に入る。魔法で合成した水晶だからである。テレマコス達魔法学者はその気になればこういった巨大な水晶を魔法儀式で作り出すことができた。要するに人造宝石である(鑑定すればわかる)。それなりに高価だが子邑のおもっているほどではない。詐欺というわけではないが、さすがに少しばかり後ろめたい気もする。まあしかし、おかげでこれだけの好意を関氏から引き出すことができたのであるから、テレマコスは黙って苦笑しているしかないのである。

しばらく水晶玉を見つめて驚いていた子邑だが、今度はこれをもたらした客人、つまりテレマコス達を驚いたように眺めた。
「サクロ…いや、我々は朔州と呼んでいますが、はるばるそんな遠くから、さぞかし道中苦労がございましたでしょう?」
「いえいえ、なんの。中原にひかれて参ったのです。歴史をたずねるものとして、これくらいは当然のこと…」
テレマコスはそういうと笑った。朔州というのはテレマコスの故郷サクロニア世界のことである。飛行呪文を使って彼らはこの中原にやってきた。大変といえば大変だが、歩いてきたとかそういうわけでは決してない。こういう点でもなんだかかなりおおげさに評価されているわけである。
彼はこの関家に「歴史家」として自己紹介したのだった。「アンゴルモスの大魔道士」…サクロニアでは押しも押されもせぬ魔法学者のテレマコスだったが、この中原ではそういうわけにはいかない。それに「魔道士」という言葉が、魔法文明の栄えるサクロニアではまだしも、この中原ではあまり受けがいいとは思えなかったのである。実際、彼自身の目的からいっても歴史家というのが一番似ている。中原の伝説的英雄「黄帝」についての調査というのだから歴史の分野だった。「黄帝」をなぜ調査しているのかといわれるといささか話が変わってくるのだが、それはおそらくこの関子邑にとっては関係のない話だろうし、興味もないことだろう。
とにかくお茶を飲みながらのテレマコスと子邑との話は意外なほど花開いた。テレマコスの話す遠いサクロニアの話題や途中目にした様々な国の話題、子邑は子邑で中原、特にこの会稽の最近の話やらなにやらである。間に光っている宝石の力もあるのだろうが、テレマコスと子邑はどうも波長が合うらしい。これは無論テレマコスにとっては好都合だった。中原地方ではコネがない彼なのだから、こんな実力者にお近づきになれるということは非常によいことに決まっている。とにかくあんまり話の花が開いてしまい、いつのまにやら夕闇が近づいてくるのに気がつかない程だった。
とはいうものの、これだけ長い間しゃべっているとお互いに空腹になってくるのはあたりまえだった。それに気付いたのか召使…おそらくその長である家宰だろう…が現れて子邑に耳打ちをした。子邑は苦笑してうなずく。
「おお、そうでした。長旅でお疲れなのに申しわけない。お部屋に案内いたします。それから風呂も準備させます。また後程ぜひ続きを…」
子邑はもうすこし話したそうにテレマコスに微笑んだ。お世辞ではなく、この初老の豪族にとってサクロニアの大魔道士との茶話会は興味深く楽しいものだったのである。少なくともテレマコスはそう確信することができたのだった。
* * *
熱い風呂に入って旅の汚れを落としたテレマコス達に待っていたものは夕食会への招待だった。無論テレマコスに異存があろうはずはない。普段テレマコスはあまり食にはこだわらないほうだったが、うまいものにありつけるというのはそれでもありがたいことだった。
「リンクス、どうかね?」
「いえ、僕は…」
テレマコスがリンクスに問いかけたのは言うまでもない。客人ということになっているテレマコスに対して、付き人というふれこみのリンクスはこういう場合おいしいご飯にはありつけないからである。
リンクスという少年…いや、年齢から言えば既に十分青年といってもいいのだが、未だにテレマコスから見ると少年のように感じられる…は、こういう身分の高い連中の間に立ち混じらせるのは不向きだった。なにせあまりに無口で社交的ではないし、豆タンクみたいながっちりとした身体である上に、顔にも全身にもひどい切り傷のあとがあるし、それに無骨な金属製のヘッドギアまでしているし…別にひねくれているというわけではない(むしろとても素直である)のだが、やはり戦場からやってきた修羅という感じは否めない。
いや、実際彼はそうなのである。軍事用に調整され、意志を奪われた戦闘用奴隷…それがリンクスの正体だった。経験豊富な大魔道士であるテレマコスすら驚く戦闘能力をもつ生体兵器だったのである。暗殺者として鍛え上げられた肉体と、頭にはめ込まれたヘッドギアによって引き出されるサイオニクス…精神エネルギーを応用した一種の戦闘魔法…まさに殺人機械としか言いようがない。筋骨たくましいものの少年のように見える外見も、暗殺者として肉体の成長を調整されているがための、いわば傷跡のようなものだった。
数年前に彼を拾ったテレマコスはそんな彼を人間に戻すために仲間とともに尽力した。家族のように接し、学校にも行かせ、彼の失われた過去を取り戻すために旅をしたのである。たぐいまれな潜在的サイオニクスの力をもつがゆえに、闘うことを運命づけられたこの少年剣士に人間の暖かさを教えたのはテレマコス、そしてその旧友達だったのである。
いろいろあったものの、今では泣きもすれば笑いもするこの少年剣士はテレマコスにとって弟同然の存在だった。そういう理由もあって、リンクスにはうまいものを食わせてやりたいという気持ちがするのである。
「遠慮はいらんよ。疲れているからとかいって断れば良いからな。」
テレマコスがそういうと、リンクスは例の透明なグリーンの瞳でこの魔道士をみて首を横に振った。
「いえ…出席したほうがいいと思います。テレマコスさん。」
「というと?なにかあるのか?リンクス」
いぶかしげにテレマコスは聴いた。この少年剣士はテレマコスが気付かないようなところが直感的に判るらしい。いつもあまり余計な口は挟まないが、その分周囲の様子をじっと観察しているからであろう。
とにかくリンクスは静かに言った。
「多分今日の夕食会はテレマコスさんにいろんな方を紹介するつもりだと思います。」
「ううむ…やれやれ。」
リンクスの観測はおそらく当たっているだろう…そう感じたテレマコスはいささか疲れたように肩をすくめた。どうも扉の外側の喧騒ぶりはかなりのパーティー準備の様相である。間違いはなさそうである。
関子邑との茶話会は楽しいものだったが、それ以外の人物にまで会うとなると楽しいことばかりとは限らない。いや、まちがいなく極めて社交的なパーティーである。一気に旅の疲れが吹き出してしまうかもしれない。それに加えてリンクスが食事に預かれないとすると、これはさすがに困ってしまう。
しかし…そういうイベントである以上、断るというのもやはりまずかった。せっかく歓迎してくれている関子邑の心証を害するのもつまらない話だし、彼らの目的に必要な人物に会える可能性もある。となると…今夜もリンクスには我慢してもらうほかはないかもしれない。
「そうか…すまないな、リンクス…」
しかたがないというように首を振ったテレマコスは、鞄の中から黒のローブを取り出した。魔法学者が正式な場所に出るときの礼服である。リンクスに着るのを手伝ってもらいながらテレマコスは「これで手がかりがつかめなかったら悲惨だな」と思わずにはいられなかった。
(2へ続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
