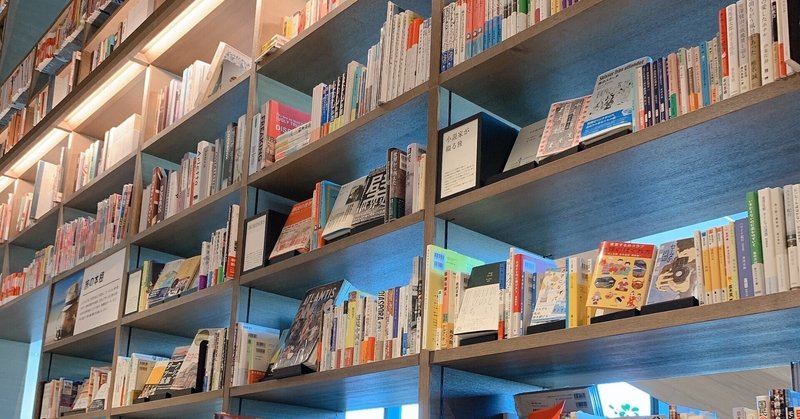
2020年プロ雑用が読んだ書籍BEST11+
こんにちわ、プロ雑用です!
毎年年末は、いろんなことがあったなぁ、と振り返るものですが、今年こそいろいろなことがあった!と言える年だったのではないでしょうか。
世界レベルでガラリと何かが変わってしまった年。
まさにパラダイムシフトが起きた年だと、後で振り返って思うのでは。
というわけで、今年の総括として、読んだ書籍の中から、とても影響を受けた11冊+αをご紹介したいと思います。
例年通り、ビジネス書籍など限定で、コミックや小説は除いています。
順番に紹介しますが、順位ではありませんのであしからず。
(順位なんてつけようがないくら学びが多いものばかりでした)
ではどうぞ。
★2020年 BEST11
PIXAR 〈ピクサー〉 世界一のアニメーション企業の
今まで語られなかったお金の話
ローレンス・レビー (著), 井口耕二 (翻訳)
著者のローレンス・レビーさんは、ある日、スティーブ・ジョブスからピクサーの最高財務責任者に誘われる…1994年、いまだピクサーは世間にその名を知られておらず、ジョブズが自腹で会社を支えていた時代。
トイ・ストーリーの爆発的ヒット以前、投資先を見つける苦労や、ディズニーとの関係、そしてジョブズの死。
財務、お金という視点から見たピクサーという企業の実態を、著者の実体験に基づいて描かれている情熱の一冊。
お金の話になっても、ピクサーはピクサーなんだなと感じました。
日本人はとかくお金を忌避し、また軽視しがちだけど、お金が無いとどうしようもない。逆にお金があれば加速できる。でもお金は使い所がある、ということを学びました。
いま、拠って立つべき“日本の精神” 武士道
新渡戸稲造 (著), 岬龍一郎 (翻訳)
かつて5000円札に描かれた明治・大正を代表する教育者、新渡戸稲造氏が、1899年に「海外に向けて英文で書かれた」武士道を、現代語に翻訳した書。
武士道は、かつて日本にいた武士という階級を通し、日本の文化について語る。明治維新によって急速に欧米化していく当時の日本において、教育者として冷静に武士というものを分析し、日本人のアイデンティティを詳らかに語られています。
現在においても急速なグローバル化によって、日本人の嫌な点やだめな点が強調されがち、あるいは過剰に美点を探すような行動が見られますが、その根底には日本全体の「自己肯定力の低さ」があります。
これは、そういう現代人こそ読んだほうがいい書籍。
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ 500年の物語
田中靖浩 (著)
先に紹介したピクサーの財務の話から、投資やお金の流れについて興味をそそられ、巡り合ったのがこの一冊。
会社と簿記の誕生から、財務、管理会計、そしてファイナンスと、歴史を追いかけながら、どうやってお金の取り扱いが発達してきたのかを紹介されています。
語り口が軽妙で、誰もが知ってる歴史の人物たちの背景を絡めながら紹介されており、へぇ!!と思いながら、スラスラと読めました。
ダ・ヴィンチがあんなに作品を残せたのは、紙をおおく扱える親の職業が影響してた…とか、ケネディ大統領の父親は、天才的な相場師だったとか…
会計に興味がなくても、歴史の一旦として学べる一冊。
組織にいながら、自由に働く
仲山進也 (著)
楽天大学学長の仲山さんの著作。
昨年紹介した”今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則”ではチームで働く、ということでしたが、こちらは個人としての視点(もちろんチームも関係しますが)で、働くとはどういうことかが解説されています。
この本が書かれたのは、2018年ですが、ここで書かれていたことが、まさしく今年やってきた感じ。このコロナの時代をうまく利用できている人は、ここで書かれているような働き方をしています。
逆にうまく利用できてない取り残されている人は、この本を読むと新しい気付きが得られるはずです。
最軽量のマネジメント
山田理 (著)
これも、コロナ前に書かれたのに、コロナの時代を予見していたかのような内容ですよね。いろいろマネジメンというものを考えた結果、こうやったら成功した!ではなく、いろいろやってきたけどことごとく失敗した…というところから「もう管理すんのやーめた!」と潔くあきらめた話。
これだけ書くとなんか全部放棄してるみたいですが、それが如何に時代にあっているか。本書を読めばわかります。
形だけの働き方改革でいちばん損しているのは、間で板挟みの中間管理職なんだ!という著者の叫びが聞こえてきます。
シチリア・マフィアの世界
藤澤房俊 (著)
イタリア、シチリア島。わたしは観光の島としてしか認識していないこの島は、「イタリアという国の中の国」と呼ばれる独立意識の高い土地。
マフィアと聞くと、日本人ならヤクザと同じような連想をしてしまいますが、学んでみると全く似ても似つかないものだということがわかりました。
日本は日本、イタリアはイタリア、と認識しがちですが、日本でも地域性というものがあり、犯罪率とってみても様々な差があります。
イタリアは日本以上に地域性の違いが顕著で、考えてみれば絶えず国境争いをしている地域と、島国では違うのはあたりまえですね。
シチリアという島の過酷な歴史を紐解きながら、マフィアという存在がどうして生まれ、そしてどう支配層と繋がり、そして今どうなっているのかが丁寧に描かれていて、これだけで映画が何本も作れそうです。
マフィアの世界を知りたいなら、これ、という一冊。
反応しない練習
草薙龍瞬 (著)
ブッダは実は「超クール」。
帯に書かれたこの一文は、ブッダや原始仏教を知らない人にとってみれば衝撃的だと思います。しかし、もともと原始仏教は、世の苦しみから開放されるためにはどうするか、ではなく「そもそも生きることは苦痛」で、そこから脱するにはどうしたらいいのか、を超論理的に考えた哲学思想です。
この本は、それを真摯に解説してくれる一冊。
はっきりいってこれ読んでも救われない。原始仏教は「自分自身で実践あるのみ」なので、拝めば救われるとは言ってない。
ただただ論理的に、悩みが生まれるのはなぜなのかを論理的に考える一助になるとは思います。
もともと原始仏教を勉強していた私にとっては、新しいことは書いてありませんでしが、これらの考えに触れたことにない人にとっては、入門編として最適な一冊です。
残念な「オス」という生き物
藤田紘一郎 (著)
卵が先か、鶏が先か、っていう議論があるますよね。
これ、オスとメスの話でいえば、即効決着が付きます。答えは♀です。生物の基準は♀であって♂ではないんです。メスだけで繁殖できる生き物は数多くいますが、オスだけで繁殖できる生き物は存在しません。
この本は、そんな生物界では脇役である♂について、その残念すぎる特徴をこれでもかと語ってくれます。
単独で販促できないオスは、メスの気を惹こうと涙ぐましい進化を遂げてきました。オスはメスにモテナイのが当たり前だし、メスより先に死ぬのも当たり前なんです。なんでオスに生まれてきたんだ!というのを悲哀たっぷりおもしろおかしく学べます。
女性のみなさんにはぜひこれを読んでいただくと、自分の隣に居る♂を新しい目線で(たぶん憐れみたっぷりに)見ることができます笑
カメの甲羅はあばら骨 ~人体で表す動物図鑑~
川崎 悟司 (著)
人とは異なった体を持つ様々な動物たち。
その特徴を骨格から分析し、それをなんと人で表現しようという変態的…いやいや独創的な試みの一冊。
タイトルに有る亀の甲羅はあばら骨から発達した、というのは、実はごく最近発見された話で、それまで甲羅が発達過程の化石は発見されておらず、議論が別れていました。
著者の川崎さんの本業はイラストレーターで、さまざまな生物のリアルなイラストを書かれています。その方が描く、リアルなカメ人間やウマ人間は、きもかわいいならぬ、キモリアル…かつて流行ったアフターマンを彷彿させるイラストともに楽しめます笑
悪いヤツほど出世する
ジェフリー・フェファー (著), 村井章子 (翻訳)
出世競争、と揶揄されるように、会社における出世ゲームは、ルールがあるようで無いゲームです。創業者にはサイコパスが多い、とも言われますが、この本では、それを感情的に批判しているものではなく、よくリーダー教育で語られる「リーダーは謙虚であれ、誠実であれ、そして部下への思いやりを持て」というのは、実際の成果を上げていない、優れたリーダーとされる人はみな「虚言や裏切り、自己中心性によって地位を獲得している」ということを様々な実例とデータで指し示しています。
ただ、それだけではなく、そのファクトをベースとして、どうやったら組織を生き抜けるか、あるいは理想の組織を作れるのかを、これまた実例とデータで示してくれます。
今に始まったことではないですが、日本にはリーダーがいない、足りないと言われ、盛んにリーダー教育なるものがたっかい料金で行われていますが、如何にそれがなんの意味もない「幻想」なのかを教えてくれます。
知りたくない現実が書いてあるので、組織に迎合していたい人にとっては、読みたくない一冊。
NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX
リード・ヘイスティングス (著), エリン・メイヤー (著),
土方奈美 (翻訳)
この本は、これまでのビジネス書籍とは、ちょっと違う描かれ方をしています。リード氏は、NETFLIXの創業者ですが、共著者であるエリン・メイヤー氏は、NETFLIXの関係者ではありません。
彼女は、異文化マネジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とするビジネススクールの教授、そして国際社会における異文化マネジメントのプログラムをビジネス・パーソンに提供しているディレクターです。
内容は、この二人が交互に記す形で進みます。
リード氏が、NETFLIXを育てる上での失敗談、その経験に基づいてどのようにNETFLIXのカルチャーを作ってきたかを語り、エリン氏は、リード氏以外のNETFLIX社員にこれらの内容の裏とりインタビューを行っていきます。
インタビューなどの対話ではなく、あくまでNETFLIXの成長の原動力とそれを支えるカルチャーを、主観と客観の双方で記されているのが特徴です。
先にあげた、悪いヤツほど出世する、あるいは不都合な真実、ファスト&スローで学んできた内容、現在の多くの組織における欠陥を、どのようにNETFLIXはクリアしてきたか、あるいはチャレンジしているのかがわかり、個人的にはものすごい学びがありました。
しかし、本著作も書かれているとおり、他の企業がNETFLIXの文化を取り入れることは容易ではなく、表面的に真似てもなんの意味もないだろうということも、同時に理解できます。
一つの理想の形として参考にするのはよいでしょうが、これを目指すのは難しいと考えられます。しかし、多くのヒントをもらった一冊でした。
★今年の再読書籍
今年も何作か再読しましたが、その中での一冊を紹介します。
ほぼ日ブックス#001 個人的なユニクロ主義
随分昔の本になります。刊行は2001年。
この頃は、ユニクロフリースがブームになり、ユニクロが世間に広く認知され始めたころ。あまり当時は柳井さんはマスコミに出ることはなかったので、人柄を知れる貴重な対談内容でした。
いちようビジネス書には分類されますが、特に商売の秘訣みたいなものとかは出てきません。同世代の糸井さんと、楽しく雑談しているだけですが、そこにはマスコミの釣り上げた「完全合理主義経営者」としての柳井さんはいません。
「自分は全然できてなかったけど、ついつい子どもに小言いっちゃう」とか、一人の人間としての柳井さんが描かれています。
しかし、今読むと、今のユニクロにつながる柳井さんの哲学的な考えが垣間見えて非常に面白いです。表面は変化すれども、信念は同じ、なんですね。
最後に、2020年の読書を振り返って。
今年は、コロナで休業した時、AmazonPrimeで映画やアニメを、You Tubeで様々なコンテンツに触れ、生涯で最も多くのコンテンツに触れた一年だったなと思います。
書籍は基本的にKindleで読むのですが、今年はKindle Unlimitedにも加入し、ますます読みたい本が多くなりました。積ん読だけは増やさないようにと頑張って読みましたが、まぁ、去年も書いたんですけど、何冊読んだ、は全然意味がないんです。
何を読んで、どう思ったか。それが大事だし、こうやってアウトプットすることが本当に重要だなと。アウトプットはインプットがないと出来ませんが、一方で、アウトプットのないインプットは何の意味もないよね、とも強く考えるようになりました。
残念ながら、アウトプットのほうが思ったより少なかったのですが(12月20日時点で、note13本しか書いてなかった…)、インプットは倍くらいに増えました。
来年は今年のインプットを、しっかりと咀嚼し、アウトプットを高めていきたいと思います。
以上、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
それじゃ、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
