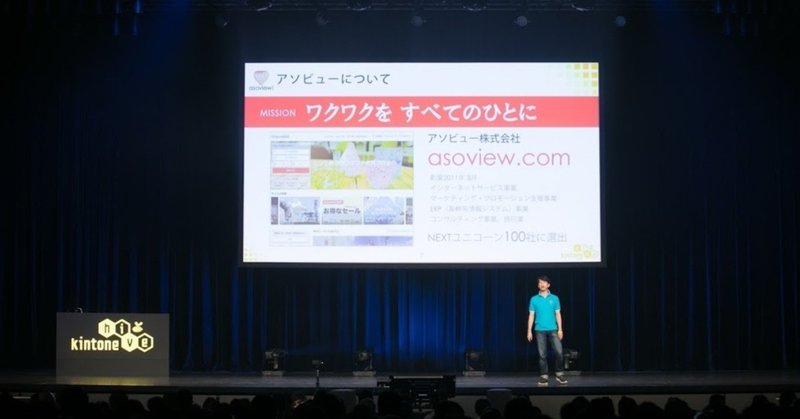
理想と現実のロジカルシンキング4
プロ雑用です。
前回は、ACフレームを用いて、
目的を、工程、役割まで下っていきました。

今回は、さらにその下の各論に近づいてきます。
いよいよ、kintoneアプリに近づいてきました。
歩数は万歩計、自分の重さは体重計、では、仕事は?
何かを成し遂げよう、と思ったら皆さんは何をするでしょうか。
たとえば、ダイエットで考えてみましょう。
ダイエットを決意したあなたは、
その涙ぐましい努力をどのように把握するでしょうか?
体重計に乗ったり、ウェストを測ったりするのではないでしょうか。
また、鏡をみて、自分の体型を確認することもあるでしょう。
いずれにせよ、客観的な何かを参照するはずです。
そのことで、自分の行動が、結果につながっているかを確認するわけです。

では、これを仕事に置き換えるとどうでしょうか。
前回に続いて、以下の実例で考えてみます。

あそびを集めるという目的は、新規開拓の役割を持ちます。
また、魅力を伝えるという目的は、商品造成の役割と記しました。
新規開拓の役割を果たし、目的を達成するには、何が必要でしょう?
例えば、サイト未掲載のパートナーが”どれくらい”いるのか?
また、そのパートナーのあそびのジャンルが、
どれくらいの市場規模なのかという情報も必要かもしれません。
そもそも営業活動をしているわけですから、
受注状況も把握するために、活動量や交渉の進捗状況も必要ですね。

次に、商品造成の役割を考えてみましょう。
当然、製造工程なわけですから、
商品がどれくらい完成したかなどを把握する必要があるでしょう。
つまり、一般的な用語でいえば、生産管理ですね。
また、商品を単に作れば良いというわけではないでしょう。
求められるクオリティがあるのであれば、品質管理が必要かもしれません。

これはどういうことでしょうか?
何を「見たいか」は、その先に何を「得たいか」という問い
ACフレームでは、役割の下に、
その役割を担うために必要なこととして”指標”を置いています。
つまり、指標というのは、
その役割を担うためには、何を見るのか・把握したいのか、ということ。
もっと端的に言うと、
目標をゴールとした時、KGIを何に置くか。
※KGI = Key Goal Indicator/重要目標達成指標
では、実際に新規開拓の役割のKGIはなんでしょうか?
前述した文章から以下のようなKGIが見えてきます。
サイト未掲載のパートナーがどれくらいいるのか?=見込み顧客の数や規模
あそびのジャンルの市場規模はどの程度か?=市場の情報
受注活動量や交渉の進捗状況はどうか?=受注活動の内容
競合掲載商品がアソビューにも掲載されているか?=競合サイトの情報
このように考えていきます。
だいぶ頭の中がこんがらがってきましたか?😂

全体を見渡してみると関係が見えてくる
KGIなどの単語も出てきて、難しそうに感じるでしょうが、
最初にあげたダイエットの話を思い出してください。
ほとんどの人が、無意識でこれと同じことを日々しているはずです。
料理を作る時も、ドライブに行くときも、
わたしたちは、普段の生活で、ごく自然に、
目に見えないものを、何か別のものに置き換えて可視化しています。
可視化することで、自分の置かれている状態が把握することができます。
把握できれば、目的のために何をすべきかが理解できます。
要するにそういうことです。
では、実例のほうに話を戻します。
新規開拓、商品造成と同じように、他の役割でも指標を考えました。
そこに目的と工程も含めて、プロセス順にまとめてみました。

すこし、全体像が見渡せるようになったのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、ACフレームを使ってこうやって考えていくことで、いつでもブレずに考えていくことができる、というわけです。
実在と概念の誤解
そういえば、新規開拓の話の時に、ジャンルの話がでましたね。
そもそもあそびのジャンルってどれくらいあるでしょうか?
調べておく必要がありそうですね。
これは市場情報に関連する話題なので、
”新規開拓”の役割が担うべきでしょうか?
また、パートナーから、掲載中商品の情報を変更依頼が来た場合、
もともと掲載商品(掲載ページの制作)を作ったのは、
商品造成の役割でしたから、製造工程に含まれるでしょうか?
答えを言ってしまうと、どちらの例も、役割に該当しません。
別のふさわしい役割があるでしょう!
なぜでしょうか?
それは、工程と役割がはっきりしているからです。
”購買”工程の”新規開拓”という役割を把握していることで、
ジャンルの数や種類を調べたり把握したりすることが、
役割本来の仕事ではない、と理解できるわけです。
副次的にはありえますし、
実際、同じチームや人が行っていることもあるでしょう。
しかし、それは「分担」の話です。
同時に別々の役割を担っているチームや人は、居て当然です。
間違えていけないのは、
「個人」の話ではない、ということです。
往々にして、個人と、その役割は混同されがちです。
しかし、これらは別々のものです。
いわば、ラベリングのようなものです。

一人で多くの役割を担う人がいる一方で、
一つの機能を多くの人で分担することもあります。
ここを誤解すると、この後の話が理解できなくなってくるので、
しっかり意識して、個人とは別の、概念として捉えてください。
さて、長くなりましたので、今回はここまで。
次回は、ようやくアプリの話になります。
(あと一回で終わるだろうか…)
次回「武器を作ろう/アプリを見つめる」
それじゃ、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
