
2023年度上半期読書録 1-10冊
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』(1~5)
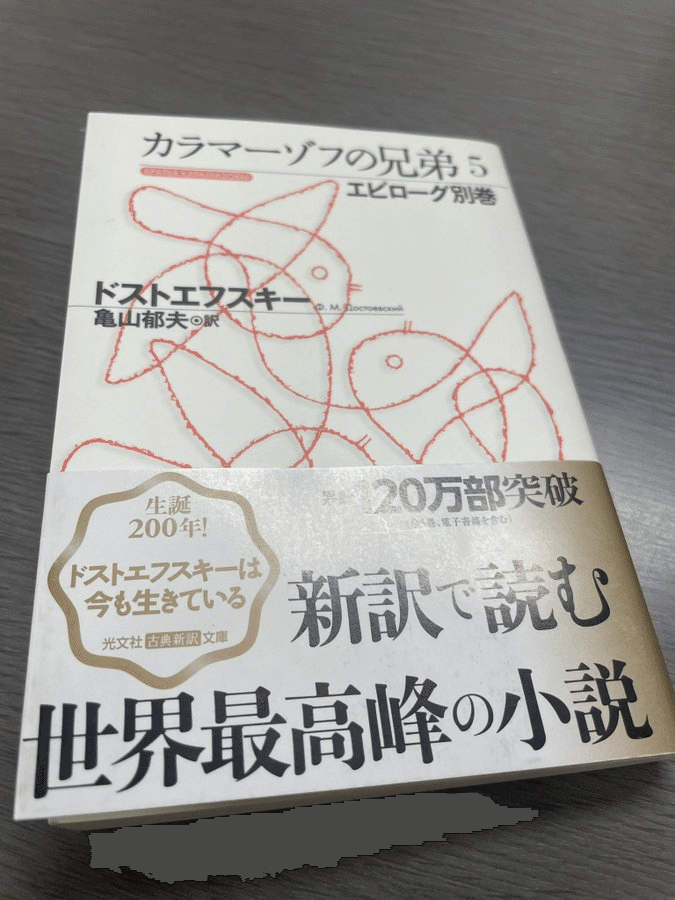
中学1年生の時、家にあったこの小説を読もうとした。背伸びをしたい年頃である。当然この大作を読み切れるはずもなく、第1部の僧庵でのドタバタくらいで頓挫してしまった。
それを社会人になって引っ張り出してなぜ読む気になったのかは覚えていない。フロイトのせいにしておこう。13年前の苦い経験から、外堀を周到に埋めることにした。
まず僕が入門書の入門書としてよく読む100分de名著に『カラマーゾフの兄弟』の回があるため、テキストを購入して読む。全体で4部構成になっており、テキストの著者が「自伝層ー物語層ー歴史層ー象徴層」という構造を見出していることが分かり、それぞれの層がどのように小説に現れているかが簡潔に説明してある。
そしてこのテキストの著者である亀山郁夫、光文社古典新訳文庫の『カラマーゾフの兄弟』の訳者なのである。文庫版の各部の解説はその部の総括になっており、まず解説を読んでから本文に進むと大変なじみがよかった。
このようにして、遅読が悩みの僕でも、この大作を読み切ることができた(「大審問官」やゾシマ長老の伝記、イッポリートの論告など心が折れそうになる場所は何か所もあったが)。少しだけ読書に対して自信がついた気もする。
三浦綾子『塩狩峠』

いつだったか、高校生のころ、夜にAMラジオの乾いた音を聞いていると、小説の朗読が流れてきた。この『塩狩峠』のクライマックスである。
勉強をしながら耳に入れていたので細かい内容までは頭に入っていなかったが、刻刻と場の緊張が高まるのは感じていた。
ある時、撥ねるバネのように声色の緊張が外れたのでつい聞き入ると、どうやら暴走した列車を止めるのに主人公が線路に飛び込み、血と肉をもってブレーキとし、乗客を救ったらしい。「いい話」にしては刺激が強いなと思った。どうやら北海道での実話がもとになっているようだ。
長らくこの小説の存在を忘れていた。札幌に行く用事があったのでふらっと書店に入るとこれが目に入り、あの緊張と弛緩が脳裏に蘇る。
つい買ってしまった。旅先の常である。
主人公は熱心なキリスト教信者であり、信仰に生き、信仰に死んだのであろう。僕はそれを感得するにはまだ若い。
全体を通して穏やかに、淡々としており、クライマックスでさえ、つむじ風に舞い上がった木の葉が推力を失って舞い落ちる程度に思えた。
國方栄二 訳『ヒポクラテス医学論集』
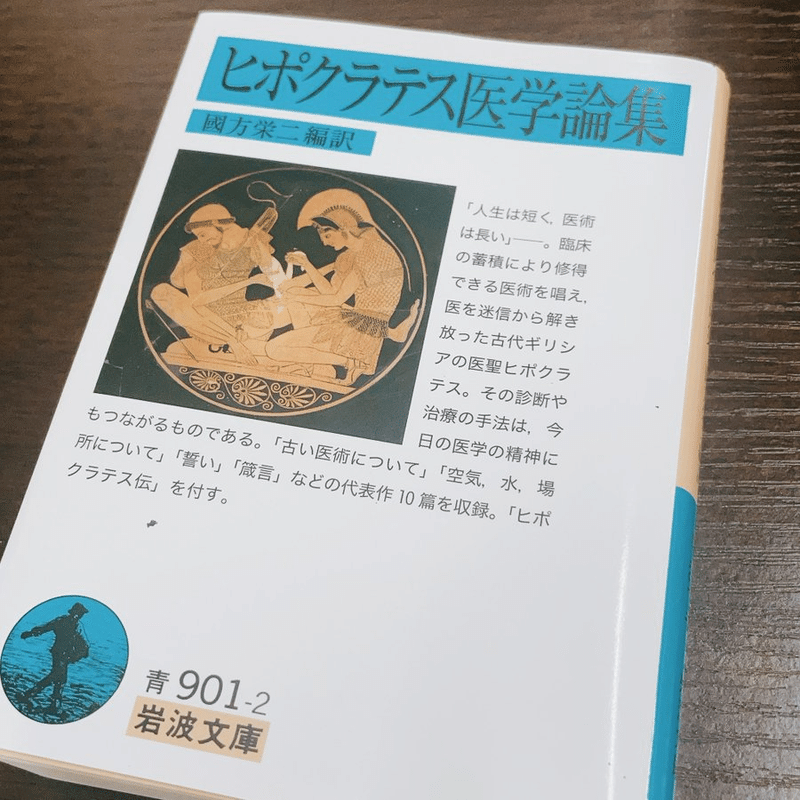
医聖・ヒポクラテスの論文集。医学教育で「ヒポクラテスの誓い」は耳にタコができるほど聞いたのに、一次情報に当たらないのも医学教育に反するわけである。
これを読むに、ヒポクラテスは確かに体液説に基づいていたことや、風向・温湿度・日照・河川湖沼との関係などから風土論的に疾病を考えていたこと、また食餌療法を重視していたことが読み取れる。
さて、医学教育者たちが尊崇している「ヒポクラテスの誓い」を見てみよう。
医師の心得、口述したもの、その他あらゆる教えを、私の息子たち、私の師の息子たち、さらには医師の法にしたがって契約を交わし誓いを立てた門下の者たちに伝え、ほかのいかなるものにも漏らすことをしない。
つまり、医学は門外不出であると。多職種連携やインフォームド・コンセントの時代に真っ向から背く教えである。
たとえ懇願されても、致死の薬をなにびとにもあたえず、このような助言で人を導くことをしない。同様に、婦人に堕胎具を供することもしない。
最も有名な一節のひとつである。しかしこの節には注釈がついている。注釈には以下のようにある。
『誓い』の中で最もよく知られたこの二つの文言は、「ヒポクラテス全集」のほかの箇所の記述との不一致が指摘されており、そのためにこの『誓い』はヒポクラテスのものではない、という主張の根拠にもなっている。
この文言はヒポクラテスのものでない可能性があるというのである。同書の解説によると、多くの研究者は『誓い』そのものがヒポクラテスによるものではないと考えているようだ。
われわれは何を学ばされてきたのだろうか。
ゴーゴリ『鼻/外套/査察官』
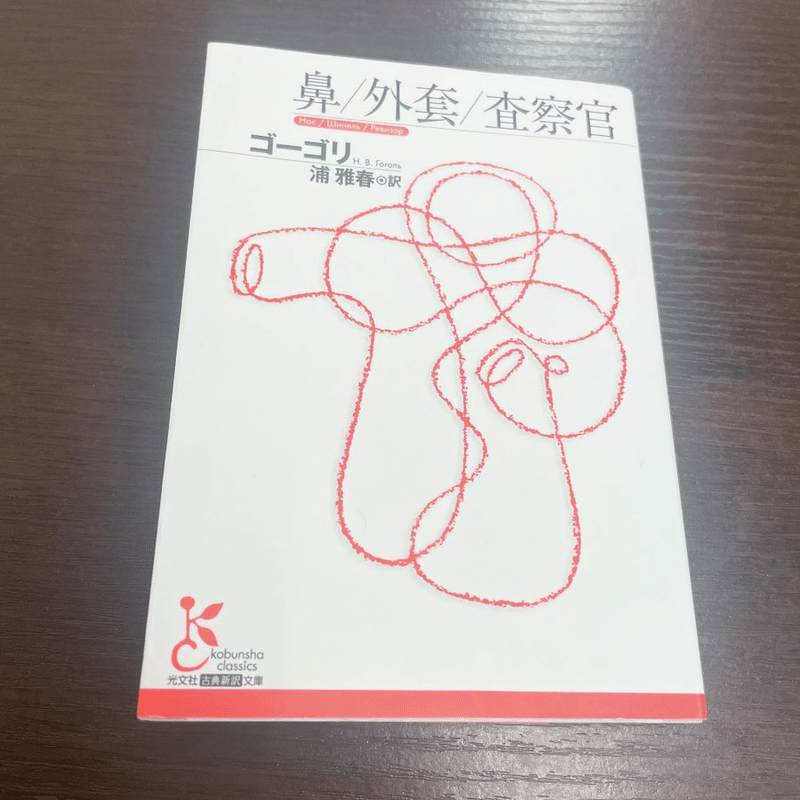
ゴーゴリは、先述のドストエフスキーを読んでいる際に頻回に言及されており、ロシアの気持ちが冷めやらぬうちに、と読んでおいた。
最初から「鼻がなくなってどこかにいった、探そう」という奇天烈な設定で始まる。可笑しいのか可笑しくないのか今一つわからないひずみの中で終わる。
古典を現代に再構築するという意味で、このゴーゴリは、ロシア文学にもかかわらず、江戸っ子らしいべらんめえ口調で訳されていた。庶民階級のことばというものを我々日本人の視点から解釈したものであろうが、光文社古典新訳文庫は、そういう挑戦的な訳を許容できる文庫だと思う。
何より重厚な作品を岩波の重厚な訳で読むと僕のような人間は力尽きてしまう。光文社にお世話になりっぱなしである。
オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』
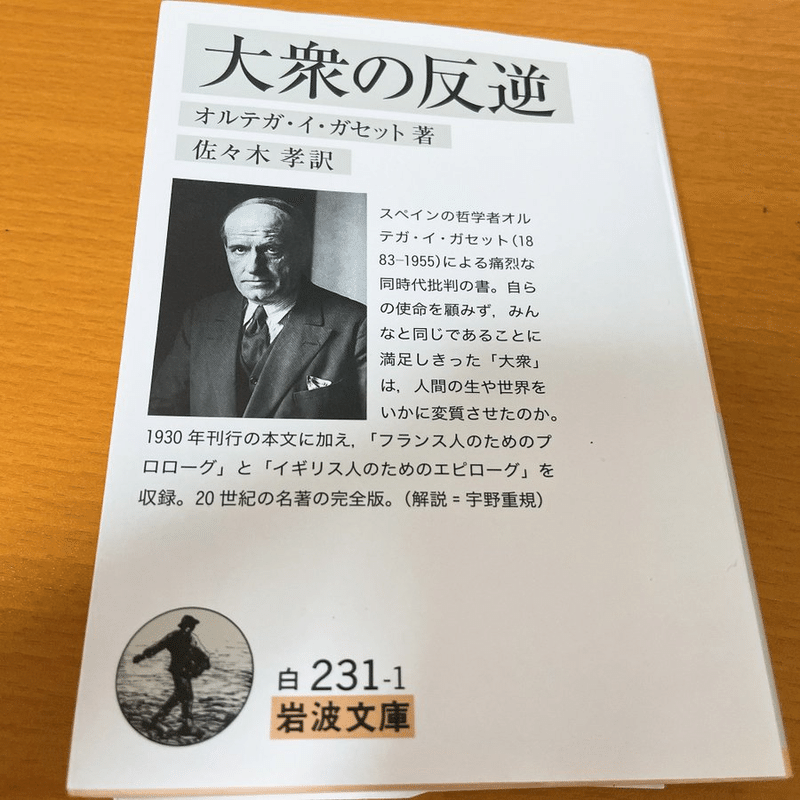
尊敬する先輩が東大大学院卒業式で総代としての式辞で引用されていて知った本。
僕がこの本を買ったのは、197ページから展開されている科学と科学者と専門主義批判を読むためといっても過言ではない。
オルテガは、科学者をはじめとして医者・技術者といった集団こそが現代の大衆の代表であり、近代の野蛮人であると痛烈に批判している。
科学は宇宙全体の真理を突き止めるために進歩しているはずにも関わらず、分野はますます細分化していき、科学に従事するひともそれに従っていよいよ専門化していった。
その結果、「ごくごく狭い専門分野については詳しいが他は何も知らず、そのくせ他の分野に知ったような顔で首を突っ込み論を張る」専門家がたくさん輩出されるという結果になる。我々の周りでよく生じている現象である。
彼はある特定の科学しか知らない。しかもその科学の中でも、彼はその熱心に研究している極小部分しか知らない人間なのだ。ついには、特別に開拓した狭い風景の外にあることについては何も知らないことを、一つの美徳であると宣言するまでになり、総合的な知的好奇心を偉そうにディレッタンティズムと呼ぶのである。
専門化だけが知ではない。全体を志向した知をやっていかなければならないと刃を突き付ける書籍だった。
松本卓也『症例でわかる精神病理学』
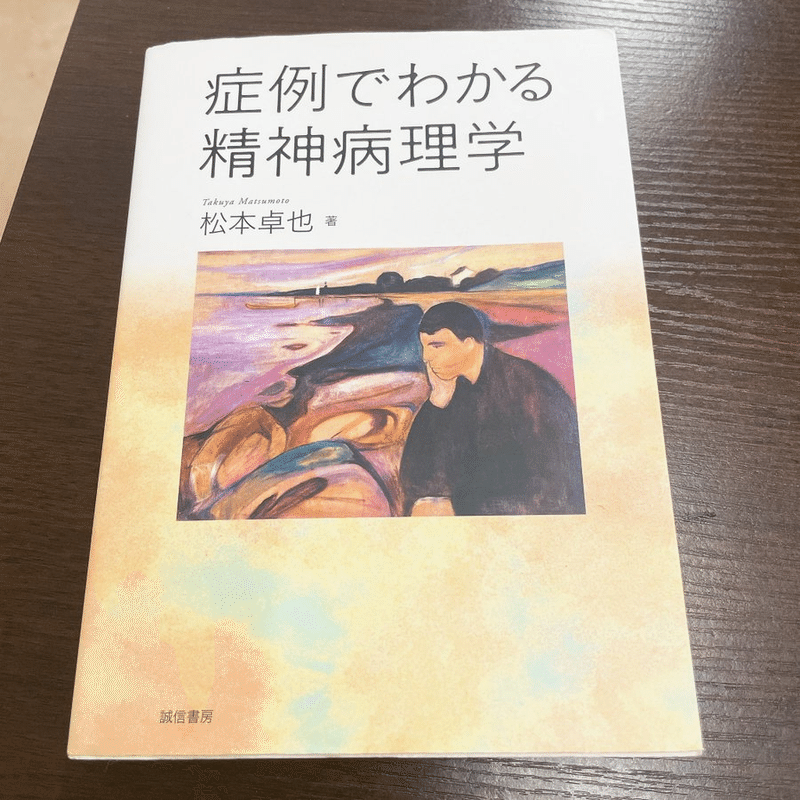
いやしくも「精神病理学」という医学の一分野の、最近出版された書籍にも関わらず、日本語に併記されているのが英語よりドイツ語の方が多いのではないか、という他の診療科ではあまりなさそうな感じの本。
精神病理学の入門的知識を系統立てて解説する、入門書・教科書。
「症例でわかる」とある通り、症例の記載が豊富にあり、症状を表す四字熟語が、実際にどのような言葉で語られ、どのような文脈で発現するのかがよくわかる。
「彼らが何をみているのか」に興味がある限り、僕はこの分野に引力を感じ続けるのだと思う。僕も変なものが視えたことがあるので。
鈴木健『なめらかな社会とその敵』

ほんとうは、カール・ポパーの『開かれた社会とその敵』という全体主義批判の書から読まないといけないのだが、好奇心と怠惰に負けてこちらを読んだ。
300年後の社会の基盤システムを提案する挑戦的な論考である。
貨幣と商品との取引によって、それまでその商品に生産者・中間業者として携わった人にも価値が減衰しながら伝播していく貨幣システム。
持ち票を分散可能にするとともに、投票の委任も可能にする投票システム。
これらのシステムは、局所的に既存のシステムと共存可能であり、なじみがよさそうなシチュエーションでは今後そうなっていくかもしれない。
全体的に進歩主義の香りを感じた。300年後に知的な人類が存在していることを自明の前提にしている点など。第4次世界大戦は石と棒で戦われるというのに。
ソポクレス『オイディプス王』
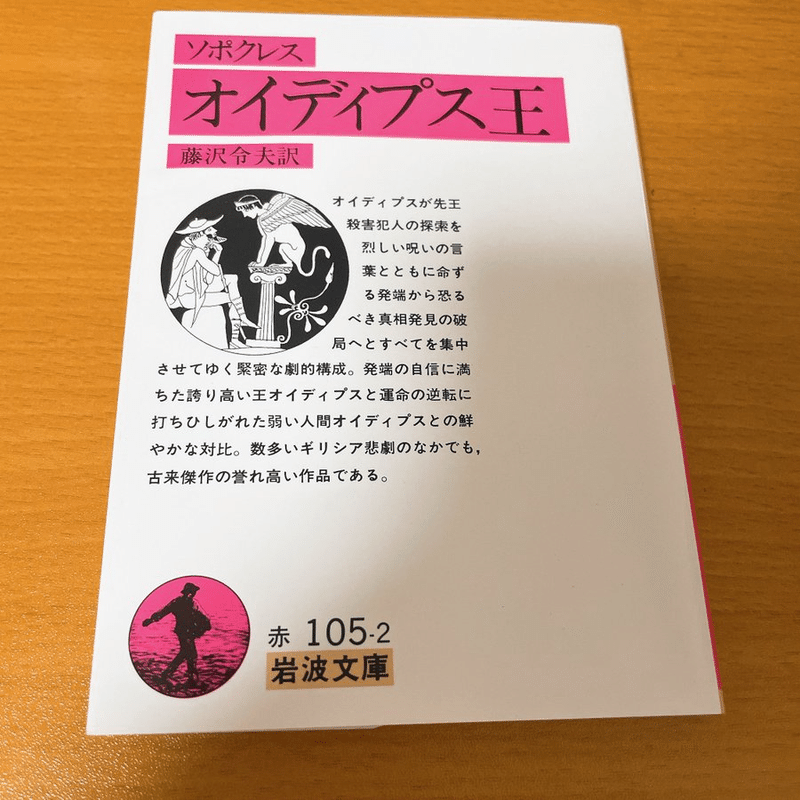
「無意識の発見者」フロイトは、ギリシャ悲劇が好きだったという。彼の精神分析の中核理論の一つである「エディプスコンプレックス」がこの悲劇から命名されたことは周知の事実である。
フロイトは精神を分析するにあたり性的な側面を強調したため疎まれることも多かったが、エディプスコンプレックスはより抽象化された形でラカンに引き継がれ、ユングはエレクトラコンプレックスを提唱し、ドゥルーズ=ガタリは『アンチ・オイディプス』という題名そのままの主張の書籍を書いている。
表紙絵は、旅人に難問を投げかけては答えられないものを殺す魔のスフィンクスと、難問に正答することで退治する旅人オイディプスの絵である。
スフィンクスを斃して王として迎え入れられたオイディプスは何者かに殺された国王の元妃を妻として十数年ほど国を治めていた。しかし疫病が蔓延し、作物は枯れ、国は乱れる。
アポロンの神託によると、前の王を殺した者が生きてこの国にいるのが災いのもとであるという。早速捜査を命じたが10年以上も前のことでありうまくいかない。
「予言が必ず当たる」という老人に聞くと、「オイディプス王が犯人である」という。王は激怒、老人を紹介した妃の弟ともけんかし、処刑しようとする。
しかし王が死んだ状況を妃から聞くと、いやな予感が走る。状況証拠が集まる。緊張が高まっていく。焦る王。そのうちに「証人」の羊飼いが現れる。
オイディプス王は前王と前妃が「実子に殺される」という神託をもとに山に捨てられた子供であり、偶然羊飼いが拾って隣国の王のもとで育てられた。
隣国で「お前は実父を殺す」と神託があり、実父と思っていた隣国の王から離れるために旅人となった。その道中で偶然鉢合わせた前王の車とけんかになり、ついに殺してしまった。
この顛末を悟るにいたり、妻であり母である女性は首を吊る。オイディプスは妻=母の上着の留め金を外し、自分の両眼に突き刺してこう叫ぶ。
もはやお前たちは、この身にふりかかってきた数々の禍も、わしがみずから犯してきたもろもろの罪業も、見てくれるな!いまよりのち、お前たちは暗闇の中にあれ!目にしてはならぬ人を見、知りたいとねがっていた人を見わけることのできなかったお前たちは、もう誰の姿もみてはならぬ!
盲目の王は追放され、幕を閉じる。
エディプスコンプレックスと、『オイディプス王』、父と母をめぐる葛藤というだけの共通点であり、意外と共通項がないように思うのは僕だけだろうか。
梅原猛 全訳注『歎異抄』
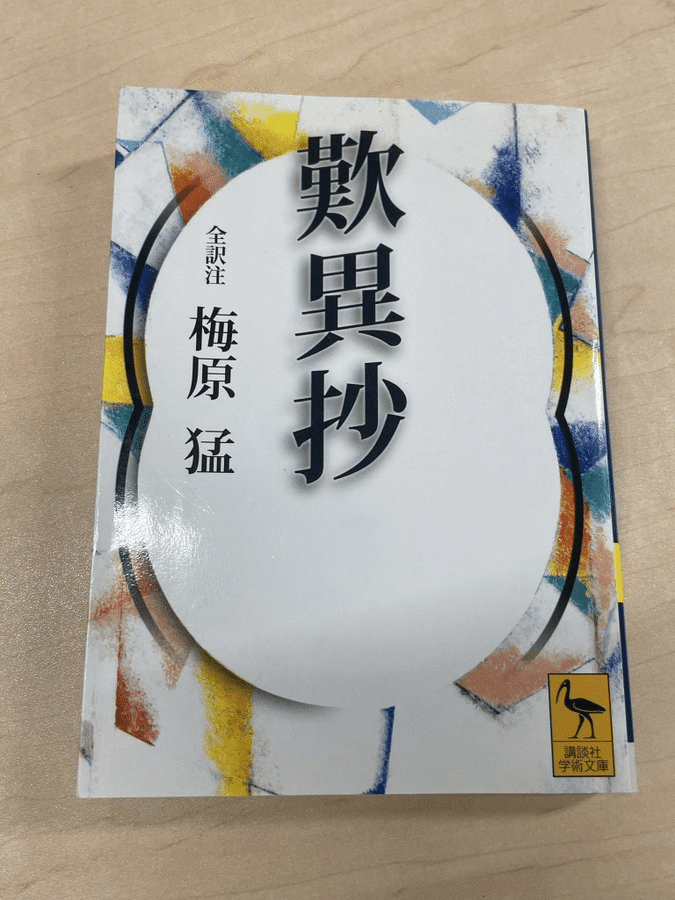
言わずとしれた浄土真宗の聖典の一つ。
親鸞の弟子であった唯円が、親鸞の死後はびこるようになってきた「異」説を「歎」き、親鸞の語りと、唯円の異説批判を後世に遺すために綴ったものである。
親鸞本人が著した『教行信証』は経典の引用が多いようで、むしろ使徒言行録のような『歎異抄』のほうが親鸞のナマの言葉を伝えるものとして人口に膾炙しているのはうなずける。
いくつか引用しよう。
善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを、世のひとつねにいはく、悪人なを往生す、いかにいはんや善人をや。
浄土真宗関係の言葉で間違いなく最も有名な「悪人正機」の部分である。
悪人正機説は親鸞の独自思想と思われがちだが、法然からその思想はあり、親鸞はそれを重心に持ってきたのだ、という説もあるようだ。
しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、念仏にまさるべき善なきゆへに。悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆへにと云々。
キリスト教の香りがほのかに漂ってくる二文目である。
実際、明治期の廃仏毀釈後の仏教低迷期に活躍した浄土真宗本願寺派の島地黙雷は西洋を視察し、西洋文明の根底にはキリスト教があり、わが日本においてそれに相当しうるものは一神教に近い真宗である、と主張したそうである。(出典:放送大学教材 末木文美士・頼住光子『日本仏教を捉え直す』)
たとひ法然聖人にすかされまひらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずさふらう。
(中略)
いづれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし。
親鸞は、愚かであることを恥じることがなかった。「難しいことは南都北嶺に任せて、俺たち愚かな凡夫は念仏で阿弥陀さまにすがろうぜ」という潔い認め方である。親鸞は比叡山で20年修行しているので仏教経典に関して愚かであるはずがないのに。
現代における反・知性主義であろうか。どうも彼らの気持ちは違うような気もする。親鸞は(少なくとも表面上は)知性としての南都北嶺も謙虚でありつつ、かつ救い主・阿弥陀に対しても謙虚であった。僻みではない純粋なへりくだりであるところが、彼を人間らしい聖人たらしめているのだろう。
『歎異抄』の語り口は、もはや地元の和尚さんである。
荒牧典俊ほか 全現代語訳『スッタニパータ [釈尊のことば]』
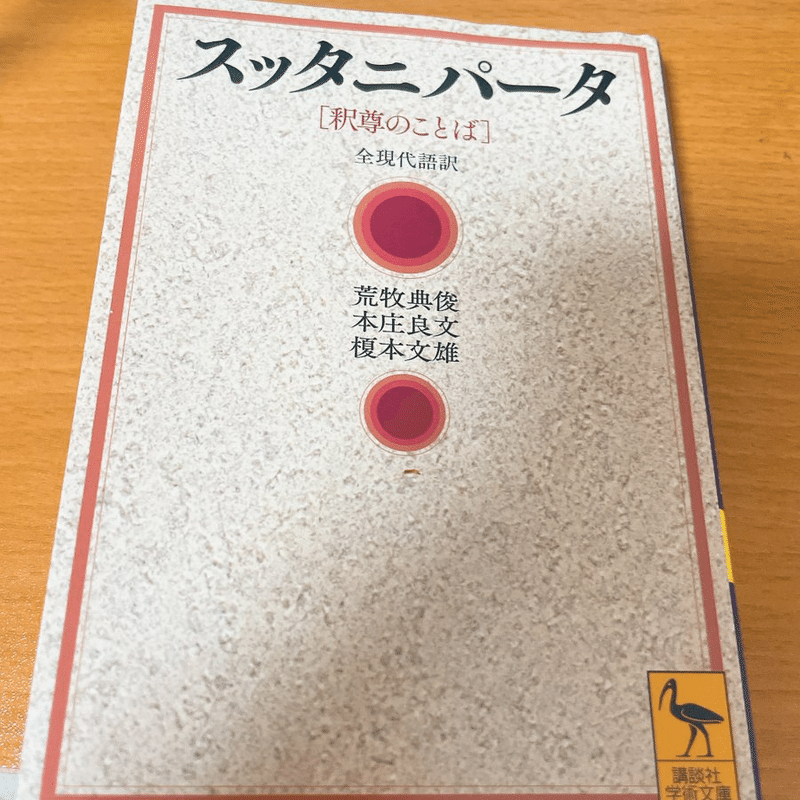
2400年前の釈尊のことば。南伝系のパーリ語の経典からの翻訳とのこと。
これを読むと、日本仏教はそもそも中国仏教のフィルターを通しており、インドの原始仏教とはかなり思想が変わっていることがわかる。
当然だが、釈尊の語りに「仏」はでてこない。大日如来や阿弥陀如来などは、真理としての釈尊の一つの現れであるからである。
釈尊は、沈黙の聖者として、出家しながら修行・遊行する人であった。
今日日本でみられる仏教を外側から見ているだけではなかなかわからなかったが、仏教は「解脱」と「真理」という抽象を求める修行の教団であった。
真理は拈華微笑という言葉のとおり、言葉では伝わらず、修行をもって体得するしかなかったのだろう。
禅のひと・道元は、釈尊による正伝の正法を求めていたという。しかし彼は中国というフィルターを通してしか触れることができなかった。
インドの原始仏典など、のどから手が出るほど欲しかったのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
