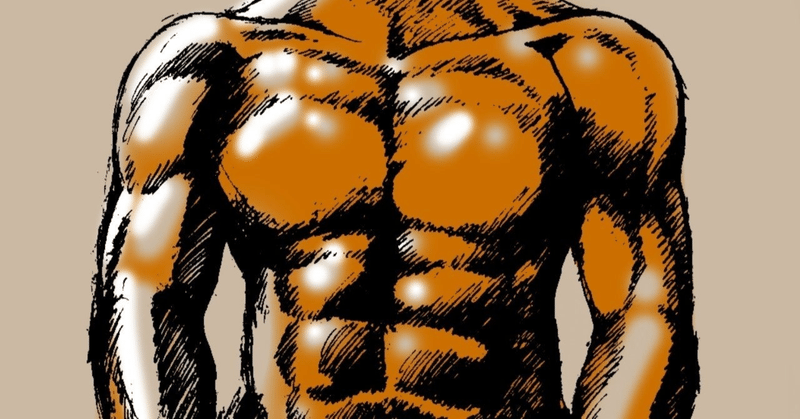
忍者になってもらいたいんだけど
「拳法部のイキのいい2人に、忍者になってもらいたいんだけど」
突然の指名スカウトだったが、俺とシオリ(男)は前のめりに二つ返事で忍者になることを決定した。
そのオファーがあったのは高校3年の8月末、いわゆるインターハイも終わり(俺のやっていた部は加盟というか認可?されてなかったのでインターハイではなくただの全国大会だったが)秋のエキシビジョン大会を持って引退しようかというクールダウン的心の安定期間に入っていた時だった。
全国大会でまあまあいい成績を収めた俺とシオリは、高校1年からずっとパートナーとして組み手演舞をやってきいていた。背格好も175cm前後と同じぐらいで、二人ともキレもスピードもあるので結構見栄えのする組み手だったのだと思う。が、競技人口自体がとても少ないので野球やサッカー等で好成績を残す者たちに比べれば特に自慢できるものでもないのかなと思う。
シオリは若干爬虫類に似た撫で肩のアニメ好きで、ヒーローシンドロームというか「役」になり切れる没入得意系の人間だ。俺は逆にそういうのが苦手だったのでリスペクトがあった。
大会での入賞記事は地元の新聞にも掲載されたし市から表彰されたりもしていたので、その分野に関わる小さい文化圏の中ではそこそこ知れ渡っていたのかもしれない。
オファーをしてきたのはセキハタという小柄で中肉な歳の頃38くらいに見える男で、地元の電器店の社員らしかった。ざんぎり頭なのはブルースリーに憧れを持ってプライドを持って「そうなっている」のかもしれない。
それまで面識も繋がりも何も無いその男がある日道場にやってきて
「拳法部のイキのいい2人に、忍者になってもらいたいんだけど」
と鬼監督に申し出た。
イキのいいといえば1も2もなく俺とシオリだろう、この中ならば。
2年生なんかは話にならないし何なら再来年くらいには鬼監督と渡り合える実力になろうと誰もが思うほど肉体も気力も充実していた頃だ。若年期にありがちな根拠なき自信。
「ほう、忍者とはこれまた趣のあることで。男よ、その詳細を申されてみよ」
鬼監督が問う。
いやあなた上忍だったんですか。まあ確かに似たようなものかもしれない。俺らはいつも下忍のような働きで首=『シルシ』を上げてくるだけだ。
「今度の秋祭りで、山車の先頭で舞う忍者をやってもらいたいんです」
秋祭りは市内の各グループが山車で市内を練り歩く、多分収穫祭といった意味合いなのだろう。山車には大太鼓小太鼓笛やらが満載となり、行列が前後について掛け声とともに順路を回る。ねぶた・ねぷたほどでは無いが中々賑やかで荘厳である。
「いいんじゃないか、来年に向けて部の宣伝にもなるだろう。どうだ。」
俺とシオリは隣町の出であり、その祭りには客として数回来ていただけで運行等々の詳細はよく分かってはいなかったが「やります」と答える選択肢しか無かった。
次の日から芝居作りは始まった。
芝居は10分ほどの構成で簡単にセキハタが「赤い忍者と黒い忍者が戦う、たまにセキハタが乱入する」という小学生が考えたようなシナリオを設定したが、それだけでは30秒ほどで終わってしまうので俺とシオリで肉付けをしていく。
二人とも中学生時代は体操部だったのでバク転とか宙返りを交えながら、道を縦横無尽に駆け巡り「型」をいくつかやりながら軽いスパーリング的なものも挟み、時には懐から万国旗を出すといった憎い演出も取り入れた。
セキハタを交えた練習は、彼の勤め先の電気屋の奥の方にある倉庫で土曜の午後に行われた。
練習を順調に重ねていく日々だが、休憩中に数度「キミらは相当鍛えてるんだね、いいカラダだなあ〜」とうっとりした目で胸やら尻やらを摩られて気持ち悪かったがオジサンだからしょうがないのかと我慢していた。
現役当時の我々の突き蹴りは高校生とはいえ非常に重いものであり、セキハタに当てる(実際は軽めの当て止めという難しい手加減具合)と
「いいねえー、いいパンチだよぉ!」と目を見開き完全にキマった顔になるのがさらにヌメっとした気持ち悪さを覚えた。こいつ大丈夫なのか。
いよいよ最終練習が終わり、さて本番頑張ろうねと少しの打ち合わせがてらでしばしの休憩中、俺は急に便意を催して倉庫内のトイレを借りた。さっき飲んだ冷たいコーヒーが効いたのか、少し下し気味で長めのトイレタイムになってしまったかもしれない。
「ごめんごめん、ちょっと下したわー」とトイレのドアを開けたときシオリとセキハタがバババッと離れた。
シオリは椅子に座り少し上気した顔をしているし、セキハタは少し離れたところに慌てた様子で立ちこちらをみている。
なんだこれは。
「おおう、シリウス君大丈夫か。まあ今日はこれで終わりにしよう。」
二人で電器店を後にしつつ、自転車で40分の帰路につく。
「なあ」
勇気をだしてシオリに聞く。
「んん?」
「さっき、キスしてねがった?」
「…いや」
「なんか急いで離れだがらさ」
「ああ、ちょっと皮膚が赤くなったがら見でもらってだんだわ」
別に誰とどうなろうが構わないが、あのザンギリとどうにかなるんか?
彼女こそいなかったが、かれこれ知り合って6年のあいだ男色趣味の片鱗も見せたことが無かったので俺はすっかり混乱して色々な未来を想像して不安になった。
かくして本番の山車運行は無事終わり(9月とはいえまだまだ暑い中6時間に渡り飛び回ってさすがに瀕死状態だったが)18時ごろ晴れて解放となった。
「よっしゃ屋台でかき氷でも食って帰るか」
と俺はシオリに促すが、
「いや、ワはちょっと風呂に行ってから帰るから」
「風呂?風呂って銭湯?」
「んだ」
「一人で行ぐの?」
「ん、んん。セキハタさんも行くっていうから。家の風呂壊れでらし、今」
「あー、ああ。んだのが。へば、先に帰るわ」
超絶な運動の後でテリッテリに体が火照っているので屋台で氷水に入ったカルピスジュースを買い、カッチカチのタコヤキを買いしばし道端の花壇に腰掛けボーッとしてクールダウンをしていた時、遠くにセキハタとシオリの姿が見えた。
当時既に視力が落ちていたので定かではないが、手を繋いでいるように見える。
俺は一息にカルピスを飲み干してたこ焼きを袋にしまい、急いで自転車にのり夢中でひたすらにペダルを踏み家へと向かった。
正体不明の恐怖のような感情が湧き、向かい風のせいか目から少し涙がちょちょぎれ何度も拭いた。
2年後、電器店は不採算のためか閉店しセキハタは2つ隣の町へ引っ越したと風の噂に聞いた。
シオリは綺麗な嫁さんを見つけて結婚し、2児の父となり平和に暮らしていて311大震災の津波が自宅50m前まで来るなどしたが元気に生き延びている。
当時の真相は、もう聞かないことにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
