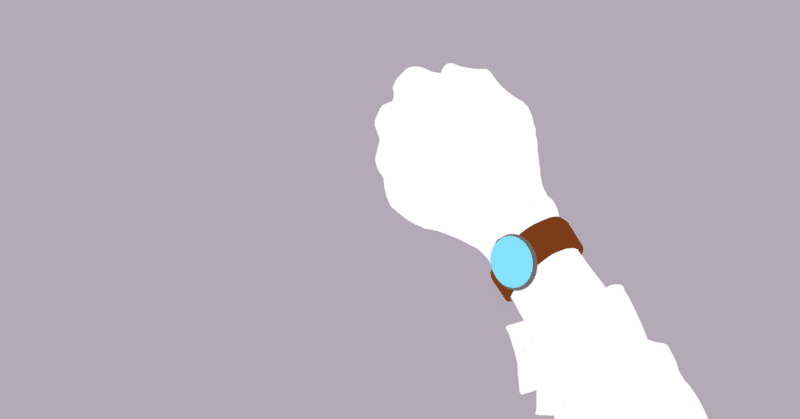
時間・自由・芸術
丸谷才一の『たった一人の反乱』(1972)を読んだ。
それなりに面白く読んだが、正直言って、この小説にはさほど強い感銘を受けなかった。
なによりも主人公である「ぼく」にほとんど共感することができなかった。
それはそうだ。
主人公の馬淵英介は、通産省のエリート官僚出身で、民間の電機会社の重役に天下りし、妻の病死後一年も経たずに若い美人モデルと再婚する人物である。
やっかみ半分と言われればそのとおりだけれど、そんな鼻持ちならない人間に感情移入などできるわけがない。
おそらく、あえてそのような人物を主人公に据え、なおかつ一人称の語りを採用したところに丸谷の文学的意図があったのであろうし、事実、講談社文芸文庫版の解説を執筆した三浦雅士氏はその文学的意図を見事に読みとり、巧みに解き明かしている(ように思う)。
三浦氏の解説を読んで大いに感心したのだけれど、評論家でもなんでもないわたしが、この作品自体について何かを論じたいとは思わない。
わたしがこの小説で最も興味深かったのは、ある有力雑誌が主催する写真賞の表彰式が描かれる場面である。
というのも、その表彰式で写真賞の審査委員の一人であり、主人公の舅(妻の父)である元大学教授の野々宮が行った祝辞(というよりは講義)が、型破りでありながら、知的刺激に満ち、非常に示唆に富むものであったからだ。
*
野々宮は、写真賞の副賞として贈られる腕時計を題材に、市民社会において「時計」というものが持つ本来的な意義・役割について、ヤクザ映画や都市の時計塔を引き合いに出しながら雄弁に物語る。
つまるところ、「実用品としての時計」とは、市民が労働時間を切り売りし、報酬を得て生計を立てるための仕掛けであり、これを逆に言えば、「市民社会とはすなわち時計によって運営される社会」であると論じるのだ。
野々宮によれば、腕時計は「市民であることの象徴」であると同時に「市民社会の課す手錠」である。映画の中でヤクザが腕時計を身につけていないのは、市民社会の秩序の外にいる「彼らの自由のしるしにほかならない」というわけだ。
さらに野々宮は、ジャン・ジャック・ルソー以来の伝統である市民的人間と自然的人間との相克というテーマに論をすすめ、常に市民社会の秩序から脱出しようとする芸術家と近代的市民とはそもそも相反・対立するものであり、極論すれば「芸術は広場の時計塔を破壊する兇悪な行為」であるとまで断言する。
「……御存知の方も多いと思いますが、ニューヨーク近代美術館に『記憶の持続』というダリの絵があります。このシュルレアリスムの傑作では、懐中時計がぐにゃぐにゃ折れ曲り垂れ下っているのでありまして、市民社会に生きながらそれに悪意を抱き、芸術というたった一人の反乱を企てつづけている者、おこないつづけている者、すなわち芸術家の暗い夢を、あれほど鮮やかに示してくれるものはほかにない。わたしは以前からそう思っているのであります。」
この小説のタイトルは、まさにこの元大学教授の演説に由来するものであったようだ。
*
ところで、この長たらしい祝辞の場面を読みながらわたしが面白いと思ったのは、丸谷がここで「時間」と「自由」との関係を直接的に論じているように感じたからだ。
きわめて単純な思い付きのようでお恥ずかしいくらいであるが、人間にとって「自由」の多寡とは、時計のような道具に拘束されない「時間」をいかに多く持つかで測ることができる、そんな風に言えるのではないか、と思ったのだ。
自由な人間とは、より多くの時間をもっている人間である。
人間というものは(心身ともに健康であるという前提つきではあるが)誰もがより長生きしたいと思うものだ。
手塚治虫の有名な『火の鳥』の登場人物たちは、不老不死を得ようとして「火の鳥」の生き血を求める。もちろん、永遠の寿命など手に入れてしまったら結局は時間を持て余さざるを得ないのだが、持て余さない範囲で可能な限り長い健康寿命を享受したいと思う。それが人情だろう。
人間にとっての自由の総量は、与えられた(残された)時間の長さで測ることができる。
だから、人は誰もが日々自由を失いつつあるのだ、と言うといささかペシミスティックすぎるだろうか?
「時間ばかりあったって金がなければ自由とは言えない」なんて野暮な声が聞こえてきそうだけれど、この際金の問題は横に置いておきたい。(それに与えられた時間の絶対量が大きければ、それだけ多くの時間を金を得るために費やすことができるわけだし。)
くどいけれど、人間にとっての自由の総量は、可処分所得ならぬ可処分時間の長さで測ることができる。
*
しかし、そこでハタと考える。
時間というものは万人にとって平等だろうか? 一時間の価値は誰にとっても等しく一時間だろうか?
実はそうではない。
わたしは子どもの頃から自他ともに認める愚図で、のろまである。不器用で要領が悪く、なにをするのにも人より時間がかかる。
例えば体育の授業の際の着替え。高校一年のとき、更衣室で一緒に着替えていたクラスメートに「愚図は嫌いだな」と言われたことを未だに覚えている。
現在の話なら、例えばネット検索で利用する料理のレシピ。「調理時間30分」とされていたら、慣れたメニューでも最低一時間、たいてい一時間半くらいはかかる。
考えてみれば、時間の価値が人間の能力によって異なるのは当然のことで、それは労働の対価としての「時給」が求められるスキルによって大きく異なることからも自明なことだ。
さらに言えば(つい先ほど横に置いたが)人間の財力だって時間の価値を左右する。
自分で働かずとも、他人の労働によって生み出された付加価値を購入して必要を満たすことができれば、つまり他人の時間を買い取ることができれば、それだけ自分の時間を節約できる。
結局(なにをいまさらと思われるかもしれないが)ある人間にとっての時間の価値は、彼の持つ能力や財力によって大きく変動する。
*
と、ここまで書いて、またしてもハタと考える。
「人間にとっての時間の価値は、能力や財力によって大きく変動する」
そうした考え自体が、すでに市民社会の秩序・価値観に毒されたものなのではないだろうか?
労働に費やす時間よりも、娯楽や趣味や休息に費やす時間の方が自由で貴重な時間である、と言いきれるだろうか?
もちろん、休息に費やす時間は貴重であるが、そもそも休息の意義や価値は労働あってのものだろうし。
ここで言いたいのは「人間にとって大事なものは労働だ」などということでは決してない。
自分及び他者の労働時間を効率的に管理・統制することが、必ずしも自由な時間を生きることであるとは限らない、ということだ。
時間とは「自由と引き換えに提供する労働の量」の指標であり、時計とはその量を測るための仕掛けであり、「市民社会とは時計によって運営される社会」である。
なるほどたしかにそうかもしれない。
しかし、そうした市民社会の秩序・価値観に縛られた時間の概念とは別の「時間」というものがあるのではないだろうか。
市民社会の日常にとらわれない「時間」を生きること、それこそが「自由」ではないだろうか。
そうした市民社会とは別の次元の「時間」を人間が豊かに生きるための入口となるのが、例えば芸術なのだ、そんな風に言えないだろうか。
野々宮元教授は「芸術とは市民社会の秩序を破壊しようとする行為だ」と言う。
なるほど、そのような側面もあるかもしれない。
だが、市民社会の秩序のもとに営まれる時間と併存しつつ、それとは異なる時空で流れる時間を紡ぎだそうとする行為も、芸術の一側面であるように思う。
豊かな想像力によって日常の時間を超越し、異次元の時間の流れに身を委ねる経験を与えてくれる、それもまた芸術が持つかけがえのない可能性なのだ。
そして、芸術が生みだすそのような時間こそが、きっと、能力や財力にかかわらず万人に平等に与えられる時間なのだ、と思う。
※タイトル画像は hisuiiroさんからお借りしました。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

