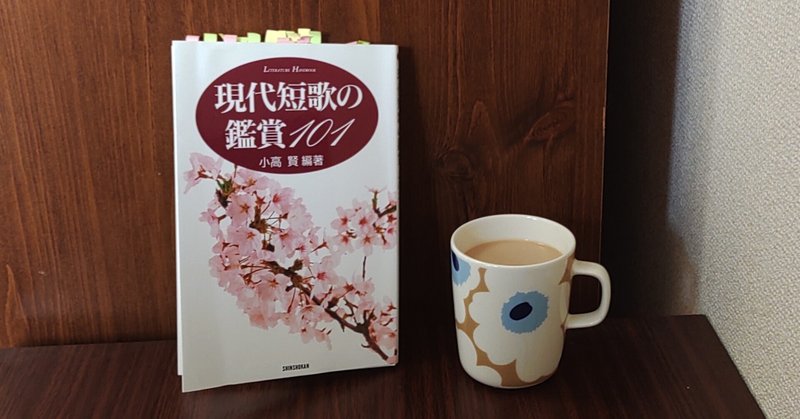
『現代短歌の鑑賞101』を読む 第六回 佐藤佐太郎
佐藤佐太郎の項の書き出しが「いうまでもなく佐藤佐太郎は斎藤茂吉の弟子である」と書いてあってムッとする。この本で佐藤佐太郎を知る人もいるのが当然なのに、「いうまでもなく」ということはない。おどかすのはよくないことである。
秋分の日の電車にて床にさす光もともに運ばれて行く
この短歌は私も繰り返し鑑賞するよい短歌である。秋分の日の電車の床に、光がさしている。電車が動くと、光もともに動いていくように思える。私も運ばれてゆく。光もいっしょに運ばれてゆく。
興味深いのは、この短歌はそれほど五七五七七の韻律に忠実ではないということである。なるほど確かに、
秋分の/日の電車にて/床にさす/光もともに/運ばれて行く
と切って読めるし、私は頭の中ではそのようなリズムで読んでいる。一方で意味内容で厳密に切った場合の以下の読み方も意識している。
秋分の日の/電車にて/床にさす光も/ともに運ばれてゆく
「秋分の/日の」「床にさす/光も」というリズムは、意味内容は前後で繋がりながら、一度リズムの切れ目を置いている。文のリズム、短歌のリズムの両方に多少の違和感を持たせつつ、するりと読める面白い短歌だ。
『現代短歌の鑑賞101』におさめられた短歌ではないが、
なにごともなき昼過ぎの路上にて石ころほどの融くる雪あり』
という一首もある。「なにごとも/なき」のようなわずかな違和感を残すリズム、それでいて五七五七七として読んで飲み込みやすい短歌に、佐藤佐太郎のひとつの技術がある。
参考:
『現代短歌の鑑賞101』小高賢・編著
『鑑賞・現代短歌 四 佐藤佐太郎』秋葉四郎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
