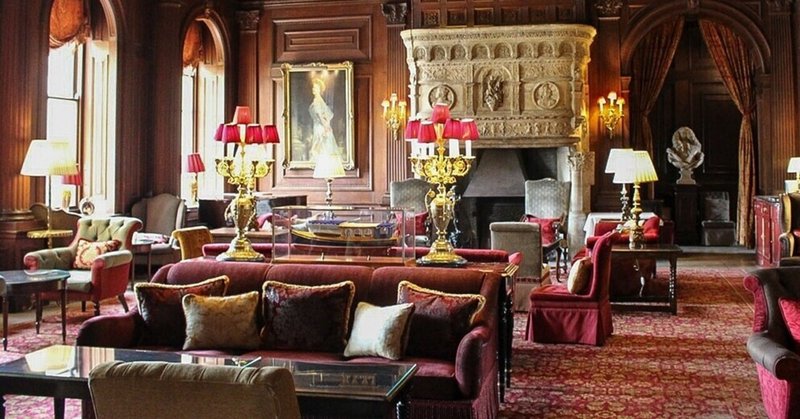
作中作の迷宮(ホロヴィッツの職人芸)
Story within a story
今年、刊行されたアンソニー・ホロヴィッツの新作も面白かったな~
ここ数年、ホロヴィッツの新作ミステリーを読むのが、毎年の楽しみだったりするんです。
2018年は『カササギ殺人事件』
2019年は『メインテーマは殺人』
2020年は『その裁きは死』
と、どの作品も話題になって、年末のミステリーランキングを独占してたりするんで、毎回、期待値が上がるものの、やっぱ面白いのです。
まあ、他の作家さんの作品と比べて突出してるかというと、そこまでではない感じなんですが、全体のクォリティがとにかく高いのです。
そんなホロヴィッツが今年リリースした新作が
『ヨルガオ殺人事件』
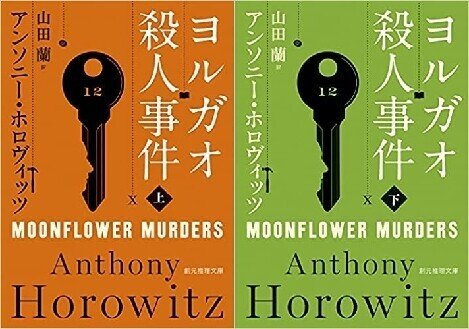
上下巻の大作なんですが、長くなるのは仕方がなくて、実は、このシリーズは、架空のミステリー作家の本が題材になっていて、物語中に、丸々、その作家の本が挿入されている”作中作”の体裁をとる本なのです。
(あらすじ)
『カササギ殺人事件』から2年。クレタ島でホテルを経営する元編集者のスーザン・ライランドを裕福な夫妻が訪ねてくる。
彼らが所有するホテルで、8年前に起きた殺人事件の真相をある本で見つけた... そう連絡してきた直後に娘が失踪したというのだ。
その本とは名探偵アティカス・ピュント・シリーズの『愚行の代償』。それは、かつてスーザンが編集したミステリーだった……。
主人公は、2018年の『カササギ殺人事件』でも主人公だった(元)編集者のスーザン・ライランド。
過去、自分が編集に携わった、作家:アラン・コンウェイの ≪名探偵アティカス・ピュント・シリーズ≫ の一冊に、現代の殺人事件のヒントが隠されているらしいということで、力を貸してほしいと依頼されることから物語は始まるのです。
=物語の構成=
(スーザンのパート)
現代における8年前の殺人事件の調査編
↓
(アラン・コンウェイの小説パート)
『愚行の代償』
↓
(スーザンのパート)
8年前の殺人事件の調査の続き・解決編
上巻の中盤から、下巻の中盤まで、『愚行の代償』が挿入されているのですが、表紙、目次、人物紹介など、ほんと、まるまる入ってるのが楽しいのです。
この、作家:アラン・コンウェイの ≪名探偵アティカス・ピュント・シリーズ≫ というのが、アガサ・クリスティーのパスティーシュになっていて、こちらはこちらですごく面白いのです。
この趣向は、前作『カササギ殺人事件』でも同様なんですが、作中作の小説が挿入されるタイミングは異なります。
『カササギ殺人事件』
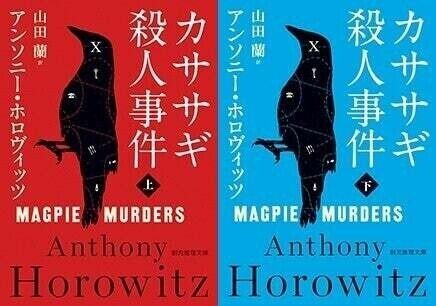
=物語の構成=
(スーザンのパート)
編集者のスーザンがアラン・コンウエィの新作を読み始める導入部
↓
(アラン・コンウェイの小説パート)
『カササギ殺人事件』(ただし解決編なし)
↓
(スーザンのパート)
『カササギ殺人事件』の解決編を探す調査・事件、解決 ※終盤、小説の解決編の提示
前作『カササギ殺人事件』では、上巻がまるまる小説パートで、下巻が現代の調査パートになっている構成だったのですが、『ヨルガオ殺人事件』の方では、途中に挟まる構成になっています。
『ヨルガオ殺人事件』では、小説の中に現代の殺人事件のヒントがある設定なので、上巻の前半部では、現代の殺人事件の概要と、容疑者となるべき人物たちが提示され、その後、満を持して小説が挿入される構成なのです。
現代の事件との関係性を考えながら、”挿入された小説”を読むというのが、なかなか楽しい感じなんです。(途中から、そのことを忘れて、その小説を楽しんじゃうんですが…)
また、下巻の後半、読み終わった小説と現代の事件との関係性を考察する部分の楽しいこと、楽しいこと。
好みは分かれますが、個人的には前作『カササギ殺人事件』以上に『ヨルガオ殺人事件』の方が楽しかったのです。
このシリーズに登場する作家、アラン・コンウェイというのが、なかなかくせ者の作家なんですよね。
このコンウェイの著した《名探偵アティカス・ピュント・シリーズ》は、全9作ある設定なんで、まだまだ、残ってる作品もあるんです。なのでホロヴィッツは、この作中作シリーズを継続することを予定してるみたいで、楽しみなんですよね~。
ちなみに物語の中で提示されている全9作の一覧は以下の通りです。
≪名探偵アティカス・ピュント・シリーズ≫
アティカス・ピュント登場
慰めなき道を行くもの
愚者の代償
羅紗の幕が上がるとき
無垢なる雪の降り積もる
解けぬ毒と美酒
気高き薔薇をアティカスに
瑠璃の海原を越えて
カササギ殺人事件
アラン・コンウェイという作家は、自分の小説の中に、アナグラム(文字を並び替えて違う言葉にすること)などの言葉遊び的な情報を仕込んでいる作家として描かれています。
『ヨルガオ殺人事件』に出てくる『愚者の代償』でも、そういう仕込まれた情報を読み取っていくことが事件の解決につながったりするのですが、シリーズのタイトルにも仕掛けがあって、タイトルを縦読みすると、「ア、な、愚、羅、無、解、気、瑠、カ」→「アナグラム解けるか」になるんですよね~。
もちろん英題での趣向を、翻訳者さんが苦心したものなんでしょうが、こういう仕掛けが溢れてるのが、このシリーズの楽しさなのです。
◎作中作のある作品について
作中作のあるミステリーって、ある種、メタな展開を見せたり、複雑な構成になることが多いので、作家さんにとっても技巧を必要とするものなんだと思うんですよね。
残された手記や日記から事件を読み解いていくパターンなどは、島田荘司さんのお得意のパターンで、『眩暈』や『ネジ式ザゼツキー』など、名探偵:御手洗潔シリーズの中でも見れます。
記憶に障害を持つ男が書いた奇妙な童話『タンジール蜜柑共和国への帰還』。そこには蜜柑の樹の上の国、ネジ式の関節を持つ妖精、人工筋肉で羽ばたく飛行機などが描かれていた。
それらはいったい何を意味しているのか? 御手洗潔は男の脳内の迷宮を探り、男の過去と童話に隠された驚愕の真実に到達する!
また、5つのリドルストーリーを探す米澤穂信さんの『追想五断章』や、竹本健治さんの問題作『匣の中の失楽』も、昨中作が重要な意味を持った作品です。
五つの物語にひそむ秘密。精緻な本格ミステリ
古書店に居候する芳光は、依頼を受けて五つのリドルストーリーを探し始める。やがてその著者が、未解決事件の被疑者だったことを知る...
探偵小説愛好家の仲間うちで「黒魔術師」と綽名されていた曳間が殺害された。しかも友人のナイルズが現在進行形で書いている実名小説が予言した通りに……。
そして、今回の『ヨルガオ殺人事件』のように、まるまる1冊の本が挿入されている構成とすれば、やはり、綾辻行人さんの『迷路館の殺人』だと思います。
奇妙奇天烈な地下の館、迷路館。招かれた4人の作家たちは莫大な“賞金”をかけて、この館を舞台にした推理小説の競作を始めるが、それは恐るべき連続殺人劇の開幕でもあった!
この『迷路館の殺人』では、迷路館で起きた事件の真相を描いた小説がまるまる挿入されているんです。
当時の講談社ノベルスにそっくりに構成されていて、奥付まで付けられてたんですよね。
その凝った造りに、当時、痺れたのを憶えてます。
かれこれ30年以上前の作品ですが、アンソニー・ホロヴィッツにも影響を与えてるんじゃないかと、本気で思ってたりするのです。
*
