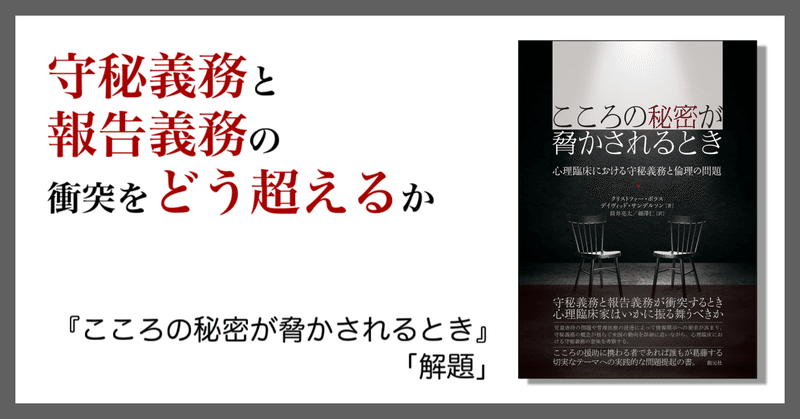
守秘義務と報告義務の衝突をどう超えるか 『こころの秘密が脅かされるとき』「解題」を無料公開
守秘義務と報告義務が衝突するとき、心理臨床家はいかに振る舞うべきか。こころの援助に携わる者であれば誰もが葛藤する切実なテーマへの実践的な問題提起の書『こころの秘密が脅かされるとき』が2024年4月に刊行されます。
児童虐待の問題や管理医療の浸透によって情報開示への要求が高まり、守秘義務の概念が揺らぐ米国の動向を詳細に追いながら、心理臨床における守秘義務の意味を考察した一冊です。
本書の刊行に先立ち、訳者・筒井亮太氏による「解題」を無料公開いたします。
(書籍版と一部表記の異なる箇所があります)

本書は精神分析家クリストファー・ボラスと弁護士ディヴィッド・サンデルソンによる共著 “The New Informants: The Betrayal of Confidentiality in Psychoanalysis and Psychotherapy” (1995; Northvale, NJ: Jason Aronson)の全訳である。原題は『新たな情報提供者:精神分析と精神療法における守秘義務の背信行為』となるが、わかりやすくするため『こころの秘密が脅かされるとき:心理臨床における守秘義務と倫理の問題』という邦題にした。本書は、多作な作家である分析家のボラスが法律の専門家と共同で執筆した異例の書物である。
本書は、二種類の「ルール」――外的規則としての「法律」と内的規範としての「倫理」――をめぐる書物である。二〇一五年九月一六日、公認心理師という国家資格に関する法律「公認心理師法」が公布された。二〇一九年以降、公認心理師が実際に存在するようになったことで、心理臨床界隈にも教育・研究・研修などの領域でいくらか変動が生じている。
このような趨勢のなか、再度、こころの臨床に携わる者たち――精神科医、心療内科医、小児科医、看護師、臨床心理士、公認心理師、産業カウンセラー、社会福祉士、精神保健福祉士など――が常に念頭に置くべき「法と倫理」に関する文献を紹介する必要があるのではないか、というのが本書を訳出した動機である。国によって異なる法律を概観するような本を邦訳してもあまり需要はないだろうし、高邁な倫理的精神を掲げる書籍【*1】も大部となればとっつきにくいだろう。その点、本書は、職種や分野を問わず「相談業務」に携わっていれば無関係ではない「守秘義務」を法律と倫理の観点から取り上げているため、最適であると判断された。
当時、ケンプら(Kempe et al. 1962)の「殴打児症候群」に端を発し、米国社会では児童虐待の問題が盛んに取り上げられていた。密室で繰り広げられる虐待に対して予防・介入するためには、家族という聖域に侵入する必要があるのではないかという議論が巻き起こっていた。また、管理医療の浸透により、治療内容を開示する必要も生じており、精神分析や精神療法の実践を成立させる骨子「守秘義務」という概念が揺さぶられている時期でもあった。この時期、ボラスは大きな使命感をもって本書を上梓した。粗雑ながらも一言でまとめるならば、精神療法家(さらに限定すれば精神分析家)は守秘義務を堅持すべきである、というのが本書の主張である。
1 守秘義務をめぐる倫理規定と関連法規
通常(嘆かわしいことであるが)、日本の臨床家の多くは自身の実践にいかに多くの法律が絡みついているのかについて無自覚である。法律と倫理という観点から伊原(2012)は、心理臨床において問題になりやすい項目として、(1)守秘義務、(2)報告義務、(3)多重関係を挙げている。「境界侵犯」を代表とする多重関係に関しては成書(e.g., Gabbard and Lester 1995; 村本 1998, 2012; Raubolt 2006)に譲るとして、ここでは相互に衝突することもある守秘義務と報告義務を注視してゆこう。
特に守秘義務は本書の焦点なので、各種臨床家の倫理要綱に目を通してみたい。まず、「日本臨床心理士会倫理綱領」第2条「秘密保持」を見てみよう。「会員は、会員と対象者との関係は、援助を行う職業的専門家と援助を求める来談者という社会的契約に基づくものであることを自覚し、その関係維持のために以下のことについて留意しなければならない」とある。
1 秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。
2 情報開示
個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うよう努めなければならない。
「日本心理臨床学会倫理綱領」第6条でも「会員は、臨床業務上知り得た事項に関しては、専門家としての判断の下に必要と認めた以外の内容を他に漏らしてはならない」と定められている。同学会の「倫理基準」では次のようにある。
第6条 会員は、法律に別段の定めがない限り、対象者の秘密保持のために、他の関連機関からの照会に対して、又は対象者の記録の保存と廃棄等については、十分慎重に対処しなければならない。
2 会員は、対象者本人又は第三者の生命が危険にさらされるおそれのある緊急時以外は、対象者の個人的秘密を関係者に伝えてはならない。この場合においても、会員は、その秘密を関係者に伝えることについて、対象者の了解を得るように努力しなければならない。
3 対象者の個人的秘密を保持するために、研修、研究、教育、訓練等のために対象者の個人的資料を公開する場合には、会員は、原則として、事前に当該対象者又はその保護者に同意を得なければならない。(第7条第1項参照)
4 前項の同意を得た場合においても、会員は、公表資料の中で当人を識別することができないように、配慮しなければならない。
心理職以外の場合はどうであろうか。「日本精神保健福祉協会倫理綱領」の倫理原則によると「精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し、その秘密を保持する」とある。「日本社会福祉士会倫理綱領」の倫理基準では「8.(プライバシーの尊重と秘密の保持)社会福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し秘密を保持する。9.(記録の開示)社会福祉士は、クライエントから記録の開示の要求があった場合、非開示とすべき正当な事由がない限り、クライエントに記録を開示する」と示されている。
「日本医師会医の倫理綱領」の「医師の守秘義務」には次のような記載がある。「医師は患者の医療情報やプライバシーを守る義務がある。もし、医師がこの規範を破るようなことがあれば、患者は医師に正直に話をしなくなるであろうし、医師と患者との間の信頼関係は崩れてしまうことになる」。「日本看護協会看護職の倫理綱領」によると「看護職は、対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報は適正に取り扱う」。「看護職は、個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の秘密に触れる機会が多い。看護職は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を口外してはならない。また、対象となる人々の健康レベルの向上を図るためには個人情報が必要であり、さらに、多職種と緊密で正確な情報共有も必要である。……看護職は、個人情報の取得・共有の際には、対象となる人々にその必要性を説明し同意を得るよう努めるなど適正に取り扱う。家族等との情報共有に際しても、本人の承諾を得るよう最大限の努力を払う」とさらに続いている。
守秘義務と関連する各職種の関連法規に目を移してみよう。「刑法」第一三四条「秘密漏示」によると「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以上の懲役又は一〇万円以下の罰金に処する」とある。「保健師助産師看護師法」や「社会福祉士及び介護福祉士法」「精神保健福祉法」「公認心理師法」「地方公務員法」「国家公務員法」でも同等の規定が記されており、各職種でなくなった後においても秘密保持の義務がある点が明記されている。秘密漏示罪は親告罪であり、違法行為に及んだ場合、刑事処罰となる。
また、たとえば「医療法」第七二条「秘密漏泄」では、当該職種のみならず、関係者に対しても守秘義務を規定する記載が設けられている。「児童福祉法」第六一条「守秘義務違反の罪」では、その職種を問わず、「児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とある。各職場と密接に関係する関連法規に関しては成書(e.g., 金子 2016)を参照されたい。
2 守秘義務と衝突する報告義務
いずれの援助職の倫理網領や関連法規を見ても、秘密保持・プライバシー確保が業務上相当に重要である点が強調されているのがわかるだろう。東山(1999)は次のように指摘している。
守秘義務が、あらゆるといっていいほどほとんどの身分法に規定されているのは、ひとの秘密には、人と人との間に、上下関係や力関係を生じたり、利益・不利益をもたらすからである。また、罰則規定まで設けてそれを規制しているのは……心理学的な問題、人がいかに自分しか知りえない秘密を守ることが難しいか、人の秘密を暴露する誘惑が高いかの心理的要因があるからである。(ibid. p.50)
秘密の保持が重大であるからこそ、「刑事訴訟法」第一四九条では「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない」とある。なお、医師などは証言を拒む権利を有することで秘密を保持しうるが、心理職が証言拒絶権の主体として挙げられていない以上、いくらかの議論が存在する【*2】(出口 2009; 後藤・徳永 2004)。
しかし、この守秘義務であるが、本書でも示されているように、いくらかの葛藤をもたらす場面が存在する。伊原(2012)によると、雇用契約上の報告義務との衝突、警察・司法当局との関連による衝突、そして未成年者の心理的援助に際する保護者への情報開示の問題がそれである。内的規範としての「倫理」に従うだけでは、臨床家は自身の実践を遂行することができない。外的規則としての「法律」にも同じように拘束されているのである。
たとえば、スクールカウンセラー(以下SC)であれば、学校設置者(各種自治体や学校法人など)と取り交わした雇用契約に拘束される。二〇一九年以降、会計年度任用職員として雇用されるSCには「地方公務員法」(そのSCの身分によっては、さらに「医師法」や「公認心理師法」)が適用されることとなった。「公認心理師法」第四二条第二項によると「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」。ところが、クライエントがカウンセリング内容を主治医であっても伝えてほしくないと望む場合もある。守秘義務があるからこそ、安心してこころの内実を打ち明けることができるのである。ゆえに、クライエントの同意を得ることなく主治医に相談内容を共有することは秘密保持義務違反となる(津川 2022)。
他方、出口(2009)によると、医療機関等で医師の指示に従ってカウンセリングを行っている場合、その心理職は業務内容について、そのすべてを医師に報告する義務を負っていると解するべきである。「心理職の判断・報告ミスで患者の自傷他害や自殺が誘発された」と立証されれば、損害賠償責任が医師に課せられ、心理職には注意義務違反により「民法」第七〇九条「不法行為による損害賠償」に基づく損害賠償責任が負わされる。
以上のように、何らかの機関や組織に所属している援助職は、雇用主や上長に対して報告義務を負っている。その報告義務を怠ると「不法行為」として法的責任を課されることがある。再度、SCを例にあげよう。報告義務を厳守すると、学校の「SCだより」などに「話された秘密は守られます」と記載しておきながら、実際にはカウンセリング内容を報告・共有するという、信用失墜をもたらしかねない事態が横行することになる。かといって、いじめや虐待など、生徒本人や周辺生徒の生命に関わる案件は別としても、相談業務の一切を秘匿にしておくことも日常業務の遂行に支障をきたしかねない。そこで「集団守秘」という発想が現場の知恵として案出された。SCがひとりでクライエントの情報を抱え込むのではなく、関係者全体が必要な情報を共有し、厳密な守秘義務を背負うという考え方である。
しかし、子どものプライバシー権などの基本的人権を尊重するという立場に立てば、SCの守秘義務は尊重されなければならず、学校長らも子どもの基本的人権を侵害するようにカウンセリング内容を詮索すべきでないし、報告を命ずる職務命令を発するべきではないという主張もある(出口 2012)。出口は、集団守秘という考えに疑問を呈し、SCが「子どもの立場に徹頭徹尾寄り添うという姿勢をとらず、学校におけるさまざまな立場の人たちの調整的立場になる役割を演じ、子どもの権利を守るという立場になる役割を果たすということをしていないのではないだろうか」(ibid. p.104)と難詰している。援助職は、守秘義務と報告義務の葛藤状況を、「赤信号みんなで渡れば怖くない」といわんばかりの安直な妥協形成で回避してよいのだろうか?
何らかの法的・倫理的な「正当な理由」があれば、守秘義務は破られる。逆にいうと、それほどまでの例外的事態が存在しない場合、守秘義務は堅持されるのである。ここでいう「正当な理由」とは、(1)クライエントや患者が自身の秘密を第三者に開示する点に同意している場合、(2)法令により秘密保持義務が解除される場合、(3)クライエントや患者が自傷他害に及ぶ可能性がある場合である。この(3)の要件の発端となったのが、本書でも引用されているカリフォルニア州の〈タラソフ〉判例である。この判決以降、ある患者やクライエントが他者に対する害意と行為企図を明確に表明した場合には治療者は、犠牲となりうる他者に対してその内容を知らせるために守秘義務が免除されることとなった。
しかしながら、切迫した自傷他害の危険性に遭遇した場合に守秘義務が解除されるという発想には当初より疑問も投げかけられていた。たとえば、スロヴェンコ(Slovenko 1976)は、守秘義務を墨守するだけでは第三者視点によるケアの質が担保できなくなり、種々の研究も発展しづらくなると指摘しつつも、〈タラソフ〉で争点となった危害の程度のアセスメントや事件発生の予見がどれほど可能なのか問いを立てている。また、ベルソフ(Bersoff 2014)ははっきりと〈タラソフ〉を「悪法」であると断じている。彼の示唆するところでは、〈タラソフ〉判例以降、臨床家は、事前に守秘義務の例外をアナウンスして「インフォームド・コンセント」(Appelbaum, Lidz, and Meisel 1987参照)をとる「倫理的」義務と、患者が起こす暴力の可能性や危険性のアセスメントをする「臨床的」義務を負うこととなった。「臨床家が守秘義務を破る代わりにできる介入は無数にある。しかし、開示を義務づけている州では、訴訟を避けるために、臨床家は安全な道を選ぶだろう」(Bersoff 2014, p.466)。
本書刊行後、著者であるクリストファー・ボラスが守秘義務をめぐる諸問題について言及した論考(Bollas 2003)は示唆的である。彼は精神分析を「フロイトの方法によって構成される体験の一形態であり、それぞれの学派のパラメーター内で、必然的に個人的な作業手段に従って、さまざまな精神分析家が解釈する形で、思考と行動の無意識のプロセスを引き出すものである」(ibid. p.162)と定義し、それ自体がセラピーや治療とは異なるディシプリンとして成り立つ道を模索するように提言している。医療行為やそれに準ずる援助行為として精神分析が定義づけられてしまうと、その内実の客観的査定や第三者評価が国家から求められ、結果的に分析家たちが法的領域に引きずり出されることをボラスは懸念しているのである。
歯科医であれば、患者が犯罪行為を疑われるような見識について語っていても、歯を削ることはできる。弁護士であれば、クライエントが違法行為に及びそうだと悩んでいても、その人に助言することはできる。別の職業すべてで、話し手が自殺を考えていると話したり、自身が殺人者であると述べたり、自らを虐待被害者と称したり、虐待に及んでいる人物の隣人であると語ったり、大手麻薬ディーラーの友人であると喋ったり……していても、その人の話を聞くことはできるし、そのような開示がその関わりの機能を破壊することもない。ほかの精神療法すべて――認知療法、行動療法、心理劇、人間性精神療法など――も、これらの専門職のいずれも話し手と聴き手の自由連想に依存していないため、機能することができるだろう。分析の道具――私が「フロイトのペア」と呼ぶもの――が使えなくなると、精神分析だけが破壊されてしまう。
(ibid. pp.165-166)
3 児童虐待の通告義務をめぐる葛藤
先ほどの(2)に挙げられている法令とは、たとえば、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」であったり、本書でもクローズアップされている「児童虐待」をめぐる法律であったりする。二〇〇〇年に公布された「児童虐待の防止等に関する法律」第二条によると、児童虐待とは「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう……)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう……)について行う次に掲げる行為をいう」とある。その行為とは「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」を指す。また、同法第三条によると、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」。これら四種の虐待に加え、さらに特殊な虐待として「乳幼児揺さぶられ症候群」「代理によるミュンヒハウゼン症候群」「医療ネグレクト」も挙げられている(日本弁護士連合会子どもの権利委員会 2017)。
同法第六条によると「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」。また、第三項には「刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない」と記されている。
すなわち、守秘義務を負う各種専門職であっても、虐待が疑われるような事例に遭遇した場合は当局に報告しなければならないのである。故意による虚偽の通告や、それに準ずるような重過失の場合を除き、虐待の報告後に虐待の事実がないと判明しても報告者が罪に問われることはない。これは、誤通告に対して法的責任を課すのは酷であり、そのために通告が躊躇われるのを避けるためであろう(日本弁護士連合会子どもの権利委員会 2017)。
児童虐待防止法の目的は「児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、……もって児童の権利利益の擁護に資すること」にある。この目的を達成するべく、児童虐待が社会的な水準でも法的な水準でも対応を必要とする問題である点には議論の余地がなく、この問題に対処するためには虐待の通告義務が欠かせないという点でコンセンサスが得られているにもかかわらず、臨床家のあいだでは、通告義務が虐待の過少報告も過剰報告も引き起こすと主張されている(Smith and Meyer 1984)。業務上、目の前で虐待が起こる現場を目撃する場合に通告する義務が生じるのは当然である。あるいは、眼前でドメスティック・バイオレンス(以下DV)が発生している場合には関係当局に通報するように努めるのも当たり前である。けれども、支援者は、実際の場面を目にすることよりも、加害者や被害者である患者・クライエントによる言語報告という形でその事実に遭遇することのほうが圧倒的に多いのではないだろうか。秘密が保持されるという前提のもとに支援を受ける人が語った言語内容でもって報告するのかどうか、葛藤することだろう。
通告義務のメリットと守秘義務違反のデメリットを適切に天秤に乗せているのかを疑問視し、数回の診察や面談の場合には治療関係が成立していないために、虐待通告に迷うことは少ないかもしれないが、長期的な精神療法やカウンセリングの経過のなかでは葛藤が生じやすいと指摘する声もある(Miller and Weinstock 1987)。児童の権利を守るため、種々の問題の報告義務が課せられた結果、たとえば小児性愛者や性的犯罪者を治療するための機関が姿を消し、高度な技能をもっていた精神療法家たちが現行法の下に作業する困難を覚えて児童精神療法の分野から撤退するという悲劇も起こっている(Bollas 2003)。
ベルソフ(Bersoff 2014)も指摘する点であるが、臨床家は法的義務に盲目的に従うのではなく、自身の臨床判断を活かすように、情報開示の裁量権を与えられてもよいのだろう。報告義務化が臨床判断や専門職間の協力を破壊してしまうと警鐘を鳴らすボラス(Bollas 2003)は、守秘義務を破るような傾向に抗うために支援してくれる法律家や法学者との相談も欠かせないという。目下、守秘義務が危機に晒されている事態を憂いているコヴィントン(Covington 2003)は、専門職間で連携し、法律家から法的助言を得て、政府や行政と協議を重ね、広報活動を展開し、専任のロビイストを雇うなどの策が必要であると示唆している。
精神療法上の守秘義務と虐待通告義務の衝突を概観し、ミラーとウェインストック(Miller and Weinstock 1987)はいくらかの指針を示している。すなわち、(1)現在虐待を受けている疑いがある場合、過去の虐待であっても治療が必要な(一八歳以下の子どもの)場合、通告されるべきである、(2)外来ベースで治療する場合には虐待加害者ではなく、虐待(疑い含む)被害者の身元を一八歳以下に限り通告すべきであり、加害者が治療に入らない場合に加害者も通告すべきである、(3)入院ベースで治療する場合(つまり現在進行形で虐待は防止されている)、虐待疑いは通告されるべきではなく、過去の虐待に起因する治療が必要な場合にのみ過去の虐待が通告される。虐待の事実と疑いを峻別し、被害者と虐待者双方に通告することが与える影響を吟味し、どちらにも必要に応じた治療を提供するという姿勢がここには表れている。
4 熟慮を要する事例
ここまで、守秘義務を中心に、それを支える倫理と法律、それに拮抗する事案と法律を見てきた。守秘義務という観点から臨床実践を捉えれば、通常、秘密の厳守が優先されるのはいうまでもない。たとえば、医療機関を受診している患者が違法薬物を使用していると発覚した場合、医療者は「犯罪の告発に関して裁量することが許容されて」おり、「医療者として最も望ましいと思う選択」をすることが推奨されている(松本・杉山 2020)。無論ケース・バイ・ケースであるが、犯罪行為があっても、医療的処置が相応しいと判断されれば、報告・通告することは保留されうる。
ブレット・カーはその未公表の論考(Khar 1996 in Venier 1998)のなかで、良性の守秘義務違反と悪性の守秘義務違反を区別している。良性の違反とは、クライエントや社会を保護するためのものであり、入院患者の自傷他害のリスクを院内で共有したり、児童虐待を通告したりすることを指す。悪性の違反とは、患者の噂話をしたり、同僚に不適切な情報を伝えたりすることである。いずれにしても、臨床家は常に法律や倫理を念頭に置きつつ、その臨床状況で最善と思われる判断を下していかなくてはならない。
生徒から通報に値する事実を聞かされ、「このことは絶対に言わないでほしい。ほかの人に言ったら自殺する」と言われた場合、このSCはどうすればよいのか。あるいは、明らかにDVを受けていると思われる事例のカウンセリングに際して、口止めされた場合、そのカウンセラーはどのように対応するべきなのか。このようなジレンマをもたらす事例に関しては出口(2009)や津川(2022)を参照いただくとして、ここでは二事例、熟慮を要する場面を提示したいと思う。
◎HIV患者のパートナー告知をめぐるジレンマ(Remley Jr. and Herlihy 2020を加工修正した事例)
医療機関に勤めるカウンセラーXは、三〇代の患者Aのカウンセリングを担当している。Aは、パートナーである日との関係に問題をもたらしてしまうという主訴を抱えていた。その問題の解決を図るために、XとAは、家族や幼少期以降の経験を振り返るようなカウンセリングの契約(週一回五〇分)を取り交わした。セッションを重ねるなかで、Aは徐々にXを信頼するようになり、なかなか他人には言えないような事柄をXに話せるようになった。ある回、AはBと出会う前に、不注意な形で性的な接触を不特定多数の人たちともっていた点を打ち明け、その過程でHIVに感染したのではないかと不安であると涙ながらに語った。翌回、Aは、HIVの検査を受けた結果、HIV陽性である点が確認されたとXに知らせてきた。
ここで問題になるのが「パートナー告知」である。HIVが感染症である以上、感染者がパートナーと危険な性交渉をもつと、パートナーもHIVに感染する可能性がある。しかし、往々にして、HIV患者は、自身がHIV陽性であるとパートナーに知られたら見捨てられてしまうのではないかと不安になるため、告知の必要性を理解しつつも、そのことを打ち明けられずにいる。ここにジレンマが生じる。HIV陽性である情報は診療情報であるため、正当な理由なく、本人の了承もなく他人に伝えることができない。しかし、この事態を放置すると、BにHIVが感染する可能性もある。結果、感染したBから訴訟を起こされる場合も考えられるだろう。
カウンセラーであるXは、Aの秘密を厳守する義務があるのだろうか。あるいは、守秘義務を破ることになっても、Aの状態をBに知らせる義務があるのだろうか。Xは、当然、告知の必要性を告げ、Aと話し合いを続けた。Aは告知の必要性を実感したが、そのことを告げるまでには時間がかかりそうであると答えた。この状況でXはAの秘密をどれほどの期間保持すればよいのだろうか。
本事例の原案(Remley Jr. and Herlihy 2020)、つまり米国の場合では、〈タラソフ〉判例が引き合いに出され、Xは守秘義務を維持することができず、主治医に連絡して、Bに事の顛末を伝えるように依頼することが推奨されている。また、Bが感染したかどうかを確認する方法がない以上、Aが考える時間を待つのは危険であるため、Xは、性交渉をもつ場合には感染症を防止した上で実施するようにAと約束するようにも示変されている【*3】。では日本の場合はどうであろうか。
「患者がHIVに感染しているという秘密を医師が配者やパートナー等の第三者に告知する義務は感染症予防法一二条に定める医師の届出義務には該当しないため、配偶者やパートナー等の第三者に告知する行為は法令に基づき告知する場合には該当せず、またHIV感染者が同意しているわけではないのでこれらを理由として秘密を告知する行為が正当化されることはない」(未道 2013, p.74)。とはいえ、国連合同エイズ計画と国連人権高等弁務官事務所が作成した「HIV/AIDSと人権に関する国際ガイドライン」に記載されている「パートナー告知が行われる際に踏まえるべき基準」を参照すると、一定の基準を満たすことで、医療者による通知は「許可」(「要求」される、ではない)される。
◎役割葛藤が招く不幸(名島 2020に紹介された一例を加工修正した事例)
大学相談室に勤務するカウンセラーYは、所属大学に通う大学生Cのカウンセリングを実施していた。Cは指導教官からセクシュアル・ハラスメントを受けており、その相談をYにしていた。カウンセラーYは、大学のセクシャル・ハラスメント対策指針に反して、Cの同意を得ぬままに調停を開始し、守秘義務を破って上長に相談内容を報告した。結果として、Cは調停委員会の事情聴取で、調停委員から「自らの落ち度が嫌がらせを招いたのではないか」などと指摘され、二次被害も被った。
その後、Cは「純粋な悩みの相談のつもりで行ったのであって、調停などはまったく想定していなかった。調停委員の言動で二次被害に遭った」と主張し、大学を相手に訴訟を起こした。大学は「相談員が担当当局に内容を伝えるのは、手続きを円滑に進めるためには必要なことである。調停に関しても、電話による同意を得ていた」と反論した。Yの立場に立てば、学生相談室は組織上、学生部厚生課に所属しているため、学生相談室への相談内容の詳細を上司の厚生課長に自主的に「報告した」のも道理である。雇用主である大学には業務の報告義務があるため、ハラスメント案件を伝えるのも当然である。
しかし、裁判所は「相談員が守秘義務に違反して上司に相談内容を報告するなどしたことで、プライバシーを侵害した」として、大学側に損害賠償を命じた。裁判長によると、「電話は一方的であり、調停の同意はなかった。公式手続きの選択が話し合われる前に上司に伝えたのは守秘義務違反である」。
調停手続き上、Yが学生部厚生課長に相談内容を報告しなければならなかったとしたら、Yはその点をまずCに述べて、Cの了承を得るべきだった。了承が得られなかった場合、その旨を課長に報告し、Cに対しても相談内容の報告ができなければ調停手続きには入れないことを説明するべきだった。そのプロセスを踏んでいれば、Cに調停の意図がないことが判明していただろう。
なお、Y自身が調停手続きを行ったとすれば、Yは「カウンセラー」の役割と「ハラスメント対策委員」という二つの機能を果たすことになるだろう。純粋に心理的な事柄を主として取り上げる前者と、所属機関における種々のハラスメント撲滅のためのリアルな対処を図る後者とでは求められるスタンスや水準が異なるため、Yのアクションは不適切なものといわざるをえない。
しかしながら、昨今のハラスメント対策の強化を鑑みると、ハラスメント案件を知った臨床家がその対策に乗り出すというのは珍しいことではないだろう。忘れてはならないのは、社会的・組織的な対応に動く際、その患者やクライエント個人に対して臨床家自身が「守秘義務」を負っているという認識である。
最後に、一考に値する法律専門家の見解を、孫引きになるが引用しておこう。「間違いをおかすなら、ある特定の事例において情報を開示するのが適切かどうか自問した上で、用心をとって、開示しなかったということで間違うのがおそらくベストであろう。……守秘は義務だというしっかりとした信念に立ってトラブルに巻き込まれた治療者を私は知らない。一方、これもしっかりとした信念の上のことだが、情報を開示するように権威づけられていると考えて実際に開示してトラブルに巻き込まれたたくさんの治療者を私は知っている」(Leslie 1989; 村本 1998 にて引用)。
5 事例研究の終焉?
さて、これまで守秘義務が相当に重要である点をさまざまな角度や事案から説明してきた。臨床家は自身が見聞きした他者の秘密を厳守しなければならない。守秘義務こそが臨床実の基礎なのである。ところが、その臨床家たち自身が守秘義務を揺るがせるような行為に及んでいる場合もある――しかも、パブリックな形で。それは、研究や論文の刊行 publication である。臨床家は個々の患者やクライエントの秘密をその生涯にわたって秘匿する義務がある。その一方で、自身の自験例をもとに研究という形で専門分野の発展に貢献する責務も担っている。このトピックについて最後に触れることで解題を締めくくりたい。
心理臨床の事例研究の嚆矢であるS・フロイトは、現代の臨床家たちと同様に、事例を公表することに慎重であった。たとえば、症例「ドラ」(Freud 1905[1901])でフロイトは、治療過程が極秘であるために第三者の視点が入らない点が気がかりであり、秘密の内容を公開することで批判されることを恐れており、一方で最初から刊行されることを知らされていれば事の真相に至ることはなかったとも考えていた。また、彼は、自身を症例として公表する許可を患者自身に求めても無駄であると考えてもいた。
一般の医療実践と異なり、精神療法の内実を報告するのは至難の業である(Slovenko 1976)。ひとりの患者やクライエントとの臨床実践を公表する際、(1)そのタイミングはともあれ――初期の契約時に伝えるのか、治療終了前後に伝えるのか――インフォームド・コンセントでもって公表の同意 consentを得る、(2)臨床素材を書く上で何らかの編集作業――修飾 modifcation や偽装 disguise や削除 erasure ――を加える、という工程が必要となる。
「人権擁護」の視点から捉えると、論文による公表はもちろん、会員に限定された学会の発表やスーパーヴィジョンにおいても、患者の同意を得るように義務化するという要請(皆川 2008)も当然のごとく理解できる。とりわけ医療領域では顕著であるが、治療にしても研究にしても患者に対して説明責任を果たし、提供する内容を納得してもらい、その上で共同的に事に臨むというインフォームド・コンセントの発想は倫理的にも法理的にも実践の前提となっている(Appelbaum, Lidz, and Meisel 1987)。マーク・ブレッシュナーが示す原則は「臨床素材を公表したいのであれば、患者の同意を得よ。患者がそれを読みたがれば、読ませよ。患者を傷つけると思ったり、患者に同意を求めたり臨床記述を読ませたりすることに抵抗がある場合は、公表しない」(Blechner 2012, p.17)というものだ。
しかし、タケット(Tuckett 2003)は、医学雑誌編集者国際委員会(International Committee of Medical Journal Editors; ICMJE)による指針に対し、『国際精神分析誌』(International Journal of Psychoanalysis; IJPA)の編集者が同意しかねる場面があったと報告している。その理由は、「転移関係に関する精神分析的理解と、患者関係におけるその意味を鑑みれば、本当の意味で有意義な同意を得ることは困難であり、押しつけがましいものであるため、必ずしも患者の最善の利益にはならないと思われた」(ibid. pp.177-178)ためだった。また、日本の『精神分析研究』に掲載されているシンポジウムの記録(2008)によると、訴えられる覚悟をもち、同意を取る種々の影響を考えた上で患者から同意をほとんど取っていない分析家も存在している。つまり、インフォームド・コンセントそのものから悪影響を受ける人もいる点を忘れてはならない(Barnett 2012)。
患者から同意を得ているにせよ得ていないにせよ、精神療法のプロセスをそのまま公表することは難しいだろう。精神療法が濃密な二者関係によって成立している以上、書き手はそのプロセスから完全に隔離されて物事を捉えることができない。双方の関与者にとって真実たりうる「臨床事実」をそのままに書き下すというのは原理的に不可能でもある。そのため、望むと望まざるとにかかわらず、必然的に編集という作業が入り込む。ここでは、事実と異なる情報を付け加える工程を「修飾」(例:ずっと定職についていた患者に転職歴を加える)、事実と虚構を入れ替える作業を「偽装」(例:男性患者を女性患者と表記する)、論旨とは無関係と思われる情報は書かないでおくことを「削除」(例:出身を記さない)として暫定的に定めておく。特に論点となりやすいのは、偽装であろう。
偽装を施すことを認めてしまうと、患者の身元のみならず、場合によって臨床プロセスそのものも偽られてしまいかねず、非科学的なデータの産出を許してしまうことになる(Blechner 2012)。しかし、精神分析や精神療法の実践において、インフォームド・コンセントをとる営為が相当に高いハードルである点も疑う余地がない。自身の臨床家が公表しようとして、同意を求めてきており、許可すれば全世界に自身の内面の苦しみが発信されるという恐怖や不安(あるいは恍惚)を抱きかねない患者に対して、真に倫理的な振る舞いとは何なのか。慎重なアセスメントと段階的な手続き、そしていくらかのチェック・リストを活用することで、患者に同意を取るのか、あるいは同意を得ずに偽装や修飾を加えて発表するのかを決めなければならない(Sieck 2012)。
松木(2008)は、精神分析過程の本質を妨げない形であれば、削除は当然として、修飾や偽装という手段が取られうる点を指摘している。その偽装も中途半端なものであれば、当人が気づく可能性は十分にありうる(Fischer 2012)。ストーラー(Stoller 1988)が記しているように、当事者が著作物のなかに自身を認めた場合の心痛は計り知れないものがある。その刊行物の性質や目的もあるだろうが、公表することに伴う意思決定のプロセスを経る上で、参考になる問いかけを紹介しておこう(Thomas-Anttila 2015, p.372)。
1.患者を十分に偽装できるのか? 患者(や患者の親族、同僚、友人、知人)がセラピストの作業の記述を読んだ場合、自分自身を認識することができるのか?
2.合成事例でも同じ目的を果たせるのか?
3.同僚をその研究の著者として提示したほうがより匿名性が保たれるのか?
4.事例の決定的な要素を保ちつつ、個人情報はどの程度まで含めることができるのか?
5.公表することで、患者やその人生に関わる周囲の人びとがどのような気持ちになるのか?
6.公表することは患者にとって有益になるのか?
7.素材の準備と出版は、患者とセラピストの共同作業となりうるのか?
8.セラピーのどの時点で同意を求めるべきなのか?
9.同意を求めることで、治療関係にどのような影響を及ぼすのだろうか?
10.実際に患者に対してインフォームド・コンセントを取れるのか?
6 おわりに
いまでも覚えている。学生の時分、法律に関する講座か講義に出席したときのことだ。私は、ワークの一環で、児童虐待の事実を知った際にどのように対応するのかという問題にグループで取り組んでいた。ある種の正解は決まっていた。「当局に通報する」、それ一択だった。私は、そのように回答しつつも、ある種の迷いを示した。通報してその後のことはどのようにすればいいのか、どのように子どもに伝えればいいのか、通報を受けた家庭の親子がどのような処遇を受けるのか、何よりも親を通報される子どもの気持ちはどうなるのだろうか、と。通報が法的義務であり、倫理的責務であるのは論を俟たないが、その決断と行為の周辺に横たわる心理的な影響を考えると、当時の私は素朴に逡巡したのだ。
それを聞いたグループの参加者のひとりは憤慨し、「こんな人に支援者になってほしくはないっ」と私を罵倒した。いま振り返っても至極当然の反応であると思う。明らかに虐待を受けている子どもを前にして、躊躇などしていられない。それでも、である。虐待を受けた子どものケアにも携わっていたロナルド・フェアベアンがかつて述べた言葉が思い出される。「子どもからすれば、悪い親でも、いないよりはマシである」。子どもは親を選べない。どうしようもなく困難で逆境的な環境であっても、その親を自身の養育者として据えなければならないのは痛切な不幸である。虐待をするような親は矯正されなければならないし、子どもを守るために引き離されなければならない。それと同時に、残された子どもの心情や心痛もまた考慮されるならば、私たちは葛藤する。葛藤するからこそ、考えようとする。葛藤なきところに思考は生まれえない。「法律で決まっているから」とか「倫理的にはこれが正しい」とか「ポリティカル・コレクトネスの視点ではそれは間違っている」とか、直線的に特定のコンセプトを当てはめる行為は臨床実践の対極に位置する。
私たち臨床家は、その実践の倫理的基盤に「守秘義務」を背負っている。「正当な理由」なく、患者やクライエントから知りえた情報や秘密をみだりに発信してはならない。昨今のSNSを見ると、少なくない数の援助職の人間が業務上知った内容を書き連ねている。また、少なくない数の同業者たちがその発言された内容に反応をしている。これらを見て、現在のクライエントや、のちに患者となりうる人たちがどのような気持ちになるだろうか。再度、本書が専門家たちの倫理的姿勢の点検を促す契機になれば幸いである。
【註】
*1 日本語で読める心理臨床の倫理の書籍としては、村本(1998)やネイギー(Nagy 2005)が参考になる。特に後者は浩瀚であるが、非常に勉強になるので、一読をお勧めする。
*2 本書刊行の約一年後、一九九六年の米国最高裁判所〈ジャッフィー 対レッドモンド〉判例は精神療法家と患者のあいだの秘匿特権を肯定するような見解を示した(Jaffee v. Redmond, 518 U.S. 1〈1996〉)。「効果的な精神療法が実施できるかどうかは、患者が率直に事実・感情・記憶・恐れを包み隠すことなく打ち明けようと思えるかどうか、そのような信頼状況が生まれるかどうかにかかっている。患者が精神療法家に相談する問題はきわめて繊細なものであるため、カウンセリング中に行われる、相当に高い守秘義務を要するパーソナルな相談内容が開示されるとすれば、患者は深く傷つき、辱めを受けることとなる。このような情報が開示されると、治療が奏功するために必要なきわめて親密な信頼関係の構築を妨げることになりかねない」。
*3 守秘義務という視点で考えると「感染症」というのは悩み多きトピックである。感染症予防の観点からすると、患者の診療情報は適宜共有されてゆくことが望ましいのかもしれない。近年の新型コロナウイルス(Covid-19)のような世界的なパンデミックに際して、医療上の守秘義務も再考されなければならないだろう(Shekhawat, Meshram, Kanchan & Misra 2020)。
【目次】
謝辞
イントロダクション
第1章 告白に背くこと
第2章 作成時欠席
第3章 秘密の喪失
第4章 情報提供者を創ること
第5章 秘匿特権を再建すること
解題
訳者あとがき
文献
索引
【著者紹介】
[著]クリストファー・ボラス(Christopher Bollas)
米国出身の精神分析家。英国精神分析協会所属。ニューヨーク精神分析訓練・研究インスティテュート名誉会員。父親がフランス人であった影響か、英語以外の言語も堪能であり、大学では政治学や文学を学んでいた。自身が学生時代に精神療法を受けた影響で、精神分析や精神療法に関心を抱く。30歳前後で英国にわたり、精神分析の訓練を始め(訓練分析家はマシュード・カーン)、英国の精神分析界で頭角を表す。60歳を過ぎたころ、米国に戻り、臨床実践以外にも執筆活動や絵画作成に打ち込むようになる。非常に多くの著作物を発表しており、日本語で読めるものとして、『対象の影:対象関係論の最前線』(館直彦監訳:岩崎学術出版社 2009)、『精神分析という経験:事物のミステリー』(館直彦・横井公一監訳:岩崎学術出版社 2004)、『終わりのない質問:臨床における無意識の作業』(館直彦訳:誠信書房 2011)、『太陽が破裂するとき:統合失調症の謎』(館直彦監訳:創元社 2017)がある。
[著]デイヴィッド・サンデルソン(David Sundelson)
米国出身の控訴弁護士。開業弁護士を営むかたわら、ニューヨーク州立大学ジェネセオ校やカリフォルニア工科大学などで文学や精神分析学の教鞭をとっている。法と倫理の観点から心理臨床を論じた論考として「被害者のアウティング:倫理上の手続きにおける守秘義務違反」(Outing the victim: Breaches of confidentiality in an ethics procedure. In C. D. Levin, A. Furlong, & M. K. O’Neil(Eds.)Confidentiality: Ethical Perspectives and Clinical Dilemmas. New York: Routledge, 2003.)がある。
[訳]筒井亮太(つつい・りょうた)
香川県出身。関西大学大学院心理学研究科修了。臨床心理士。現在、たちメンタルクリニック・上本町心理臨床オフィス勤務。著書に『トラウマとの対話』(共編著:日本評論社 2023)、訳書にジェイコブス『ドナルド・ウィニコット』(共監訳:誠信書房 2019)、コトヴィッチ『R・D・レインと反精神医学の道』(共訳:日本評論社 2020)、スチュワート『精神分析における心的経験と技法問題』(単訳:金剛出版 2020)、ボウルビィ『アタッチメントと親子関係』(単訳:金剛出版 2021)、エヴァンス3世『ハリー・スタック・サリヴァン入門』(共訳:創元社 2022)、ドゥシンスキー他『アタッチメントとトラウマ臨床の原点』(単訳:誠信書房 2023)、ペダー『アタッチメントと新規蒔き直し』(単訳:みすず書房 2023)などがある。
[訳]細澤仁(ほそざわ・じん)
栃木県出身。神戸大学医学部医学科卒業。精神科医。現在、フェルマータ・メンタルクリニック院長、アイリス心理相談室代表。著書に『解離性障害の治療技法』(単著:みすず書房 2008)、『精神分析を語る』(共著:みすず書房 2013)、『日常臨床に活かす精神分析』(共編著:誠信書房 2017)、『実践に学ぶ30分カウンセリング』(共編著:日本評論社 2020)、『日常臨床に活かす精神分析2』(共編著:誠信書房 2022)、『寄り添うことのむずかしさ』(共編著:木立の文庫 2023)、訳書にスチュワート『バリント入門』(共監訳:金剛出版 2018)、ホームズ『アタッチメントと心理療法』(共訳:みすず書房 2021)、ショア『無意識の発達』(共訳:日本評論社 2023)などがある。
※著者紹介は書籍刊行時のものです。
