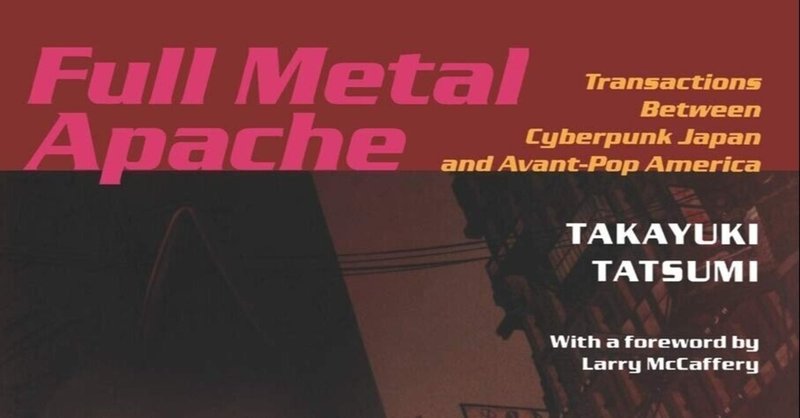
Takayuki Tatsumi, 『Full Metal Apache: Transactions Between Cyberpunk Japan and Avant-Pop America』(2006) 書評
*本稿はたしか、『英語青年』(研究社)の書評欄に掲載していただいたものだったと記憶している。巽孝之氏のそれまでの仕事の集大成としてデューク大学出版局から発行された本書は、今でも(あるいは今でこそ)読まれるべきものだろう。ということで、あえて再掲させていただいた。
あなたは「なぜ日本人なのにアメリカ文学を研究しているのか。なぜ日本文学を学ばないのか」と質問されたら、どのように答えるだろうか。私は先日ある場所で、旧知の大学院生からこう尋ねられた。彼女自身が留学中、ことあるごとに聞かれた質問だそうだ。たしかに私自身の答えはないわけではない。だがここに「日本人」としてのアイデンティティを求められると、答えに窮してしまう。われわれアメリカ研究に携わる日本人研究者は、このアイデンティティの問題に対してどのようなスタンスを取るべきなのか。アメリカと日本を互いに「他者」と看做すべきなのか(つまりあくまで「対象」と看做すのか)、理解可能な普遍性を共有する存在なのか(つまり「我がこと」としてとらえるのか)。巽孝之氏のFull Metal Apache: Transactions Between Cyberpunk Japan and Avant-Pop America (2006)は、そんなアイデンティティをめぐる難問を抱えた時代に出るべくして登場した書物である。
未見の読者のためにまず断わっておくと、本書はまったくの書き下ろしではない。これまでの巽氏の論考の集大成として過去の日本語および英語で書かれた論文・エッセイなどを大幅に加筆訂正し、テーマごとに整理した「リミックス盤」、あるいは「セルフ・カヴァー」とでもいうべき書物である。したがってこれまで巽氏の著作に接してきた読者であれば馴染みの深い題材や修辞、あるいは「私」で語り始める文体や網羅的な情報のカタログ的披瀝などの独自のスタイルがここでも展開されている。この「巽節」がアメリカの読者にはどのように受け入れられるのか、たいへん興味があるところである。
全体は5部構成(に結論部)となっており、それぞれの章には”Theory”, “History”, “Aesthetics”, “Performance”, “Representation”という題が添えられている。だがこれも厳密な構成というよりは、ある程度の大枠程度に考えたほうがよさそうだ。「理論」と「歴史」が完全に連動しているとは言い難かったり、「美学」と「パフォーマンス」、「表象」はそれぞれの章の内容を的確に示してはいるものの、それぞれの関係や厳密な区分が分かりにくいなど、論旨や理論の構築に厳密さや緻密さを求める向きには、細部にわたって気になることがあるかもしれない。だが先に書いたとおり、これまでの巽氏の長年の研究・執筆活動のエッセンスを「リミックス」した本書に、厳密な意味での「統一」を求めるのは酷である。それよりも「リミックス」の「ベスト盤」でありながら、その論旨に大きなブレがないこと、共通した興味関心やモチーフが、これほど長大な時空内で持続していることに、まずは感心する。
本書は総体として、アメリカと日本という二つの国が、相互影響と相互参照によってどのような文化現象が構築してきたかを論じている。巽氏の読者にはおなじみの、時代やジャンルを超えた博覧強記、その知識のカタログ的な提示、各事象の並置や意外なもの同士の連結から生み出される思いもかけぬ展望などから垣間見えるのは、昨今のメディアを賑わせている「戦後日本」の再検討である。だが誤解しないでもらいたい。これはどこか国の首相が言うような「戦後レジーム(=第二次大戦後の日本の社会・文化体制)がアメリカを模倣することによって形成されてきた、という言説そのものの基盤を脱構築する試みであり、安易な日米比較論あるいは日本異質論に対する異議申し立てである。
巽氏の著書は、的確かつキャッチーなキーワードでテーマが提示されることが多い。本書で核となるキーワードは二つ、”creative masochism”と”synchronicity”であろう。都留重人を引きながら巽氏は、戦後日本の歴史をアメリカ追従と模倣以上のものとみる視点を提供している。アメリカをモデルとした戦後日本の復興は、一種のマゾヒスティックな構造を孕まざるをえない。だがそのマゾヒズムそのものが日本を、単なるアメリカの模倣から遠ざけ屈折した創造性を発揮させる契機となった。これが巽氏描くところの”creative masochism”である。そして高度成長が終わりバブルへの地ならしが始まる80年代、一方通行的な影響関係から文化的な相互参照へと日米関係が変質し、そのころから類似した作品や文化現象が日本とアメリカで同時発生的に見られるようになる。これが”synchronicity”である。この語彙は本来ユング心理学の用語で一般的には「共時性」と訳されるが、ここではユングの意図とは全く異なった意味で用いられている。たとえば同じニューヨークのレストランを舞台に用いて「孤児」の物語を紡いだPaul AusterのMoon Palace (1989)と島田雅彦の『彼岸先生』(1992)。フェミニスト・ナラティブとしてのKathy AckerのThe Empire of the Senseless (1988)は、その後継者としてEurudiceのF/32 (1990)と松浦理恵子『親指Pの修業時代』 (1993) を生み出す。90年代後半には、ほぼ同時に日米で『ゴジラ』の読み直しが行われる。情報化社会の進展により、日米間でのタイムラグが限りなく縮小した結果、ほぼ同時と見えるようになったのかもしれない。だがいずれにせよ日米で何らかの問題系が共有されているからこそ、この共時的発生という現象が可能になることは間違いない。
一読すると巽氏は、アメリカの”orientalism”に対して日本の”occidentalism”を対置しているように見える。だがオクシデンタリズムとはオリエンタリズムの対立概念ではなく、オリエンタリズムの枠内でのみ成立するものである(少なくとも評者はその立場をとる)。自らを「オリエンタル」なものと自覚した(言い換えるとオリエンタリズムを内面化した)日本人(東洋人)による西洋の表象がオクシデンタリズムであろう(だから正確には”orientalist-occidentalism”とでも表記すべきか)。したがって、「オリエンタリズム」と「オクシデンタリズム」は単純な対立概念ではなく、その間には非対称な関係が横たわる。これがポストコロニアル研究の出発点であったはずだ。
もっとも、「西洋近代にとっての不気味な他者」(78) としての「オリエント」は、当の西洋近代によって産出されるものである、などということは巽氏も先刻ご承知だろう。というより西洋近代を成立させるために「他者」として排除したものを「オリエント」として表象する働きが「オリエンタリズム」であるならば、巽氏の取り上げる柳田国男の『遠野物語』は、そこで見出された「日本」が西洋的方法論によって構築された民俗学の対象である限り、オリエンタリズムの好例である。だからこそ巽氏は柳田国男の民俗学のモデルとして、小泉八雲/ラフカディオ・ハーンの『怪談』を措定する。ハーンが見出した「日本」は、怪異や幽霊によって表象される「他者の空間」ともいうべき仮想的な時空であった。その「日本」は柳田の『遠野物語』を経て1970年代以降の日本人自身による「日本」の発見に行きつく。その「ディスカバー・ジャパン」や「エキゾチック・ジャパン」に象徴されるドメスティック・ツーリズムによって再発見された「日本」とは、資本主義システムの内部に取り込まれた、Larry McCafferyいうところの「現実スタジオ」なのである。こうして「戦後レジーム」の問題がAvant-Pop理論へと接続されることで、「美しい国日本」とは内面化されたオリエンタリズムの産物以外の何物でもないことが明らかになるだろう。
一方その小泉/ハーンの「他者の空間」としての「日本」を生み出した「西洋近代」は、自己の内部に存在する他者恐怖が具現化した対象として、アジア/日本を「侵略者」として表象することにもなる。それがH.G. WellsのThe War of the Worlds (1898) に代表される一連の”Future War Novels”に登場する異星人である(不勉強な評者は本書を読んで、エキゾチックな女性として東洋を表象したMadame Butterflyが、『宇宙戦争』と同年であったことを 初めて知った)。
こうして巽氏が素描する19世紀末から20世紀後半の日米文化交流史から、「日本」という特異な空間が構築される過程が浮かび上がってくる。日本がオリエンタリズムを内面化する一方で欧米に対するマゾヒスティックな自意識も醸成し、結果として日本人は自らに対しても外に向かっても、仮想的な空間としての「日本」を形成するしかなかった。また80年代以降の”Pax Japonica”(個人的には抵抗もあり疑問もある用語ではあるが)以降、「日本」の表象は日本人の特権的領域ではなくなっている。ハーンの見出した「日本」がWilliam GibsonやMichael Keezingの描く「日本」と本質的に差がないのと同様に、島田雅彦も小松左京も塚本晋也(『鉄男』)も、その描く「日本」がフィクショナルな「現実スタジオ」であるという点において、日本の表象において日本人である特権を享受する可能性はあらかじめ剥奪されている。
巽氏はそこまでは言い切ってはいないが、この論理を外延していけば、そこに出現するのは日本人としてのアイデンティティを「不可能」とする地平であるはずだ。この後期資本主義システムの中では、日本は「日本」という仮想空間としてしか表象しえない。その仮想空間で構築された「日本人」としてのアイデンティティを持つ存在とは、「日本人」という「サイボーグ」である。だが巽氏の言う「サイボーグ」は、決してネガティブでもペシミスティックでもないアイデンティティの在り方である。それは実際に読めば確認してもらえる。そしてここが最初の疑問に対する答えの出発点になるだろう。
もちろんこの結論を妥当とするかどうか、それは人によって判断が分かれるはずだ。だが昨今のアイデンティティ・ポリティックスをめぐる諸所の議論、とくにWalter Benn MichaelsのThe Shape of Signifier (2003)やThe Trouble With Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (2006) を併せて読むことで、このアイデンティティを巡るアポリアに対する新たな洞察を可能にしてくれる書物であることは間違いない。
*ウォルター・ベン・マイケルズの議論については、今はやや(かなり?)批判的に見るようになった。それはアイデンティティ・ポリティックスと経済格差を二項対立として単純化し、その結果新自由主義的な枠組みに落とし込まれる危険性を危惧するからである。この点については、拙著『70年代ロックとアメリカの風景』(小鳥遊書房、2021)の最終章で論じているので、ご参考に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
