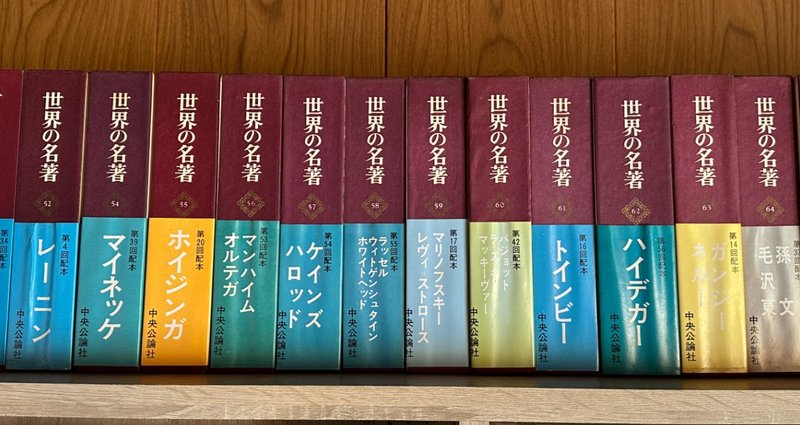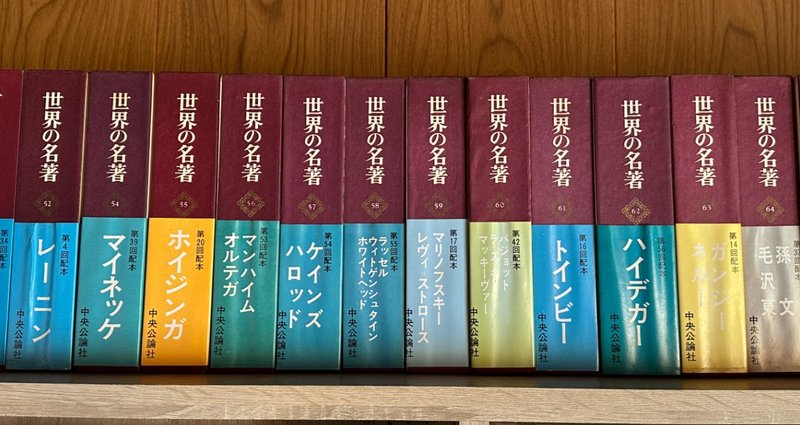15対50問題——メリトクラシー(能力主義)が分断する社会
語っているのは1956年英国生まれのジャーナリストであるデイヴィッド・グッドハート(David Goodhart)。現代社会や世界情勢などに鋭く切り込むことで定評のある、イギリスの総合評論誌『プロスペクト』誌の共同創刊編集者である。このインタビューにおいて彼は、現代の「メリトクラシー」社会を批判する。
「メリトクラシー(能力主義)」という言葉を使ったのは、イギリスの社会学者マイケル・ヤング(Michael Young, 1915 - 2002)が最初である。現代では「能力主