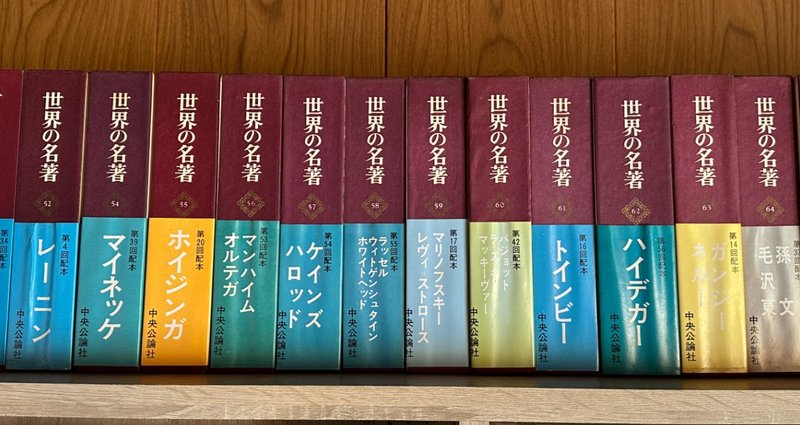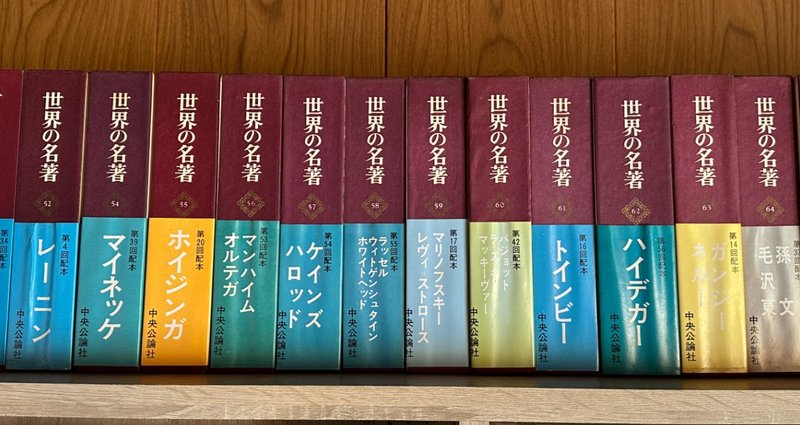ソクラテスの「ダイモニア」とは何か——プラトン『ソクラテスの弁明』より
ソクラテスは、心の内にある神的なもの、ダイモニアを信じていた。そして、そのダイモニアがときどき彼に「◯◯をするな」と諫止してきたと述べている。一体この「ダイモニア」とは何であろうか。というのも、これは後にアリストテレスが幸福の概念として述べた「エウダイモニア」、つまりダイモンあるいはダイモニアを声をよく聴くことに通じているからである。
岩波文庫の『ソクラテスの弁明』の翻訳、解説をしている哲学者の久保勉(くぼ まさる, 1883−1972, 東京帝国大学卒の哲学教授)によると