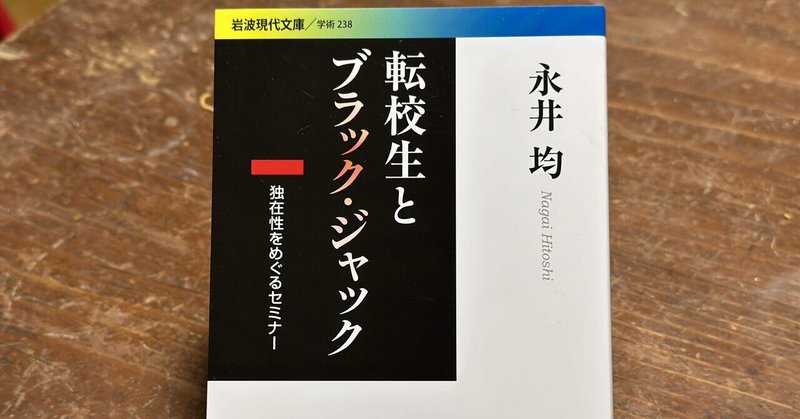
永井均氏の『転校生とブラック・ジャック』から考える独在論
学生C 《おれ》であるという性質?そんなの誰だって持っているんじゃないの?男だけかもしれないけど。
学生E そういう意味での《おれ》性ではなくてね、ある一人の人間だけが、世界そのものが現にそこから開けている、世界の中心であるという、特別なあり方をしているってことなのさ。つまり、一つの世界は必ずここで《おれ》といわれているようなただ一つの心から開けているんだよ。この物語の世界ではたまたま太郎である《おれ》、この世界ではもちろんたまたまEであるこのおれだよ。そして、その特殊な性質は、その人間の物理的性質とも心理的性質とも独立に成り立っているんだ。C君にも、D君にも、G君にも、他のみんなにもそれぞれ個性があって、まったく違う人たちだけど、その中で、Eと呼ばれているこの男だけがぼくであるという特殊なあり方をしている。それが何なのか、それが、それだけが問題なんだよ。
永井均(ながい ひとし、1951 - )氏は、日本の哲学者・倫理学者。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得。現在、日本大学文理学部哲学科教授。主な著書に『存在と時間』(文藝春秋)、『世界の独我論的存在構造』(春秋社)、『これがニーチェだ』『私・今・そして神』(講談社現代新書)、『ウィトゲンシュタイン入門』(ちくま新書)、『西田幾多郎』(角川ソフィア文庫)など。
本書のテーマは「なぜ、この〈わたし〉は、いまここにいる〈わたし〉なのか?」という問いだ。「独在性」あるいは「独在論」と永井氏は呼んでいる。このテーマが、さまざまな変奏曲となって本書では語られ、議論される。この問いは、当たり前のようであって、実に不思議な問いなのだ。この哲学的な問いは、「なぜ、よりによってこいつが私なのか」という問題ではないと永井氏は言う。それは、サイコロを100億個ふったらすべて「1」の目が出たというときの「なぜ」であり、それは確率論的な驚きであるからだ。「わたし」や「いま」の成立には、そのような確率的な驚きがあるのではない。そして、もし世界に一人しか人間がいないときにも、この問いは際立つという。その場合、この問題は「なぜ、そもそもまったくの無ではなく、ともあれ何かが存在しているのか」という存在論的問いと重なってくるからである。
「転校生とブラック・ジャック」(略して「転ブラ」)では、ある「転校生」が他人とぶつかったときに身体と心が入れ替わってしまう。そのとき、天才外科医ブラック・ジャックがあらわれて、脳(心)を入れ替える手術をしてくれる。そのときその手術によって元の身体におさまった〈わたし〉は、はたして元のままの〈わたし〉であるか、という思考実験だ。
この議論においては、まずライプニッツ、デカルト、カントが出てくる。つまり「認識論」に関する議論が先にある。しかし話はそれでは終わらない。むしろこの問題の本質は「なぜ、そもそもまったくの無ではなく、ともあれ何かが存在しているのか」という「存在論」に関するものだからだ。〈わたし〉という実在、「いま」という時間の問題。「存在と時間」の問題として、つまり現象学的系譜(ハイデガー)があり、絶対無としての〈わたし〉の議論をした西田幾多郎も視野に入る。さらには「意味論」の問題もかかわってくる。例えばウィトゲンシュタインである。
「なぜ◯◯が《おれ》でなければならないのか」という問い。これは、要するに「第一人称指示詞かまたは自己意識というものの働きのなかに、その自己自身を唯一特別のものとして他から切り離す働きがある」ということなのではないか。そして、この問題は、一般論への吸収を拒むものが現に存在するということを意味する。つまり、私が◯◯であるこの現実世界が存在し、現実世界としては「それしか存在しない」ということである。同じ構造が他の可能世界(つまり他者)で反復できたとしても、「これが現実である」ことは動かない。
しかし、そのことは語れないのだ、と永井氏は言う。語られてしまえば、そしてひとに理解されてしまえば、もうその〈現実〉そのものが移動してしまうからだ。独我論は語りえず、ただ現に現れているだけだ、というのである。これはつまり、言語のはたらきそのものの中に「悪霊の欺き」であるようなことがらが含まれているということであると。ここでは「意味論」としてのウィトゲンシュタインが想定されている。
あとがきで永井氏は、こうした議論にもかかわらず、この独在性の問題は、依然として少しも解決されずに問題であり続けているという。それどころか、このような問題が解けたところで、世の中に劇的な変化が起こるわけでも、人類が今より幸福になるわけでもないという。しかし、哲学者とは、普通のひとが気にしないような、足元の問題、つまり、私たちが普段気にもせずに立って生活しているようなその「土台」あるいは「大地」について考えざるをえない人びとである。実はその土台がなければ、私たちの存在や生活がガラガラと崩壊してしまうことに、人びとは気づいていないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
