
小説『水蜜桃の涙』
「第6章 悲劇」
この章の登場人物:
成沢清之助・・・・高等師範学校の最終学年に通う都会育ちの青年
谷口 倖造・・・・高等師範学校の教授
石田 英二・・・・清之助の同級生
石田 律・・・・・石田英二の従妹で、女子高等師範学校の学生
時は無情に過ぎ、その年の冬を迎えていた。
「成沢さん、私も行くわよ!その恩師の故郷とやらへ」
石田律さんは、鼻息も荒くそう断言してはばからない。とんでもない行動力だ。
そのやや勝気な性格を、ほんのちょっとでいいから僕にも分けてもらいたいものだ。
「いついらっしゃるの?とにかく、その輝子さんを助け出さなきゃ!その村ではとんでもないことが起きているのよ。そんな酷いところにいつまでも置いておけないわよ」
僕から相談を持ち掛けた輝子のことを聞き、彼女は怒りがすでに爆発していた。
石田律、彼女は僕の同級生の石田英二の従妹であり、女子高等師範学校に籍を置いている。
石田の後を追うように高等教育を受け、自らもいずれ後続の女子たちの教育をするべく学んでいる。
同時にどうやら最近活発化している女性解放の活動組織にひっそりと加入しているらしきことを、石田から先日聞いたばかりだった。
男女が公に堂々と会って話ができないので、こうやって石田の実家に遊びに行き、従妹の律さんがたまたま遊びに来ていたという体で、輝子のことを相談する席を設けてもらっていたのだ。
「律、そう急くなよ。もっと細かく清之助の話を聞かないと。田舎は特に保守的だからな。彼女の親はもちろん、教授だってどうにもできずにいる」
石田が威勢のいい律さんを冷静に制する。
「そんな…手をこまねいている時間が何とももどかしくて。うん、でも、ここは丁寧に計画を練って動くべきね」
なんとかやや落ち着いてきた律さんを前に、輝子との生きる運命の違いを目の当たりにして切なくなってきた。
「言った通り、僕は学校に戻ってからもずっと気になってはいたが、まだまだその村で教師になる覚悟まではできていなかった。迷いに迷っていたのに、東京の中学校の教職の話もとりあえず進めていた。このあたりは僕の卑怯な部分さ。逃げ道をちゃんと作っているんだからね。それなのに、輝子のことは忘れられずにいた。たとえ縁談が決まっていたとはいえ。でもまさか、教授からこんな話を聞かされるとは想像だにしなかったから…」
「いや、別の道を探るのは迷いがあるのなら尚更もっともなことだよ。でもそっちの準備をしていたおかげで、とりあえずは君の職は無くならなかったわけだからね」
石田が慰めてくれる。確かに彼が言う通り、村の教師を引き受けると返事をしてその道を信じていたのなら、僕はそのあと別の職を見つけるのにもっと苦労しただろう。
そんな折、谷口教授から衝撃の話を聞かされたのはつい一週間ほど前のことだった。
僕は苦悩を抱きながらも、輝子のことだけは甘い記憶の中で、美しい彼女の顔と涼やかな声とまだあどけない話しぶりを脳裏に描きつつ毎日を過ごしていた。
谷口教授の教官室に呼ばれたのは、久しぶりだった。
教授の故郷へ一緒に行ってほしいと頼まれたのは夏の初め。それからすでに五か月ほど経っていたのだ。
「成沢です。失礼します」
教官室の扉を開けると、教授が机に座って頭を抱えている姿が目に入った。
具合でも悪いのだろうか。「大丈夫ですか」と声をかけようとしたが、すぐに顔をあげて僕に座るように促した。部屋は石炭ストーブの上にやかんが置かれ暖かく、教授がお茶を入れようとしてくれていたが、その手つきが何とも緩慢で、これは何かあるな、と訝し気に僕は教授を見つめていた。
「成沢君、君はずっと私の村での教職に就くという話には気乗りがしなかったようだね」
お茶を入れた湯呑をこちらへ差し出しながら、ついに教授が口を開く。
やはりその話か。いよいよ腹をくくれとのお達しだろうか。
はて、どう答えよう。未だに決めきれずにいるのだ。なんとも優柔不断な性格に我ながら嫌気がさす。
湯呑を受け取りながら、
「いただきます。その件ですが、僕にはいまだ覚悟ができていないんです」
正直に答えるしかない。自分の不甲斐なさに頭を垂れていると、
「そうか。それでいい。もうこの話は忘れてくれ。要らぬことで頭を悩ませてしまい申し訳なかった」
教授からは思いもかけない言葉が飛び出し、何が起こったのかよくわからないので続きを待った。
「昨日、村長から手紙が届いてね。学校の話が頓挫したというのだ。あれから、数度手紙のやり取りをして進捗状況を知らせてくれていたのだが、とんでもない事件があの後起こっていたのだよ」
「事件って…、何かよからぬことでも?」
恐る恐る聞いてみるが、いったいどんなことが起こったというのだ。
あの景色から、のどかな村の印象しか思い浮かばないではないか。
「宗一郎君だよ。あの伊ケ谷氏の息子。そもそもあの縁談にはやはり無理があったのだ。ただでさえ父親に反感を持ち始めていた頃合いに、父親が自分より年下の娘と結婚だなんて、相当許せなかったのだろう。気持ちは理解できるが、しかし…」
「いったい何があったのですか!?」
教授の言い方がもどかしすぎて、つい強く詰め寄ってしまった。
「私たちが帰ってすぐに、宗一郎君も学校の寮に帰ると言って家をあとにしたというのだが、おそらくそのままあの娘に会いに行ったのだと思われる。そして…言いにくいのだが、彼女を呼び出し、その、乱暴をはたらいたようだ」
頭を固いもので殴られたような衝撃があった。
いや、そのような気持ちがしたぐらいの教授からの告知であった。
彼が、あの宗一郎君が、よりにもよって輝子を!?
「な、ぜ、彼が」
どうにも言葉にならない。喉元がざらざらと砂を飲み込んだように苦しく、息も絶え絶えになりそうなくらいだ。
「何がどういう経緯でとか、詳しいことはわからないが、数か月後には彼女が子を宿しているらしいことが村中で噂になった。伊ケ谷氏の子かと思いきや、伊ケ谷氏は全く持って身に覚えがないという。怒り狂った伊ケ谷氏は娘を自宅の離れの部屋に閉じ込め、娘を詰問したところ宗一郎君の名前をやっと引き出したというのだ。そこで伊ケ谷氏は宗一郎君の苦悩もよそに、彼を相当せっかんしたらしい。そのあと、今度は逆上した宗一郎君が娘の所へ行き彼女ことを殴ってしまい、結局、子は流れてしまったという訳だ。これが村中に広まり、もちろん縁談はなくなったのだが娘はそのまま部屋に閉じ込められたままだ」
この一連の話に、こっちが逆上したいくらいだった。
何ということだ!何というむごいことを。かわいそうな輝子。
こんなことだったら、あの時会う約束をとりつけて、連れてくるべきだったか。
いや、思うだけできっと僕にはできない。そんな度胸など持ってはいない。こんなちっぽけな自分にも情けなくなってくる。
もっと僕が強い心根を持った男だったなら、と自分のこの性格を本当に恨めしく思う。
「彼女は…ずっと閉じ込められているのですか?」
ようやく声に出して問うてみた。
「そのようだ。実家の親は娘を思いやって、部屋から出してくれるように頼んでいるらしいが、元々自尊心も高い伊ケ谷氏は怒りが収まらないのだろう。耕作地を返上するならばと脅しこそすれ、聞く耳を全くもたないらしい。おかげで学校設立の話も立ち消えてしまったよ」
恐ろしい話だ。
完全に常軌を逸している。いくら何でも一番つらい思いをしている輝子のことをまだ苦しめるのか。
それにしてもいったい宗一郎君はどうしたというのだろう。
父親が嫌いとか許せないとかいう問題以上の感情があったのだろうか。
とにかく輝子のことが心配でならない。
「学校の話が立ち消えて、そのままにしておくおつもりですか?村へ、村長に話を詳しく聞きに行かれないのですか?」
僕はつい感情の赴くままに、教授に訴えるようにして問い詰めていた。
「うむ、誠に残念なことだが、せっかく村に高等教育の芽が出始めようとしている矢先のこの話だ。私としても、はいそうですか、と簡単には引き下がれない。そもそも、伊ケ谷氏がやっていることは道徳的にも問題がある。何とかそのあたりのことも、冷静になってもらわねばならぬ。君が言う通り、一度は向こうに行って事の経緯と今後の話を聞いてみないとこのままでは村が衰退していくだけだ」
「そうですか。では先生が行かれる際は、僕にもまた声をかけていただけませんか。再びいっしょに参りたいと思います」
いてもたってもいられない気持ちから、この時はそう言ったのだった。本心だった。
「いや、君はもう東京の中学校での仕事に向けて準備を始めるのだろう?」
「でも少しは関わった事実がありますから、行く末だけでも見守りたいと思います」
「そうか、わかった。元は私が君に声をかけた責任があるのだからね。申し訳ないとも思うのだ。でも君の方からそう言ってもらい少しは安心したよ。行く日が決まったらまた連絡するよ」
教官室を出て、教授ではないけれど頭を抱えてしまった僕は、ふらふらと教室まで歩いて行ったようだが、どうやってたどり着いたのか記憶がない。
あまりにひどい顔をしていたのだろう。友人の石田が僕を見て声をかけてきた。
「どうかしたのか?教授の部屋に呼ばれたようだが、何か思わしくない話でもされたのか?ずいぶんと具合が悪そうな顔をしているぞ」
「あ、いや、まあ。何と言えばいいのやら。僕には到底解決できなそうな話なのに、教授の村へ再び同行すると言ってしまった。言ったはいいが、いったい何をどうするというのだ。石田、ちょっと相談に乗ってもらえないだろうか」
そして、核心は後ほど話すからと言って、まだ幼い娘が閉じ込められているのをどうしたら助け出せるかを問うてみたのだ。彼だって帝大を目指すほどの優秀さだ。僕の思いもしないような何かの手蔓を提供してくれるのではないかと期待した。
しかしさすがの彼も即座には応えることができなかったのだが、ふと思いついて彼の従妹のことを教えてくれた次第だ。
という訳で僕は彼とともに石田律さんに会い、教授から聞いたままを話したのだった。
第7章へ続く
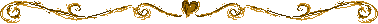
※ 文中の「女子高等師範学校」については、これまで出てきた「高等師範学校」と同じく全くのフィクションであり、かつて実在した学校とは何の関係もありませんことをご了承ください。
第1章はコチラ
https://note.com/soware/n/n929f8ababa57
第2章はコチラ
https://note.com/soware/n/nbe86df520d77
第3章はコチラ
https://note.com/soware/n/n16d7c672023f
第4章はコチラ
https://note.com/soware/n/n00060f4a6acd
第5章はコチラ
https://note.com/soware/n/n9bceda9253bc
今回もお読みくださりありがとうございました。
次回もまたご訪問いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

