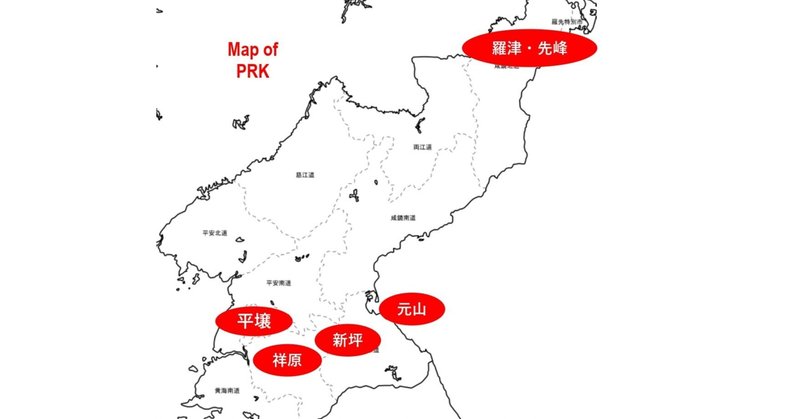
長編小説「平壌へ至る道」(75)
年齢は三十から三十五、見ようによっては二十五にも感じられる。徴兵制度がもうすぐ変わり、間もなくこの国では三十歳の男は軍隊の中でしか見かけられなくなるが、まだこの時点では二十五歳を過ぎればシャバに戻ってこられた。しかし周囲にこれだけ人が溢れ返っており、新婚旅行と思われる二人組もそれなりに散見されながら、相慶と同世代おぼしき男性は確かに圧倒的少数派ではあった。
この「夫婦」を至近距離で観察しつつ、保衛部員は判断に迷った。チョッパリには見えないし朝鮮人民軍の制服も着ていない。若干白いものが混じったぼさぼさの髪と、その顔色、痩せた体躯。我がチョソン人民平均値の王道を行くような外観だ。野菜を担いだ女も売春婦には見えない。
保衛部員はそれでも声を発した。
「公民登録証を」
周囲の者たちが身じろぎした。とうとう容疑者が現れたのか?しかし誰も二人の方へと振り返ろうとはしない。見たいものを自由に眺め、話したい事柄を自由に喋る、ここはそんな世界ではない。
相慶とチャンスクは、求められた証書を提示した。彼女の手の震えについて尋ねられれば、単に取り調べに対する畏れで、と答えてやればいい。
保衛部員は公民登録証を点検した。元山に住む造船所の職工、三十二歳と、党幹部子弟の通う高級幼稚園の教師、二十六歳。二人とも先祖は貧農。核心階層。
相慶は彼女とこの駅で交わした最初の頃の言葉を思い出していたーそうなると、君はもう戻れないな。
誰も聞いていなかったという確信はあった。しかしそれは平和ボケした国で育んできた感覚がもたらしたものだ。密告が奨励され、普遍的な日常風景にすらなっているこの北朝鮮で、その甘い認識が通用するか。
そんな後悔ももう遅い。会話が誰の耳にも入らなかったことを今更ながら願うしかない。飢餓が進行する昨今、治安要員に喜んで協力する住民なんて最早存在しないという朴泰平や李昌徳のアドバイスを信じるしかない。
「新婚旅行か?」保衛部員が質問してきた。
はい、と相慶は答え、チャンスクが野菜の詰まった袋を指さした。ついでに平壌に住む叔父にこれを持っていくのです。
男は登録証を二人に返した。相慶がそっと息を吐こうとしたそのタイミングを見計らっていたかのように、保衛部員は告げた。通行許可証を。
相慶の心拍が跳ね上がった。沈黙がその空気までも染め始めているような駅構内に、その音が響き渡るのではないかと思われるほどに、心臓が早鐘を打つ。
ジャンマダンで偽造書類屋のアジュモニから雛形用紙は貰った。しかしそれは白紙だ。
今時通行許可証を持って国内移動する者などいない、彼女はそう言っていた。しかしそれは食糧運搬といった緊急避難的措置に限った話だろう。自分たちのケースはそうではない。あらかじめ計画された新婚旅行なのだ。許可証の不備は旅行本来の趣旨とは相容れない。
しかしどうなのだ、今はもう新婚旅行でもいちいち通行許可証の申請などしないものなのか。
分らない。全く何も分らない。
相慶はポケットをまさぐり、探すフリをした。そんな時間稼ぎが何の意味を持つか不明だったが、ともかく最終的には白紙の許可証に何がしかの賄賂を添えて目の前の男に提供する腹づもりを固めていた。
その時、別の場所で金切り声が上がった。さすがに取調者被疑者の区別なく、誰もが思わず声の方向へと目を転じるぐらいの音量だった。
駅構内の二箇所で、何らかの事情により治安要員との関わりを避ける必要のあった男と女が一人ずつ、脱走を試みてあっけなく捕まっていたが、すぐ近くにいた男の方が激しい抵抗を示していた。まだ若かった。軍の脱走者か、不法物資の運搬者か。この国で逮捕の際に抵抗すれば後々どのような処置を招くことになるのか知らない訳でもなかろうが、それでも彼は身をよじり、捜査員の手を逃れようとした。
相慶に通行許可証の提示を求めていた保衛部員が助太刀に走る。
男は駅の外に待機してあるトラックに載せられた。そのすぐ横で朝鮮人民軍元山特別軍区第二十四師団の隊員たちが男の人着に首を振っている。その光景に恐慌をきたした者が新たに脱走を試み、駅構内は騒然となった。幌で覆われたトラック荷台に収監された人民が六人に増えた。兵士たちは六度、やはり首を横に振った。
さきほどの保衛部員はそちらの対応業務で手一杯になったのか、相慶たちの所へ戻ってくる気配はなかった。
いつもとは明らかに様子の違う趙秀賢が歩き始めた。駅の中はまた静かになった。モーセを迎えた海のように、あれだけ詰まっていた人の群れが割れていく。
改札口に着いたカリスマは、そこに元からいた保衛部員にホームでの警備を命じ、自らはその場に立ちはだかり、周囲を睥睨した。
ただならぬ雰囲気は、誰しも感じていた。保衛部唯一の良心とも言える趙秀賢が初めて民衆に見せつけた厳しい態度、撃っていいという言葉。そして、相容れないはずの人民軍と保衛部の共同調査。何もかもが異例づくめで、それだけの出来事が起こっているのだと人々は理解した。
「駅の外にはもう出られない」
チャンスクの言葉は相慶にも理解できた。ここから違うどこか、に移動するからこそ人は駅に来ている。そこを手ぶらで立ち去るのは、ではオマエは何をしに元山駅まで出向いたのだという疑念を安全部や保衛部の係官に与える行為となる。
「いずれ地方からの列車が元山に到着する。それを待ちましょう」
それから一時間以上、駅は沈黙に支配され続け、ひたひたと歩き回る保衛部員の足音だけがその例外となった。
どこかで我慢の限界を超えた者が失禁し、その臭いが漂ってくる。
更に数名が、駅入口まで連れ出され、トラックのある場所へと引っ立てられた。
夕方五時近く、列車が元山駅のホームに滑り込んできた。
相慶の視界をわずかにかすっただけの列車は、しかし壮絶な様相を垣間見せてくれた。
屋根を覆う人、人、人。機関車の上にも、連結器の回りにも、そして客車の窓枠にも、人が立っていた。振り落とされれば死が待っている。後遺障害を負うのは更に不幸だ。この国では身体障害者に対する社会保障は何もない。逆に国が定める兵役、生産、収穫といった各種ノルマの規定水準に応じることができない者として、いずれ闇に葬られる。
あるいは平壌に連れて行かれ、WHOやユネスコのスタッフが来朝した際の見学コースに組み入れられる、普段はありもしない障がい者リハビリセンターの中で、外国人の目が注がれている時間だけは親切に振舞ってくれる見目麗しい女性スタッフから、もう少し、頑張ってと励まされる者の役割を与えられ、そこで演じ続けていく人生を送るか、だ。
そうまでして人々は地方に赴き、食っていくため自分ができる最大限の行動を起こしている。
相慶は目元が潤むのを感じた。そんな感傷がこの体内に残っていたとは自分でも驚きだったが、日本からわずか二千キロ離れた場所で、多くの同胞がこの地獄で必死に毎日を生き抜いている姿は、彼の心を激しく揺さぶった。
改札から下車した人の波が溢れ出てきて、駅ホールの中は混沌に陥った。
趙秀賢がまたも叫ぶ。
「今列車から降りてきた者だけが駅の外に出て良い!元々ここにいた者はその場に留まっていろ!従わない者は痛い目に遭うぞ!」
その脅しに効力はなかった。チャンスクの見立て通り、明らかに列車からの乗客でない者も、入口でバリケードを組んでいた朝鮮人民軍を押しのけ、外の世界へと散らばっていった。
威嚇射撃の発砲音はしかし、群集心理となって更なる恐慌を彼らに与えるだけだった。列車から降り、この町に用のある者のみならず、これから列車に乗り込もうとする者たちも、追われるようにして誰もが我先に駅出口へと殺到し、相慶もチャンスクの手を固く握りながら、それに続いた。
アジアハイウェイ六号線を渡り、昼間歩いた住宅街の細い道へと足を運んだ。
暗くなりつつある空が、家々のみすぼらしさを闇に隠し始める。
「今日は鉄道移動は無理だな」
「そうね」
「泊まる場所のあてはあるか」
「一旦ジャンマダンに戻って仕切り直ししましょう」
「ちょっと待て」
別の声が背後を襲った。相慶とチャンスクも足を止めた。
男が近づいてくる。さきほど元山駅で、自分たちを至近距離で眺め回した保衛部員だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
