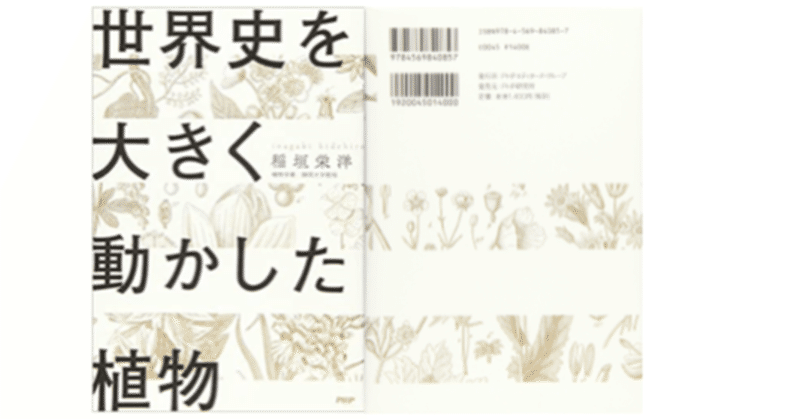
2020年で読んだ一番面白かった本『世界史を大きく動かした植物』
2020年に買った本は55冊で6万5千円ほど使いましたが、その中でも強烈に面白かった本がこの『世界史を大きく動かした植物』。
食べ物や飲み物の世界史の本を何冊も読みましたが、まず読むべきはこの一冊だと思います。
14の植物(小麦、稲、胡椒、唐辛子、ジャガイモ、トマト、綿、茶、サトウキビ、大豆、玉ねぎ、チューリップ、トウモロコシ、桜)を章立てで紹介しています。
一つの食べ物や飲み物の歴史で本一冊になっているものも多いので、14も取り上げていると内容が薄いのか?というと全くそんなことはなく、原産地・語源・伝播の経緯がまとめられていて、非常に面白いです。
14の植物の原産地、名前の由来、伝播の歴史、その植物が与えた食文化や産業・貿易への影響がまとめられているので、あまり考えずに口にしていたものの経緯や特徴が分かり、知的好奇心をくすぐられます。
そうなんだ!と思った文章を取り上げると膨大になってしまいますので、まず、日本の食文化の変遷について。
日本の食文化の変遷
日本食の基本は、米と大豆ですが、この組み合わせは三大栄養素である炭水化物・タンパク質・脂質がバランス良く取れます。稲は長江文明、大豆は黄河文明を代表する作物で、稲・大豆が来る前の日本の主なデンプン源は「Uri」と呼ばれ、クリ(Kuri)、クルミ(Kurumi)でした。
まず、東南アジア原産の里芋がやってきます。その後、稲作が弥生時代に、大豆が奈良時代にやってくるのです。
味噌は保存が効くため、軍事食品としても有効で、徳川家康の赤味噌、武田信玄の信州味噌、伊達政宗の仙台味噌と各地で発展。
江戸時代に鹿児島からアメリカに伝わり、薩摩弁の醤油を意味する「ソイ」から、大豆は英語でソイビーンと呼ばれるようになります。
世界恐慌でトウモロコシが供給過剰になり、代わりに大豆が植えられ、現在、アメリカが世界最大の大豆生産国になっています。アメリカでは大豆は食用せずに、ほとんどが家畜の餌と利用されています。
戦後のアメリカの農業政策によって、日本国内の大豆生産は縮小され、日本食の根幹を支える大豆の自給率は1割を下回っているのです。
日本では飛鳥時代に仏教を取り入れたことで、肉食が控えられていましたが、明治時代に肉食とともに、インカ文明を支えたジャガイモが普及します。
江戸時代に西日本に普及した、中米原産のサツマイモは甘くて日本食に取り入れられますが、ジャガイモは淡白なため、あまり普及しませんでした。
ところが肉との組み合わせはとてもいい。
肉とジャガイモを組み合わせたのが、肉じゃがであり、醤油・みりんなど日本の調味料の代わりにカレー粉を使うとカレーライスが作れます。
ジャガイモはビタミンCを含むため、船乗りの食品として重宝され、カレー粉を発明したイギリスはジャガイモを使ったカレーライスを海軍で食べていました。
日英同盟で関係があった日本海軍は、イギリス海軍の食事を導入し、日露戦争後にカレーライスが一般家庭にも普及していったのです。
産業革命と日本の自動車産業を生んだ綿
この本は飲食物以外の植物も取り上げているのが、また面白い点です。
インドの伝統産業は綿織物で、ガンジーが糸紡ぎの写真を見たことがある人も多いでしょう。
イギリスはインドを植民地にして、インドの綿布を手にすると、綿布が本国で爆発的な人気を博します。作れば作るほど売れる。さらに綿織物を作るために紡績機が発明され、これが産業革命の発端となります。
日本で綿が作られたのは、灌漑が不十分で稲作ができなかった愛知県三河地域。
綿は乾燥に強く、三河地域でも栽培ができました。
人力織機を発明したのが豊田自動織機を操業した豊田佐吉で、トヨタ自動車につながっていきます。
三河からほど近い浜松の織機メーカーは、その技術を利用して、オートバイや軽自動車を作り、現在のスズキになります。
古代文明を支えた作物
エジプト文明には大麦、メソポタミア文明には小麦、インダス文明・長江文明には稲、黄河文明には大豆、アステカ文明・マヤ文明にはトウモロコシ、インカ文明にはジャガイモがありました。
それぞれの作物の特徴や伝播した経緯については本を読んでいただけたらと思いますが、この中でも世界1位の生産高を誇る作物トウモロコシに関する逸話が興味深いです。
他の作物と異なり、トウモロコシには明確な先祖種である野生植物がないそうです。
トウモロコシの原産地に栄えたマヤ文明の伝説では、人間はトウモロコシから作られたとされています。神々がトウモコロシを練って、人間を創造したと言われています。トウモロコシには黄色や白だけでなく、紫色や黒色、橙色など様々な色があります。そのため、トウモロコシから作られた人間も様々な肌の色を持っているのだというのです。
しかし、伝説とだけ言えるのではないのが面白い点です。
トウモロコシは様々な加工食品や工業品の原料となっており、コーン油、コーンスターチ、かまぼこ、ビール、チューインガム、スナック菓子、栄養ドリンク、コーラ、特定保険用食品などに使われる難消化性デキストリンなど。一説による、人間の体のおよそ半分はトウモロコシから作られているのではないか言われるほどだそうです。
トウモコロシの語源は、日本と中国の関係を知る上で興味深いですが、これは是非、本書をご覧ください。
農業は自然豊かな場所に発展するのか?
世界的に作られている作物の原産地と古代文明が栄えた場所は重なります。
さて、農業は自然豊かなところで発展するのか?それとも豊かでないところで発展するのでしょうか?
答えは豊かでないところで発展すると言います。
農業は自然の貧しいところが発展する。
農業は重労働です。農業をしなくても暮らせるのであれば、その方が良いに決まっているといいます。自然が豊かで、森の果実や海の魚が豊富にとれるのであれば、何も農業などしなくても生きていけるのです。
一方で、自然の貧しいところでは、農業を行うことで安定的に食べ物を得ることができるようになります。そのため、人々は働くのです。
笑い話がある。
南の島で人々はのんびりと暮らしている。外国からやってきたビジネスパーソンが、それを見て、どうしてもっと働いて稼がないのかと尋ねる。そんなに稼いでどうするんだと問う住民に、ビジネスパーソンはこう答える。「南の島で、のんびり暮らすよ」。それを聞いた島の人々はこう言うのだ。「それなら、もうとっくにやっている」。
食用とされなかったトマト
世界1位の生産高の作物はトウモコロコシ、2位は小麦、3位は稲、4位はジャガイモ、5位は大豆。穀物が並ぶ中、6位はトマト!
しかし、トマトの原産地はジャガイモと同じアンデス山脈原産ですが、現地では食用されておらず、トマトを持ち帰ったヨーロッパでもしばらく食べられていませんでした。
トマトを食用としたのはイタリアのナポリ王国。一説では、飢饉がおこり、仕方なくトマトを食べたといいます。
ナボリはスパゲティの大量生産を確立させ、ピザの発祥地としても知られますが、ピザも元々は貧しい人々が小麦粉で作った生地にトマトをのせた食べたことに由来するそうエス。
ケチャップは、元をたどれば古代中国で作られていた「茄醬(ケツイアプ)」という魚醬だったと言われています。これが東南アジアに伝えられて「ケチャップ」と呼ばれるようになり、アジアでケチャップを知ったヨーロッパ人がアメリカに移住して、現地で豊富に取れたトマトでケチャップを作ったのがトマトケチャップです。
フルーツとは植物の果実ことですが、トマト、ナス、キュウリは植物の果実であり、分類上はフルーツです。
植物の果実以外をベジタブルと呼んだそうですが、アメリカで野菜に関税がかけられた際に、トマトはフルーツなのか野菜なのか論争があったそうです。
ちなみに、日本語の果物は「木の物」という言葉に由来し、日本の農林水産省では、木本性の植物を果物、草本性の植物を野菜と言うため、トマトは野菜です。
まとめ
面白いと思った内容の中から削って削って、頭に残っていることを書いてみましたが、それでも長くなってしまいました。
身近なものの歴史を知るのは非常に楽しいです。
また、よく昔から食べてきたものを大事にしよう!とも言われますが、各食品がいつ日本にやってきたのかを知り、世界での作物の伝播の流れを知ると、もう少し冷静に考えられそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
