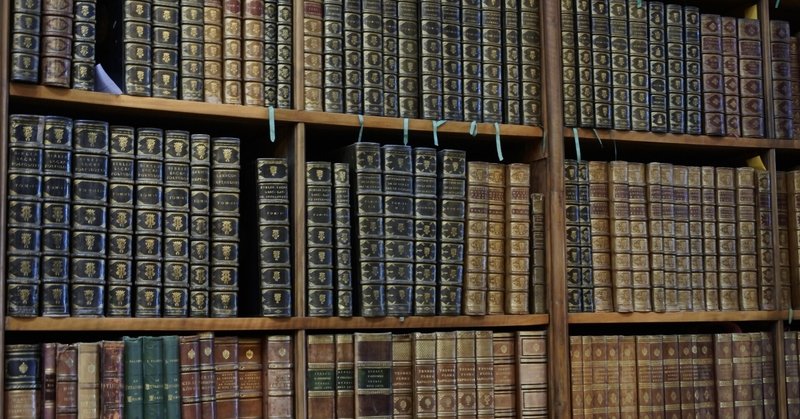
世田谷文学館さんで、ちょっとだけ本屋さんになってみた話(もしくは「時をかける本屋」渾身の10冊)
はじめに(本屋さんになってみた)
今秋、東京の世田谷文学館で、架空の本屋を考えるワークショップが開催されました。しかも、選んだ10冊の本は実際に文学館に並べて販売とのこと。
【募集開始!】
— 世田谷文学館 (@SETABUN) August 27, 2021
〈3日間のワークショップ「ひと箱本屋のつくりかた」〉
参加者それぞれが架空の本屋を考えるワークショップ。
1・2日目はオンライン、3日目のみ文学館で実施します。
・10月2日(土)・23日(土)・11月13日(土)
・抽選10名
・参加費無料
申込はこちらから↓https://t.co/fwgPiZBbRp pic.twitter.com/mm0lm5X3au
もともと本も本屋さんも好きなボクは、早速申し込んで受講。色々と自分の好きなものを見つめ直した末、
「時をかける本屋 ~四半世紀を振り返る~」
という本屋をオープンさせることにしました。
何せ貴重な体験だったことと、販売ブースに添えられるPOPには書ききれない思いも出てきそうなので、どういうコンセプトで、実際どんな本を選んだのかを、ここに記録しておきます。
……あ、なお同施設の一画で実際に販売はされます(2021/11/20~12/19)が、売上その他は一切ボクの元には入りませんので、あしからず(笑)。
コンセプト(ボクが「25年」を好きな理由)
講座の初日に先駆け「どんな本屋をつくりたいか考えてね」という宿題が出ました。色々悩んだ末に「時の流れをしみじみと感じる本屋」ということで「時をかける本屋」ということにしました。
(店名はなかなか決まらず、当初の仮案のままの提出でしたが、逆に「わかりやすい」と好評でした)
ただ「タイムトラベル本を集めた本屋さんは既にあるので、もう少し詰めたほうがいいよ」とのアドバイスが。ふむふむ。
あれこれ悩んでいくさなか、世田谷文学館さんのスケジュールページを見ると、ちょうど本屋がオープンの期間に「開館25周年記念」を謳ったコレクション展が開催されることを知りました。
おおー!
実は、ボクは「25年」というキーワードが大好きで。
多分、小学生の頃に読んだ小説『二十四の瞳』の冒頭の一節(十年をひと昔というならば、この物語の発端は今からふた昔半もまえのことになる)が好きだったり、その後「四半世紀」というカッコいい表現があることを知ったり。
クイズ作家兼クイズマスターという職業についてからも、25年前のことだけのクイズを開いたりするようになったり(こういうイベントや、こういうイベントなど)。
あらためて、世田谷文学館さんに確認したところ、開館日が「1995年4月1日」で、去年コロナ禍があったとはいえ、25周年を謳うのは間違いないとのこと。
よっしゃ。じゃあ、自分の中であらためて「25年」というキーワードに向き合いつつ、本を選んでみようと思ったのでありました。
「時をかける本屋」の10冊のコンセプト
では、あらためて選んだ本と、その理由をば。
まず「過去に話題となった本を時系列に並べたものは、眺めるだけでも面白い」という自信がありました。
とはいえ、今回置ける本は10冊のみ。
というわけで、5年おきにタイムスリップをしてみることにしました。これで、1995、2000、2005、2010、2015、2020で6冊。
加えて、他に「時をかける」要素のある本も集めてみました。しかし、集めていくと、結構この「1995年」もしくは「25年」というキーワードと相関が高い本を見つけることができました(中には、僕が大好きだったタイムトラベル物語の中に、25年という年月が深く関わっていたものも。。。)。
と、本来ならば世田谷文学館さん内にある「時をかける本屋」に行って、眺めつつ買って頂きたいところなのですが、文学館さんから公開許可が出ましたので、特別に公開。
1995年に建てられた同館の25周年を祝うと共に、その様々なポイントとなるタイムトラベルを、「本」の世界からお楽しみくださいませ!(もしお近くで現地に来られる人は是非ご来館をば)。
1冊目:1995年の本
『パラサイト・イヴ』(瀬名秀明)
その後の『リング』などの新たな日本のホラー文学(Jホラー)の記念碑的な作品でもあり、「ヒトゲノム計画」など当時時代の先端だった遺伝子などのキーワードもある小説です(1997年に三上博史・葉月里緒菜の主演で映画化)。
しかし、何よりもポイントなのは、「刊行日が1995年4月1日で、世田谷文学館とまったく同じ誕生日」という点。
また同じく当時の話題本『FBI心理分析官』(プロファイリングの分野を説明)も同じ誕生日で悩んだのですが、こちらをチョイス。
その他の1995年本の候補には、『魍魎の匣』『ソフィーの世界』『残像に口紅を(文庫版)』『小説 金田一少年の事件簿 幽霊客船殺人事件』もあったのですが、この同じ誕生日のインパクトにはおよびませんでした(とは言え、この後また別の1995年本も並ぶことになるのですが、それはまた改めて)
2冊目:2000年の本
『話を聞かない男、地図が読めない女』(アラン・ピーズ バーバラ・ピーズ)
ちょうど今年(2021年)は「ジェンダー平等」が強く推されていますが、男女間の差について論じた本を。読んだことは無くても、タイトルに聞き覚えある人は多いのでは?
そして、この本の発売日は2000年4月1日で、丸5年の誕生日本となるのです。すばらしい!(ただし、この後の年も4月1日発売本を探したのですが見つからず、ここまで)
他の2000年本の候補は、同じく4月1日発売だったのが『経済ってそういうことだったのか会議』(佐藤雅彦・竹中平蔵)。この20年間の竹中さんの功罪は色々語りたいけど政治色が強いので省略(笑)。
また、別の角度からの候補として、『プラトニック・セックス』(飯島愛)もありました。いや、こちらこそ功罪色々かもしれませんが、飯島愛って本当平成という時代の要所要所で特徴的だった女性だと思うのです。夭折が惜しまれる。
3冊目:2005年の本
『容疑者Xの献身』(東野圭吾)
今や人気作家の東野圭吾センセ。個人的には2000年頃までは「手堅く面白い本格推理小説から冒険要素・社会派要素のあるものまで書いているが、大ヒットとまではいかない」イメージでした(失礼!)。しかし、ガリレオシリーズの映像化、そして本作による直木賞受賞で見事に花開く(この受賞会見時のコメントが少し皮肉交じりな感じもあってとても好き)。
2008年の映画化では、ドラマ版の福山雅治・柴咲コウコンビに加え、堤真一の犯人役も実にいい味を出していました。
一部のミステリ好きの間ではトリックについても色々話題となっていましたが、「幾何の問題と見せかけて、じつは関数の問題」というフレーズに象徴される物語に、個人的には「やられたっ!」感が満載でした(そして、何よりほろ苦い結末よ)。
他の2005年本の候補は多く、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』、『1リットルの涙』(幻冬舎文庫版の刊行)、『わたしを離さないで』(カズオ・イシグロの英国での刊行)、『国家の品格』(藤原正彦)、『ナラタージュ』(島本理生)、『半島を出よ』(村上龍)、『決断力』(羽生善治)、『ベルカ、吠えないのか?』(古川日出男)、『私の奴隷になりなさい』、『すごい会議-短期間で会社が劇的に変わる!』などなど。
その中でもイチ推しだったのは『生協の白石さん』だったのですが、今は入手困難のためNGとのこと。うー、無念。ひさしぶりに、あのひとことカードの心がほっこりするQ&Aを読みたかったなあ。
4冊目:2010年の本
『桐島、部活やめるってよ』(朝井リョウ)
青春小説の傑作。これこそ、読んだことは無くても「(苗字)、◯◯ってよ」というフレーズは一斉を風靡し、今でも目にします。
僕は実際「スクールカースト」あるいは「中学イケてない芸人」などの言葉が特に無かった時代に学生生活を過ごしました。ですが、もしこれらの言語化があったら、きっと「自分の居場所」を当てはめていたんだろうなあと、良くも悪くも考えます。
2012年に映画化されましたが、こちらは輪をかけての大傑作。主演の神木隆之介・彼が恋焦がれる橋本愛はもちろん、松岡茉優・仲野太賀・山本美月・前野朋哉など、大勢の学生の中には今活躍する人も多数。それぞれの若者がそれぞれの青春と悩みを、それも派手なことがあるわけではなかったりもする中で生きているんだなあと感じさせられます。
他の2010年本で最後まで迷ったのは、ハーバード白熱授業のサンデル教授による『これからの「正義」の話をしよう』。その他『1Q84』(Book3 村上春樹)、『ゴールデンスランバー』(文庫版 伊坂幸太郎)、『民王』(池井戸潤)、『謎解きはディナーのあとで』(東川篤哉)、『超訳 ニーチェの言葉』、『KAGEROU』(齋藤智裕=水嶋ヒロ)などがありました。
5冊目:2015年の本
『君の膵臓をたべたい』(住野よる)
恋愛小説。実はボツ案の1つとして、時代を彩った同ジャンルの物語を並べるといったものがあり、先程の『1リットルの涙』(小説ではなくて実話。1986年刊)や『世界の中心で、愛をさけぶ』(2001年刊)を並べると、また時代背景も見えて興味深いかなとか考えていました。
これも『桐島…』同様、読んだことなくてもタイトルは知ってる読書好きのかたは多いんじゃないでしょうか。
実写&アニメで映画化されており、特に実写映画版は「高校教師になった主人公が、高校時代の恋愛を思い出す」という原作にはない物語が付与されており、「時をかける」(いやタイムトラベルはしないけどね)要素があってジーンと来ます。
他の2010年本で最後まで迷ったのは、又吉直樹の『火花』。その他、『ナイルパーチの女子会』(柚木麻子)、『家族という病』がありました。
6冊目:2020年の、そして時をかける本
『四畳半タイムマシンブルース』(森見登美彦)
そして2020年ですが、ついこないだのことなので象徴するような本が思い浮かばず、悩むことしばし。そんな中で、ついに見つけたのが『四畳半神話大系』の森見登美彦センセの最新刊。
タイムトラベル好きの僕は、ヨーロッパ企画による演劇『サマータイムマシン・ブルース』が大好きでして。これはタイムトラベルものの作品の中での傑作、さらに2005年の映画版は夏の終わりに見たくなる青春映画の大傑作だと思っています(監督・本広克行。瑛太、上野樹里の他、当時はまだ無名だった真木よう子やムロツヨシも光ってる)。
閑話休題。この本は、京都を舞台にした森見センセの作品と、同じく京都を拠点のヨーロッパ企画とのまさかのコラボ(私事ながら、大学が京都だった自分としてはテンションMAX)。そして小説の中には「未来人」が出てくるのですが、これがなんと「25年後の未来」から来たという!
いやー、これに気づいた瞬間、今回の「四半世紀を振り返る本屋」としては、絶対に置かないといけない本だなと気づきました(笑)。
7冊目:1995年と2020年の本
『後ハッピーマニア』(安野モヨコ)
安野モヨコの恋愛追求漫画『ハッピー・マニア』は、1995年に連載スタート。稲森いずみ・藤原紀香らの出演で1998年にドラマ化もされた人気作です。世田谷文学館と同じ1995年に生まれたということで、まずアリだなぁと。
で、なんと今、その続編が約四半世紀を経て、また描かれている!
こんなにエモいことはない!!
というわけで、加えさせて頂きました。
20代だった登場人物らが40代半ばとなったことによる時の流れに加え、社会や恋愛価値観などの変化が、同じ作者の同じマンガということで、より立体的に浮かび上がると思います。
8冊目:1995年がわかる本
『1995年』(速水健朗・ちくま新書)
よくよく考えると、ボクにとっては生きた時代でもあるので「1995年」というキーワードを普通に使っていましたが、人によっては思い入れが薄い、記憶がない、そもそも生まれていないなどあるよなぁと。
何か体系的にこの時代を語った本ってあるかなぁ、と調べていたら発見。
……と、実はこの本は全く読んでいません。ただ出版社のサイトを見るに、震災・オウム・Windows95・社会党政権などのキーワードは押さえつつ、「1995年は転機であった」という主張には納得するものがあったのでチョイス(また、これまで選んだのが文芸寄りだったので、少し新書を入れたかったという思いもあった)。
何よりも『1995年』というタイトルが、そのままズバリで印象的にもなるかなぁと。
9冊目:1995年の、そして時をかける本
『スキップ』(北村薫)
タイムトラベル作品大好きのボクが、特におすすめの小説。引っ越しで紛失するまでは、年に1度は読み返していました。
主人公は17歳の女子高生・真理子で、舞台は昭和40年代のはじめ(「シャボン玉ホリデー」などの描写もあり)。ある日うとうと居眠りをしていたら……
……いきなり長い年月をスキップして、夫と17歳の娘がいる42歳の国語教師になっていました! しかも体は(年を経た)自分自身。
当然パニックにもなりますし、単に記憶喪失ではないかとも思われます。ただ幸いなことに「家族(もちろん結婚した記憶も出産した記憶もないのですが)」は半信半疑ながらも信じてくれて、真理子も一歩一歩自分の人生を進みだしていきます(これまたスキップ)。
実際の物語については、ぜひ本を読んで欲しいのです(本が手元にないけど、思い出せるだけでも、「片栗粉」という言葉、女子生徒のニコリの質問への解答、文化祭のクイズでのやらせのくだり、バレーボールのジュース、「答は簡単だったかなー?」、人工衛星型洗濯機など、好きなシーンが多数)。
一旦選書理由に戻ると、まず彼女がスキップした年月というのが、「17歳の女子高生」から「42歳の国語教師」なので、42マイナス17で、なんとこれが25年!
そして、昭和40年代のはじめから「現在」に来るのですが、この『スキップ』が刊行された現在はいつかといいますと……なんとこれが1995年。
自分の大好きな本が、今回のテーマにここまでピッタリだったなんて! というわけで、これは外すわけにはいきませんでした。
そして、それ以上に「25年という年月をスキップ」させられてしまった主人公の真理子の健気なこと!
(ネタバレになりますが一応申し上げますと、どういう理由で彼女が時間をスキップしたのかという理由は一切不明のまま終わります)
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のように、自分の体そのままでタイムトラベルをするのではなく、ある時気付いたら25年経っていて、その間の記憶は全くないのに加齢による体の衰えなどは感じる、さらにはその間に亡くなって会えなくなった人もいる。
もし自分が真理子と同じ状況になったら(ましてや17歳という青春真っ只中で)、絶望で終わりそうです。しかし、彼女はこの時代で生きていこうとし、全く記憶がないのに国語教師役を見事に勤め上げます(そのための家族での作戦会議シーンも面白い)。
「25年」という時の重みを感じさせる、と同時に、その重みすらもスキップすることができる「人の素敵さ」を味わえる、まさに「時と人」の名作だと思うのです。
10冊目:トータルで、25年の時の流れを感じさせる本
『平成クロスワード』
最後はトータルで感じさせる本を選択。
歴史の教科書だったり、「平成」の時代を包括的にまとめた本なども考えたのですが、変化球的にこちらをチョイス。
パズル制作会社のニコリによるタイトルの通り「クロスワードパズル」の本。平成元年から31年までの順番に31の章があり、各章基本は全4ページ。見開き2ページの大きなクロスワードと、同じく2ページの解説やその年の出来事紹介とで構成されています。
というわけで、ペラペラとめくって眺めるだけでも楽しいのですが、凝っているのは各年のクロスワードのカギのヒントの多くはその年にまつわるものになっている点。
例えば「平成5年(1993年)」のクロスワードのヒントは、
・寒天のような見た目とコリコリの食感で人気のフィリピンの食べ物
・柴門ふみ原作で、石田ひかり、筒井道隆主演のドラマ『◯◯◯◯白書』
・1月、東京の石神井で矢が刺さった状態で発見され、大きく話題となった鳥
なんてのがあります(より具体的にはコチラ)。
当時を生きた人には「懐かしい!」、知らない人でも「何か聞いたことある、この時期だったのね」と感じることができるんじゃないかなぁと。ですので、単なる歴史年表よりも楽しめるし(例えば「イチロー」はクロスワード内に何度か登場しますが、色々と出来事が違います)、本のジャンルとしてもパズル本は素敵じゃないかと思う次第です。
そうそう、あともう1つ大事な理由。
実はワタクシもこの本の制作に関わっています(笑。上述の平成5年と平成4年のクロスワードを作成しました)。というわけで、キッチリと宣伝でありました。えへへ。
最後に
今この文章を書いているのは、11月11日。あさってがワークショップ最終日かつ初の対面講座です(過去2回の講座はリモートだった)。実際に、世田谷文学館さんに行き、取り寄せて頂いた本を並べて、POP広告を付けて売れる状態にします(実際の販売は、11/20土曜からの一ヶ月間)。
さてはて、興味をもって手に取ってくれるお客様はいらっしゃるのでしょうか。
そして、実際に売れるのでしょうか?
いろいろと楽しみです。
そして、せっかくなので、この文章の一部をPOPに載せたり、あるいはここへのリンクのQRコードを装飾に入れようと思っています(お越し頂いたかた、ありがとうございます)。
あ、ちなみに販売終了となる12/19日曜は、僕の誕生日であります(笑)。
PS.ついでに宣伝
ちなみに当方、パズルの制作に加えて、実際に自らの著書もございます。
(本当はそれも並びたかったけど、さすがにタイムトラベルとは関係がなくって……笑)。
複数冊ございますので、よろしければ刊行元である主婦の友社さんのサイトでご確認をば。
さらに、今年2021年の夏~秋には、電子書籍限定となるパズル・クイズ本を3冊連続で刊行しています(主要電子書籍サイトにて販売中。ここではAmazonへのリンクをペタリ)。
・親子で楽しめる ことば遊びパズル モジトレ
・地頭をキレキレにする 次世代ビジネスパーソンになるクイズ
・脳をアップデートさせる! 京大式ひらめき発想クイズ
こちらも、ご興味あるかたは是非ポチッと。特に1冊目の「モジトレ」は、親子と謳っているとおり幼児向けではありますが、大人でも歯が立たないときもあるパズルが全140問近く掲載。コスパもよくてオススメです。
というわけで、本を出す著者&編集者さんの苦労などは重々承知していましたが、本屋さんは本屋さんで色々な苦労があるんだなぁと。同時に、本屋さんになることは、単にモノとしての本を売るだけでなく、こんなに世界観や共感体験を伝える場でもあるんだなぁと感じたワークショップだったのでありました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
