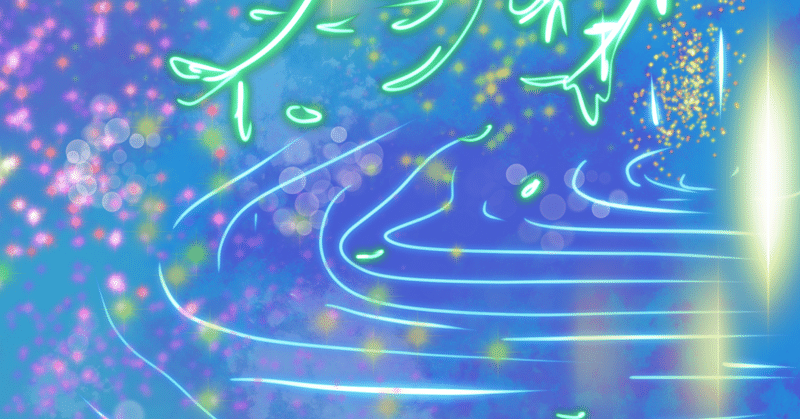
俳句と三弦の共鳴
いま『20週俳句入門』を読みながら、句作に取り組んでいます。
そんな中での自分の気づき。
まず経過。
本全体通読:9/26~10/2
句の暗誦:9/29~
20週開始:10/1~

暗誦は、英単語で培った記憶要領(忘却曲線に沿って)に基づいて。

記憶力の悪い私は、3日間連続でやって復習するスタイルです。
①3日間連続(朝・昼・晩)
⇩
②一週間後復習
⇩
③一ヶ月後復習
一日の中でも、朝・昼・晩やった時とやらなかった時ではその後の覚えも違いました。
好きな句はそれと関係なくすぐ覚えられるけど。
人間の意識って結構影響しますね。
さて、
本題の気づき。
実作編に入り、目次でいうところの「第8週」「第9週」をこなし、いまは「第10週」の実作をしています。
「第8週」は【型その1】で句作。
ちなみに「第9週」も【型その1】で句作するので、約二週間かけてひたすら【型その1】に専念する流れになっています。
【型その1】は簡単な構造
上五(季語(名詞)+や)
中七
下五(名詞止め)
正直、いくつか作ると飽きてくる。
自分はもっと難しい型で作れるようになりたいんだ! なんて思ったりもします。
んがしかしっ!
わざわざ二週間もこの型に専念するようにこの本は構成されています。
そして本書の中でも
この〔型・その1〕は、〔四つの型〕の中でも一番の基本型とも言うべきもので、もっとも俳句らしい型、俳句の原型と言ってもいいほどのものである。
~中略~
五十句でも百句でも、撤退してこの型で作る。イヤというほど作ってみることをすすめたい。
と書き記されている。
俳句の本質がここにあるのかもしれない。
と「第8週」を何度も読み返しながら、歳時記※を読み、句を作ってみた。
型1は、とてもシンプルなカタチ。
だからこそ取り合わせと言われる効果が分かってきた。
それは
季語と取り合わせた名詞の響き合い。
取り合わせは二物衝撃とも言われるけれど、
私としては「共鳴」という表現の方がしっくりくる。
例えばこの句(実作に際して、歳時記から同じ型の句を抜き出してメモしています。その中のひとつ)
団栗や似て声たかき母と妻 白岩三郎
分かりやすい!
団栗といえば、思い浮かべるのが団栗の背比べ。
似ているものの比喩に使われる言葉。
そこに母と妻を取り合わせる面白さ。
きっと、親と同居している作者。妻が母親と仲良しで、女ふたりで楽し気におしゃべりをしているところを見て、似ているなあと思って詠んだんだろう、なんて妄想してしまいました。
そして、この句も
朝寒やからくれなゐの唐辛子 村上鬼城
寒さと唐辛子の組み合わせ(寒さと身体を温める食べ物)と、なんといっても「からくれなゐ」の色彩が好き。
寒さは色で表現するなら青、そこに鮮やかなつやつやの深紅の色。
こんなふうにして、俳句の五七五が響き合っている。
「共鳴」というイメージでまず思い浮かべたのが、三味線。
(これは漫画『ましろのおと』を読んでいる影響)
三味線は三本の糸の共鳴で音に深みが増すようです。




https://gmaga.co/c/mashironooto/
俳句も五・七・五という言わば三本の弦(韻律)から構成される作品。
それぞれ、
五音の言葉
七音の言葉
五音の言葉
が響き合い共鳴し、その句の世界を作り出す。
なんだか、共通するものを感じ、三味線の三弦が共鳴し深い音を奏でることを考えると、俳句で五七五を共鳴させて世界を作り出すことのイメージがつかみやすい気がする。
そして、
それに気づいてから、プレバトを見ると
夏井先生は「季語〇〇と〇〇の取り合わせの是非!」とよく仰っている。
そして「響き合っている」という表現も。
やっぱり共鳴が大事!
ということを自分なりに発見した「第8週」「第9週」でした。
気づいたものの、実際に句に反映させようとしてもなかなか難しい。
実作で行き詰って、二週間経たないうちに「第10週」型1の応用をやってしまっている私ですがw
(先に進んで分かることもあるさ~ナンクルナイサ~)
そうは言っても、型1も作り続けていますよ(言い訳😋)
目指せ月30句!
現在(10/22)、10月分は33句で目標達成していました🎊
°˖✧◝(^▿^)◜✧˖°
余談
※歳時記、やっと買いました!
(準備編読んだら、やっぱり1冊は用意しないと、という気にf;^^)
紙本が欲しかったんですが検討の結果、普段から利用しているBookLiveで30%クーポンもらったタイミングで電子本をゲット♪
電子本のいいところは、スマホにアプリいれておけば思い立った時に気軽に読める。
文字検索できるので、気になる言葉を検索欄に入力すれば本の中のその言葉のページに飛んでくれる。
こちらの本は一年間の季語1800語が載っていて、他の歳時記に比べたら少ないですが、一日一句作ったとして、全部の季語を使うのは5~6年かかると思えばまずはこの量でいいかな、と。
でも決めてはなんといっても水原秋桜子の解説!
例えば
立春
春立つ 春来る 寒明け
陽暦では二月の四日または五日。すなわち節分の翌日である。
外界は昨日までの冬とさして変わりはないはずだが、立春と聞くだけで心に春が宿るのであろうか、あらゆるものを明るい気持で眺められるようになる。
陰暦では大体新年と一致するので、新年と春とを一度に迎えた古人の喜びはいかばかりかと思われるが、現代でも長い冬から解放される第一歩として、その喜びをうたわずにいられないところであろう。
句を詠む上にもそいういう気持をこめることが大切であって、明るくかつ引締まって力強くなければならない。
こういう解説なら季語と仲良くなれそう!(あくまで主観)
また、この本は作句するときに参考になるように考慮されています。
「また、作句の要領を随所に述べて、すぐにも詠んでみたい気持をおこさせる」
このように、序で水原秋桜子自身が語っている通り、この歳時記を読むとそれを感じます。
そして、なにより自分が読んでワクワクしたのがポイント✨
初めての歳時記とは仲良くやっていけそうです^^
おまけ
津軽三味線のおすすめYouTube。
めちゃくちゃカッコいい(≧▽≦)
これぞ日本のブルース!
『ましろのおと』はアニメ化されていて、作品中で津軽三味線が聴けます。
Amazonプライム会員なら追加料金なし。(2022/10/22現在)
漫画『ましろのおと』は最終巻(31)発売中!
とうとう終わってしまいました(TT)
あらすじ
津軽三味線を背負い、単身、青森から東京へやってきた津軽三味線奏者・澤村雪。師でもあった祖父を亡くし、自分の弾くべき音を見失ってしまった雪だが、様々な人々と出逢いながら今、自らの音を探す旅を始める。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
