
人生100年時代の逝き方・見送り方~在宅死の看取り~
**発売中(2018夏号)の「編集会議」の後半部分に、宣伝会議がおこなっている「編集ライター養成講座」の最優秀作品が掲載されています。
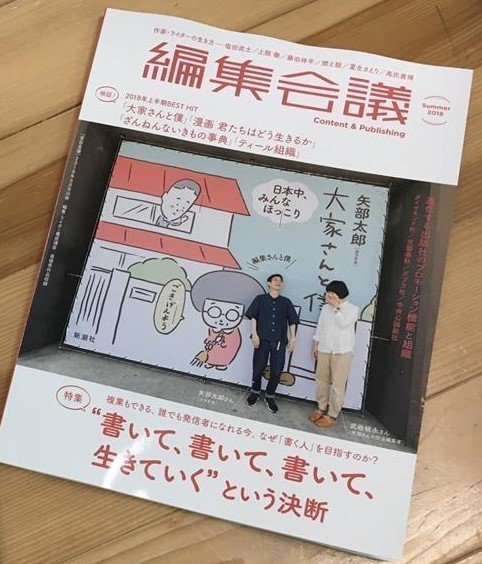
そこに、わたしが去年金沢教室で受講した際に受賞した作品も掲載されているのですが、このnoteでも全文公開することにしました。「6,000文字程度の取材記事」という課題を講座の卒業制作として出したものです。
「note」では、文字数は1,500文字くらいのものがよく読まれる傾向があるらしいので躊躇していましたが、雑誌だけでなくWEB上でも一人でも多くの方に読んでいただきたいので長文ですが公開しています。**
超高齢社会を迎えた日本では、今後「在宅死」がこれまでよりも一般的になると考えられる。
そこで、2017年9月に夫を自宅で看取った富山市の松尾三代子さん(72歳)と、訪問医療の現場をよく知る「富山市まちなか診療所」の渡辺史子医師(38歳)に、在宅死の現状を聞いた。
私たちが家族のために、また自分が当事者になったときのために、後悔しない「在宅死」を迎えるためのヒントを探すために。
「家に帰りたい!」 末期がんの夫の最期の願い
「夫は私のことを、まるで子どものように思っていたんですよ」
小柄で柔和な三代子さんは、そう言って微笑み、亡き夫の勲さんについて語りだした。勲さんは、彼女より30㎝も身長が高く、亡き父親に似て、優しく思いやりに溢れた人だったという。
そんな愛妻家の勲さんが亡くなったのは72歳。スキーのインストラクターの資格を持つスポーツマンで、ゴルフも週に数回行き、退職後も精力的に活動していたという。
2016年4月のある朝のこと。
夫の勲さんが日課となっていたゴミ出しをしようと、ゴミ袋の口をしばろうとしたとき、右肩に激痛が走った。痛みを何とか我慢し、総合病院へ着くと、まず整形外科に走り、診断を仰いだ。そこでわかったのは、ガンが骨まで転移し、骨がもろくなっていたこと。内科で精密検査をした結果、進行性の小細胞肺癌で、余命半年の宣告を受けた。
その後、勲さんは入退院を繰り返しながら、抗がん剤治療に励んだ。三代子さんの懸命なサポートもあり、余命半年の宣告から、一年が経過。放射線治療にも挑戦するが、ガンの進行は止められず、医師から緩和ケア病棟へ移ってはどうかと勧められた。
三代子さんは、それが夫の最期を意味しているように聞こえた。
「ちょうど、その緩和ケア病棟ができたばかりで、今いる病室よりもキレイなのは間違いない。だけど、主人がそこに移るということは、死ぬ準備をしなさいと言われているようで、すぐに返事ができなかった」
そんな三代子さんの気持ちを慮ってか、医師は「死を待つところではないよ」と優しく話し、今の病室よりも静かで広く、快適な場所で過ごすことができると伝えた。
緩和ケア病棟へ移り、一ヶ月が経とうとしていたある日、医師から「もし家に帰りたいんだったら、帰ってもいいよ」と声をかけられた。すると、勲さんの態度が急変していく。
「いつも穏やかで優しい主人が、『家に帰る!すぐに帰るんだ』と興奮しちゃって、手がつけられないようになったんです。それまでは、優しく接していた看護師さんたちにまで、『(私と)二人きりにしてくれ!』と言い放って、部屋に入れないようにわがままを言いだしたんですよ」
医師の許しを得たことにより、これまで抑えていた「家に帰りたい」という気持ちが爆発したようだった、と三代子さんは振り返る。
「抗がん剤治療をしていたときには、退院してもいいのに、自分が家に帰っては私が休めないだろうからと、先生に入院をお願いしていたくらい優しい人なんです。それなのにそのときは、病気の進行でせん妄状態だったのも手伝って、『家に帰るんだ』と言ってきかない。
寝間着も脱いで、いつでも家に帰れるようにと服に着替え、その状態で三日間、病室で過ごしていたんですよ」
夫の強い気持ちに動かされ、三代子さんも在宅で医療を受けられるよう準備をしていく。
まずは、地域包括支援センターに相談した。「すぐに準備します」と、介護用ベッドなどの手配をし、在宅でケアできる体制を整えてくれた。段差がある部屋やトイレには、ポールを取り付けてもらい、弱った足腰でも家で過ごせるような準備が、数日のうちに行われた。
子供がいない松尾さん夫妻。一人で夫を看ていく不安はなかったのだろうか。
「不安というのは、それほどなかったですね。ケアマネジャーさんがいろいろ手はずを整えてくださいましたし、先生方にも、いつでも連絡してくださいって言われていましたから。
遠方の主人の姉弟も、私が一人で主人を自宅で看ることについては、『そんな無理しなくていいよ。兄貴を病院に入れてくれていいんだよ』と心配してくれました。でも、主人があんなに帰りたがったから、もう病院に連れて行く気はなかったですね」
訪問診療の体制と多職種間の連携がしっかりと整っていたことも、三代子さんの不安を打ち消してくれた。

<富山市まちなか診療所の渡辺史子医師>
勲さんが在宅生活にかわってから、訪問診療をし、看取りにも立ち会ったのが、家庭医療専門医でもある渡辺医師だった。渡辺氏は、早稲田大学人間科学部で文化人類学を専攻し、卒業後に医師の道を目指した。文系から理系に転向し、医師を目指した彼女のような経歴の持ち主は、医師としてはめずらしい。しかし、人間を相手にし、その人の背景を探る「文脈を読む力」が重要になる家庭医療の分野では、彼女のように文系からの転向が少なくない。
渡辺医師によると、病院からの紹介、ケアマネジャーからの相談等から、終末期患者の訪問診療に入ることが多いという。
患者の退院時には、診療所の医師と看護師が病院に行き、情報の共有と、今後の療養についての話し合いが綿密に行われる。医療者同士が専門の話をしている間は、診療所のソーシャルワーカーが患者と家族の今後の生活についての相談を受け、家族に寄り添う。
家で過ごす余生
勲さんが家に帰ってからは、毎日のようにいろんな人が、日曜、祭日関係なくお見舞いに来てくれた。来客と一緒にコーヒーとケーキを食べながら、楽しそうにしている三代子さんを見ているのが、勲さんには嬉しかったようだ。
「訪問看護ステーションの看護師さんたちも毎日訪問してくれたので、安心でしたよ。渡辺先生も看護師さんと一緒に、週に二回診てくださっていたし。ケアマネジャーさんや、お医者さんから処方が出たときには、薬剤師さんも薬を持ってこられました。
みなさん、若い方たちばかりだから、主人はまるで自分の子供が家に来たみたいに、嬉しそうに話していましたね」
ときには、少量だが晩酌も交わす日もあったそうだ。だが、次第に飲めない日が増え、ジュースなど他の飲み物で代用した。

<真ん中・松尾勲さん。自宅にて、看護師さんと一緒にジュースで乾杯!>
「家に帰ってからは、いつもそばにいないと不安がっていましたね。お風呂に入っていて私の顔が見えないと、大きな声で私の名を呼び、『ここにいるわよ』と顔を見せると、ニコッとして(笑)。ホッとするんでしょうね」
これまでの人生で頼りになる存在だった夫が、家で過ごした最期の一ヶ月間は、「かわいい人」になっていた。

<在宅での勲さんと三代子さんを囲んで。渡辺医師と看護師たち>
元気になっていきそうに感じるときもあれば、逆に食事もしたくないというときもあって、そんなときは不安になる。夫の体調の波に、三代子さんの気持ちも揺れ動く、その繰り返しの日々でもあった。
食事がまったくとれなくなったのは、亡くなる二日前。渡辺医師からは「いつでも、何時でも良いから、心配なことがあったら連絡してください」と言われていた。それまではベッドの横に布団を敷いて寝ていた三代子さんだが、翌晩は、「もし寝ているときに何かあったら…」と思うと不安で眠れず、部屋の電気もつけたままにし、一夜を明かす。
朝の5時を過ぎて、訪問看護ステーションに連絡をすると、一人、また一人と看護師が駆けつけた。渡辺医師も駆けつけ、聴診器を勲さんの胸にあてる。その後は、しばらく大きな変化がなかったので、三代子さんは皆にコーヒーを振る舞った。
コーヒーカップを洗うため、隣の台所で洗い物をしていると、「奥さん、奥さん」と呼ばれ、「えっ!」と飛んで出た。
「もう、危ないかもしれない」
渡辺医師の言葉を聞き、三代子さんは夫のそばへ行き、大きな声で伝えた。
「トコちゃん、トコちゃん(勲さんの呼び名)、大丈夫? よく頑張ったね。感謝しているよ。ありがとう」
その言葉を嚙みしめたのか、勲さんは一度大きく目を見開き、皆に見守られながら、静かに旅立った。
「目を開けてくれて、すーっと逝ってしまった。聞こえたんでしょうね。最後の言葉が。本人に聞かないとわからないけれど、穏やかに逝った。私はそう思っています」
自宅で夫を看取れて良かったと三代子さんは話す。
「病院に入院させていたら、息を引き取る瞬間に立ち会えたかわからない。いろんな面で、家で看取れたっていうのは悔いが少ないですね。
家に帰ってから、ちょっと何かするにも主人が『ありがとう』と言ってくれていました。
『ありがとうなんていいのよ、当たり前なんだから』と言っても、『ありがとう、ありがとう』って」

<夫を看取った自宅にて。松尾三代子さん>
在宅で看取ることの大きな意義
松尾勲さんを看取った渡辺医師は、現在の富山市まちなか診療所だけでなく、長野の諏訪中央病院でも訪問診療を行い、これまで多くの患者を在宅で見送った経験をもつ。なかには、車椅子で生活保護を受けている方の訪問診療や、いわゆるゴミ屋敷のようなお宅に伺ったこともあるという。一人暮らしで天涯孤独な方のユニークな暮らしを目の当たりにすることもある。
そんな渡辺医師は、在宅診療の現場で「その家族や親戚の一部に混じらせていただく感覚を持つことがある」と語る。
「家というのは、匂い、音など、五感で感じられることも含めて、その人がその人らしくいられる場所だと思うんです。見慣れた空間に居られるっていうことが、より『本人が主人公の人生』に近づくのではないかと思っています。その方のその人らしさを、ずっと支えていく感じですね」

<富山市まちなか診療所は、医師、看護師の他に、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士が常駐している。>


<晴れた日には、コムス(小型電気自動車)に乗って訪問診療に行く>
また在宅の看取りの場面では、小さな奇跡が起こることがあるそうだ。
父を在宅で看護していたある姉妹のケースでは、父と折り合いが悪かった長女が、父の死期が近づくにつれ、互いの関係が和らいで、家族が一致団結していくのがわかったという。
また、別の大家族のビッグママである祖母の最期でも、バラバラだった家族が一つにまとまっていくのを感じとった。
祖母の命があとわずかとなったとき、10人近くいる孫やひ孫のうちの一人の誕生日を祝うために家族が集まった。それぞれ一緒に、感謝の言葉をかけながら、祖母とスマホで写真を撮り終わって間もなく、祖母の具合が急変し、亡くなった。まるで、家族が一つになったことをしっかりと確認したかのように。
「それまで疎遠だった家族が、やっぱり家で最期を過ごそうってことで、皆で一致団結されて、それこそあと数週間というところで、交替で泊まり込み、それぞれが本人と久しぶりに時間を過ごされるなかで、ほんとに良い時間が持てた、本当に家で良かったと言う方が多いですね」
在宅での看取りを可能にするのは、まずは本人の意志、医療者の存在、そして何より家族の覚悟が必要になる。
「一人暮らしの方でも在宅で看取ることはできます。家族がいる場合は、介護の負担が一番かかる方が『私は家ではみられない』とおっしゃると難しい部分があります。やっぱりご家族の覚悟があると、お家で看取れるケースが多いですね。
覚悟があれば、あとはどんな病気であろうと、医療的に何の処置があろうと、何の機械がついていようと、どんな状況であろうと、家にいたいっておっしゃるからには、いられます」
夫を看取った三代子さんのケースも、やはり本人の強い意志があり、その気持ちに寄り添った家族、そしてくつろげる我が家で、愛情に包まれながら迎える最期のために、医療者がチームワークを発揮した。
三代子さんは言う。
「やっぱり主人は家が良かったんですね。こんなにぐちゃぐちゃでも(笑)
緩和ケア病棟は新しくて、あんなにきれいな部屋だったのに。もしかしたら、何もないキレイな所より、こういうごちゃごちゃとした空間が落ち着いたのかもしれない。だから、思ったより長く生きてくれたのかなって」
在宅医療と介護・多職種連携の重要性
訪問診療を受けられるのは、一人で通院が困難な方となるので、要介護認定を受け、自宅で訪問介護を受けながら、訪問診療を受けている方も少なくない。医療と介護の連携をどうしていくかは、在宅医療に限らずとも、まさにこれからの世の中に必要なことだ。
国も医療と介護などの多職種間の連携を推進している。渡辺医師たちも、保健師を中心に連携の仕組みづくりをして、研修会を年に何度か開いている。
会議の内容は、主にワークショップだ。事例検討会では症例を一つ出して、違う職種になりきってロールプレイングもする。そうすることで、さまざまな職種の理解に役立たせている。
「医者ってなんだかんだ言って、多職種連携でも一番、阻害因子と言われています(笑)。医者が出しゃばりすぎて多職種連携がストップしてしまうという事例が往々にしてあるのです。医師はもっとそのことを自覚していく必要があります」
渡辺医師によると、今までのヒエラルキーでは、介護より医療の方が偉く、医療は一番上にいると認知されているふしがあるという。たしかに病院ではその方がスムーズにいく。とくに救急医療ではリーダーがいないと緊急時に混乱してしまうため、リーダーが指揮系統を持つ方が整然とうまくいき、患者の命が助かる可能性がある。しかし在宅医療では、医者はむしろ黒子のような立場に立つべきだという。
「医者が、『私は、私は』って主張してしまうと、患者さんの生活が損なわれ、他の職種を委縮させてしまうことになりかねないので、逆にいかに医者が出しゃばらないかっていうところが、在宅医療には必要だと、私たちは考えていますね。
やっぱり医者は見えないところで下支えをして、患者さんが患者さんらしく、他職種がそれぞれの想いを発揮して、遺憾なく活動できるというところを保障する必要があります」
いよいよ看取りという段階になると、医療の役割は少なくなるとも言う。
「できる限り薬を減らし、痛みをとるといったことはできますが、その生活をみている家族や介護職を、看護師が支え、医師がそっと見守る立場にいる状況でしょうか。
死亡診断書は医師にしか書けないので、最後の法律的な部分を任せられる医師がいるから、在宅にいられると言われることもあります。そういうところで私たちも最後に役に立てるのだったら、ありがたいですね」
終末期の病気を選ぶことはできない。終末期医療をどうするかの選択についても、価値観は人それぞれ違い、家族のあり方もそれぞれだ。だが、平均寿命がいくら伸びたとしても、死は必ず、皆に平等に訪れる。
渡辺医師は言う。
「死は敗北だと言いがちですけど、そうではなくて、ほんとうに豊かな場面です。年齢を重ねられて、これからいよいよ大往生を遂げようとする方の凝縮された部分に立ち会えるのが看取りの醍醐味です。
病院だと、死も日常に紛れてしまいがちですが、在宅医療では、各関係者が良かったと思えるような関係性で過ごせることが多いように感じています」
後悔しない生き方が問われるようになった現代。
在宅で死を看取ることは、その死に関わるすべての人にとっても、「死と生」を考えるきっかけとなっているようだ。悔いのない「死」は存在し得ないが、個々人が、より納得できる「最期」を求めることはできる。つまるところ、それは、「どう生きるのか」を考えることになるのではないだろうか。
<インタビュー&文 砂田嘉寿子>
【お知らせ】
本業であるお墓屋さんの仕事をとおして、人とお墓の関係をつづった創作物語「墓ありじいさん 墓なしじいさん」。
「墓ありじいさん 墓なしじいさん」を収録した「おはかの手帖」をつくりました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
