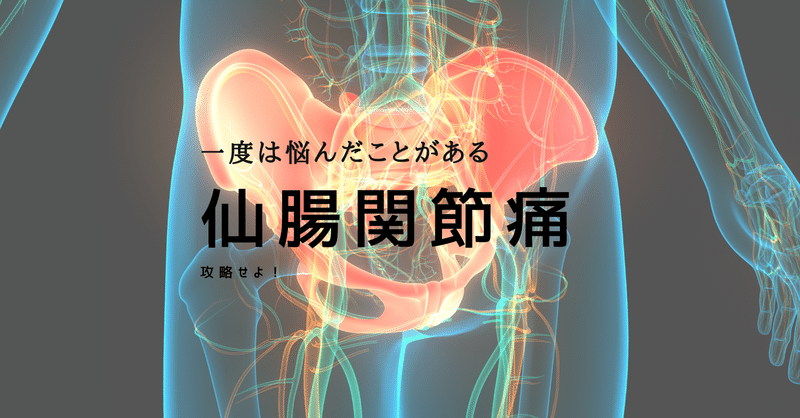
仙腸関節痛を攻略せよ
こんにちは
今回はセラピストの多くが一度は悩んだことがある仙腸関節についてです。
仙腸関節の評価って難しいですよね?
動く!っていう人もいるし
動かない!っていう人もいます。
そもそも動くか、動かないかって痛みにどう影響するのか?というのも悩みどころです。
ということで、今回は仙腸関節痛について考えていこうと思います。
ちなみにこんな記事を書いていますので参考までに
仙腸関節の解剖学からの考察
仙腸関節は文字通り仙骨と腸骨をつなぐ関節ですが、滑膜性結合と線維性結合による半関節という特殊な構造の関節です。
滑膜部分はレール状の関節構造で、その前側に強固な靭帯が存在しています。円形の関節内に二種類の結合様式が存在するために半関節という言い方をします。
仙腸関節は個体差の多い関節です。
・老化による変形
・先天的なもの
・経産婦
・腰痛や骨盤帯痛
などによって仙腸関節の構造的な形状に差異が生じることがあるとされています。
しかし共通点は関節前方は前仙腸靭帯があり、骨間部では三日月状の滑膜構造で、後方は後仙腸靭帯、骨間仙腸靭帯が螺旋状に付着しています。後仙腸靭帯は浅層と深層に分かれています。
LPSL(長後仙腸靭帯)は、骨付着の近位および遠位領域を有することが観察された。これらの付着領域の間で、中央のLPSLは、脊柱起立筋腱膜、「深部筋膜層」、および臀部腱膜の3つの層の合流点として観察されました。「深い筋膜層」の深部に、脂肪と疎性結合組織の層が観察されました。 Joint Bone Spine Volume 76, Issue 1, January 2009, Pages 57-62
後仙腸靭帯は骨に付着するだけでなく、主に筋膜層に付着していて、深部は脂肪と疎性結合組織の層があると観察されています。
よって後仙腸靭帯周辺の筋膜や空間の神経におこる侵害刺激が仙腸関節痛の発症部位である可能性が高いとされます。
加齢によって仙腸関節は不動化します。20代に変性ははじまり、30代では多くの人の仙腸関節に可動性の低下がみられ、それ以降は不動化の傾向が強まります。
仙腸関節痛は関節自体の変形や変性でおこることはあっても、仙腸関節周囲の軟部結合組織間にある神経が何らかのストレスによって障害を起こしていることの方が可能性が高いと思います。
仙腸関節を動かす力
仙腸関節を語る際によく論争になることがあるのが
仙腸関節は動くか?動かないか?
という話。
仙腸関節は加齢による変化で癒合し(特に腸骨側に変性は見受けられる)、不動化していきます。
そのため、動いていたけど動かなくなっていくという表現が妥当になります。
仙腸関節を動かす筋を考えると仙骨または腸骨に付着する筋を考察することになります。
【殿部の筋】
・大殿筋
・中殿筋
・小殿筋
・梨状筋
【股関節の筋】
・大腿直筋
・縫工筋
・腸腰筋
・上下双子筋
・内閉鎖筋
・大腿方形筋
・恥骨筋
・長短内転筋
・薄筋
・大小内転筋
・外閉鎖筋
・半腱半膜様筋
・大腿二頭筋
【体幹部の筋】
・固有背筋群
・腸腰筋
・腰方形筋
・腹斜筋
・腹横筋
・広背筋
仙腸関節と関連するであろう筋を思い浮かぶだけ書いてみましたが、少なくともこれくらいはありそうです。
大きく分けると
*殿部(骨盤部)
*股関節
*体幹部
に分かれます。
これらの作用から仙腸関節の動きを考察すると
・仙腸関節単体で動かす筋は存在しない
・レール状の関節方向以外に平面関節として内外方、上下方などにも作用する
・関節としての役割よりも外力からの緩衝役と上半身と下半身の力を統合する役割が主なはたらきではないか?
このような推測が立ちます。
ここで考えなくてはならないのは、仙腸関節が動くための力ではなく、仙腸関節の役割を発揮するために力学的にどんな力が影響するのか?という視点を持たなくてはなりません。
仙腸関節独自の運動としてはさほど重要ではないが、力学的には非常に重要なメカニズムを有しています。
仙骨は腸骨との関節面が平端なわけではありません。仙骨の関節面は上方は内方に角度を持ち、下方は水平なため重力(体重)に対して前方に負荷(仙骨前傾位)がかかったときは後方の靭帯が、後方に負荷(仙骨後傾位)がかかった場合は前方の靭帯が制限できるような構造をしています。
この構造体の強度はどんなものなのでしょうか?
59歳から74歳までの8人の成人から得られた新鮮な死体標本で、単一および対の仙腸関節(SI)の両方の荷重-変位挙動を測定しました。両方の腸骨を固定した状態で、静的試験荷重を仙骨の中心に、上SI終板に平行で垂直な軸に沿ってその周りに加えました。294 Nまでの試験力が、上、下、前、後、および横方向に加えられました。42 Nmまでのモーメントが、屈曲、伸展、横方向の曲げ、および軸方向のねじれに適用されました。仙骨の中心の変位は、ダイヤルゲージと光学レバーシステムを使用して、各荷重増分が適用されてから60秒後に測定されました。次に、腸骨を1つだけ固定してテストを繰り返しました。最後に、各SI関節の3次元位置と全体的な形状が測定されました。最大試験荷重での孤立した左関節の場合、力の方向の平均(SD)仙骨変位は、内側の0.76 mm(1.41)から前方向の2.74 mm(1.07)の範囲でした。モーメント方向の平均回転は、右横曲げの1.40度(0.71)から上から見た時計回りの軸ねじれの6.21度(3.29)の範囲でした。また、より大きな荷重下での荷重-変位挙動を調べました。単一の仙腸関節は、500〜1440 N、および42〜160Nmの荷重に明白な障害なしで抵抗しました。 J Orthop Res. 1987;5(1):92-101. doi: 10.1002/jor.1100050112.
Load-displacement behavior of sacroiliac joints
死体の骨盤で仙腸関節に荷重をかけ、変動した距離感を調べたところ上記のようになったようです。
死体ということは神経的な反応がないわけで、純粋に物理的外力に対する抵抗になります。そのような状態であっても数mmしか可動せずに、強度は高いことが示せました。(500N=50.99kg)
*筋肉的には運動よりも姿勢制御
*骨格的には緩衝、安定機能
この2点の構造的な理解が必要であり、仙腸関節のバイオメカニクス的破綻は骨盤の不安定性と姿勢制御に問題が生じる可能性があります。
仙腸関節と腰痛
腰椎椎間板ヘルニアと診断された患者の仙腸関節機能障害の有症率とそれに付随する症状を調査した。
患者の63.2%が女性で、36.8%が男性でした。平均年齢は46.72±11.14歳でした。仙腸関節機能障害のレベルは、研究対象集団で33.3%でした。性別の分布に関しては、仙腸関節機能障害のあるグループで女性の割合が高かった(P <0.05)。視覚的疼痛スケールを使用して評価した疼痛強度にグループ間で有意差は観察されなかったが(P> 0.05)、神経障害性疼痛のレベルは機能障害のあるグループで有意に高かった(P <0.05)。仙腸関節機能障害のあるグループでは、うつ病の存在が有意に高く(P = 0.009)、機能的能力が悪化し(P <0.001)、運動恐怖症の存在が高かった(P = 0.02)。 Spine (Phila Pa 1976). 2020 Apr 15;45(8):549-554.
椎間板ヘルニア患者の仙腸関節機能障害は女性の方が男性よりも多く、これに伴う随伴症状も見受けられます。
仙腸関節機能障害を持つ患者は腰椎椎間板ヘルニアだけでなく梨状筋症候群、変形性腰椎症、子宮筋腫などでも見受けられます。
仙腸関節機能障害は仙腸関節痛を伴う腰痛と同義ではなく、仙腸関節由来の異常が鑑別の決め手となります。
機能解剖学上、仙腸関節は複雑で、理解が難しい構造体であり、障害の有無だけでなく、心理社会的要因や環境要因も多く関与していると思われます。
非特異的な症状も仙腸関節周囲に発現しやすく、仙腸関節周囲の固有受容器は疼痛感受性が高いものも多いようです。
仙腸関節をモデリングして考察する
仙腸関節が複雑な構造体であり、腰痛の15~30%ほどの原因にもなるとされていますが、考え方としてモデリングした解説があると治療戦略を立てやすくなりますので紹介します。
仙腸関節は不安定性を呈することで痛みの感受性を高めます。
これは妊婦または生理中の女性に仙腸関節痛を訴えることが多いことから、実際に不安定であるかは置いておいて、ASLRによる主観的な不安定感を考察すると妊婦(産後も含む)と生理中の女性が有意に不安定感を感じ、仙腸関節痛を訴えるという結果もあります。
そのことから仙腸関節の安定的なモデルを頭に入れておくことが重要です。
仙腸関節は上下の力学的負荷と左右の力学的負荷が安定性に関与します。
上下の力学的負荷をフォームクロージャ―、左右の力学的負荷をフォースクロージャ―と呼びます。
フォームクロージャ―は姿勢的な上下の力への安定性であります。
フォームクロージャ―は胸腰筋膜から大殿筋~仙結節靭帯~大腿二頭筋という筋膜の連結からなり、特に大殿筋の筋力低下または活動低下はこれらの筋膜連結を弱め、仙腸関節にストレスを引き起こします。
大殿筋の活動低下は腰部への代償動作を促進し、腰痛の機械的因子にもなります。
フォースクロージャ―は仙結節靭帯と後仙腸靭帯が筋収縮によって緊張あるいは伸張を起こすと仙腸関節面の圧迫力は増加します。
フォースクロージャ―の安定作用は腹横筋をはじめとしたインナーユニットと腰方形筋や内転筋群を連結するアウターユニットからなります。
腹横筋は吸気によって中心腱を下方へ引き下げ、胸腔の垂直の長さを増加させながら、後方の多裂筋を圧迫することで抑制します。
アウターユニットはグローバルな筋膜システムで、これらの筋または筋膜に損傷が起きた場合は、体幹の維持機能が制御しにくくなるためにインナーユニットにも影響し、仙腸関節の安定性を損ねます。
仙腸関節単体で考えると、その機能は断片的にしか見えてきませんが、マクロな視点で考えていくと広範囲の筋膜層の連結が仙腸関節の機能に影響すると考えることもできます。
しかし注意が必要なのは筋膜というのは概念的な解釈であり、英語でいうFasia(ファッシア)とは類義語ではあれ、認識は少し違います。
Fasiaは疎性結合組織といって組織と組織の間にある主に水とコラーゲンを原料とした線維性結合組織です。
仙腸関節のモデリングで説明したものは筋膜という概念的な連続性で説明しています。
仙腸関節痛の徒手検査
仙腸関節痛誘発テスト
Yeoman's TEST
Compression TEST
Gaenslen's TEST
仙腸関節痛のテストはとても数が多く、疼痛を誘発するテストが主です。
仙腸関節の痛みを誘発しますが、仙腸関節の障害、損傷があるとは限らないので注意が必要です。
仙腸関節痛の改善には何が必要か?
仙腸関節痛はここまで調べてみると、構造的破綻による症状である可能性は低く、心理社会的要因や環境要因も大きく関与していると思われます。
また、仙腸関節単独で考えるのではなく、運動連鎖や筋膜連結などの概念も利用し、皮膚運動や末梢神経の活動などという視点からも診ていく必要があると思います。
筋力としては殿筋の活動、傍脊柱筋群、ハムストリングスの伸張性を保つことはトレーニングの観点から診ることができます。
骨盤というユニットは複雑であり、構造としても生理的にもまだ未知の部分がたくさんあります。
単純に腰痛として括るのではなく、患者の生活の中や経験、信念からも疼痛感受性に関することを探りながら、精査していくようにします。
仙腸関節痛は深殿部痛と鑑別が難しい場合もあります。似たような症状との鑑別にも意識を向けていけるようにしましょう。
ここまでの知識は最低限あった方がいいかと思います。
その上で、臨床上で判断がつきにくいものもあると思いますので、安易に仙腸関節が原因と判断せずに、時間をかけながら患者さんと症状を確かめ合いながら進めていくことをおすすめします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
